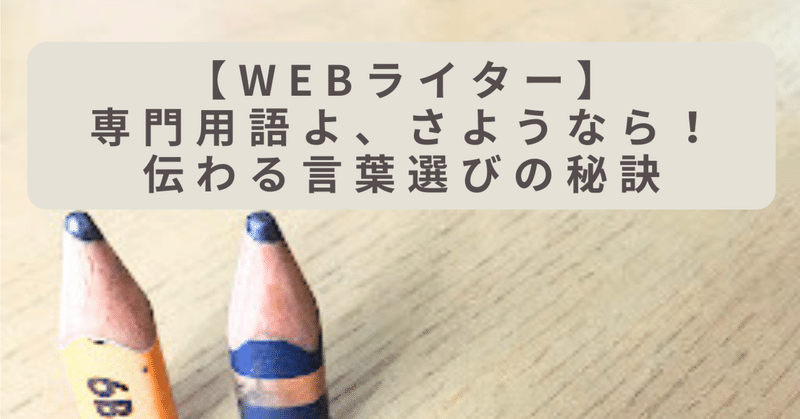
【うまい文章を書く方法1-2】専門用語よ、さようなら!誰でもわかる言葉選びの秘訣
文章を書くとき、分かりやすい言葉を選ぶことはとても大切です。
読者が文章をそのまま読み進めてくれるかどうかは、「直球勝負」のようなもの。
文章を読んでいて、知らない言葉が出てくると、離脱してしまったり、意味が分からないまま最後まで目を通したものの結局分からなかった……という経験をしたりした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今日は、なぜ分かりやすい言葉を選ぶべきなのか、そして難しい専門用語を避けるべき理由についてお伝えします。
カタカナ言葉に要注意!
気をつけるべきは、あなたが日常的に使っている言葉。
あなたにとっての「日常」が、読者にとっての「日常」とは限らないのです。
カタカナにめっぽう弱い私は、カタカナ言葉の壁に跳ね返されてしまうことがしばしば。「アジェンダが…」「デフォルトの形式で…」「このアプリのローンチは…」とweb会議で飛び交うと、平然とした顔で慌てて意味を検索しています。そしてあまりにも意味が分からないときには、質問してようやく解決。
でも、文章ってその場で質問できませんよね?
だから、読者を置いてけぼりにしないよう心がけましょう。
誰でも知っているような言葉で説明することで、文章はぐっと読みやすくなります。
専門用語は意味を添えて!
難しい専門用語を避けることも、分かりやすい文章を書くためには重要です。専門用語は特定の分野に詳しい人たちには理解できるかもしれませんが、読者の中には、初めて目にする人も。
たとえば、広告でよく使われる言葉に「インプレッション」という言葉があります。これをそのまま使うよりも、「インプレッション:人が広告や記事を見た回数」と説明した方が、多くの人にとって分かりやすいです。
文章を読む人全員がその用語を知っているとは限らないので、専門用語を使う場合は、簡単な言葉でその意味を説明するようにしましょう。そうすることで、より多くの人が文章の内容を理解しやすくなります。
小学校高学年に伝わる言葉を
複雑な言葉や専門用語を多用すると、読者は壁を感じてしまうかもしれません。シンプルでやさしい言葉を使うことで、読者に親しみやすい印象を与えることができますよ。
私がよくイメージするのは、小学校高学年。今子どもが小学校高学年ですが、小学生をあなどるなかれ。最近の若者、ものすごい情報量の中で平然と生きているので、理解力も情報の取捨選択も速いです。この世代に通じる内容をイメージすれば、ほとんどの大人にとっても伝わりやすいと思います。
分かりやすい言葉を選ぶことは、読者に対するやさしさの表れでもあります。読者がどのような背景を持っているのか、どれくらいの知識があるのかを考えながら、誰にでも理解しやすいような言葉選びを心がけてみてください。
ありがとうございます♫ いただいたお金は大切に使わせていただきます^ ^
