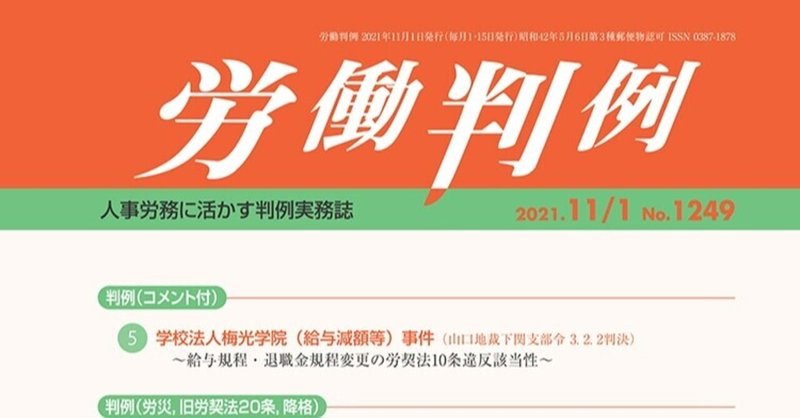
労働判例を読む#340
今日の労働判例
【国・大阪中央労基署長(リーヴスホーム)事件】(大阪地判R3.3.15労判1249.35)
この事案は、営業職員Xが仕事のストレスによってうつ病になったとして、労災支給を求めた事案で、裁判所はこれを不支給とした国・労基署Yの主張を否定し、労災の支給を命じました。仕事のストレスがうつ病の原因である、と認定したのです。
1.事案の特徴
この事案で特に注目されるのは、①労働時間の認定に関し、実際にXが行っていたそれぞれの業務に必要な作業内容を詳細に検討したうえで、必要な残業時間が認定されている点と、②これによって長時間の労働時間が認定されたことが主な理由となって、労災が認定された点です。
このうち①は、タイムカードなどの記録が信用できないときに、実際の仕事の内容から、この程度の作業時間が必要だったはず、という蓋然性に基づいて労働時間を認定する方法の1つです。実際の労働時間を個別に計算して足し上げるのではなく、平均的な労働時間を概算する方法ですから、厳密な立証が必要となる刑事事件の場合にも採用されるかどうかは問題がありますが、民事の労働時間の認定に限って言えば、労働時間を適切に管理すべき会社の側が、適切な労働時間管理をしなかったことによってメリットを受けるのは不公平ですので、それなりの合理性が認められる労働時間認定方法であると言えるでしょう。
②は、本事案に先立ってXと会社の間で民事損害賠償に関する訴訟があり、長時間労働に関する会社の責任を前提にした和解が成立したことが事実認定に影響している点が、特に注目されます。
すなわち、Yの仕事の進め方に対して、上司が度々厳しい指導教育を行っていて、それがパワハラなど、業務上のストレスを強化する理由になる、とXは主張しているのですが、裁判所は、もちろんどのような言動がどのような状況でなされたのかを詳細に認定しているものの、民事訴訟での和解の際に、ハラスメントなどの点は考慮されなかったことから、上司の言動はハラスメント等に該当しない理由の一つとされているのです。
2.実務上のポイント
結局、労働時間の長さが労災認定の決め手であり、上司の言動がハラスメントなどに該当するかどうかは、結論に影響を与えなかったと評価できます。
けれども、Xの納得感を得るために重要だったのでしょうか。あるいは、会社側の今後の労務管理の観点から相当程度の評価が欲しかったのでしょうか。上司の言動のハラスメントなどへの該当性について、かなり詳細な検討と判断が示されています。
指導教育などとして許容されるのはどのような場合なのかについて、参考になる裁判例です。
※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
