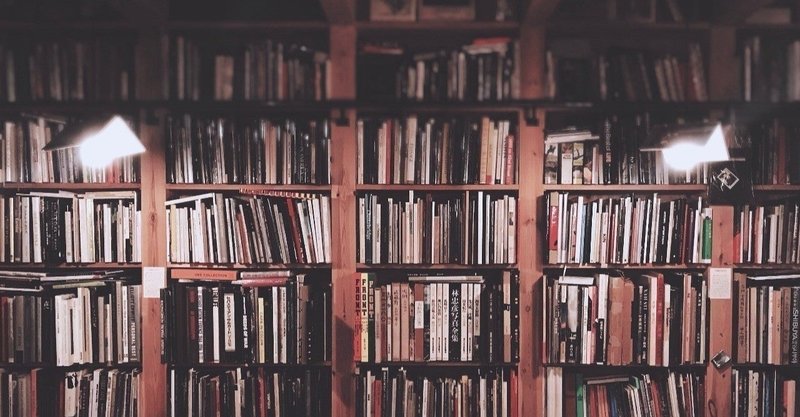
私とピアノと文学
これは私の子どもの頃の思い出話で、個人的なnoteです。
子どものころはピアノを弾く、ピアノ少女でした。
私の家にはピアノがなく、裕福でもありませんでしたが、私が新聞広告の紙の裏に鍵盤を書いてピアノの練習していたのを見て、親がピアノを買ってくれ、近所の先生のところにレッスンに通うようになりました。
今でも思い出すのが、11月23日の勤労感謝の日に毎年発表会があったこと。先生が国立音大出身の方で、毎年東京・立川のホールを借りて発表会をしたものです。
発表会の時はみんながシルクの素敵なブラウスを着たり、ベルベットのワンピースを新調してもらったり、みんなで当日おしゃれをして演奏し、たくさんお花をもらったり、普段はいかない、クリスマスに向かう立川の街(当時はすごい都会という印象がありました)の素敵なお店やイルミネーションを眺めたりと、特別な季節でした。
小学校高学年になってピアノの先生が変わり、近所の優しい先生で、モーツァルト、バッハ、ショパン、ベートーベンを演奏するようになりました。
中学2年になって、ピアノの先生から「和子さんは才能があるので、音楽の道に進んだ方がいい」と紹介されて、東京芸大の有名な先生のところに通うようになりました。
先生のご自宅が表参道でしたので、毎週表参道に通うようになりました。
原宿から表参道まで歩いて通うのですが、世界が開けた感覚は半端ではありませんでした。それは1980年のこと。1984年まで通っていました。
デザイナーズブランドのショップが立ち並び、ラフォーレ原宿がマイケル・ジャクソンの音楽を流し、同潤会アパートがシックで、竹下通りのショップに行くと松本伊代ちゃんがお買い物をしている、など。まさに原宿に巨大なエネルギーがあるころで、ワンダーランドのようでした。
表参道駅の先、骨董通りに近い方でしたが、そのあたりのおしゃれさと言ったらありませんでした。
多くのショップは気後れしては入れませんでしたが、控えめでシックなたたずまいのヨックモックが好きでよくいきましたね。今でも行きます。
しかし、先生は厳しく、よく泣いて帰りました。
あなたは自己流のくせがついていてまずそれをなおすのが大変、芸大は無理だし、音大のピアノ科も難しいと言われました。挫折です。
でも、芸大に入ったお弟子さんたちも、芸大の先生から雷を落とされて泣いて先生のところに駆け込んできたりと、
「音楽の道って私が思い描いていたほど、楽しい道ではないかも」
と思うようになりました。権威ある教授に完全服従を求められる、自由のなさを感じました。
高校に入ると、軽音楽部にもちょっと顔を出していて、ユーミンとかサザン、洋楽(!)にもはまり、「今の音楽はもっと自由なのに」とピアノのレッスンに違和感も覚えるようになりました。権威に対する批判的な視点ですね。
高校一年のころ、ピアノは一日平均4時間練習しても怒られてばかりでしたが、高校の国語の成績は何もしなくても学校一番で、先生から褒められてばかりでしたし、文学のほうが心地よいし、好き。
小学校の時の「好き」から出発してピアノを習ってきたけれど、もっと今の、自分の本当の好き嫌いや感受性を大事にして生きるべきではないかと思うようになります。
高校では、ロマン・ロランなどのフランス文学に傾倒するようになっていました。
ある日、風邪をひいて近所のお医者さんに行ったとき、医師から
「和子さんも高校生になったんですね、文学は読まれますか?」と聞かれ、「はい」と答えたところ、
「読書はいいですね。私が高校の時に読んで感銘を受けたのは『チボー家の人々』という小説でした。あれは。。。私に影響を与えた小説です。いまもよく覚えていますね。」
と言われ、チボー家の人々も読み始めました(これは長くなるので、いつか書きます)。
ピアノの先生には、「高校の音楽の先生になるのがよい。安定しているし、いいですよ」と言われました。そして演奏方法についてテクニカルな指導を受ける日々でした。
でも、激動の時代を生きたベートーベンやショパンの伝記を読んだり、ロマンロランの小説やチボー家の人々、その他の文学を読んでいると、自分が音楽に求めていたのはもっと情熱的なことだったし、音楽の先生になるよりもっとやりたいことがあるのではないかと思うようになりました。もっと社会に関わる仕事がしたい、何ができるかわからないけれど。。。
社会派の文学者になりたいなあ、と思ったりしていました(※残念ながら、日本では職業として成立していないと思いますので、その後断念しました。最近、そうでもないんだなあと思って、社会的テーマに果敢に取り組む作家の皆さんの活躍を応援しています。)
そんな思いに突き動かされて、私はピアノの先生に謝りに行き、ピアノ受験を断念し、進学は普通の大学の文系に変え、ピアノは趣味として続けるようになりました。
地元の二番目の先生のところには時々顔を出していたので、ピアノ発表会には参加し、高校の最後にひいた曲はショパンの幻想即興曲でした。
そんな私が高校の時に好きだったのが、同じクラスだったサッカー部の男子。繊細な人で、ピアノができ、音楽室でベートーベン「月光」の第三楽章(難しいので私は第二楽章までしか進んでいませんでした)を譜面も見ないでひいていたときに「やられた」と思いました。
自分よりはるかにピアノができる人がいる。
その後、音楽のクラスで「日本人の詩人の詩を選んでそれに曲をつける」というグループワークがあり、私たちのグループは中原中也の詩を選びましたが、彼のグループは荻原朔太郎の
フランスへ行きたしと思えどもフランスはあまりに遠し
という詩に彼が華麗な曲をつけ、ピアノ伴奏をして披露してくれました。
その曲はフランス文学に傾倒していた私の気持ちにもとてもフィットしていて、いまでもときどき思い出します。
(今にして思うと、こういう情操教育や芸術に触れる機会、環境に恵まれていたことに感謝しかありません。1980年代は時代的にも、いろいろ余裕がありました)。
しかし、大学は法学部に入ってしまい、ピアノから遠ざかります。
結局、文学で道を立てることもできず、子どものころから蓄積していた芸術分野から遠ざかったことに後悔があり、これからもう少し埋め合わせをしていきたいと思っています。でも、
もっと社会に関わる仕事がしたい
と考えて進路変更をしたのは、今にして思うとよかったなと思い、そのことに悔いはありません。
でも、音楽も文学もかけがえがないもの。できる限り音楽と文学で生活を満たしていきたいなと思っています。
前の事務所は東京芸大に近く、奏楽堂で第九を歌わせていただいていましたが、いまの事務所の近所、#神楽坂 にはこんな素敵なところもありますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
