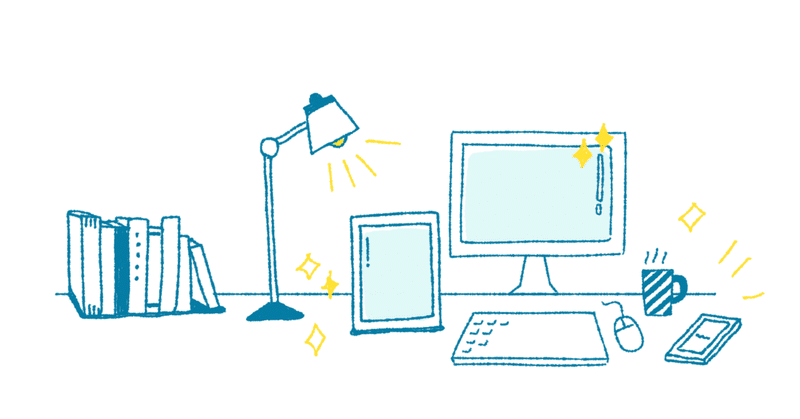
WACATE 2023 冬に参加した
前回から1年半ぶりの2回目の参加だけど、初のオフラインかつ冬の回に参加した形でもあります
■WACATEとは
Workshop for Accelerating CApable Testing Engineers:内に秘めた可能性を持つテストエンジニアたちを加速させるためのワークショップ
要するにワークショップ形式のソフトウェアテスト勉強会です。
しばらくオンラインでの開催となっていましたが、2023年の夏の回からオフライン開催に戻ったようです。
なお、「若手」をテストに関する業務経験を問わず「35歳以下」と定義しているようですが、40代に入ってから全くの未経験でこの業界に迷い込んでしまった”年齢だけは行っているけどレベルは若手以下”の自分にとってはまだまだ難しいところも多いです。
■SNS繋がりの知人と会えた
今回の参加者の中に4名ほどSNS経由で知り合った人が参加していました。
SNSでしか付き合いのなかった人、自分が一方的に知っている人、オンラインで話したことのある人、対面で会ったことのある人…。
事前にその内の1人は参加することを知っていましたが、その他の人は当日会場で会ってびっくりしました。
やはりリアルタイムで会えたのは嬉しかったです。
■夏と冬の両方に参加してみて
2022年の夏の回に続いて2回目の参加となりますが、冬の回の参加は初めてとなります。
元々WACATEの各回のコンセプトは
・夏のWACATEは、ひとつのテーマを「狭く深く」集中的に取り組むこと
・冬のWACATEは、テストに関するテーマを「広く」取り組むこと
となっています。
夏冬どちらも体験した身としては、自分に向いているのはどちらかと言うと夏の方かな、と思いました。
冬は色々なテーマで話が聞けて楽しいのですが、この件はもう少し深掘りして欲しいと思っていたら休憩を挟んで次のテーマに移ってしまうので、頭を切り替えるのも大変でした。
これは人それぞれかと思います。
■印象に残ったワークショップ
・JSTQB FL 最後の幻のテスト技法「ユースケーステスト」を学ぶ
今回参加して一番自分の中で勉強になったと思ったのは、実行委員長でもあるブロッコリーさんこと風間裕也さん(以下ブロッコリーさん)の「JSTQB FL 最後の幻のテスト技法「ユースケーステスト」を学ぶ」です。
この後のセッションのスライドはこちら!#WACATE https://t.co/9Hcp5KhlU0
— broccoli (@nihonbuson) December 24, 2023
理由の一つにJSTQB ALのテストアナリストの試験対策になる、と言うのもあります。
実際にブロッコリーさんから説明を聞いて手を動かして作業をすることで内容がストンと入りました。
デシジョンテーブルの時と同様、独学でやっていたら理解するのに時間がかかったと思います。
ユースケーステストについては、今回使用した問題や秋山さんが書かれた記事や「ユースケース駆動開発実践ガイド」なども参考にして実際に使えるレベルまで持って行けるようにしたいです。
・QMファンネルを使って自分の立ち位置/やりたいことを可視化しよう
遅くなりましたが、WACATE2023冬のQMファンネルのセッション資料公開しました。#wacatehttps://t.co/qURkaxvQKC
— かくげん (@ryo328kgn) December 29, 2023
元々QMファンネル自体は知っていたのですが、かくげんさんから改めてきちんと説明を聞いた上で今後どの方向に進みたいのか、自分の中で今後のキャリアについて考えるように諭してくれたと思いました。
感想としては、QMファンネルでのスペシャリティの定義で言うと、今の仕事はテストの方に全振りしているなぁです。
あと現在第三者検証会社にいるので、ロールの定義で言うとスプリットに該当するでしょうか。
PNについてはテスト自動化自体が未経験なのと、関われるかどうかは今後アサインする案件やプロダクト・プロジェクトもしくは所属会社次第になると思うので、現時点では何とも言えないです。
話を聞いていて、例え該当案件に関わる機会がなくとも最低限のテスト自動化に関するスキルについては学んでおいた方がよさそうに思いました。
また、QAについて。
QAについての定義そのものが結構色んなところでバラけてる印象なのですが、QMファンネルの定義に沿って言うとそもそも現在テストに全振り状態なので、どう意識してQAについて学び、仕事に活かせるように持って行けるかが今後の自分の課題になりそうです。
今後のやりたいこととしては、
・ロールはインプロセスを目標に
・スペシャリストとしてはテストとQAの割合を最低半々、できればQA寄りに持って行く
・該当案件に関われる関われない問わず最低限のテスト自動化のスキルは身に付けておく、またスペシャリストの割合の中にPNを割り込ませられることができたらなおベター
ざっくり言うとこんな感じに持っていけたらいいなぁと。
・WACATE実行委員座談会 〜Specialist シラバス編〜
こちらは現在サイトに掲載されているJSTQB FL Specialistの下記の4つのシラバスについて実行委員がトークセッションする形で行われました。
・FLシラバス(Specialist) AIテスティング
・FLシラバス(Specialist)自動車ソフトウェアテスト担当者
・FLシラバス(Specialist)モバイルアプリケーションテスト担当者
・FLシラバス(Specialist)性能テスト担当者
聞いていて面白かったのが、自動車ソフトウェアテスト担当者のシラバスについて。
やはり自動車のソフトウェアということもあって、安全面の部分などでガチガチに決められていることが多いという話が印象的でした。
もし、他にも安全面でガチガチに決めないといけないジャンル(医療機器や飛行機など)のソフトウェアテストのシラバスがあったらどんな内容になりそうか、と思いました。
JSTQBのシラバスは資格試験に関するものは試験対策の一環で読んだことはあるのですが、それ以外のものはなかなか読む余裕がないので、読むようにしたいなと反省しました。
・単体テストソムリエになろう
これは今回難しかったものの一つです。
と言うのも、そもそも単体テストを行う案件に携わる機会がなかったからです。
WACATEの午後イチセッションの講義部分を補助のために一時的に公開します。見えなかった時のためにお手元でご確認ください。予告なく変更削除すると思います。。すみませんがよろしくお願いします。。#WACATE
— べにちどり (@scarletplover) December 23, 2023
単体テストソムリエになろう!(WACATE参加者用) https://t.co/rCot7RWQ6j
そのため、ワークをしていても「これで合っているのか?」としっくり来なかったのも事実です(べにちどりさん、ごめんなさい)。
これもQMファンネルでのテスト自動化と同じように、案件に携われなくても必要最低限の知識やスキルは学んでおいた方がいいと思いました。
なので、スライドとこの本で復習しておかないと。
■分科会について
1日目の夜は自由参加という形で分科会が行われました。
各テーマごとにグループに分かれてセッションしたりワークをする会なのですが、以前から知人であるMark Wardさんがテーマオーナーのグループに参加しました。
他にも興味のあるテーマがあったので折を見て他のグループにも参加しようかと思っていましたが、結局Markさんのグループのテーブルから動かなかったです。
こちらのテーマは「明日の品質文化をつくる品質ナラティブ入門」。
ちょうど彼が翻訳した「LEADING QUALITY」を現在読中なのですが、第2章に品質ナラティブが取り上げられており(そこから今回のテーマにしたのではないかと)、この分科会のグループに参加したおかげで理解に役立ったと思います。
■その他のエピソード
まこっちゃんさんが「顧客が本当に必要だったものゲーム」と言うカードゲームを持参していてゲームに参加させてもらったのですが、実際に遊べる時間があったのが2日目の昼休憩が終わる10分前くらいしかなく、しかも意外とルールが難しくて説明書を読んで理解するのに時間がかかり1セット目の途中でタイムオーバーとなりました。
システム開発における要件定義の難しさを表した風刺漫画をベースにカードゲームにするなんてなかなか面白いなぁと思いました。
自分でもその内入手しようかと検討中です。
あと、実行委員の方が「Software Testing "ManiaX”」の在庫の残っている巻の販売を行いました。
実は2022年の夏に参加した時に抽選で何冊か当てており、とは言え全巻ではないので持っていないものが欲しかったのですが、何巻を持っていないのか覚えていなかったのと現金の持ち合わせがなかったので買えずじまい…。
※帰宅後に確認したら、Vol.1・3・7・10の4冊が欠けていました。
実行委員の並木さんが仰るには残りの在庫はそれだけらしいとのこと、そして終わる頃には売り切れだったかと(そのため、今後の入手は難しくなりそう)。
確か販売開始の時点で既に何巻か在庫がなかった巻があったので残り全部を揃えるのは難しかったとは思いますが、在庫がある巻だけでも買えなかったのは残念でした。
また、何冊かの本のプレゼントの抽選がありました。
既に持っているものもありましたが、所持していない物の中から「なぜ重大な問題を見逃すのか? 間違いだらけの設計レビュー第3版」に申し込んだのですが、外れてしまいました。
因みに後日購入済みです。
■参加して改めて感じたこと
それは説明を聞きながら実際に手を動かすワークショップスタイルの勉強会は自分に向いていると言うことです。
ユースケーステストのセッションでも書きましたが、実際に説明を聞きながら課題を解く方が理解し易かったです。
あと、スキルも経験値もまだまだであることを改めて実感しました。
■次回について
2024年の夏の回については余程のことがない限り参加する予定です。
次回参加する時までにどこまで成長できているかわかりませんが、WARAIに参加した時にも思ったように勉強は続けていきたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
