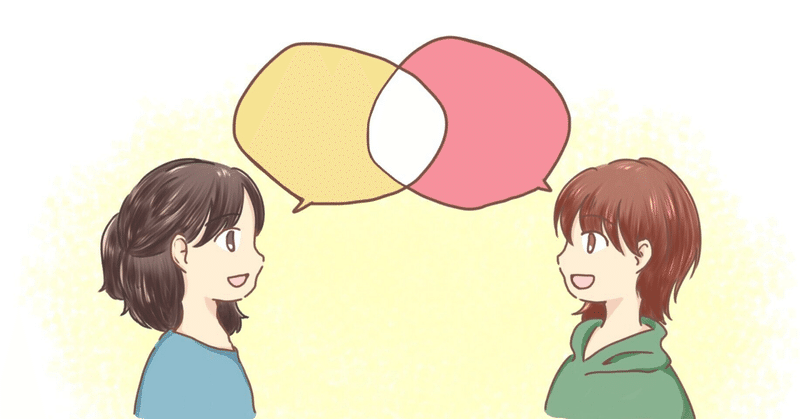
「伝える」と「伝わる」
昨日(9月25日)、第137回中央教育審議会が開催された。議題は次の4点だったそうだ。
(1)急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について(諮問)
(2)教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)について
(3)生涯学習分科会社会教育人材部会 中間的まとめについて
(4)日本語教育機関認定法について
会議の中で、埼玉県戸田市教育長の戸ヶ﨑勤委員は、議題(2)に関連して次のように発言したという。
(ちなみに、議題(2)で取り上げている緊急提言は、ざっくりと言えば教職員の働き方改革に関する内容である。いずれは議事録が公開されると思うが、ここでは戸ヶ崎氏のFacebookから該当する箇所を原文のまま引用させていただく。)
肝煎りで出された緊急提言ですが、未だ届いていない自治体や学校現場はないだろうか。イベント案内等の文書と同じ扱いを受け、ファイリングの中に眠ってしまっていないだろうか。(1)や(3)の議題にも関係するが、「令和型の戦略的広報」等について申し上げたい。
中教審答申をはじめ教育施策は、文科省において通知、HPやSNS、メルマガに加えて、トークイベントや動画配信など、様々な手法で広報発信の努力が行われている。
しかし、伝えると伝わるは違う。国から自治体等を経由し現場に着くころには、本質的な意味や魂が抜け、用語だけが負担感や抵抗感を伴って独り歩きしてしまうことが少なくない。様々なグッド・プラクティスが全国はもとより近隣の自治体にも政策波及されないことや、社会の変化に同期しようとせず、GIGAの取組もそうですが、課題を抱えていても「何ら困っていない」自治体や学校があることを危惧している。この中教審と現場等のギャップを常に意識していく必要があると思う。
教育は「見届け」が極めて重要です。多義的で耳当たりのよい言葉で築かれた理想の教育が演繹的アプローチにより現場に下りてくるだけでは、現場の担当者は「わかったつもり」にはなっても腹落ちはしない。立派な事例集を作成しても本当に届いて欲しい課題のあるところには届かない。気付きを促すなど人の心を動かす「インサイト」を刺激することで、国の議論等が自治体や現場に腹落ちし、実践に結びつくよう、「令和型の戦略的広報」や「コミュニケーション・デザイン」について知恵を絞る必要があると思っている。今後は、通知等の優先度や「重み付け」の戦略も必要である。また、AIやRPAなどテクノロジーも駆使して、情報を確実に受け取っているかの見届け、受け取った自治体や学校が、どのような気付きをして行動や考え方等に変容が生じたのかなども、可能な限り可視化して定量的に見届ける必要性も感じる。
先行事例として、教育課程課が学習指導要領の趣旨の実現に資するため行っている「各教科等教育課程研究協議会」が、今年度から文科省の行政説明を、市町村教育委員会もオンデマンドで視聴することができるようになった。これまでの教育界では常識であった、国→県→事務所→市町村の伝言ゲームの壁に風穴を開ける取組であり、小さな一歩であっても歴史的な一歩でもあると考える。
いずれにしても、喫緊の教育課題解決に向けてスピード感を持って取り組んでいくためには、従来からの演繹的アプローチを打破し、文科省から教育の最前線への直接のチャネルを開拓し、施策を届けると共にニーズを直接吸い上げる視点も重要である。国、自治体、学校等の各アクターが同心円状につながり、ポリシーダイレクション等を共有しつつ、助け合い刺激し合いながら、最適値を求める姿に一日も早く転換する必要があると思っている。
さすがの慧眼と言うべきだろう。そして、過去に教育行政の組織に勤務していた身としては、耳の痛い話でもある。
とりわけ、「伝えると伝わるは違う」という言葉には、頷くとともに反省をするしかない。
「ネット・トラブル防止のための通知」
「校内で若手教員を育成するための事例集」
等々
私が関わっていたこれらの取組が、
「発出すること」=「伝える(た)」
になっていたことは否めない。
一方で、それが受け手に伝わっていたかどうかは、正直に言って心もとない。そもそも、伝わったかどうかの「見届け」を十分にしていないのだ。
そして、これは学校の教諭や管理職を務めていたときの取組にも当てはまるように思う。
たとえば、懇談会や学校説明会などで、児童指導上の喫緊の課題について伝えていた。しかし、そこに出席している保護者の大半は「この話を聞かなくても大丈夫」な人たちであって、本当に聞いてほしい相手はその場にいないことが多かった。
では、どうすればよいのか。
「多様なチャネルを使う」
「個別に対応する」
ぐらいしか思い浮かばない。
おそらく、特効薬はない。やろうとすれば、これまでとは比べものにならないような時間と労力を要することだろう。
だが、本当に「伝わる」ことが必要な内容であるのならば、そうするしかないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
