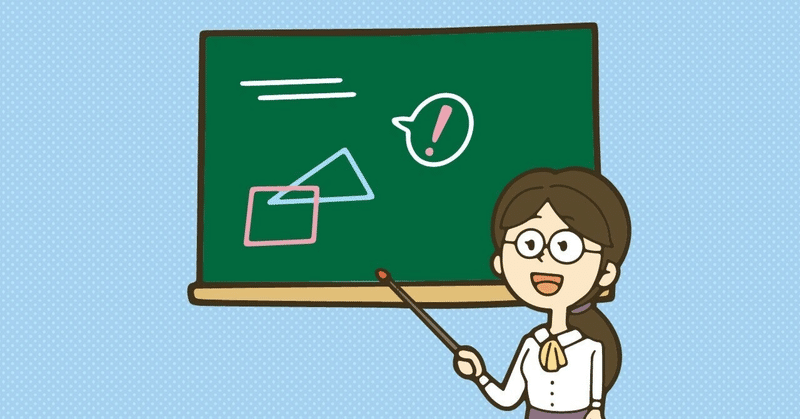
教師にとっての「2年目」
「この1年間は本当に大変でした。2年目になると、少しは楽になるんでしょうか?」
学年末を迎えるこの時期になると、昨年4月に採用された初任の教師たちからこのように質問されることが多い。
この質問に答えることは、なかなか難しい。もちろん、1年目の経験を生かして2年目に大きく成長する教師たちは間違いなく存在する。
けれども、その一方で「1年目はクラスの子どもたちとの関係もうまくいっていて、同僚や保護者からの評判も上々だったのに、2年目になったら学級崩壊を起こしてしまった」といった話を聞くことも珍しくない。
一般的に、教師の1年目と2年目には次のような違いがあると言えるだろう。
まず、1年目の教師に対しては、学校内外での研修や、初任者指導教員の配置などの制度上のサポートがある。しかし、サポートはそればかりではない。
通常、初任者が担任を受け持つ場合、対応が難しい子どもや保護者がいるクラスはベテランや中堅の教師が担当し、初任者は比較的「楽な」クラスを任されるなどの人事的な配慮があるものだ。ちなみに、これは初任者に対する配慮であるとともに、経験の浅い教師に難しいクラスを任せて大きなトラブルが生じることを防ぐためのリスク・マネジメントでもある。
また、校務分掌と呼ばれる校内での業務分担についても、1年目は軽減されていたり、ベテランや中堅教師の補助に回ったりすることが多い。
しかし2年目になると、こうした特別扱いはほとんどなくなってしまう。
そして、「まだ1年目だから」という周囲の温かい視線も、「もう2年目なんだから」という乾いたものに変わっていくのだ。
2年目になると、こうした1年遅れの「リアリティショック」を経験するケースが少なくないように思う。
それでも、この1年間の経験は大きい。
苦しいことや失敗もあっただろうが、それを乗り越えて経験値は確実に上がっているはずだ。
そして、「この時期までには、これとこれをやって」と、見通しをもって計画をしたり、逆算して考えたりできるようになることは、2年目の教師がもつアドバンテージだろう。
昨年4月に採用された初任の教師たちには、ぜひ2年目を飛躍の年にしてもらいたいものだ。
まずは、年度末の事務仕事などを全て片付けることが先だけれども。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
