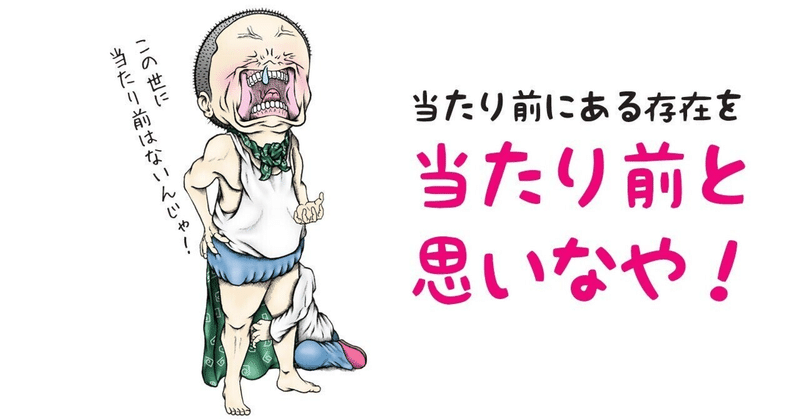
【経済ニュース振り返り】10/10~10/14
注目決済指標
・米国 9月 FOMC議事録
【ワシントン=高見浩輔】米連邦準備理事会(FRB)は12日、9月20~21日に開いた米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨を公開した。世界経済の悪化懸念が高まるなかでも、多くの参加者が「金融引き締めが甘すぎるのと厳しすぎるのでは、前者の方がコストが高くなる」と強調。高インフレの長期化を回避するための追加利上げに強い意志を示した。この会合では3回連続となる0.75%の利上げを決定。短期金利の指標であるフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標は3.0~3.25%となり、同時に発表した経済見通しでは政策金利見通しの中央値が22年末に4.4%、23年末に4.6%となった。次回の11月会合でも0.75%の利上げが有力視されている。
・米国 09月 消費者物価指数(CPI)
米労働省が13日発表した9月の消費者物価指数(CPI)は前年同月より8・2%上昇した。事前の市場予想(8・1%上昇)を上回った。伸びは3カ月連続で減速したものの、なお高水準を維持し、米国の激しい物価高(インフレ)は収まっていない。
・米国 09月 小売売上高
米国商務省によると、9月の小売売上高(季節調整値)は前月比0.7%増の6,254億ドルと、2カ月連続の増加となった。ブルームバーグがまとめた市場予想の0.2%減を上回った。なお、8月の売上高は0.7%増(速報値)から0.9%増に上方修正した。BMOキャピタル・マーケッツのシニアエコノミスト、サル・グアティエリ氏は「堅調な小売売上高は、個人消費の回復力と価格上昇の両方を反映している」とした。「現在の主な懸念は、サプライチェーンの混乱や半導体の不足が拡大していることにより、(消費者の)選択肢が制限され、商品の需要が抑制されているようにみえることだ」と指摘した
来週の注目決済指標
・米国 09月 鉱工業生産指数
・米国 10月 フィラデルフィア連銀景況指数
・米国 09月 中古住宅販売件数
原油価格の動向
週間では、約8ドルの減少。
米国の消費者物価指数が前年同月より上昇した結果を受け、世界的な景気後退(リセッション)リスクの高まりと、中国での新型コロナウイルス規制強化による燃料需要への打撃が懸念され、原油価格下落の結果を招きました。
先週のOPECによる原油減産の決定から、価格を上昇させてましたが、前回高値を超えることなく、反落する形になりました。

・気になった原油関連記事
[カイロ 13日 ロイター] - サウジアラビアは13日、同国が盟主である石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国で構成するOPECプラスの大幅減産が政治的決定だとする批判について「事実に基づいていない」と反論した。米政府が再び反発して応酬となり、両国関係の冷え込みがさらに鮮明になった。バイデン米大統領は記者団に、この問題についてサウジ側と近く協議すると述べた。サウジ外務省は声明で、減産は需給のバランスを考慮しコンセンサスで決定し、市場のボラティリティー抑制も意図したとして、消費国と産油国双方の利益に沿っていると主張。匿名のサウジ当局者の発言を引用し、「純粋に経済的事情」で減産が決まったとした。10月5日の決定前に米国との協議で減産を1か月遅らせるよう求められたことにも言及。「あらゆる経済的分析に鑑み、減産を1か月先送りすれば経済上のマイナスの影響をもたらすと一連の対米協議で明確に伝えていた」とした。声明はサウジと米国の関係を「戦略的」と位置付け、相互の尊重が重要だとも強調した。減産決定後、米国側は「OPECプラスはロシアにくみしている」と厳しく非難。バイデン大統領は今週、決定によって米国とサウジの関係に「重大な結果」が生じることになると表明した。米政府内では減産決定によって11月の米中間選挙前にガソリン価格が上昇しかねないとの懸念が強まっている。米国家安全保障会議(NSC)のカービー戦略広報調整官は13日に声明で、サウジには生産目標を引き下げる根拠が市場で見当たらないとの分析結果を提示し、状況を見極めるために1カ月後に決定を持ち越すよう促したと説明。また、サウジ以外のOPEC加盟国はサウジの決定を支持するよう「強制された」と感じたと米国に伝えてきたと明かした。
米国債10年利回りの動向
ミシガン大発表の10月の期待インフレ率(暫定値)は、1年先が5.1%、5年先が2.9%で、いずれも9月の確報値(4.7%、2.7%)から上昇した。1年先期待インフレ率の上昇は、3月以来7カ月ぶり。前日発表の9月の米消費者物価指数(CPI)に続いて根強いインフレ圧力が確認され、米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレ抑制のために大幅利上げを続けるとの市場の見方を強めた。

米ドルの為替動向
今週のドル円相場(USDJPY)は、週初145.35で寄り付いた後、早々に週間安値145.17まで下落しました。しかし、心理的節目145.00をバックに下げ渋ると、①10/7に発表された米9月雇用統計の良好な結果や、②ブレイナードFRB副議長による「金融政策は暫くのあいだ制限的になる」とのタカ派的な発言、③政府・日銀が実弾介入に踏み切った9/22高値145.90を上抜けたことに伴う仕掛け的なドル買い・円売り、④146.00に観測されていたリバースノックアウトオプションのトリガーヒットに伴うオプション勢のストップBUY(ガンマ消失→ストップBUY)、⑤黒田日銀総裁による「2%の物価目標を持続的・安定的に達成するまで金融緩和を継続する必要がある」とのハト派的な発言、⑥米9月生産者物価指数(結果8.5%、予想8.4%)の市場予想を上回る結果、⑦ミネアポリス連銀カシュカリ総裁による「ドル高で米国のインフレ率が低下するだろう」とのドル高容認発言、⑧鈴木財務相による「水準ではなくボラティリティに注目」との円安容認とも受け止められる発言(急騰は認めないがボラティリティを伴わないじり高なら良いとの解釈が可能)、⑨米9月消費者物価指数(結果8.2%、予想8.1%、※前年比)および米9月消費者物価コア指数(結果6.6%。予想6.5%、※前年比)の市場予想を上回る結果、⑩上記①⑨を背景とした米FRBによるタカ派傾斜観測(次回11月FOMCでの75bp利上げを完全に織り込むと共に、一部で100bpの大幅利上げ観測も浮上)、⑪米金利上昇に伴うドル買い圧力(米10年債利回りは2008年10月以来、約14年ぶり高水準となる4.07%へ急上昇)、⑫米10月ミシガン大消費者信頼感指数(結果59.8、予想59.0)の良好な結果が支援材料となり、週末にかけて、1990年8月以来、約32年2ヵ月ぶり高値となる148.87まで急伸しました。引けにかけて小反落するも下値は堅く、本稿執筆時点(日本時間10/15午前4時45分現在)では、148.66前後で推移しております。

ドル円は9/22に記録した直近安値140.35(政府・日銀による実弾介入後に記録した安値)をボトムに反発に転じると、週末にかけて、1990年8月以来、約32年2ヵ月ぶり高値となる148.87まで急伸しました。この間、主要レジスタンスポイントを軒並み上抜けした他、強い買いシグナルを示唆する「一目均衡表三役好転」「強気のパーフェクトオーダー」「強気のバンドウォーク」「ダウ理論の上昇トレンド」の全てが成立するなど、テクニカル的に見て、地合いは「極めて強い」と判断できます。ファンダメンタルズ的に見ても、①米FRBによるタカ派傾斜観測(米9月雇用統計・米9月PPI・米9月CPIが軒並み市場予想を上回ったことで11月FOMC、12月FOMCでの連続75bp利上げを織り込む動き)や、②日銀による金融緩和の継続方針(黒田日銀総裁は米ワシントンで開催された国際金融協会の年次会合で「2%の物価目標を持続的・安定的に達成するまで金融緩和を継続する必要がある」と発言)、③上記①②を背景とした日米金融政策の方向性の違い(日米名目金利差拡大に伴うドル買い・円売り)、④本邦貿易赤字拡大に伴う構造的な円売り圧力、⑤米政府・米当局によるドル高容認スタンス(ミネアポリス連銀カシュカリ総裁による「ドル高で米国のインフレ率が低下するだろう」との発言)など、ドル高・円安トレンドの継続を連想させる材料が揃っています。政府・日銀による介入警戒感が引き続き上値を抑制する材料として意識されてはいるものの、今週は週初に記録した安値145.17から3.7円急伸しているにも係わらず為替介入が実施されなかったため、鈴木財務相による「水準ではなくボラティリティに注目」との発言や、松野官房長官による「過度な為替変動には適切な対応をとりたい」との発言に対する信頼性が失われつつあります(週に3.7円動いても、鈴木財務相や松野官房長官が言うところの「過度なボラティリティ」や「過度な相場変動」には当たらないことへの不信感→円売り安心感)。以上を踏まえ、当方ではドル円相場の続伸をメインシナリオとして予想いたします(先週予測した一時的なベア見通しをブル見通しへ再び変更)。尚、来週は複数の米経済指標(米10月NY連銀製造業景況指数、米9月鉱工業生産、米9月建設許可件数、米9月住宅着工件数、米ベージュブック、米10月フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米9月中古住宅販売件数、米9月景気先行指数)に加えて、多くの米当局者発言(ミネアポリス連銀カシュカリ総裁、シカゴ連銀エバンス総裁、セントルイス連銀ブラード総裁、ジェファーソンFRB理事、クックFRB理事、ボウマンFRB理事、NY連銀ウィリアムズ総裁)が予定されるなど、重要イベントが目白押しとなります。米経済指標の中では、住宅関連指標への注目度が高まっています。足元の住宅ローン金利の高騰を受けて、住宅指標がどのような数字を出してくるのか注意が必要でしょう。また、米当局者発言は、ブラックアウト期間に入る前の最終週となるため、今回の米雇用統計や米CPIの結果を踏まえて、市場に対してどのようなタカ派メッセージを送るのか注目されます。米経済指標が市場予想を上回るサプライズを見せる場合や、米当局者よりタカ派的なコメントが発せられる場合には、ドル円が150.00に向かって急伸する恐れもあるため、来週は政府・日銀による円安牽制・実弾介入を意識しつつも、日米金融政策格差を背景としたドル買い・円売りが続きそうです(万が一、円買い為替介入が入ったとしても、下がったところが絶好の押し目買い機会になる可能性あり)。
NYダウの動向
週間では約200ドルの微増。
米CPIの結果や金利の上昇とは裏腹に株価を上げる形になりました。13日には、短期筋の投資家による買い戻しが相場を押し上げ、日中値幅は1500ドル強と2020年3月以来の大きさを記録した。米景気の先行きに対する警戒感は底流にありながら、投資マネーの動向に振り回される展開となりました。

日経平均の動向
週間では約300円の上昇。
13日までは景気後退懸念などにより、価格を押し下げていましたが、13日米国市場の大幅上昇を受け、14日は大幅に値を上げる形になりました。
円安が進んでおり輸出企業に追い風があっても、米国市場の動きに気を付ける必要があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
