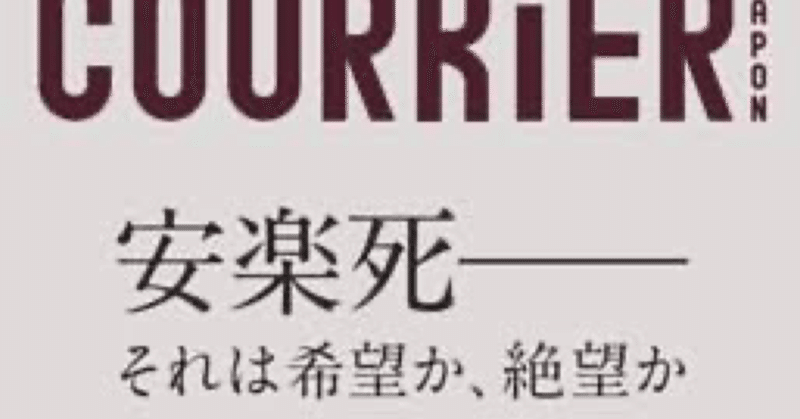
【死生観】安楽死について考えてみた
安楽死について特集している雑誌を読みました。本書は安楽死のことを当事者やその家族、医療従事者など様々な角度から取り上げていました。本noteはその雑誌の中から興味深いキーワードをピックアップして、私自身の考えをまとめたものになります。
安楽死を選ぶ動機は肉体的と言うよりも精神的苦痛の比重が高いことを意味している。
鬱や認知症、又は健常者であっても未来への不安が強くなると生きる活力が無くなってしまう。「令和2年中における自殺の概況」という厚生労働省出典の資料を確認してみた。自殺の原因には経済問題、健康問題、家庭問題、勤務問題、学校問題、男女問題と大きく大別され、その中でも1番割合が大きいのは健康問題だった。ただ単純に健康問題と言っても健康を害するまでのプロセスで色々なストレスの要因を抱えていると思うので、結局は家族や友人関係、仕事で上手くいっていないケースが多いのではないかと思う。
私をあなたの自殺に巻き込むのはやめて下さい。
自殺は大勢の人を巻き込む。親族や遺体発見者。場所が家なら大家さんや土地の所有者、外なら公共機関。場所がどこであれ警察や救急などの対応をする方達。
自殺をしてしまう人から見れば、大勢の人を巻き込むとか、もうそんなのどうでもいいのだろうが、社会的に見れば自殺者が出てしまうことそのものが問題であり、それによる経済的損失は大きい。
自殺者が出ない皆幸せな世の中は作れるのか。気になったので諸外国の自殺率(総死亡者数を自殺者数で割った数字)を調べてみたのだが、自殺率が0.5以下の国は一応あった。だがいずれも発展途上国であり、それらの国の経済が一気に発展した後、その水準を保てるかは正直微妙だろうとも思った。
少なくとも自殺者が出ることを今の社会で実現することが困難であるなら、安楽死を認めてしまっても良いのではと思う。
安楽死が他の医療行為として大きく異なる点は医療行為後に、それは果たして成功だったのか否かを、患者と一緒に評価できないことだ。
安楽死を選択していなかったら、いつかその患者の容態は好転していたのかもしれない。医療従事者も安楽死を行うのは辛い決断。当事者以外の人たち、例えば家族や医療従事者など安楽死が1番良い判断であると全員から合意を取るのは難しいと思う。安楽死が法的に認められたとして実行する決断を誰が下すのが良いのだろうか。
安楽死が認められているスイスでは「治る見込みのない病気」「耐え難い苦痛や障害がある」「健全な判断能力を有する」という条件があるとのこと。スイスでは医者から薬を投じる「積極的安楽死」は禁止されている。認められているのは処方された致死薬を患者本人が体内に取り込んで死亡する「自殺ほう助」だ。
人の人生の終わりをいつにすべきか、そのことを決める権限はどんな医者にもないはずですよ。
病状を一番理解している医療従事者でも患者の安楽死を決める権利は無い。むしろ別の観点から見れば医療行為が中断するということは、病院の売上も減るということなので積極的に安楽死の提案を医療従事者側からかしにくいと思う。家族の視点からでいうと、絶対に治る見込みがないと診断されたとしても、はたまた介護に負担がかかってしまうからだとしても、他人が安楽死を決めるのは殺人と同義になる。やはり安楽死を決めるのは自分自身であるべきだし、そしてそれを他人が止める権利は無いように思える。
死への願望が体が病気になる前からあるんです。肉体的な苦痛を訴えて安楽死を要請するのですが、本当の理由はもっと根深いわけです。
安楽死が法的に認められたとしても、ちょっとした人生の挫折で簡単に死を選んでしまう人たちが増えてしまうかもしれない。安楽死が認められている国で生活をしている人たちの死生観がどういうものかは分からないが、少なくとも安楽死が認められる基準はある程度線引きしないといけないのだろう。ただそうなると突発的な自殺の数は減らせなくなる。自殺者の数を減らすためには安楽死を合法化するのではなく別の手段が必要だろう。
末期の肺がん患者が安楽死を要請したのに医師に認められなかったといって憤る人がいる。そうした人が医師に断られた後に自殺するかというと、そうでもない。自分で毒を飲むのも点滴を注入することも嫌がるのだ。
死を受け入れるのはものすごい覚悟がいるのだろう。もしくは死ぬ間際に苦しみが待っているのが怖いのかもしれない。楽に死ねるのか、楽に死ねないのか、この差はかなり大きいと思う。
誰にも自殺を手伝ってもらうことはできないの。でないと殺人になってしまうから。私は自分でやらなきゃいけない。だから自分が何をしているのか分かっていると感じられるうちにやらなきゃいけないの。
例えば精神疾患の患者が安楽死を決断するには末期症状になる前に決断する必要がある。だが症状が重症化しない内は治癒する可能性に縋りたくなるし、重症化してしまった後では正常な自己判断が出来なくなる。これはかなり忌々しいジレンマである。
例えば筆者は精神疾患が重症化まで進行してしまったら家族側から安楽死を提案してほしいと思っている。何故ならそれはもう別人みたいなものだし残された側の経済的、精神的負担になってしまうのが嫌だからだ。逆も然りなのだが、実際に両親が精神疾患になったとしてそんな判断が下せるだろうか。また前項で記載したとおり安楽死は他人が決めるものではないと思う。それは同意なのだが精神疾患や植物人間状態などは例外として考えたいとは思う。
クライアントは「耐えがたく、我慢できない」苦痛を経験してる限り、末期患者である必要も近い将来死ぬ状況にある必要もない。
人は耐え難い激痛か死を選べと言われたら死を選ぶ人が多いと思う。安楽死を決める基準に関して、末期症状が必須条件でなくてもいいと思うが、その痛みを無くしてやるならば、安楽死を承認、実行するまでのスピード感は大事だろう。
スイスでは自殺ほう助が認められるまでに数ヶ月間は要するとのこと。この受理までのプロセスやスピード感も議論の余地が残るとこだろう。
欲深い親族や行き詰まった家族が患者に自殺を勧めないだろうか。周囲を思いやる患者が愛するものの預金や忍耐を使い果たす前に「死ななくては」と思わないだろうか。
安楽死が法的に認められた後、死を選べる様になった分色んな画策が生まれてしまうかもしれない。生命保険狙いの親族が現れたり、介護から解放されたいあまり安楽死を仄めかしてしまったり。だが1番不幸なのは生きる意志がまだある患者が、周りのプレッシャーに負けてしまい安楽死を選択してしまうことだと思う。生きる意味を問いただす幸福論の哲学なんかを義務教育で必修にすれば少しは自制心を保ちやすくなるのだろうか。
私が感じていることを理解するのは難しいと思う。なぜならあなたが目にしている私も、耳にしている私の話も本物ではないから。これはフェイクよ。私は装っているの。
認知症患者など精神疾患の患者を病前の本人と同一人物として扱うかどうか。倫理的な問題もあるだろうが、筆者自身は同一人物として扱ってもらわなくて大丈夫という考えだ。出来れば死に際は美しい思い出だけで終わりたい。最後の最後に迷惑や心配をかけて嫌われたくない。そうなってしまうのならば傷が浅いうちに葬ってほしいと思う。
手足の自由は効かなくなり、力は無くなり、おそらくは失禁し目も見えなくなります。肉体的な衰退がある段階に達したら、もう尊厳は無いのだと自分に言って効かせる必要があるということです。
老衰後の生きる尊厳について考えさせられる。特に重い病にかかっていなくても介護がないと生活出来ないレベルまで衰弱してしまった時点で安楽死を決断してもいいと思う。ましてや孤独死になってしまうよりも遥かにマシだ。寿命を全うすること。死の間際まで自分だけの力で生活することができているのであれば素晴らしいことだが、周りに迷惑をかけることになってしまう時点で筆者は安楽死を選びたい。
感想・まとめ
この記事は「COURRiER Japon」2021年11月号の雑誌の内容から知見を得て作成しました。印象的なキーワードを引用し感想や意見を述べたものになります。
いろんな角度から安楽死のことを考えてみた結果、自分は安楽死賛成派です。ぜひ日本でも実装してほしいと思いました。法的な線引きや日本人の文化に合った倫理観など様々な課題をクリアしないと施行できないでしょうが、いざ自分が重篤化したときに安楽死の選択肢が合った方が良いです。精神疾患系の病気だけ家族と話し合う必要があると感じました。自分がなった時はもちろん安楽死を選びますが、家族がなった時にも安楽死を選んでほしいです。なんなら正常な判断が出来なくなっているとしたら、自分から安楽死させたいとも思います。死に際の思い出は美しく終わらせたいし、双方が負担になることは幸せの形ではないと思うからです。これはあくまでも私の意見、感想であり世間に同調を求めるものではありませんが、各個人の人生の権利の中で死を選べるというのは至極健全な世の中であると思います。死生観は人それぞれ違うだろうし、いざ病にかかってから変化することもあるでしょう。その時にどんな選択をしようがその人の考えが尊重されるべきですが、人権として死を選べるというのは有りだと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
