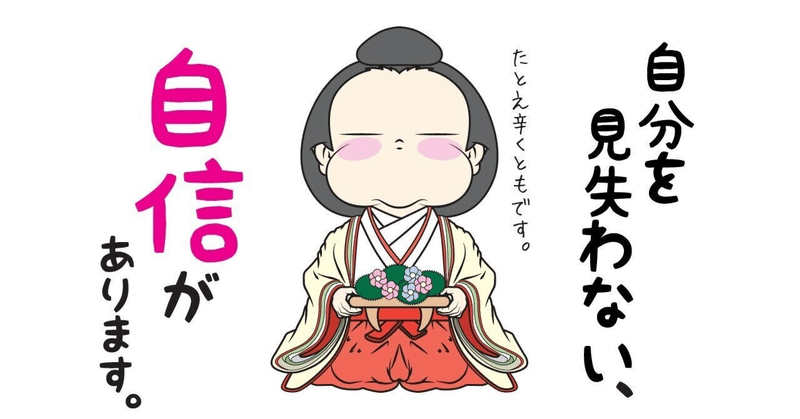
【経済ニュース振り返り】10/17~10/21
注目決済指標
・米国 09月 鉱工業生産指数
9月の米鉱工業生産指数は前月比で0.4%上昇した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は0.1%上昇だった。前月は0.1%低下(速報値0.2%低下)に上方修正された。9月の製造業の生産指数は0.4%上昇。市場予想は0.3%上昇だった。前月は0.4%上昇(速報値0.1%上昇)に上方修正された。
・米国 10月 フィラデルフィア連銀景況指数
米フィラデルフィア地区連銀が20日発表した10月の連銀業況指数はマイナス8.7と前月のマイナス9.9から小幅に改善した。ただ、マイナス圏に沈んだのは過去5カ月で4回目。市場予想はマイナス5.0だった。支払価格指数は29.8から36.3に上昇。新規受注指数はマイナス17.6からマイナス15.9に、従業員数指数も12.0から28.5に上昇したものの、6カ月予測はマイナス3.9からマイナス14.9に落ち込んだ。設備投資の6カ月予測は4.4。9月は4.6だった。
今月、活動が全般的に低下したと報告した企業は全体の約24%、活動が活発化したと答えた企業は15%だった。過半数の企業は活動は先月と同様とした。また、工場経営者から雇用とインフレの圧力が高まっているとの声が聞かれたほか、今後6カ月の活動が低下することが見込まれているとした。
今後6カ月の設備投資に関しては削減するよりも増加させると回答した企業が多かった一方、設備投資を削減すると予想する企業の割合が増加すると予想する企業を上回ったのは6業種中4業種となった。
・米国 09月 中古住宅販売件数
全米リアルター協会(NAR)が20日発表した9月の米中古住宅販売戸数(季節調整済み)は年率換算で前月比1.5%減の471万戸となった。減少は8カ月連続で、住宅ローン金利急上昇と住宅価格の高止まりによって住宅取得が困難となる中、コロナ禍初期の2020年春の低迷を除き、12年9月以来の低水準となった。販売価格中央値は前年同月比8.4%上昇の38万4800ドル。在庫は前年同月比0.8%減の125万戸。
ジェフリーズのチーフ金融エコノミスト、アネタ・マルコフスカ氏は「住宅市場がもはや売り手市場ではないことが示唆された」とし、「パワーバランスが売り手から買い手にようやくシフトしつつある」とした。
来週の注目決済指標
・米国 10月 製造業PMI
・欧州 10月 ECB政策金利
・米国 第3四半期 実質GDP
原油価格の動向
週間では約1ドルの微減。
供給不足に対する警戒感と需要減退予測が交錯しており、上げ下げの方向感が出ない1週間になりました。週足も上ヒゲ、下ヒゲがともに伸びているような形です。

・気になった原油関連記事
[ワシントン 19日 ロイター] - バイデン米大統領は19日、年内に戦略石油備蓄(SPR)から1500万バレルを追加放出し、備蓄の補充を開始する計画を発表した。米中間選挙が11月8日に迫る中、ガソリン価格抑制に取り組む構えを鮮明にした。計画では、石油価格の高騰を防ぐために十分な供給量を確保すると同時に、価格が過度に急落するような場合には、政府が買い手として市場に介入する。バイデン大統領は「他国の行動によって変動が引き起こされている時期に、われわれは引き続き市場を安定させ、価格を押し下げる」と言明した。バイデン氏は、ロシアのプーチン大統領によるウクライナ侵攻が原油とガソリンの価格上昇につながったと非難。価格が今年初めのピーク時から30%下落したとしつつも、価格は「十分に速いペースでは下落していない」とし、「ガソリン価格は家計を圧迫している」と述べた。石油輸出国機構(OPEC)とロシアなど非加盟産油国で構成する「OPECプラス」が今月、日量200万バレル減産で合意したことで、ガソリン価格高騰に拍車がかかるという懸念も出ていた。1500万バレルの売却は、今年5月に開始した1億8000万バレルのSPR放出の一環。政府は当初、11月に放出枠からの売却を終える予定だったが、夏場に石油各社による買い付けが予想より鈍り、1500万バレル程度が未売却のままとなっている。政権高官によると、未売却分は12月に引き渡せるよう入札にかけられる見通し。バイデン氏は、価格抑制のため来年早期にも追加放出を行う用意があると述べた。米政府の現在の備蓄量は4億バレル強で、1984年以来の低水準にある。バイデン氏は「緊急に取り崩しが必要になっても十分だ」と述べた。今後数年間で備蓄を補充する方針も示した。ホワイトハウスによると、原油価格が1バレル=67─72ドル以下に下落した際に、政府が購入に動く見通しという。バイデン氏は、政府が買い戻しを表明することで、石油会社は安心して生産への投資を行うことができるはずだと指摘。「石油会社は記録的な利益を上げている。われわれは確実性を提供しており、石油会社は増産に向けてすぐに行動することが可能だ」と述べた。
米国債10年利回りの動向
週末21日のニューヨーク金融・債券市場では、米利上げペース鈍化への期待から全体としては債券買いが優勢となり、長期金利は小幅低下した。長期金利の指標である10年物米国債利回り(終盤)は前日比0.01%ポイント低下の4.22%となった。10年債利回りは朝方、2007年11月以来約15年ぶりの高水準となる4.34%を付けたが、その後下げに転じた。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが、連邦準備制度理事会(FRB)が11月の金融政策会合で0.75%の大幅利上げを決めると同時に、次回12月の会合での利上げ幅縮小の可否についても、11月会合で議論する可能性があると報道。サンフランシスコ連銀のデイリー総裁も、利上げ幅縮小についての議論を始める必要があると発言した。
これらの報道や発言を手掛かりに債券買いが広がり、利回りは中盤に4.20%まで低下。その後は週末を控えて動意が弱まり、4.21%近辺で小動きに転じた。

米ドルの為替動向
今週のドル円相場(USDJPY)は、週初148.45で寄り付いた後、①政府・日銀による度重なる円安牽制や実弾介入を経ても尚「円売り地合い」が止まらないことに対する失望感や、②黒田日銀総裁による衆院予算委員会での「金融緩和を継続することが適切」とのハト派的な発言、③本邦個人投資家によるキャリートレードの活発化(外国為替証拠金取引におけるドル円売買額が9月に単月ベースで史上最多となる1000兆円を突破)、④本邦輸入企業による実需のドル買い、⑤米経済指標の良好な結果(米9月鉱工業生産、米9月設備稼働率、米9月建設許可件数、米新規失業保険申請件数、米9月中古住宅販売件数など)、⑥米当局者によるタカ派的な発言(ミネアポリス連銀カシュカリ総裁による「基調インフレがピークアウトしたとの確証を得られるまで利上げを一時停止する用意はない」との発言や、フィラデルフィア連銀ハーカー総裁による「年末までに金利は4%を大きく上回る」との発言、クックFRB理事による「インフレは依然として容認できないほど高い」との発言など)、⑦上記⑥を背景とした米長期金利の急上昇(米10年債利回りは2007年以来となる4.33%へ急上昇)、⑧心理的節目150.00突破に伴う仕掛け的なドル買い・円売りが支援材料となり、週末にかけて、週間高値151.95(1990年7月以来、約32年ぶり高値圏)へと急伸しました。もっとも、買い一巡後に伸び悩むと、⑨米ウォールストリート・ジャーナル紙のニック記者(Fedウォッチャー)による「次回11月FOMCで75bpの利上げを決定し、その次の12月FOMCで50bpに利上げペースを鈍化させるか否かの議論を行う公算が大きい」「一部のFRBメンバは過度な景気悪化を警戒し利上げペースの減速や来年早々の利上げ停止を求めている」とのハト派的な発言や、⑩サンフランシスコ連銀デイリー総裁による「利上げペースを落とす時期が近づいている可能性がある」とのハト派的な発言、⑪上記⑨⑩を背景とした米長期金利の急低下(米10年債利回りは4.33%から4.20%へ急低下)、⑫政府・日銀による覆面介入実施の思惑が重石となり、週末海外時間には、週間安値146.23まで急落する場面も見られました。引けにかけて持ち直すも戻りは鈍く、本稿執筆時点(日本時間10/22午前5時00分現在)では、147.50前後で推移しております。

ドル円は9/22に記録した直近安値140.35をボトムに反発に転じると、週末にかけて、1990年7月以来、約32年3ヵ月ぶり高値となる151.95まで急伸しましたが、週末海外時間には一転して146.23まで急落する荒々しい値動きとなりました。但し、急落しても尚、強い買いシグナルを示唆する「一目均衡表三役好転」「強気のパーフェクトオーダー」「ダウ理論の上昇トレンド」が成立しているため、テクニカル的に見て、ここからの更なる下落は容易では無い(下値余地は限定的)と判断できます。また、ファンダメンタルズ的に見ても、①米FRBによるタカ派傾斜観測(次回11月FOMCでの75bp利上げを94.5%織り込むと共に、12月FOMCでの75bp利上げも45.4%程度織り込む動き→米10年債利回りは約14年ぶり高水準を記録)や、②日銀による金融緩和の継続方針(黒田日銀総裁は先週の国際金融協会年次会合や、今週の衆院予算委員会で金融緩和の継続方針を再度強調)、③上記①②を背景とした日米金融政策の方向性の違い(日米名目金利差拡大に着目したキャリートレードの活発化。日米10年債利回りスプレッドは400bp超の水準まで急拡大)、④本邦貿易赤字拡大に伴う構造的な円売り圧力、⑤米政府・米当局によるドル高容認スタンス(バイデン米大統領による「ドル高を懸念していない。米国経済は力強い」と発言→国際協調介入の可能性が消失→単独介入のみでドル円上昇を食い止めることは難しいとの見方)、⑥本邦輸入企業による実需のドル買いなど、ドル高・円安トレンドの継続を連想させる材料が揃っています。米ウォールストリート・ジャーナル紙のニック記者によるハト派的な発言や、タカ派と目されていたサンフランシスコ連銀デイリー総裁によるサプライズ的なハト派発言、政府・日銀による覆面介入実施の思惑を背景に、ドル円は151.95から146.23へと急落しましたが、一巡後は上記テクニカル要因・ファンダメンタルズ要因に沿った動きに戻ると見られ、当方では引き続き、ドル円相場の上昇をメインシナリオとして予想いたします(円買い為替介入でドル円相場が押し下げられる局面は絶好の買い場になると判断。来週はブラックアウト期間突入で米当局者発言が予定されていないため、米ドル主導の下落も想定しづらく、結果としてドル円は自律反発に向かうと整理)。尚、来週は日銀金融政策決定会合が予定されているものの、前回会合時に黒田総裁が「2・3年は変更が無い」と発言しているため、今回も金融政策の現状維持が決定されると考えられます(フォワードガイダンス修正などのサプライズは無いと予想)。それ以外には、米10月カンファレンスボード消費者信頼感指数や、米9月新築住宅販売件数、米第3四半期GDP速報値、米9月耐久財受注、米10月ミシガン大消費者信頼感指数などに注目が集まりそうです。米長期金利や政府・日銀による介入警戒感に振らされながらも、じりじりと値を戻すシナリオを想定いたします。
NYダウの動向
週間では約1000ドルの上昇。
米連邦準備制度理事会(FRB)が利上げのペースを緩める可能性について議論していると報じられた影響を受け、約15年ぶりに4・3%台まで上昇していた米長期金利が低下し、景気後退への懸念が和らいだのを影響に、週末に大きく株価が上昇したものと思われます。

日経平均の動向
日経平均は約100円の微増。
米国の株安を受けて、低調な値動きでしたが、週末の大きな上昇につられて、週明けは大きく上昇することが予想されます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
