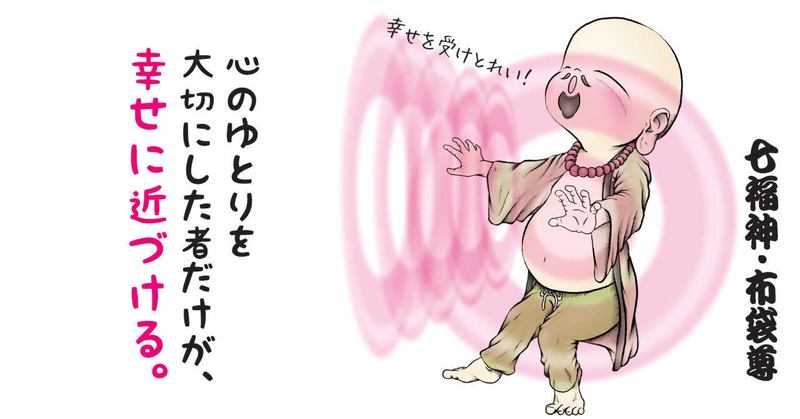
【経済ニュース振り返り】10/31~11/4
注目経済指標
・欧州 第3四半期 ユーロ圏GDP
欧州連合(EU)統計局が31日発表した第3・四半期のユーロ圏域内総生産(GDP)速報値は、前期比0.2%増と、ロイターのエコノミスト予想通りに大幅に減速した。今後数四半期でユーロ圏がリセッション(景気後退)に陥る可能性が示された。
・米国 10月 ISM製造業景気指数
米供給管理協会(ISM)が1日発表した10月の製造業総合指数(NMI)は50.2となり、2020年5月以来、約2年半ぶりの低水準となった。9月の50.9から低下した。投入価格指数が7カ月連続で低下した。米連邦準備理事会(FRB)の利上げにより財(モノ)の需要が冷え込んだ。
・米国 11月 FRB政策金利
米国連邦準備制度理事会(FRB)は11月1、2日に連邦公開市場委員会(FOMC)を開催し、政策金利であるフェデラル・ファンド(FF)金利の現状の誘導目標3.00~3.25%を0.75ポイント引き上げ、3.75~4.00%とすることを決定した(添付資料図参照)。4会合連続で通常の3倍となる0.75ポイントの引き上げ幅となった。今回の決定は参加者12人の全会一致だった。
・米国 10月 失業率
10月は比較的幅広い業種で雇用が増加。特に医療やプロフェッショナル・ビジネスサービス、製造業などで伸びが目立った。平均時給は前月比0.4%増と、前月(0.3%増)から伸びが加速。市場予想は0.3%増だった。前年同月比では4.7%増加した。今回の雇用統計は、速いペースでの利上げや景気見通し悪化にもかかわらず労働者に対する需要が引き続き強いことを示唆している。レイオフは増えつつあるものの歴史的に見ればなお低水準で、極めて高水準の求人件数を背景とした人材獲得競争が賃金を押し上げている。こうした状況は、経済のエンジンである個人消費を支える上でプラスに働く一方、インフレ沈静化を目指す金融当局の取り組みを一層困難にさせ、この先何カ月にもわたり断固とした引き締めを継続することが示唆される。
来週の注目経済指標
・米国 10月 消費者物価指数(CPI)
原油価格の動向
週間では約4ドルの上昇。
11月4日、米国時間の原油先物は上昇。米連邦準備理事会(FRB)による利上げの先行きが不透明な中、欧州連合(EU)によるロシア産原油の禁輸措置導入が12月に迫っていることや、中国が新型コロナウイルス感染対策を一部緩和するとの観測が相場を支えた。

・気になった原油関連記事
[ブリュッセル 4日 ロイター] - 米国務省のオブライエン制裁調整官は4日、主要7カ国(G7)が決定したロシア産石油に上限価格を設ける措置について、なお多くの詳細を詰める必要があるものの、導入される12月5日までに運用上の詳細は全て整う見通しという認識を示した。オブライエン制裁調整官は訪問先のブリュッセルで、価格の上限設定やガバナンスに関する技術的な協議が続いているとした上で、「重要な日程は12月5日だ。価格上限はすでに十分に長く議論されてきているため、市場参加者は理解し、導入に向けた最善の方策について意見を出している」と語った。それ以上の詳細には踏み込まなかったものの、「12月5日までに確実に準備は整うだろう」とし、保険・輸送会社などが示している懸念にも対処できる見通しと述べた。
米国債10年利回りの動向
週間では約1.3ポイントの上昇。
週末4日のニューヨーク金融・債券市場は、米金融政策の先行きに対する思惑から売り買いが交錯し、長期金利は前日比横ばいだった。長期金利の指標である10年物米国債利回り(終盤)は横ばいの4.16%となった。米労働省が朝方発表した10月の雇用統計は、非農業部門の就業者数が前月から26万1000人増となり、市場予想を上回った。平均時給も上昇が続き、インフレ圧力が続いている状況を示した。債券市場では、堅調な労働市場を受け、米連邦準備制度理事会(FRB)が利上げを継続するとの見方が強まり、債券を売る動きが強まり、10年物国債利回りは一時4.2%台に上昇した。

米ドルの為替動向
今週のドル円相場(USDJPY)は、週初147.76で寄り付いた後、米ウォールストリート・ジャーナル紙のニック記者による「米FRBのターミナルレートが予想よりも高くなる可能性がある(the peak or “terminal” policy rate may be higher than expected)」とのタカ派的なツイートや、米金利上昇に伴うドル買い圧力、米FOMCを控えたポジション調整が支援材料となり、週明け早々に、週間高値148.86まで上昇しました。しかし、買い一巡後に伸び悩むと、米経済指標(10月シカゴ購買部協会景気指数や、米10月ダラス連銀製造業活動指数)の冴えない結果や、本邦輸出企業の月末・月初のドル売り圧力、豪中銀ロウ総裁による「中銀は必要に応じて利上げペースを調整する用意がある」とのハト派的な発言(世界的な利上げペース鈍化期待)、米金利低下に伴うドル売り圧力、黒田日銀総裁による「物価安定目標(2%)の実現が見通せるような状況になったときには、イールドカーブコントロールの柔軟化が一つのオプションとしてあり得る」とのタカ派的な発言、米FOMC声明文における「将来の利上げペース決定にあたっては、これまでの金融引き締めの累積的な影響や、金融政策が経済活動やインフレに影響を与えるまでのタイムラグ、経済・金融情勢の変化を考慮するとの文言追加、パウエルFRB議長による「しばらくの間、制限的な政策スタンスが必要になるだろう」「利上げ減速の時期は早ければ次回会合となる可能性がある」とのハト派的な発言が重石となり、週央にかけて、週間安値145.68まで急落しました。もっとも、売り一巡後に下げ渋ると、パウエルFRB議長より「最終的な金利水準は従来の想定よりも高くなった」「利上げ停止を考えるのは非常に時期尚早」とのサプライズ的なタカ派発言が飛び出したことや、米金利上昇に伴うドル買い圧力(米10年債利回りは一時4.21%へ急上昇)、日米名目金利拡大に着目したキャリートレードの活発化、短期筋のショートカバーが支援材料となり、週後半にかけて一時148円台半ばまで反発する動きとなりました。しかし、週末にかけては一転、米10月失業率の悪化に端を発したドル買いポジションのアンワインド(米金利低下→ドル買い圧力後退→週末前のポジション調整誘発)や、短期筋のロスカットが重石となり、146円台後半での越週。

ドル円は10/21に記録した約32年ぶり高値151.95(1990年7月以来の高値圏)をトップに反落に転じると、10/27に約3週間ぶり安値となる145.11まで急落しました。今週は一時148円台半ばを回復する場面も見られましたが、週末にかけて再び146円台へと押し返されるなど、上値の重い展開が続いております。ローソク足が主要テクニカルポイント(一目均衡表転換線や基準線、21日移動平均線やボリンジャーミッドバンド)を下抜けした他、強い買いシグナルを示唆する「一目均衡表三役好転」も消失するなど、テクニカル的に見て、地合いの悪化を印象付けるチャート形状となりつつあります。但し、ファンダメンタルズ的に見ると、日米金融政策の方向性の違い(今週はFOMC声明文への文言追加を通じて「利上げペース鈍化」に対する布石が打たれたものの、パウエルFRB議長は一方でターミナルレート引き上げの可能性に言及しており、トータルで見れば今回のFOMCはハト派的でもタカ派的でも無いニュートラルな状態→日米金融政策格差に着目したキャリートレードの優位性は不変)や、米政府・米当局者によるドル高容認姿勢、本邦貿易赤字拡大に伴う構造的な円売り圧力など、ドル高・円安トレンドの継続を連想させる材料が残っています(仮に米金利低下→米ドル売りの流れが強まるとしても、その場合は株高・リスクアセット上昇を通じて、リスク選好の円売りが意識されるため、ドル円の下値余地は限定的)。以上を踏まえ、当方では引き続き、ドル円相場の上昇をメインシナリオとして予想いたします。尚、来週は11/10に発表される米10月消費者物価指数に注目が集まります。特にコア指数への注目度が高く、前回に続き、40年ぶり高水準を更新するような事態となれば、米利上げペース鈍化期待が剥落し、米金利上昇→米ドル買い→ドル円急伸に繋がるシナリオが想定されます。また、来週は米当局者発言(ボストン連銀コリンズ総裁、クリーブランド連銀メスター総裁、リッチモンド連銀バーキン総裁、ニューヨーク連銀ウイリアムズ総裁、ウォラーFRB理事、ダラス連銀ローガン総裁、カンザスシティ連銀ジョージ総裁など)も相次ぐことから、米当局者のスタンス確認に注目が集まりそうです(11/8に予定されている米中間選挙は相場への影響は限定的と想定)。
NYダウの動向
週間では約300ドルの減少。
FOMCの金利引き上げのニュースなどを材料に、株安となる展開が続きました。反落しているとはいえ、前回の高値は少しブレイク。時間をかけて34000ドル台を目指せるか注目です。

日経平均の動向
週間では約200円の減少。
FOMCの発表前に大胆な動きには出れず、横ばいが続き、金利引き上げの材料を主に、週末は下げる展開になりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
