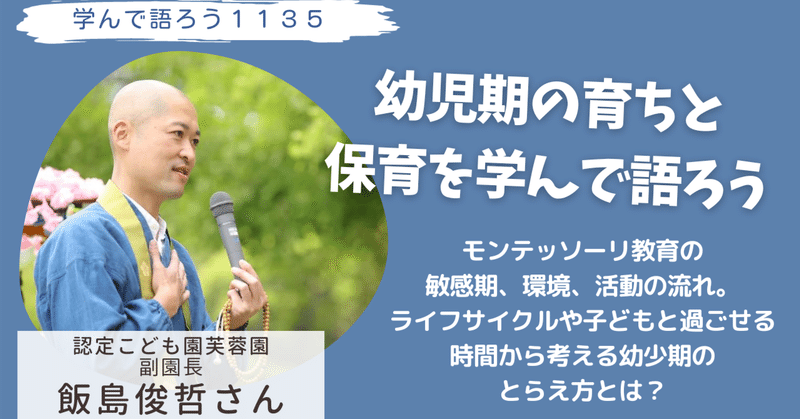
【文字起こし】小さな人たちとの生活とその援助〜学んで語ろう飯島俊哲さんお話し部分〜
2023/9/23に開催した「幼児期の育ちと保育を学んで語ろう」での、飯島さんのお話の動画を記事としてもまとめました!
(文章としてわかりやすくなるよう一部の表現を修正してあります。)
自己紹介
芙蓉園の副園長をしております、飯島俊哲と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
芙蓉園は、今は幼保連携型の認定こども園という施設形態をとっております。ちなみに芙蓉園には、海禅寺というお寺が併設されています。私こんな髪型(?笑)をしておりますが、芙蓉園では副園長ですけど、隣の海禅寺では副住職をしております。

3つの視点
今日は幼児期の育ちや保育を学んで語ろうということで、お話の起点としたいのは視野が広がる3つの視点というところで、虫の目と鳥の目と魚の目で子育てというものを見たらどうなるかなとお話をしてみたいと思います。

子育てにおける虫の目ってどういうことかなと考えると全身全霊で我が子とぐっと向き合う、もう本当に組み合うぐらいの感覚ですね。まさに皆さんのお家での日常はそうではないでしょうか。
モンテッソーリ教育とは
芙蓉園は「モンテッソーリ教育」という教育法を採用しております。
モンテッソーリ教育というのはイタリア人の女性で初めてお医者さんになったマリア・モンテッソーリという方が始めた教育法です。
医療的な視点で子どもの発達の観察をする中で見いだした教育メソッドですけれども、いろいろな特徴があるんですが、ひとつは子どもの育ちの中にある「敏感期」というものを見出しました。
これは子どもがある時期に、ある一定のものに異常なほど強い関心を持つ期間を指しています。
それから、モンテッソーリ教育の特徴の中でもう一つは、「環境」を通じて子どもの育ちを支えるという発想、「環境」を重視する考え方があります。
大事にしたいのは、何でも分かっている私たち大人が、未熟な子どもに全てを教え込むという発想ではなくて、子ども自身の成長発達する力や意志を信じて、それを支えていくということです。

視点①虫の目:「敏感期」と「環境」という考え方
子育ての中でよく語られる「遺伝」という概念。ともすると俺は頭悪いからうちの子はダメだなと思う人もいるかもしれませんが、モンテッソーリ教育ではそういうことはないと言っているんですね。環境的な要因で、人はどんな風にも育つことができる。だから子どもを取り巻く環境に心を砕きましょうよと、そんな考え方をしております。
また、周りの子どもと比べてうちの子は何か育ちが遅いとか思ったりするんですけど、人間も一つの生き物ですから、生き物の秩序の中で順番に育っていくものなんですね。人と比べるのではなくて、我が子の自分のペースがあるはず。
そして敏感期についても、必ずこの年齢になったらこうなるはずだということも一概に言えない場合があるので、その辺にも注意が必要です。
その上で敏感期という概念を知っていることで、子ども理解は深まります。
今、この会場内で泣いているお子さんいっぱいいますけれども、やっぱりこれはいつもと違うからだと思うんですね。「いつも同じ」ということに支えられて生活をしている赤ちゃんが熱望する日常の秩序感を求める敏感性が、今現在妨げられているから泣くことでその不快感を訴えているのだと思います。
スライドに「駄々をこねるには理由があります」と書いてありますけど、これも同じように敏感期のことで説明ができます。

子どもが夢中になれる活動の「流れ」
それから、これはモンテッソーリ教育で大切にしている一つですけれども、子どもが活動をする時に、全てこちらで与えてしまうのではなくて、選べるようにするといいと言われています。
それは自分で選んだ以上、子どもは夢中になって取り組みます。そこに没頭していく結果、集中して関わったり、楽しいから繰り返すとか、そういうある種の自分を高めていく、深めていく時間を持つことができます。そして活動の最後を、自分のペースで終わらせる。そのことは満足感にもつながりますし、自己肯定感を高めることにもなります。自分の自由で選んだ活動を、自分でしっかり完結していくこと。自由と責任をセットで伝えていくことが大事です。

敏感期の話をする時に、編み落としという言い方があります。
子どもは整えられた環境があれば、発達の段階を自らの力で進んで行くことができます。しかしそれを大人の思いや都合で無理に急かすことで、大切な段階を飛ばしてしまうかもしれないということです。
人として育っていく幼児期というのはその時にならないと、そうならないことってたくさんあるんです。なので、焦ることなく今の段階を味わうということが大事かなと思います。
視点②鳥の目:ライフサイクルから見る子育て
次に鳥の目ですね。どんな生命も始まりがあれば、必ず終わりが来るわけです。日常のモヤモヤした悩みというのが、この大きなライフサイクルという視点で見ることで、結構大目に見れることって多いんじゃないかなと思うんです。その時でしか味わえない色んな面白さとか人生の豊かさとか、そういうところを取りこぼさないようにできたらいいのかなと思います。
とはいえ、やはりご家庭だけで子育てってやっていると、どうしても苦しい時が絶対来る。そういう時に、こういう語り合える場があったり、今日の場合は保育園・幼稚園・認定こども園がテーマですけれども、そういった施設と一緒になって子育てをしていく。
ともかくいい意味で、楽しく面白がって子育てできたらいいんじゃないかなというふうに私は思っています。
生涯で我が子と過ごせる時間というデータがあります。
お母さんで時間を合計すると7年6ヶ月だそうです。お父さんで3年と4カ月しかないと言われています。
しかも保育園卒園までに32%、つまり小学校前で32%も終わり、高校卒業ではもう73%が終わってしまう。だから恐らく今が一番濃密に我が子と付き合える時なんですね。

視点③魚の目:流れを読んで、子どもに伴走し支える
最後の魚の目。流れを読んで未来を見通す。
目に見えない「流れ」に逆らった選択ってうまくいかないものだと思うんです。何かそういった流れを敏感に感じながら、あとは我が子の意志を確認しながら子育てしていくというのがここでのお話です。
一つの園を預からせてもらっている私の立場から一つ言いたいのは、上田市内、どの園も素晴らしい園だと思います。けれども、その園に預けられたらそれで全部オーケーということはないと思うんです。
やっぱりどこまで行っても子育ての主体者は親ですから、親である自分が何かこう我が子の全てを、しっかり虫の目で、鳥の目で、魚の目で見ながら子どもの歩みを支えていく、一緒に横を走っていく、みたいな感覚は大事かなと思います。

結局、親である私達も一人の人間であって、エゴで我が子をどこかで思い通りにしたい気持ちがあるんじゃないでしょうか。子育てはひょっとしたら親の趣味と都合だと言えるのではないかと思うんです。私自身も自分の趣味や都合で子育てしている部分が多分にあります。子どもの意志を尊重したいと思いながらも、例えば食べる物の嗜好が似るのは僕の食べている物の影響が多分にあるからでしょうし。
そういうことを考えると、やはり完璧はないので、そういった自分の危うさにも気付き認めつつ、それを許しつつ、でも立ち戻れる芯みたいなものを確認しながら色んな視点で子育てをしていけると幸せなのかなというふうに思います。
少々まとまらないお話でしたが、これで私の話を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

認定こども園芙蓉園 HP
海禅寺 HP instagram facebook

企画:1135信州
facebook、Instagramにイベント情報のせています!
#保育園見学 #幼児教育 #モンテッソーリ教育 #子育てのヒント #育児を楽しむ #認定こども園芙蓉園 #海禅寺
#1135信州 #上田で子育て #産前産後 #出産準備 #令和5年度上田市活力あるまちづくり支援金 #あったか産前産後応援事業
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
