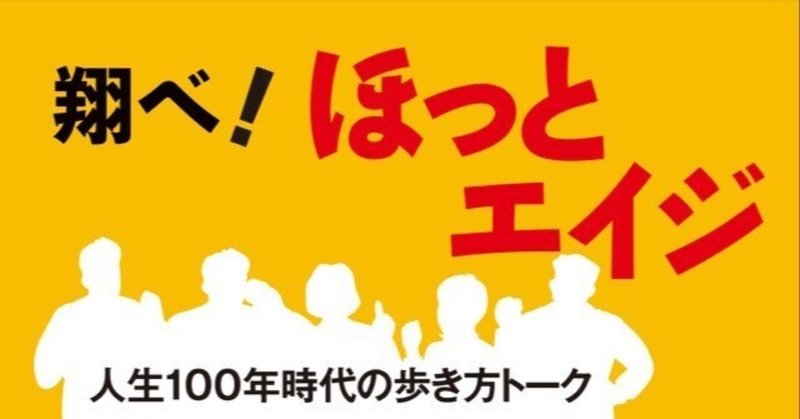最近の記事
マガジン
記事

第23回 ファクトチェック推進に尽力する弁護士の楊井人文さんに聞く(下)デマや不正確なニュースなどにだまされないためにはどうすればいいのか
今回のゲストも、ファクトチェックを自ら手掛けるとともに、ファクトチェックの普及・推進にも務めてきた楊井人文(やない・ひとふみ)さん。 私たちがデマや不正確なニュースなどにだまされないためにはどうすればいいのか。 楊井さんは「SNSの時代になって、昔は影響力を持たなかった無名な人たちのつぶやきさえ、一瞬で世界に広がるようになった。新しい技術によって、こういう現象が生まれた」とその背景を説明した上で、「不安だとか、憤りだとか、敵対心とか、そういったものが原動力になって、そ
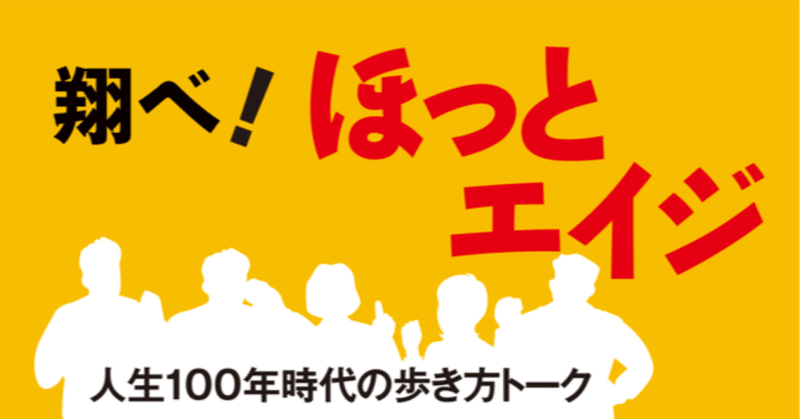
第22回 ファクトチェック推進に尽力する弁護士の楊井人文さんに聞く(上)ファクトチェックとは何か。どのようなルールでどんな分野で行われているか
今回のゲストは、ファクトチェックを自ら手掛けるとともに、ファクトチェックの普及・推進にも務めてきた楊井人文(やない・ひとふみ)さん。 楊井さんはファクトチェックの普及・推進活動を行う非営利団体であるファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)の発足から事務局長を務め、2023年6月に任期満了で退任。 「これからは、より自由な個人の立場でファクトチェックのあり方について考察や支援を行っていく」とのこと。 「ファクトチェックとは、ある情報が本当かどうかを一から調べ直すこと。一