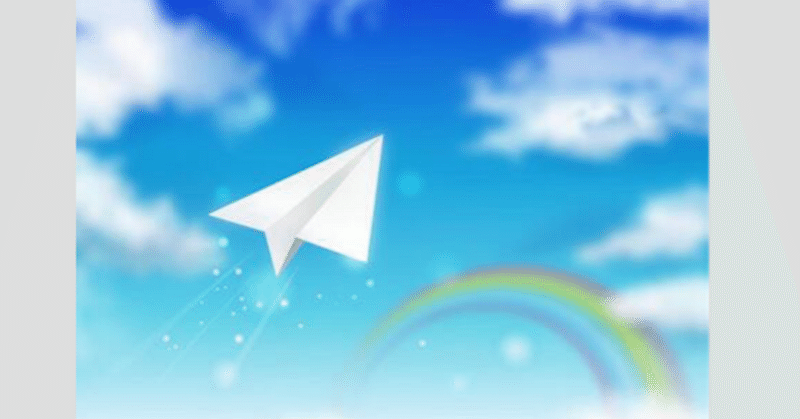
【創作大賞2024オールカテゴリー部門】【短編小説】紙ヒコーキの運んでくれた恋
あらすじ
窓に舞い込んできた、一機の紙ヒコーキ。二十年前に好きだった少女からの、恋の返信であった……
紙ヒコーキの運んでくれた恋
久しぶりに自室二階の窓を全開にすると、生暖かい春風が無邪気に流れ込み、淀んでいた冬の名残を蹴散らすかのようであった。
売れない密室の作家。つい気取って突っ張ってはみても、この所、さっぱりアイデアが浮かばない。お袋には散々嫌みを言われるし、若干とはいえその庇護を受けている甘ったれの身も、三十歳を過ぎたとあれば、そろそろ人生との折合いをつける潮時かも知れないのだ。
井上涼太は、自分の名前が不在の予選通過作品を載せた文芸誌を床に叩きつけ、太息をついた。
渾身の一作も、クズと終わったのだ。
その時、一際強い春風が頬を打つと同時、何やら紙くずのようなものが部屋に舞い込んだ。
なんだろう。ふと目を走らせると、どこぞガキのイタズラか……紙ヒコーキが一機、座布団の上に不時着している。益体(やくたい)も無いノートの切れ端で作ったものながら、見るからにヨレヨレで、風雨の中を飛び回っていたというふぜいであった。
所詮紙くずとそのまま丸めかけたが、つい好奇心にかられて機体をほどいてみると、鉛筆の文字で次のように認めてあった。
「私も、井上君のことが好き」
まさか! 時は一気に二十年を遡って……
・
・
・
小学校の六年のこと……涼太は授業中の手慰みに折っていた紙ヒコーキを、成り行きのままクラス中に流行らせたことがあった。初めは一人教室で遊んでいたのが、つい屋上に上って飛ばすことを思いつき夢中になったしだいである。これに仲の良かった数人が続き、やがて男女問わず屋上での紙ヒコーキ大会が一大ブームになったのだ。
一時は、担任の教師までもが加わったものだが、しばしの後、この遊びに禁止命令が出されることとなった。と言うのも、屋上からそれた紙ヒコーキはおのずとコースを外れ、近隣に散乱する。庭が散らかる、道路が散らかると、周辺住人からの苦情が殺到したのだ。
一月近く続いたブームも一気に収束したものの、涼太は最後の飛行に於て、同じクラスの吉岡加津江さんへの思いを紙ヒコーキに託したのだ。
「吉岡さんのことが、好きです!」
加津江さんはお淑やかで口数も少なく、勉強は常にトップ、ヤンチャな涼太とは正反対……ちょっと寝むたそうの目つきをしていたけど、全体の雰囲気は「美少女」と評してしかるべきであった。ただし、いささか気取っているふうの香気が漂っていたせいか、回りからは「すかし屋」という綽名をつけられ、あまり友達もいなかったはず。
それでも、涼太は三年生位の時から、加津江さんのことが気になっていて、一度など友達に冷やかされながらも、唯一自信のあった作文の力技で、自分を王子、加津江さんを王女様に見立ててのオリジナル脚本を宿題に事寄せて、発表したほどであった。
その加津江さんが、六年の夏の終わりに、父親の仕事の関係で転校することが決っていて、……つい、せっぱ詰まっての苦肉の策であった。
加津江さんが、当の紙ヒコーキを拾ってくれる保証などなかったにも係わらず、当時の涼太としては精いっぱいの勇気と言えた。
もとより何の反応もなく、加津江さんはその年の九月の初めに、無言のまま四国の方に転校していった。
「恋」と呼ぶには余りにも幼く、涼太にしても心の地中深くに埋葬したはず……
しかし、考えてみると、それまで書いてきた小説のヒロインは、決って「ちょっと眠そうな目つき」の女の子であったことに思い至るのだ。
時空を超えた紙ヒコーキの到来!
・
・
・
涼太は翌日から、思いつく限りの伝手を手繰り、加津江さんの消息を探してみた。
そして一週間後、加津江さんと少しは仲の良かった女性からの情報で、彼女と三、四年前電車で再会したという。なんでも、高校の時に父親が亡くなって、地元の大学を卒業した後、母親と共に再び東京に舞い戻ってきているというのだ。
幸い名刺をもらっていて、玩具メーカーの秘書課に籍を置いているらしい。もちろん、ケータイの番号も教えてもらった。
なんだか、自作のヒロインに会えるような気分のまま、涼太は取りあえず押入れを引っかき回し、小学校の卒業アルパ厶を見つけ出した。
アルバムの中には、化学の実験でもしているようなスナップもあって、記憶からは抜け落ちていたものの、二人並んで、照れ臭そうに写真に納まっているのだ。背丈は、少しばかり加津江さんの方が高い。まあ、子供時代は女の子の方が成長が早いのだろう。相変わらず、ちょっと眠そうな目つきながら、その美少女ぶりは想像を遙かに凌いでいる。
同世代なのだから、今ではさぞや美しに磨きがかかっていることだろう。
スマホを手に、アルバムの加津江さんの顔を見ながら、涼太の心臓は波打った。思えば、密室の作家を気取った身に、決った恋人など一人もいないのだ。
夜の七時……緊張を押さえるために軽くワインを飲んでから、涼太は番号をタップする。
結婚なんかしていないことを祈りつつ……
数秒も待たず、加津江さんの声が流れる……
「もしかして……井上君?」
「そう。井上涼太……覚えてるかな、不意に電話してごめん……」
「覚えてるかって……昨日の今日じゃない……」
なんだか、二十年前の紙ヒコーキ大会の日々にタイムスリップしているようなのだ。そのように、加津江さんの声……とても大人の女性の声ではない……
「……あの、僕の紙ヒコーキ……拾ってくれたの?」
ついでに涼太も子供に戻る。
「うん、拾ったよ。名前書いてなかったけど、絶対に井上君からだって分かった」
「なんだか……嬉しいよ。で、返事をくれたんだね……」
「そうよ。私も名前書けなかったけど……私だって分かった?」
「もちろんさ。今でも……手元にある。一生の宝物にするつもりさ……」
言葉に詰まってしまう。やはり小学生に戻って、アルバムの中の、同じく小学生の加津江さんと話している気分なのだ。
「……実は私、もうじき引っ越すことになってるんだけど……」
「そうだったね……。で、会えないかな?」
「私も、会いたいよ。でも……引っ越しちゃったら……」
「どこにでも飛んでいくさ……」
「嬉しい……でも……でも、すごく、すごーく、遠いのよ……」
「まさか、海外とかじゃないよね……」
「ごめんね……」
不意に電話が切れた。慌てて掛け直してみたものの、
「おかけになった電話番号は現在使われておりません」
というガイダンスが流れるばかり。その後、何度掛け直しても……
・
・
・
数日後、涼太は加津江さんが勤めているという会社に電話を入れた。
いささか手間取ったものの、かって社員として籍をおいていた吉岡加津江は二年前、乳癌で他界したと伝えられたのだ……
一月ほど、涼太はパソコンの前で呻吟を重ねた。奇跡の紙ヒコーキと共に、新しく折った最新鋭の紙ヒコーキを手元に置いて……
誰が、人生との折合いなんぞつけるものか!
またぞろ、お袋からは嫌みを言われるのだろうが、今、絶対に書かなければならない小説があるのだ!
もう、題は決っている。
そう。「紙ヒコーキの運んでくれた恋」と……
今、折ったばかりの、天の果てまで翔(かけ)て行ける紙ヒコーキを飛ばすために……
了
貧乏人です。創作費用に充てたいので……よろしくお願いいたします。

