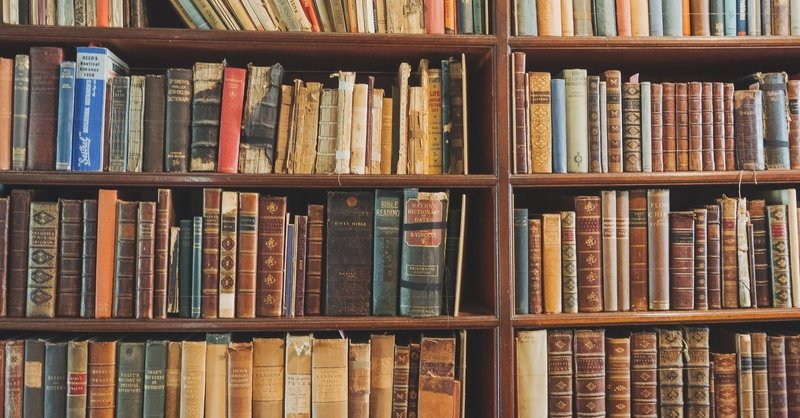
読書日記66
フェルマーの最終定理
フェルマーの最終定理(フェルマーのさいしゅうていり、Fermat's Last Theorem)とは、3 以上の自然数 n について、xn + yn = zn となる自然数の組 (x, y, z) は存在しない、という定理のことである
らしいwちょっと難しい本なんだけど、サイモン・シンというサイエンス・ライターが書いたノンフィクションでちょっと僕には理解ができない部分も多かった。アンドリュー・ワイズというイギリス人でアメリカのプリンストン大学教授がこの難問を解いたというのを1993年6月23日に発表した。すごい難問で17世紀にフェルマーという数学者が「私はこの命題の真実に驚くべき証明をもっているが、余白が狭すぎるのでここに記すことはできない」と書いて以降、難問として数学者を困らせて来た。
オイラーという天才でも解けずに永遠に解けないとまでいわれていた。「ザ・シェフ」という漫画の中で数学者がこのフェルマーの最終定理のために時間を費やしたといっているのがある。それくらい有名なもので高校の先生もネタにしていた(これは後に書くけど日本人で解いたといった人がいたため)それから何年後かに解かれたとニュースになった時は凄いニュースになっていた。冒頭でアンドリュー・ワイズが「ここで終わりにしたいと思います」と言ったこと書かれている。
x2 + y2 = z2というピタゴラスの定理から過去の数学の歴史に入っていく。この2乗が3乗4乗となった時にその自然数xyzを表すものは存在しないというのは「悪魔の証明」と言われて証明する側が相当の苦労をする。なんでそういう問題をフェルマーが好んで出したか?というとフェルマーがアマチュアの数学者で本当は裁判所の書記官だったらしく、発表することがないと勝手に当時の数学者に「これ証明できる?」と手紙を書いていたのがあるとなっている。
自分の証明をつけずに最新の定理を送り付け、相手を挑発するフェルマーが証明を決して明かさないので、ルネ・デカルトは「大法螺吹き(おおぼらふき)」と呼び、ジョン・ウォリスは「あの忌々しいフランス人」といっている。頭のいい、そして屁理屈な人は嫌われるけど、時に難問をだしていく数学の難問を解くのになぜというのは「永遠の謎を解く」喜びがあるかららしい。
そしてこの本ですごいのはこの「フェルマーの最終定理」に4人の日本人が絡んでいるところにある。それもこじつけでなく外国のサイエンス・ライターが書いてあるところにある。最初の2人は谷村豊と志村五郎という若き数学者だった。2人は戦時中に学生で飛行機の部品の組み立てをやらされたたらしい。その中で数学を選んだのは「お金がかからない」のと「独りでも続けれる」という戦時の時ならではの発想だった。
「すべての有理数体上に定義された楕円曲線はモジュラーである」という予想を2人は打ち立てる。解明したわけでなく予想なんだけど、これだけ有名なのはこの予想を証明することが「フェルマーの最終定理」を証明ことになるということがわかったのと(実際に証明された)谷村豊が謎の自殺をしていることだった。婚約がきまって幸せが絶頂の時に亡くなった。そして婚約者の鈴木美佐子という女性もその後を追って亡くなってしまう。その予想は予想のままになってしまった。
モジュールの法則というのは幾何学模様の対称性を持つステンドグラスやタイルみたいなものを数式化したものらしい。それが楕円曲線と一致するとう大胆な予想は1960年当時の数学者をビックリさせた。「モジュール」と「楕円」は別々に研究されることはあってもそれが一緒というのは誰も考えつかない発想だったらしい。
そしてもう一人は宮岡洋一という東京都都立大学の数学者だった。1988年に「フェルマーの最終定理」と解いたと発表したが不備があるとされた教授で実はその時の「フェルマーの最終定理」の火付け役のひとりでもあった。日本ではそっちの方が有名でドラマ「古畑任三郎」にネタとして採用されている。主演は唐沢寿明だったような気がする(記憶がちょっとあいまいですいません)
微分幾何学というこれまた難しいアプローチから解いたと発表したときに世界はビックリした。数学者にとって「フェルマーの最終定理」は特に実用性がないために「趣味で」みたいな感覚があったらしい。それが一気に解明したと活気づいた。そのちょっと前の1984年にドイツの数学者のゲルハルト・フライが「もし、谷山・志村予想を証明したら、フェルマーの最終定理は証明される」と発表する。そしてフェルマーの最終定理を証明したアンドリュー・ワイズが最初に着目したのが最後の一人、岩澤健吉という数学者の「岩澤理論」だった。それは失敗に終わった。
カリフォルニア大学のケン・リベットが研究してみたりしたが、この「谷山・志村予想」を証明するのはすごく難しかったらしい。アンドリュー・ワイズはフランスのガロアという若くして悲劇の死を遂げた天才数学者の「群論」を入り口として証明を始めていく。そしてこの360年と続いた疑問を解いた。証明には1つ致命的な誤りがあることが判明して難航するけど1年後に弟子であるリチャード・テイラーの助けを借りてその難解を突破し1995年2月13日に証明が認められた。世界で5人ぐらいしか正確には解っていないらしいけどwこんな高度な数学の世界に日本人が4人も関わっているというのは本当にすごいなと思ってしまった。
ホントに難しい本なんだけど、ブックオフで安かったので買ってそのままおいておいたけど読んでみたら面白かった。あとこの本を翻訳した青木薫さんは女性で京都大学理学部卒です(スゲー)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
