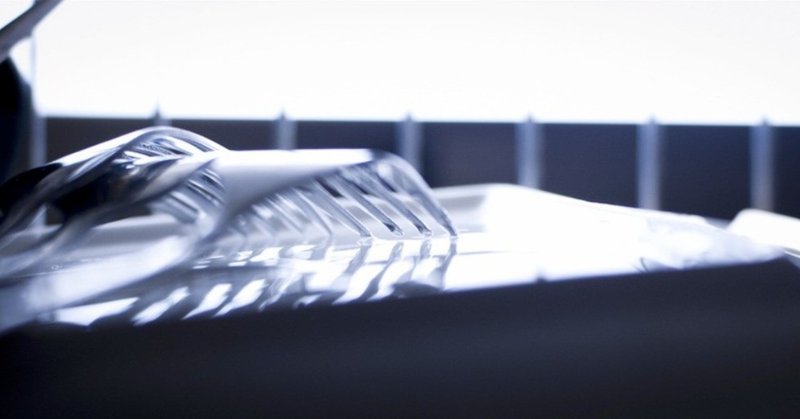
エッセイとコラムのちがい
「エッセイって、なんの意味があるんですかね?」
白いお皿にのった鶏肉にナイフをいれながら質問する。テーブルクロスの先に座っているのは、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の教授を務める柳瀬博一さんだ。
柳瀬さんは編集者として、矢沢永吉の『アー・ユー・ハッピー?』や『小倉昌男 経営学』、『養老孟司のデジタル昆虫図鑑』などヒット作を数多く作ってきた日経BP社の名物編集者だった。
東工大で教鞭をとるのも、ジャーナリストの池上彰さんが東工大の教授になった際に作った『池上彰の教養のススメ』が一つのきっかけになったという。
naoyafujii via flickr / Creative Commons
その日はちょうど会社が休みだったので、私は柳瀬さんの授業に遊びに来ていた。艶やかな肌をした大学生たちに囲まれて、90分の講義を聴く。
「人は何人までコミュニケーションが取れるのか」という根元論から「日本のインターネット草創期」までが美しく論理展開されたスライドに眩暈がした。
授業の後、大岡山の駅前にある上野精養軒で昼食をとる。「東工大の先生が、来客が来たときに使う場所」らしく、絨毯張りの床に白を基調にした店内は落ち着いた雰囲気だ。
ランチメニューのチキンソテーを食べながら「最近記事が書けない」と悩み相談をする。
エッセイの連載を持たせてもらっているものの、私はこの手のジャンルを好んで読むことは少ない。あまり意味を感じないのだ。
ニュースや論考など、しっかりとした情報のある文章を読む意味は、わかりやすい。学びがある。
しかし、一般人である私の本音や、身の回りの話に読む価値なんてあるのか? 要は、自己陶酔で「イタい」成果物にならないか心配なのだ。
実は連載が決まった当初、ケイクス編集部には「エッセイはやりたくない」と伝えていた。しかし結局、6時間ほどの説得の上、説き伏せられてしまったのだ。
案の定、筆が重い。原稿を落として2ヶ月が経っていた。
エッセイとコラムの違い
冒頭の質問をすると、柳瀬さんは「エッセイね…」と少し考えていきなり話し出した。
「この前、ランチを食べたときに窓の外から見た景色がとても綺麗で、風が気持ちよさそう。そよぐ木々の葉を見て、海に吹く風はどんなものかな、なんて考えてしまって」
まるでそこに本があるかのように、サラサラと話す。話すというより、読みあげているようだ。
「こういうタイプのエッセイもある。何か言っているようで何も言っていない。耳馴染みのいい言葉を並べるだけ。ある種、職人的な技が必要なのだけど……こういうラジオパーソナリティーっているよね」
大切なのは情報よりもキラキラした雰囲気だ。それはそれで形式として成立している。
ひどく悲観的な性格で、酒を飲んでは失敗を重ねる私には、そんな文章は書けない。渋い顔をしているのを察したのか、柳瀬さんはまた違う話をした。
「コラムとエッセイって何が違うと思う?」
たしかに2つはよく似ている。どちらもニュース的な価値は求められていないし、書き手のセンスに依存する部分が多い。
「コラムは批評を書く人による批評未満のもの。事実やロジックの組み立てが重要。エッセイはフィクションを書く人による文学未満のもの。情報よりも追憶を誘うことが魅力」
コラムは、読むと賢くなったような気分にさせるクリティカルな形式。一方、エッセイは読むと、思わず自分の過去を思い出してしまうような陶酔性がある、という違いがあるらしい。
「コラムとエッセイの一番の違いは、色気の有無じゃないかな」
色気とは何か
「本心っていうのは、見てはいけないけれど見たいもの…普段他人には隠している部分。これが少し垣間見えると、もっと見たくなる」
「でも隠れてる部分もあるから、読み手は自分で補完して見たい物語を作る」
柳瀬さんの「エッセイ論」を聞きながら、ベストセラー小説『ボクたちはみんな大人になれなかった』の著者、燃え殻さんと話したことを思い出した。
彼に自分の書いた文章を見せた時、「最後は思いっきりバツっと切ってしまいましょう」と提案された。書き切らない。これが余韻を与えるというのだ。
20世紀前半に活躍した哲学者、九鬼周造も「媚態の要は、距離を出来得る限り接近せしめつつ 、距離の差が極限に達せざることである」と説明していた。色気というのは、潔く突き離したり、曝け出した"ように見せる"ことで生まれるらしい。
私見だが、記者と呼ばれる人たちの文体は「最後の最後まで書き切る」ことが多い。コラムニストも同様だ。情報がきっちり詰まっていることが価値だからだろう。
ファクト寄りの書き方をする世界があれば、物語寄りの書き方をする世界もある。優劣はない。
前者は読む価値があるとすぐにわかるが、後者は一体どんな役割があるのだろう?
きっとそれは、内なる感情や本音の発見だ。
かつて村上龍と坂本龍一が対談で「小説家や音楽家は悲しみの代弁者」であると話していた。普通に生きているだけでは、人は「悲しみ」という感情に気が付かないので、音楽や小説はその訓練になるというのだ。悲しみがわかると、自分の傷つけ方や癒やし方もわかる。そんな機能が物語にはある。
もちろん、私が書いているものは、柳瀬さんの言う「小説未満のエッセイ」でしかない。しかし、どこかに物語的な機能があるとするならば、意味を感じることができる。
思い返せば、私が定期的に読み返す『二十歳の原点』は、学生運動が盛んだった時代に生きた女子大生のエッセイだ。彼女と私は生きている時代も社会も違う。けれども、自分を重ね、つんざくような痛みを感じた。そこで得るものがないと言えば嘘になる。
じゃあ、どうすればフィクション寄りの文章を巧く書けるようになるのだろう?
「それは……全身で文学を生きるってことじゃないかな」
狐につままれたような私の顔を見て、柳瀬さんは意地悪そうに笑っていた。
Edit:Haruka Tsuboi
Top Image : toshi.mono via flickr(Creative Commons)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

