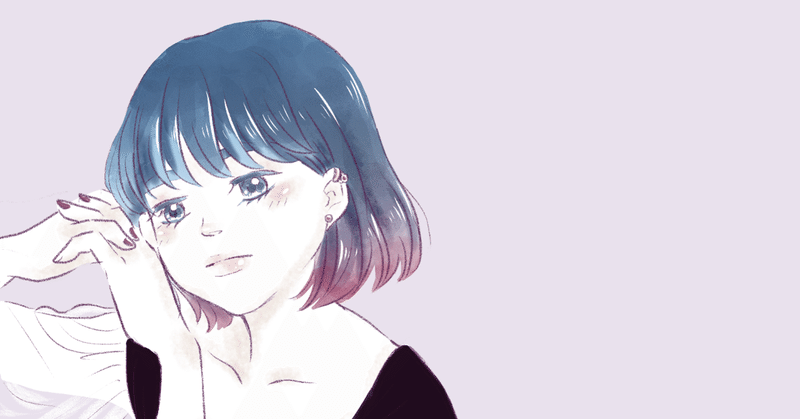
小説「初恋の卒業式」
ずっと地味な一生徒として学校生活を送っていた私が、ある担任の発言を機にクラス中の脚光を浴びることになった。
「お前、地味なようで地味じゃないよな」
「私も思った」「俺だって」
私は突然のことで周りの状況がわからなかった。中学一年の時に「身を守るため地味になろう」と決めた私が、何もしていないのにクラス中の注目を浴びるなんて。
どぎまぎしている私に、一番人気の創志が肩をぽんと叩いて話しかけてきた。
「本当に地味な人なら、勉強も、スポーツも、どっちも学年一位なんて取らないさ。もっと自信持っていいんだよ」
あんなにひた隠しにしていた成績を、なぜ私の成績をこの人は知ってるの?
程なくしてチャイムが鳴ると、私は恥ずかしくなって図書室に逃げ込んだ。図書室のめぐは優しい性格で、私のあまりの困惑を悟ってお茶を入れてくれた。
めぐの用意してくれたお茶をぐいっと飲み干すと、これまで溜め込んでいた気持ちを全部めぐに吐き出してみた。
「私が地味じゃない日が来るなんて!」
「突然どうした?」
「だって、地味だって言われないんだよ。誰にも。それどころか、羨望の眼差しでこっちを見てるんだ」
「まあ、あなたの気持ちもわかるよ」
「でしょ」
私は現状が嫌でしょうがない。だから、めぐに“身代わり”を頼んでみることにした。どうでもいい情報だが、私とめぐは容姿がそっくりだ。
「めぐ、私の身代わりになってよ!」
「やだ」
もちろん、駄目元だったが、ちょっとショックだった。私はめぐに残念そうな声を作って、平静になりかけた自分を見せないように繕った。
「やっぱり、そうだよね……」
めぐは私の方を見て微笑むと、再び本の整理を始めた。今年からめぐが図書委員長になったが、彼女が図書委員長になってから図書室が明るくなったような気がする。
結局、私は脚光を浴びるのを甘んじて受け入れることにした。修学旅行の余興では訳がわからないままアイドルっぽい衣装を着せられ、「BDZ」と「インフルエンサー」を踊った。文化祭では試しに男装をしてみたところ、これも好評だった。
驚くことに、いつの間にか彼氏も出来た。彼はレノンのようなマッシュルームカットで、ミニタリールックが非常によく似合う端正な男の子だ。成績は中の下くらいだが、性格は誰よりも優しい。よくカフェや美味しいお店を知っている。
私と彼の恋仲はあっという間に進展した。二人の恋は青春ドラマのようにきらめいていた。何日経っても、何週間経っても、何ヶ月経っても、私たちの恋はいつまでも新鮮だった。
それから、数ヶ月後、私たちの“卒業式”は突然訪れた。
世間を賑わせた感染症の影響で授業は短縮され、クラスメイトと過ごせる時間は突然「あと一日」となった。練習もできず、恒例の卒業前夜のパーティーもできず、私たちの卒業はあまりにも呆気なかった。彼氏とも高校では別々になることが既に決まっている。これからどうなるかなんて、一つも予想がつかなかった。
「卒業式かあ……」「早かったよね」
「出逢ってくれてありがとうな」
「こちらこそ、ずっとありがとう」
朝、彼氏との会話はなんだか湿っぽかった。私はいつもより早めに家を出たが、いつもの場所に彼氏の姿はなかった。
学校に着くと、彼氏は何ら変わらぬ表情で私の元にやってきた。
「ごめんね、ちょっと時間かかっちゃった」
「どうして?」「……制服のボタンを掛け違えちゃって」
「そう。それじゃ仕方ないよね」
私たちの卒業式はあっという間に終わった。放送で、歌もなく、あれよあれよという間に流れていく校長の長話。在校生の祝辞。本来なら体育館に飾られるはずだった花束たちは、卒業生たちが放送を聞く教室に「行き場がない」という表情で佇んでいた。
みんなに愛された担任は、静かに涙を流した。
「ごめんね、先輩たちのような卒業式を開けなくて。もっと私たちが賢ければって。私たちのせいじゃないかもしれないけれど、こうなる前に、なんとかして皆の門出を祝いたかった」
担任の涙に、クラスメイトも一人残らず涙した。私たちだって、普通の卒業式がやりたかった。こんな形で終わらせてほしくなかった。
最後の終礼は、声なき声で埋め尽くされた。担任から「解散」を告げられても、私たちはそこから動くことさえ出来ず、制服を涙で濡らし続けた。
数分後。私は彼氏に促され、クラスメイトへの挨拶も出来ずに学校を後にした。
めぐとは会うことさえも出来なかった。後輩との約束も、担任へのプレゼントも、全部すっぽかすことになった。彼氏は有無を言わさず、私の手を引いていた。何故、彼氏はこれほど手を強く引くのか理由がわからなかった。
「私、まだ用事があったんだけど」
「ごめん、ごめんよ」
「何かあったの?」「ちゃんとした場所に着いたら話す」
ただ、私は朝の時点から彼氏が“何かを伝えよう”と思い悩んでいるのは気付いていた。彼氏が何を伝えるのかどうかはわからなくても、私たちの関係を変えようと考えているのは明らかだった。
彼氏は私の手を引いたまま走り続ける。私は彼氏を追うだけで精一杯だった。
目の前の信号が赤になる。信号で止まると、一旦呼吸を整え、途切れ途切れの声で彼氏に尋ねる。
「いつ着くの?」「あと少し」
「私、もう知ってるよ。あなたが言おうとしてること」
「何?」「ちゃんとはわかんないけど」
「じゃあ、言ってごらんよ」
「私とあなたはもう長くないって。いや、別れようって言うんでしょ?」
私がこう言い切ると、彼氏はすべてを知っている目でこちらをじっと見つめた。彼氏の目は澄み渡っていた。
次にやって来たのは、数分間の沈黙。
だが、何度か信号が青に変わった頃。彼氏は沈黙の鍵を解いた。
「あなたの言う通りさ。僕はあなたと別れようと思っている」
……薄々わかっていたことでも、いざ言われると心の整理が出来ない。私はしどろもどろになった。
「私が、あなたと出逢って、これまで紡いできた日の、その価値が……」
「いや、そうじゃないんだ」
私の問いに答える彼氏の目は真剣だった。それでも、ほんの少しの余裕が感じられた。
「あなたは僕にとって完璧な彼女だ。いや、誰にとっても、あなたは最高の彼女だろう。あなたに出逢ってから、僕は幸せになった。“ただの日陰者”から、“みんなに注目される存在”へと周囲の扱いも変わった」
私はますますわからなくなった。彼女として、何がいけなかったの?
「わかんないよ。本当にわかんないよ」
「うん」「なぜ、完璧な彼女を手放そうとするの?」
私は彼氏に詰め寄った。一旦元の色に戻った目は、おそらくもう真っ赤になっているだろう。彼氏は私を諦めたような顔で見つめた。
「そういうところだよ」
私はもう自分自身を守ることで無我夢中だった。この時の私は、周りが何にも見えていなかった。
「そういうところって、どういうところ?」
「君は何にもわかっていないね」
彼氏は私とのやりとりを終わらせようとしていた。その様子は、誰にも明らかだった。私は溢れ出た涙を袖で拭った。
「あなたは僕には大きすぎたんだ。きっと、僕には、まだあなたの彼氏になる資格がない」
この言葉を吐き捨てた瞬間、彼氏は私を抱きしめた。でも、彼氏のぬくもりは、私にすべてを悟らせるのに十分すぎるほどあたたかかった。
「私を好きになってくれてありがとう」
「こちらこそ。僕の彼女になってくれてありがとう」
数十秒間ほど抱きしめ続けた後、私は彼氏の瞳を見つめた。それまで気付かなかったが、空からは雨が降り始めていた。
「忘れたくないから、君を」
「私だって、忘れないよ。あなたこそが、永遠に初恋の人」
合わせたままの目は、唇へと歩みを進めた。私たちは目を合わせる代わりに、唇を重ねた。
このキスは、最初にして、最後のキスだった。
「じゃあね、もう行かなきゃ」
「さよなら」「バイバイ」
私たちは背中合わせで足を動かし始めた。家に着くまで、一切振り向くことはしなかった。私が彼氏に対して持っていた未練は、雨がすべて洗い流していったから。
恋は、もうしばらくいいかな。あなたで駄目なら、もう誰と付き合っても一緒でしょ。
私がいなくても、あなたはきっと大丈夫だよ。卒業おめでとう。
あなたと出会えて本当に幸せだった。幸せな青春をありがとう。ずっと大好きだよ。
2020.3.14
坂岡 ユウ
最後までお読みいただき、ありがとうございました。 いただいたサポートは取材や創作活動に役立てていきますので、よろしくお願いいたします……!!
