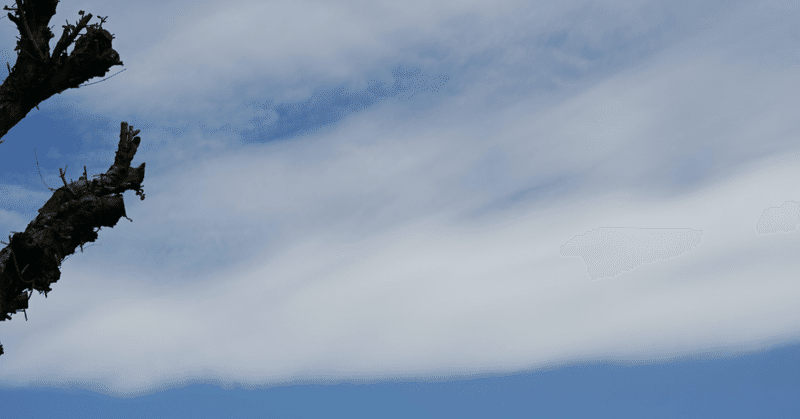
なるだけ短めの物語
以前描いた「なるだけ短い物語」という短編です。
GWの休みのあいだにまとめてみました。
ひとつひとつが独立した物語です。
自分の中では一貫したテーマがあったのですが「まあ、それはどうでもいいや、今読み返しても好きだな」と思って発表します。
短編は5つあります。4番と5番は少しつながっています。
それでは、どうぞ。
なるだけ短めの物語 1・野良猫
あの日のあとから、あの子がいなくなったような気がする。
あの子は、いつもわたしの見えるところにいるわけじゃないんだけど、ふっと家の前の道を見てみると、そこが最初からの居場所であるかのようにちょこんと道路のすみっこに座っていた。
お互いの気分がうまく合う日には、やわらかい指のはらを触らせてくれたり。
気分が合わない日にはちょっと手を差し伸べただけで、遠くをめがけてかけだしていったり。
それでも同じ町に住んでいて、おたがいが「ここにいる」ことを知っていたし、特に言葉を交わさなくても、あたしたちは、かなりお互いをよく知っている知り合い同士だったと思っていた。
なのにあの子はいなくなってしまった。
いつからそうなのか、ずっと気づいてなかったけれど、いつのまにかあの子は、わたしの目の見える場所に姿をあらわすことがなくなっていた。
いや。
正確に言うと、わたしには「あの子」が見えなくなってしまったのだ。
何度か夕暮れの路地を探してみたけれど無駄だった。
夕日はあいかわらずの夕日だったし、夏らしく遠雷の続く夜もあったし、隣のおばさんは時間どおりに帰ってこない飼猫の名前をいつものように呼んでいたけれど、あの子は見えない子になって、最初からそこにいないかのように毎日はすぎていった。
あの子の残像を描いていこうと思った。
わたしは不思議なほどにあの子の記憶が薄れてしまっていて、いつのまにか、あの子の記憶が最初から何もないみたいに自分が生きていけるんじゃないかと思って、それがすごく不安になったりもしたから。
だから、残像を描いてこうと思ったのだ。
すごくあいまいな残像のデッサン。
いなくなってから、すごくよくわかる。
わたしはあの子のことを「物語」と呼んでいて、すごく愛していたのだ。
なるだけ短めの物語 2・「ヨルム」
ヨルムは静かだ。
夜の海を見つめているように遠くをみている。
今ここで起こっていることを20メートル先から見ているような感じで、焦点があってないんじゃないかって心配することもあるけれど、それはたぶん、一定の距離を保ちながら静かに現実世界と対峙しているだけなのだと思う。
わたしはときどき、彼女とふたりっきりになって一日中話していたいなと思う。
そうだとしても、話すのはたぶんわたしがほとんどだ。
彼女はときどき、ああ、そうですねとか、あ、ほんとだとかうなづきながら私の話を聞いてくれる。
海にぽーんと小さな石を投げるような静かな会話。小石が海に沈んでゆく音だけが聞こえているような感じ。
黒目がちのヨルムの目はいつも静かな海を見ているわけではない。
彼女の心にはいつか嵐がやってくる。
それが不定期に起こるのを、わたしもヨルムも知っているし、とりあえずは何種類もの小さな錠剤が彼女を守ってくれているのも知っている。
それでも嵐はやってくる。
低くない確率で「それ」がやってくるのをわたしたちは知っている。
「眠れないんですよ」と、ある日のヨルムがそう言うた。仕事を休んだ次の日のことだった。「すぐに病院に行ったんです。しばらく再発しなかったから大丈夫だと思ってたんだけど、やぱりダメだったみたい。この病気とは一生つきあわなきゃいけないからって先生に言われた」
ヨルムは淡々とした口調だった。不謹慎な言い方をすれば嬉々とした感じにも聞こえた。
わざとではない。ヨルムはそういう病気なのだ。
その日から、静かなヨルムの心に白い波の形が見えるようになってきた。大きな波がざぶんざぶんと揺れている日もあって、そんな日のヨルムは饒舌だった。
つきあっている男の人がいるんです、ほんとは、でも会うことはあっても、なかなかカラダの関係まで行きつけないの。おまけに、今彼は、わたしのチャンネルが変わったことにとまどってる。メールもなかなか返事がこない。毎日送ってるんですけどね。あ、それからわたし、明日は仕事の面接に行こうと思って。ここの仕事ってフルタイムじゃないから、どこかフルタイムのところ探してるんですよね。わたしもほら、いつか、独立して家を出なきゃいけないから。
「大丈夫? 落ち着いてから行った方がいいんじゃない?」
「ううん。今だとなにか出来るような気がするんです。てか、今じゃないとできない気がする」
ヨルムは書類を揃えて、仕事の面接に行くがことごとく落ちてしまう。
ヨルムはめげない。
病院の先生もやんわりと止めるようだが、ヨルムは今しかできないと言う。ヨルムの病気がヨルムを動かすのだ。そして、そんなふうに無敵になって動けることがヨルムの原動力になっている。
いっしょに仕事をしている日もヨルムは饒舌だ。
ずっとおしゃべりしたり笑ったりしながら、単純でおもしろくもない仕事をどんどんこなしていく。そしてわたしも、そんなヨルムのエネルギーに乗っかるようにして、いつもよりもよく喋り、よく働く。
楽しい。
静かにいろんなことを受け止めていた彼女の心が今、潮流になって流れだしている。
頭のいい彼女の心の動きがひとつひとつわたしに染みいって、ああ、こんなふうにヨルムは思うんだなってわかるのがとても楽しい。
ときどき引きずられて疲れることもあったけれど、それでもなんだか楽しかった。
それから約1ヶ月のあいだに、わたしとヨルムのチームは膨大な量の仕事をバンバンを片付けていった。
まるで居酒屋の店員みたいに「これ、終わりました~。つぎ、どんどんいきま~す」とか言いながら、お互いの仕事をやりとりして、まわりで見ていた人たちも「ここのチームはすごく楽しそうね」とケラケラ笑う。
わたしたちも笑う。
不思議と咎められることはなかった。
わたしたちは「楽しそう」だったし、何よりも常軌を逸したスピードで、すごい量の仕事を片付けていたからだ。
それからしばらくして、大量の薬がやっと効果を発揮してヨルムはまた静かな夜の海に戻った。
暗い海にはもう波は見えなくて、ヨルムはお昼休みにはクスリを飲んで眠った。
「すごいエネルギーを使って、カラダが疲れてるんだろうって。どれだけでも眠れるんですよ。ほんとにわたし、あの1ヶ月のあいだ、ほとんど寝れてなかったし、今体中が疲れきっている感じ」
仕事が終わって駅までの距離を歩くのもつらいらしく、「車で駅とおるなら乗せていってください」って言われることが多くなった。
「いっかいね、すごくヤバかったみたいで、先生がその場で注射したの、そのとき、わたし立っていられなくってその場に座り込んじゃった。すごいショックでしたよ。だってね、なんでもできるような気がしてたのに。たった一本の注射で動けなくなってしまうなんて」
なんでもできるような気がしたんですけどね、そう付け加えてヨルムは笑った。
ああ、眠たい。そう言って車の中であくびをするヨルムの横顔を見てみる。
もう、黒目がちの瞳には何も映っていない。
わたしはとても小さい人間だから、やっぱり原因を考えてしまうのだ。
ヨルムはいつもなにかを我慢してたんじゃないかとか、幼い頃になにかのトラウマがあったのかとか。
そして余計なことだと思いながら結果までも考えてしまうのだ。
これからヨルムはわたしの傍にずっといてくれるだろうかとか。
今の仕事場のスタッフはヨルムの病気を知っていて、それでもいつまでもいていいのだと言ってくれるけれど。
でも、それではヨルムののぞむものは何ひとつ手に入らないのではないかとか。
彼女と同年代のロストジェネレーションの若者たちがそうであるように、ヨルムはなかなか手に入らないものをいっぱい抱えたままなのだろうか?
あくびをしたまま寝入ってしまったヨルムを乗せて、公園脇の大きな道に車を止めて、窓をあけた。
カラダという宇宙のなにかもわからないくせに、そうして理由をつけて片付けようとしてしまうのが愚かなことなのかもしれないなあと最近思うようになってきた。
カラダの中の海に理由はない。
ヨルムを見ているとよくわかる。
それは、ただそこに揺れていて、そしてときに激しく波立つだけ。
きっと、理由なんてなにもないのだ。
台風が近い、夏の突風に髪の毛がゆれて、それでヨルムが目を覚ました。
「あ、あ、ごめんなさい。寝てしまってたんですね」って言いながら。
「ねえ、少し前にふたりですごいテンションで仕事したとき。あれはあれで楽しかったね」
わたしがそう言うと、表情のないヨルムの目が少し涼しげに笑った。
「ほんとそう、あれはあれで楽しかったですね」
今はほんとに疲れててとてもあんなふうにはできないけれど。
でも、またいつか、そんな日が来ると思いますよ。
ヨルムは天気予報の原稿でも読み上げるように、窓の外を見ながら少し笑ってそう言った。
なるだけ短めの物語 3・ノイズ
ネットで知り合ったその人は、楽しい人だった。
会ってみてもその印象は変わらない。思ったとおりのダンガリーのシャツ、よどみないの会話、そして正確にわたしの心の奥底にマリンバのように響く感情の音楽。
なのに、彼といっしょにいるといつも気づかされてしまう。
わたしは音が苦手なのだ。
「no music no life」な人と、ちょっと大きめのジャズが流れるお店に入ると、まったく会話が成立しなくなってしまった。音だけに集中している分にはいいのだが、ちょっと会話をしようとすると、マーブルのようにその2つの音が入り交じる。
彼はわたしの混乱に気づかずに、機嫌のいいままでずっと喋り続ける。
わたしはだんだん口数が少なくなる。そして機嫌が悪くなる。気分よくカクテルをおかわりする人はそれには気づかない。
音が会話の妨げになるなんて想像もできないのだ。
となりのテーブルにグループ客がいるだけでもダメだ。そんなときも会話がマーブルになる。一度耐えられなくなって、出ようと言った。
「よくわからないよ。隣の音と身近な音は別の音だろ? それを区分できないってことがあるの?」
そう言われて改めて、自分の感覚が人より劣っていることに改めて気づかされた。
大きなプロジェクターのある彼の家のリビングには、いつも音があふれていた。
バッハだったりビル・エバンスだったり、借りてきたDVDだったり。
彼のことが嫌いだったのではないと思いたい。
彼をとりまく音の洪水につきあうことができなかっただけだ。
わたしは「変化」に弱い子供で「おおきな音」にも弱い子供だった。体育の時間に新しい体操を学ぶことも苦手で、暗記ものも苦手で、そしてもちろん、子供同士のささいな悪意の標的になりやすい子供だった。
なんで無事にオトナになれたのかも不思議だったけど、それなりの努力もしたと思う。
状況が変わるときは、紙に書いて、何度もそれを見るように気をつけたし、それは仕事をするようになってからは病的なほど大量のメモ作りへと変化していった。人の顔を覚えるための特徴とか記号のような似顔絵とか、名前を覚える記憶のキーワードとかも、いつもこっそりと小さなノートに書き留めておくのを忘れなかった。 幸いにも国語や英語など「文章で表現すること」だけは得意だった。 だからトータルで能力のことを問題にされることもなかったけれど。わたしだけは知っていた。同じことを同じようにやってもわたしにはできないことがたくさんあるのだと。
巧妙に、できないことを避けたり、苦手なことを避けたりしながら生きてきた。
多かれ少なかれ、そういう部分は誰にでもあるのかもしれない。
戦ったり傷ついたりしながら生きることも誰にでもあることなのかもしれない。
他人の事情はわからない。
わたしが知っているのは、わたしがそれと戦ってきた長い歴史のことだけだ。
そして、誰にもそのことを言えずにいたこと。
言ってもそんな些細なことに苦労していたことは誰も問題にしないだろうってこと。
誰も問題にしなくても、自分にとっては、間違いなく弱みあってで引け目であったってこと。
ゆるやかに、現実という場所にいる男を避けるようになった。
わたしはそういうふうにして「巧妙に苦手なことを避ける」のに長い時間をかけて慣れてきたから、こんな感じで自分を守ることは厭わない。
だけど、誘われるたびに使う言い訳は、少し癇に障っただろうか?
ネットの中でだけ、ふたりでいられたらいい。
文字情報だけの、音のない彼とだったら、いつまでも幸せでいられるからだ。
いちばん最初の夜、すごく緊張して音のない闇の中で二人の肌を合わせた。
細い三日月の夜の、身体のこすれあう音だけが響く闇はとても素敵だったことを、今でもずっと覚えている。
一年も前のことが、まるで昨日の夜のことみたいに鮮明だ。
それはもうおそらく、二度とないことだ。そう思うと、少し、というか、かなりさみしい気分になってしまった。
それでもわたしは、こんなふうに、混乱を避けて自分を守っていくんだろうと思う。
誰に対しても、繰り返し繰り返し。
ネットの中にいる、文字情報の彼は。
今でもせつなくなるくらいに好きなんだけど。
それでもわたしは自分を守り続けていくだけだ。
なるだけ短めの物語 4・ライ麦畑
無人島でリョウちゃんとふたりっきりになってしまった。
比喩でもなんでもない。
まがりなりにも本物の無人島だ。
大声で叫んでもふたり。
ああ、空が青いなあ。ちぎった綿あめのような雲が、気づかないくらいにゆっくりに流れている。
冗談みたいな青空。
あたしが砂浜にへなへなと座り込むと、その隣にリョウちゃんがちょこんと下を向いて座った。
「無人島体験ツアー」は今回の旅行のメニューだった。
港から船に乗って無人島を体験。とは言っても20分ほどの乗船で行ける、ゆっくり一周回れるくらいの砂浜だ。小さい東屋だってある。
降りて30分ほど砂浜で貝やヒトデや漂流物を探したり散策したり写真を撮ったりして、また船で帰る。
とても簡単はツアーだ。
あたしの働く福祉施設が、ここのツアーに参加したのは、近隣の施設と合同だし、主催団体がすごくサポートしてくれるっていう評判だったからだ。
実際にそのとおりで、打ち合わせも綿密で、車椅子の人でも自閉症の人でも大勢のスタッフでフォローしてくれた。こんな機会でもなければ、みんなで旅行なんてできない。
無人島ツアーのあとは、リゾートホテルで地元の団体との交流会。ホテルにチェックインしたら海の幸満載のシェフ自慢の料理でパーティの予定だった。
ところが予定どおりにはいかなかった。
「いや、いや! 怖い! 乗らない!」
そう言ってリョウちゃんが暴れた。行きの船でも猛烈なエンジン音でパニックだったのだ。あげくに、帰りの船には乗らないと砂浜にひっくり帰る。主催者のスタッフが二人がかりでスレンダーなリョウちゃんを抱えてくれたものの、暴れて暴れて、すごい力で抵抗する。
出発時間が迫って、まわりの障害者の方たちまで顔色が悪くなっていくのがわかり、ああ、どうしようと泣きたくなってしまった。
「これ以上時間を遅らせるわけにもいかないのです。他のお客様もいらっしゃいますし」
ツアーコンダクターの西田さんがすまなそうに言った。
「30分あとに、もういっかい船が来るのですが、そのときにお迎えするのは可能でしょうか?」
可能だと思います。直感でそう答えた。いや、それしかないんだろうな。
「わたしどもの別のツアーがこの島に来ます。そのあとのホテルも一緒です。あちらの担当もベテランで、うまく対応できます。申し訳ないのですが、この状態で乗船しても危険なような気がしますし。30分、ここで待たれてなんとか落ち着かれたりはしないでしょうか?」
ピンク色のチークも明るい西田さんはどちらかというと新人さんの部類ではないだろうか。汗で化粧もとれてしまって、困って泣きそうな胸のうちが手に取るようにわかる申し出だった。
「しばらく落ち着くと場面転換ができると思うのです。わたしとふたりで静かに過ごして、つぎの船に乗るように言い聞かせます」
そう言って、出てゆく船を見送った。
今まで2年間リョウちゃんにつきあった経験からして、パニックがおさまれば、できるような気がした。でも、ほんとに大丈夫なんだろうか?
みんなが心配そうにこちらを見ながら、それでも船は出ていった。
あたしは無理に作り笑いをして手を降って見送って、そのあとはへたりこんで、砂浜に腰をついた。
ライ麦畑からいきなり転落したような気分だった。
ライ麦畑。その言葉を今思い出すのもおかしかったけれど、大きな音や知らない場所がこわいリョウちゃんを守ろうとするとき、自分が「ライ麦畑でつかまえて」の主人公みたいなライ麦畑の番人になったような気がしていた。
そういう仕事にやりがいを感じていたといえば嘘になる。むしろ逆で、失業する前みたいにバリバリ何かを販売するような仕事に戻りたくてしかたなくて、でも、せっかく見つけた仕事を辞める勇気もなかっただけだった。
ただ、大きな音や話し声が苦手なリョウちゃんは少しあたしと似ている気がしていた。そんなときたまたま「ライ麦畑でつかまえて」を読んだものだから、ああ、こんな仕事だと思うといいのかな、と思ったくらいだ。
彼女がライ麦畑から転落しないように見守るくらいならできるだろう。
もともと専門外だからいつまでやれるかわからないけれど、それでも「ライ麦畑の番人」という設定は自分の中では悪い感じではなかった。
でも、あっというまに転落してしまったな。
ほんと、見守っていたつもりでも、あっというまだ。
真っ白なカモメが青い空と青い水平線をいったりきたりしながら旋回していた。
「ゆう子さん、ゆう子さん」そう言いながら、リョウちゃんは体操座りの膝であたしの膝でつついていた。
「ゆ・う・こ・さーん」
そう言いながら何度もつつく。
どうやら、パニックはひとまず収まったらしい。
今、リョウちゃんは、「なんだかわるいことをしてしまったな」と思ってるんだろうな。
そういうとき彼女は繕う。
きちっと理論だてて反省したり改善できたりはしない。
だけども、それでも、なんとなく繕う。
「しょーがないなあ。リョウちゃん、つぎの船が来るまでふたりでゴロゴロしていようか。それから、ちょっとしたら船がくるんだよ。今度は、その船に乗って帰るんだよ」
「はいっ」
そういって何ごともなかったように、自分の膝であたしの膝をコンコンとつつく。
おなじリズムでコンコンとあたしもつつき返してみた。
コンコン。コンコン。コンコンコン。コンコンコン。
調子が乗ってきたので、それに合わせて歌を歌ってみた。
「あ~らし、あらしっ、オーイエー♪」
リョウちゃんが大きな声でケラケラ笑った。
ゆう子さん、もういっかいっ。
何度も何度もそういうので、何度も何度も繰り返して歌った。
あたし、きっと、つぎの船がくるまでに100回くらいこの歌を歌うんだろうな。
今日、ひとつ、気づいたことがある。
ライ麦畑は段々畑になっていて、いっかい落ちたとしても、その下にはまた別のライ麦畑が広がっているってことだ。
うん、だからそんなに絶望しなくていいんだ、たぶん。
なるだけ短めの物語 5・一期一会
結局あたしはライ麦畑の番人をやめた。
そもそもパートタイムの番人だったわけだし、一生ライ麦畑の番人をやるつもりなんてなかった。でも思い返してみると、けっこう楽しんでいたように思う。
日本の狭い社会にありがちな職場のトラブルに疲弊してして、心病んで、あたしはここを離れる。
楽しかったのにな、と心の中でつぶやいてみる、戻れる自信なんてまったくないから、楽しかったなんて言っちゃいけないんだけど。
あの日、りょうちゃんと二人で砂浜で歌った日のことを、あたしは今でもよく思い出した。
太陽のまわりがまぶしいくらいの金色で、波もまた金色にキラキラしていた。
あたしたちは無人島でふたりきりで、次の船が来るのをすごーく心静かに待った。
「ゆうこさん、かわいっ!」
そう言いながら、りょうちゃんが膝をつついてくる。「りょうちゃんもかわいっ!」そう言ってあたしも膝をつつき返す。
大きな音が苦手で、先の予測ができないのが苦手なあたしたちだったが、次の船を静かに待つことはまったく苦痛じゃなくって、なぜだかとても幸せな気分に満ち溢れていた。
船は必ずやってくる、そしてこの場所にはかぎりなく静かにゆっくりとした風が吹いていた。
遠くから小さなエンジン音が聞こえて、それがだんだんおおきくなってきて、ひとりの女性がまず降りてきた。
「りょうさん?」
「はいっ」
「待たせてしまってごめんなさいね、さみしかったでしょ?」
「はいっ」そう答えながら、りょうちゃんはとてもニコニコしていた。
同じスーツを着てるからたぶん同じ旅行社の人だろう。年配で、短めのタイトスカートがピチピチな田原さんという女性は、うっすら汗をかいてるのにアイラインはまったくにじんでいない。
「嵐が好きなの?」田原さんはりょうちゃんが腕にしている嵐のリストバンドを見つけてたずねた。「嵐はわたしも好き。りょうちゃんは誰が好き?」
「にのくん」
「そう、わたしは松潤が大好きなのよ!」
それから次々に降りてきた初老の女性や男性がりょうちゃんのまわりを取り囲んだ。腰が曲がった分だけ小柄に見える、笑ったカタチのままに皺が刻まれていったような人ばかりだった。
「まあ、こんなかわいいお嬢さんを、置いてったのね。こわくなかった?」
「かわいいねえ。ウチのひ孫よりかちょっとおねえさんなのかねえ」
「暑くなかったかい?」
みんながりょうちゃんの手を握ったり肩を叩いたりしながら、取り囲む。
またパニックにならないかとどぎまぎしたけれど、りょうちゃんはあたしの心配をよそにニコニコしていた。
近隣の町の老人会の団体の方で、これからみんなでホテルに行って一泊するらしい。
「わたしたちといっしょに船に乗るけんね、ぜんぜんこわくないよ。船からバスに乗ったら、すぐにホテルたい」
30人ほどの団体は、ちょっとおざなりにまわりを散歩したりしながら、喉かわいてない?ってりょうちゃんにペットボトルの水をくれたりしている。なにしろかわいくて仕方ないって感じだった。
りょうちゃんはずっとニコニコしてた。初対面の人は苦手なはずなのに。
時間がくるとりょうちゃんは、団体の中の比較的がっしりした男性の背中におんぶされて船に乗った。
「ぐらぐら揺れるとこわいだろうから、おんぶで行くね?」って言われて、そのままカラダを預けたのだ。
そして船の一番まえの席に座って、田原さんの説明にひとつひとつ返事する。
りょうちゃんはまったくこわがってなかった。
「はいっ」「はいっ」そして時には「へええええ~」って。
誰もがニコニコしていた。りょうちゃんの言葉を聞いて笑ったりしながら。
バスに乗る頃には、もうみんなに打ち解けていて、りょうちゃんは得意の嵐の歌のサビを口ずさんだりして、そのたびに誰かが拍手をしたり笑ったりしてくれた。
これはいったい何の魔法なんだろう? 初対面の人は苦手なはずなのに。
大きなリゾートホテルが見えてきて、ゆっくりと車寄せにバスが入ってくる。
心配そうに待っているスタッフの顔が玄関に見えた。
「さあ、お待ちかねのホテルにつきました」田原さんが言った。「日頃は、移動時間はみなさんゆったりされていて、わたしの説明を子守唄にお昼寝される方も多いのです。だけど今日はりょうさんが元気よく返事してくれて、説明する方もとても楽しかったです。そして短い時間でしたが、笑い声がいっぱいの移動時間でした。これもりょうさんのおかげでした。ほんとにりょうさん、ありがとう、またどこかでお会いしましょうね」
みんなが拍手をしてくれた。
そうそう、りょうちゃん、楽しかったよ、という声がたくさん聞こえた。
「ありがとうございました~」りょうちゃんがすごく大きな声でお礼を言った。
ああ。
自分だけがライ麦畑の番人をしていて、いろんな人やモノから彼女を守りたいと思ったいた自分はただの傲慢なヤツだ。
りょうちゃんの世界はそんなふうにはできてはいなかったのだ。
りょうちゃんの心はずっと外に出たがっていた。
あの日をさかいにりょうちゃんは変わった。
先の予定がわからないとパニックになったり、知らない場所でへたりこんでしまうのは相変わらずだったけれど、それでも、何かわからないけれど何かが変わった。
「いつか、わたしはこわくなくなるんだ」って心の中で思っているような気がした。
そして実際、パニックが落ち着くと、誰の前でも天真爛漫にふるまうのだ。
彼女のふるまいは、いつも笑いを誘ったり拍手をもらったりした。そんなとき彼女は、とてもうれしそうに笑った。
あれは一期一会っていうんだろうな。
たった一回会うだけの人たち。その、一度きりの優しさ。
だけどもみんな、その一度の中で、自分の胸の中にある光る石を手渡してくれるんだ。
自分たちがその場所から消えても、けして色褪せない光る石。
そしてりょうちゃんも。自分の中の光る石をお返しに手渡せるってことを、彼女は心のどこかでちゃんと知ってたんだ。
長いスパンだったけれど、あたしとりょうちゃんだって一期一会だったんだろう。
あたしはりょうちゃんに、たくさんの光る石をもらったような気がする。
それは、宝物にしてぜんぶ並べておきたいくらいの綺麗な光る石ばかりだった。
あたしはりょうちゃんに、あたしの胸の中の光る石をちゃんと渡せただろうか?
さよなら、りょうちゃん。
今度はまた、今はまだ出会ってない誰かが、あたしとは違う石を手渡してくれるはずだよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
