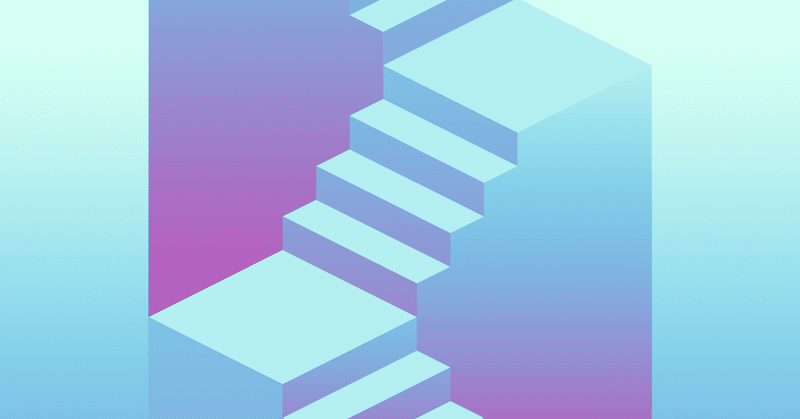
坂田昌一博士の「無限階層論」
坂田昌一博士(1911~1970)は湯川秀樹博士(1907~1981)や朝永振一郎博士(1906~1979)らと並び、素粒子・原子核物理の黎明期をけん引した物理学者だ。名古屋大学で教鞭をとり、多くの後進を育てたことでも知られている。2008年のノーベル物理学賞を受賞された益川敏英先生、小林誠先生も坂田博士の門下である。

物質の「究極」はどこにあるのだろうか?
坂田博士は物理学研究の一環として、それらを理解をするための哲学(※)も展開していた。その一つが「無限階層論」だ。
(※)本note記事中で用いる「哲学」という言葉は、学問としての「哲学」とは性質を異にするものだろう。それは、「研究の発展を鑑みながら、自然界にどのような世界観を当てはめるか」という思索のことを指す。「思想」という方が適切なような気もしている。
素粒子は物質の根源的な構成粒子だ。いわば、物質の究極的要素。坂田博士はこのような素粒子観を批判した。
坂田博士は著書の中で、素粒子であると考えられていた原子にも内部構造があったと判明した研究史に触れながら、こう主張している。
今世紀に入ってからの原子物理学の著しい発展の跡をふりかえってみますと、原子は決して物質の可分性の限界ではなく、自然をつくりあげている質的にことなる無限の階層(レベル)の一つとしてとらえるべきであったことがよくわかります。素粒子も、いまでこそ物質の究極であるかのようにみえますが、やはり物質の階層としてとらえるのが正しい観点だと思います。
1964年にゲルマン博士が「クォーク模型」を提唱した。そのため、坂田博士がここで言っている“素粒子”は陽子などのことを指している。
その陽子も、後には、クォークを構成要素として持っていることが判明するので、坂田博士の先見性が垣間見られる。
自然界をどう認識すべきか?
現在の物理学では、クォークなどの素粒子を構成するような、さらなる下層の粒子は存在しないと理解されている。なので、上述した無限階層論は“正しい”とは言えない。
しかし、物理学の先達たちが、どのような哲学を持ち、どう自然と向き合ったのか、どういう認識を試みたのか、という歴史は後進の一人として、とても興味があることだ。そして、それらから何を継承すべきなのかも考えながら学んでいきたい。
坂田博士の哲学や考えは、多くの後進に影響を与えた。僕の師匠の師匠である先生は、学部生のときに、坂田博士の著作を読み、坂田哲学を学んでいたそうだ。その先生は、とある講義の中で、原子核物理を専攻しようと思った理由をこう述べている。
(もし、無限に階層が続いているとするのであれば、)階層間の関連をちゃんと理解する方がより基本的なのではないか?原子核物理とはそういうものである。多体系の物理の方がより基本的なのではないかと考えた。
僕も物理(特に原子核物理)の研究を通して、自身の「自然界の理解」を深めていきたいと思っている。先達たちの言葉や哲学に触れるたびに、気持が引き締められる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
