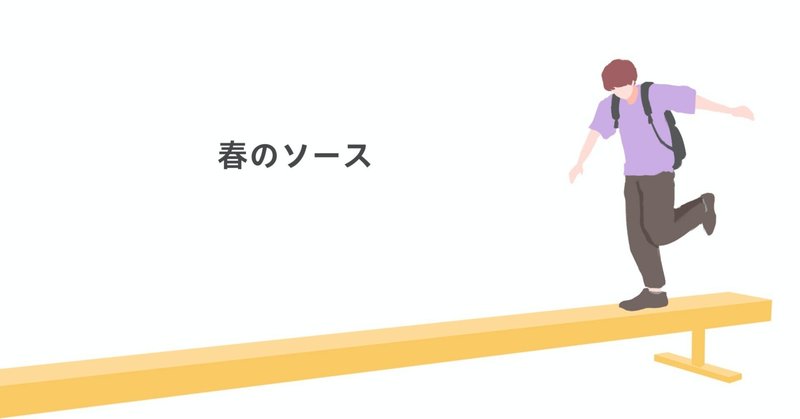
春のソース
はるさわそうすけは小学一年生のときのともだちだった。
ソースみたいな名前だと呼ぶたびに思った。漢字を習っていなかったから仕方ない。
ソースケのことで覚えてるのは「待ち合わせて一緒に児童館に行った」ということだけ。
それも、待ち合わせ場所にしていた曲がり角から、突き当たりの児童館までのまっすぐな道は、たった50メートルちょっとしかないような道だった。
児童館で何をして遊んでいたのかも、ソースケがどこに住んでいたのかも、まったく思い出せない。隣のクラスだから電話番号も知らなかったはずのソースケと、どうやって待ち合わせをしてたのかも分からない。
そもそも、隣のクラスで幼稚園も違ったソースケと、どう仲良くなったんだろう。
それなのに児童館までの短い道のことは強烈に覚えてるのには理由がある。
ソースケのおばあちゃんちがあったのだ。
待ち合わせ場所からすぐのところにあるこの家が、自分のおばあちゃんちなんだとソースケは教えてくれた。豪邸ではないけど、石造りの門がある一軒家だった。
ほらとソースケが指を指した表札には、漢字ではるさわと書いてあるらしい。
「うちのおばあちゃんいつもいないんだよ!」
そう言ってソースケは目線より上にあるインターフォンに指を伸ばした。ピンポーンと音が鳴る。
たしかに家からは何の音も返ってこなかった。
「ほらね!」とソースケが笑って「ほんとだ!」とぼくも笑った。
それ以来、待ち合わせてインターフォンを押してから児童館に行くのがお決まりとなった。
おばあちゃんはいつもいなかった。
大丈夫だよ、いないからと促されて、ぼくが押すときもあった。どきどきしたけど、結局何の音もしなかった。
反応がないと分かるまでには時間がいる。
普段ケタケタと騒がしい小学生が、インターフォンを押した瞬間、数秒静かに立ちつくす。振り返ればそれは儀式のようでもあった。
この小さな遊びが、なんだか内緒で特別で、わくわくした。
「またいないよ!」「またいないじゃん!」
毎度同じ展開にも飽きもせず、むしろ安心して、ケタケタと笑って児童館に行くまでがセットだった。
春、小学二年生になると、ソースケは引っ越していなくなった。
隣のクラスだったから公式のあいさつもなかったし、だからといって非公式のあいさつもなかった。ただ児童館に行くだけの仲なんだから当然だ。ぼくも、きっとソースケも、さみしくなかったと思う。
児童館に行くには2本の道があり、そのどちらを選んでも大した差はない。
けどぼくは自宅からは遠いほうの、いつもの道にいた。
そしてソースケのおばあちゃんちの前で立ちつくす。インターフォンを見上げる。それから指を伸ばした。
ピンポーン。
いつもの音がした。
反応がないと分かるまでには時間がいる。横にソースケはいないけど、いつもの間で、無反応を待っていた。おばあちゃん、またいないじゃん。ほらまたいつもと同じじゃん。
トタトタトタ。
そのとき、ドアの向こうから何か音がした気がした。ちょうどスリッパでフローリングを歩くような音だった。
聞き間違いかと思っていると、続けて「ooue?」と誰かの存在を確認するような声が、低い女性の声で聞こえた気がした。
その瞬間ぼくは児童館に向かって思いっきりダッシュをしている。いけない!という言葉より早く体が動いていた。どうして、どうして。底の薄いスニーカーがアスファルトを蹴る音が、タッタッタッと静かな町に響いた。
後方からはガチャとドアの開くような音が、さらにキィと門が開くような音さえ聞こえたような気がする。
「ooue?」
距離は開いているものの、さっきのように遮るものがなくなったその声は、「そうすけ?」という言葉に似ていた。
それでもぼくは一切振り返らない。やっとの思いで児童館に駆け込んでいった。
急いで入館カードを書いて、読書コーナーでマンガを開いた。気を紛らわせるためだ。
だけど何かが起こる様子はない。おばあちゃんは追いかけてこなかったみたいだ。
何分経っても状況は変わらず、おそるおそるめくっていたマンガのページが、そのうち通常のペースでめくられていった。
そのまま時間は経ち、閉館の5時が近づいて、それを知らせる音楽が鳴った。
だけど楽しくてマンガを閉じられない。もう少し、もう少しと粘っていると、児童館の女性スタッフが話しかけてきた。
「けんたくん、もしかして今日、人のおうちのピンポン押した?」
マンガから顔を上げて目を丸くする。何も言えない。
すると児童館のスタッフは「そこのおばあちゃんからね、黄色と白のしましまの服を着た男の子が、ピンポンを押して児童館に走っていったって電話があったの」と、黄色と白のしましまのポロシャツを着ているぼくに、困った表情を向けた。
「ち、ちがうよ!」ぼくは言い返す。「そこのおばあちゃんはハルサワソースケのおばあちゃんで、ソースケは引っ越しちゃって、いつもいないからってふたりでピンポン押してて、それで今日も押しただけで、いつもいなかったのにどうして今日はいたの? ソースケがいるときに出てくれればよかったのに。どうしてソースケはいないの? いつものことをしただけだよ!」
小学二年生だ。そんなこと言えるわけもない。
責められたと思えば自動的に涙が出て、えずいて言葉に詰まるだけ。
ソースケとの秘密の儀式はそこで終わった。儀式のことも、ソースケとぼくの仲がよかったことも、ぼくとソースケ以外誰も知らないし、今となってはソースケも覚えてないだろう。ただでさえ忘れてしまう小さな頃の記憶に、新しい環境と新しいともだちが上書きされているんだ。
児童館のスタッフは「いいの次からしなければ。おばあちゃんも怒ってなかったから」と泣いているぼくをフォローしてくれた。ぼくもごめんなさいくらいは言ったんだと思う。
でも悪いことをしたなんて思うはずがなかった。
このエッセイには2つの朗読バージョンがあります
他のエッセイまとめ
・投げ銭サイト
・全情報と新情報(音楽や他の活動など、毎日更新)
・YouTube
・Twitter
・Instagram
サポートは、ちょっとしたメッセージも付けられるので、それを見るのがいつもうれしいです。本当に本当にありがとう。またがんばれます。よろしくおねがいします。
