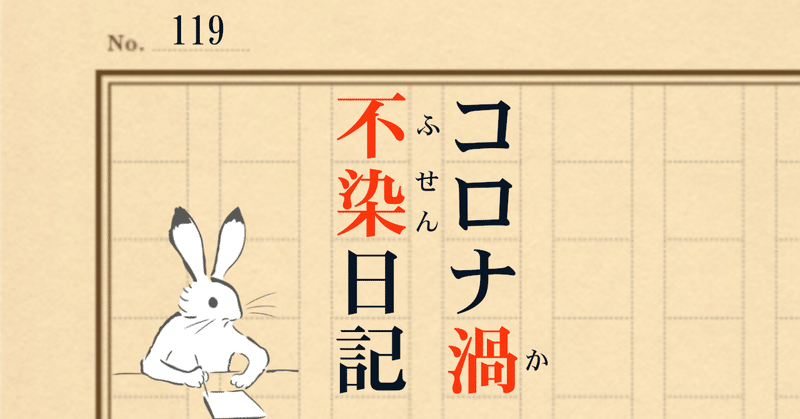
コロナ渦不染日記 #119
四月七日(水)
○本日の体温、三六・一度。
○仕事では、おとといに引き続き、カエルさんのサポートをする。
○夜。夕食の片づけをすませ、ケーブルテレビで時代劇も見て、あとは風呂に入って寝るだけとなった午後十時すぎ、ぼくたちは巣穴を出た。近所のコンビニでコーヒーを買ってから、公園へとむかう。四月の夜はまだ寒い。立てた耳の先に、ひんやりとした静寂を感じる。
静寂。あたりはしんとしている。公園は、盆地のへりにむかう坂道の途中にあって、あたりは住宅地だから、この時刻となれば人どおりもほとんどない。このたびの災禍のために、遅くに出歩く人も少なくなった。そのためか、車もあまりとおらない。
静寂。風のない夜にうごくものはない。電灯が白い光を投げおろし、草むらを照らしている。遊具はこおりついて動かない。地面を踏む音も絶えた(そもそも、ぼくたちうさぎはあまり足音をたてない。J・R・R・トールキン『ホビットの冒険』で、〈しのびの者〉と呼ばれた種族のモデルになったのは伊達ではない)。
静寂。世界が静止したような夜。これが夜のほんらいの姿であろう。人間は昼の世界の生きものである。したがって、われわれのような人間社会で働く動物を含めた「人間の文明」は、夜ねむるべきなのだ。
○夜こそは、われわれ知性生物のいない世界である。その平衡があって、はじめて昼の世界――知性生物の世界――人間の世界は明確になってくる。
人間はひとりでは生きられない、そのゆえに社会を作るのだが、してみれば、人間はその本質において孤独であり、ひとりぼっちであるからこそ、他者を求め、認識し、協調し、共働してこの世界を生きるのである。
するならば、他者は他者として、侵すべからざるものであるべきだし、それは、なにも人類にかぎらず、われわれ知性生物であっても、草木も、風も、大地も、侵すべからざる他者として、存在を認めるべきなのだ。そして、おのれが生きるのに必要な「分」を守るためにも、一線引いて踏み越えぬようにせねばならぬ――いわんや「夜」をや。
○夜が昼にならないのは、この地球の宿命である。夜が昼になる地球であれば、われわれはそもそも生じていない。
その事実をねじまげて、夜を昼のように照らしたのは、人類をはじめとした知性生物の業である。だが、そうして夜を侵して、得たものはなんであろうか。「眠りを殺した」ものがどうなったかは、シェイクスピアの傑作ノワール劇を見ればわかろうものだ。「夜」を侵してはならなかったのだ。秋谷悪左衛門が言う、「人間の瞬く間」の世界は、「人でなしの国」であるからだ――「人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう」、だのに、ただおのれの存在を誇示せんがため、あるいは、おのれと他者の境目を孤立のいいわけにして、ほんらいは避けてとおれないはずの「孤独」から目をそらすために、他者の世界に踏み込んでいった。それは、余計なことだったのだ。
○あの日――ちょうど一年前の四月七日、新型コロナウィルスの感染拡大に対応した、最初の緊急事態宣言が発出された。新型コロナウィルスが「脅威」とみなされてから、それなりに時間は経っていたものの、感染が
拡大してゆく状況が「緊急事態」であるということが、公的な認知となった日だった。
その日のおもいを、あとからさかのぼって、ぼくは以下のように書いた(この日記を書くことにしたのは四月十八日である)。
山田風太郎『戦中派不戦日記』は、若き日のかれが見た「昭和二十年」、すなわち西暦一九四五年の一月から住専に至るまでの八ヶ月と、その後の四ヶ月を大晦日までつづる。
それは、かれにいわく、
「あの戦争の、特に民衆の精細な記録があれば今どれくらい貴重な文献になるだろう」
との理由であるが、この日記にも似たような役が果たせはしないだろうかというつもりがある。なんとなれば、いまの日本人は、七十五年前の「戦中」と同じだからである。
――二〇二〇年四月七日の日記より。
(太字強調は引用時に付与)
この感覚があってから、まる一年が経った。その間は、まさに「戦中」のそれであったといえよう。
政府は、新型コロナウィルスの感染対策を「戦い」と言い、「勝ち抜く」というような言いかたで、先ゆきに希望を持たせようとしながら、後手後手の対応だけではなく、利権にまみれた無益な策をも弄してきた。あげくが、一度は延期を決断したオリンピックを、そのときと比べても感染拡大がおさまりきらないのに、今度は開催をもくろむ始末である。
対して、国民は、政府の後手後手の対策に翻弄され、不安からくる混乱と疑心に追いたてられて、生活必需品を買い占め、SNSで他者に悪罵をあびせ、「事態を変えるのは、少しずつ、時間をかけておこなうことだ」ということから、目を逸らせようとしてきた。
このことも、七十五年前、敗戦の翌日に、山田風太郎はすでに書いていた。
古い日本は滅んだ。富国強兵の日本は消滅した。吾々はすべてを洗い流し、一刻も早く過去を忘れて、新しい美と正義の日本を築かねばならぬ――こういう考え方は、絶対に禁物である。
[中略]
全然新しい日本など、考えてもならず、また考えても実現不可能な話であるし、そんな日本を作ったとしても、一朝事あればたちまち脆く崩壊してしまうだろう。
――山田風太郎『戦中派不戦日記』より。
(太字強調は引用者)
ここに言う「新しい日本」を、「新しい生活様式」だの「ウィズコロナ時代」だのということばに置き換えられることは、すぐにも察せられることだろう。新型コロナウィルスに「勝とう」とし、あるいは「新しい」生活様式を早急に打ち立てて順応しようとするなど、やろうとすること、発想することが、七十五年前となにもかわっていないのだ。
山田風太郎の卓見は、その原因をも、以下のように指摘している。
「なぜか?」
日本人はこういう疑問を起こすことが稀である。まして、
「なぜこうなったのか」というその経過を分析し、徹底的に探究し、そこから一法則を抽出することなど全然思いつかない。考えてできないのではなく、全然そういう考え方に頭脳を向けないのである。一口にいえば、浅薄なのである。上すべりなのである。いい加減なのである。
――山田風太郎『戦中派不戦日記』より。
(太字強調は引用者)
ついでながら、過去の日本の教育に関して、もう一つ痛恨の念に耐えないのは、それが各自の個性を尊重しなかった点である。頭を出せばこれを打つ。少し異なった道へ歩もうとすればこれを追い返す。かくて個人個人には全く独立独特の筋金の入らないドングリの大群のごとき日本人が鋳出された。
個人主義は利己主義と同意語と思いこんでいる一般日本人の無知笑うべきかな。憎むべきかな。
――山田風太郎『戦中派不戦日記』より。
(太字強調は引用者)
個性を尊重せず、個人主義を利己主義と同意語と思いこむ――こんなこころを持っているからこそ、日本人は、人類は、知性存在は、他者の存在を認めず、おのれの世界を歩くように他者の世界に踏み込むといった、「余計なこと」をしてしまう。
そして、その結果引き起こされた事態に対峙して、「なぜこうなったのか」というその経過を分析し、徹底的に探究し、そこから一法則を抽出することなど全然思いつかない――だから、なにごとも明確な意志のもとになしとげられるということがない。
人類の宿痾は、日本人の性質は、七十五年たっても、少しも変わっていない。
だが、それは人類と、人類の文化圏に生きる知性生物のことであって、基盤となる世界は変わらない。その変わらない世界から現れた、今回の災禍によって、人類の「余計なこと」が、すこしだけなくなった。
結果、夜が、すこしだけ、ほんらいの姿に戻ったのである。
○静寂。
公園には、ぼくと、相棒の下品ラビットしかいない。
世界には、ただぼくたちだけになっていた。
ぼくたちはマスクを外した。夜の空気を吸い込んだ。
マスクをとおさない、ひんやりとした空気は、舌先にここちよかった。
○新型コロナウィルスの災禍と、その「禍」がもたらす社会の動き――「コロナ渦」は、巨大な渦を巻いて、世界を覆い尽くした。これが動きをとめることは、いずれあることだろうが、すぐではあるまい。今日も新たな感染者が出ている。ワクチン接種はいまだ開始せず、東京オリンピックは開催する方向で社会は動いている。後者は、人の愚かさによるものであるが、前者は、ウィルスという「他者」、そしてそういう他者の集合体としての「世界」のものであるからには、その余波であるところの後者も含めて、神ならぬ個人――個人としてのこの社会――にはどうしようもないことであろう。この動きがとまるとして、それは、一年前のきょうから、いまのいままで、ぼくがつづってきたこの日記が、とおい過去の記録としてのみ、われわれの記憶に留まるようになったときである。あるいは、だれの記憶からも忘れ去られたときだろうか。
○運命の一年はこうして終わる。
日本は、人類は、混乱したままである。ぼくたちも、なにをどうしていいか、どうなったらよいか、わからないままこの一年を過ごした。
だが、どうにかこうにか、他者に染まらずにやってこれた。
しょせん、ぼくたちには他者をどうすることもできないのだ。できることは、ただ、おのれの「分」を認識して、そこが他者に染まらぬようにするだけである。
もちろん、他者を尊重はしよう。しかし、ほかに誰もいないところでは、マスクをはずして、好きなようにしよう。そうして、ぼくはぼくで、他者は他者で、ともに孤独なものとして、手をたずさえて生きてゆくのだ。
われわれは他者とともに生きなければならない。しかし、他者に近づきすぎてはいけない。この距離感を、ぼくはこの一年で得た――あるいは取り戻したように感じたが、この「不染」もまた、新型コロナウィルスの「渦」であったのだろう。
○下品ラビットが、飲んでいたホットコーヒーをベンチに置き、タバコを取り出した。
「アメリカンスピリットじゃあないけどな」
一本くわえて、マッチを擦った。
夜が少しだけ明るくなった。
ぼくも一本くわえて、火をつけた。
「やっぱり、こうでなくっちゃあな」
はき出した煙は、公園の照明が投げる光を受けて、紫色に見えた。
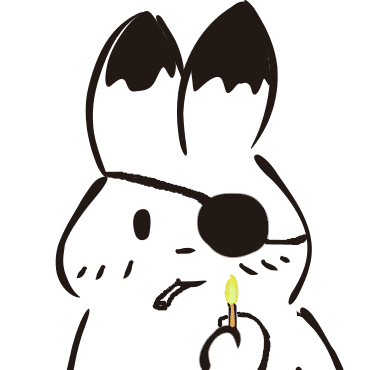
(おしまい)
引用・参考文献
イラスト
「ダ鳥獣ギ画」(https://chojugiga.com/)
いただきましたサポートは、サークル活動の資金にさせていただきます。
