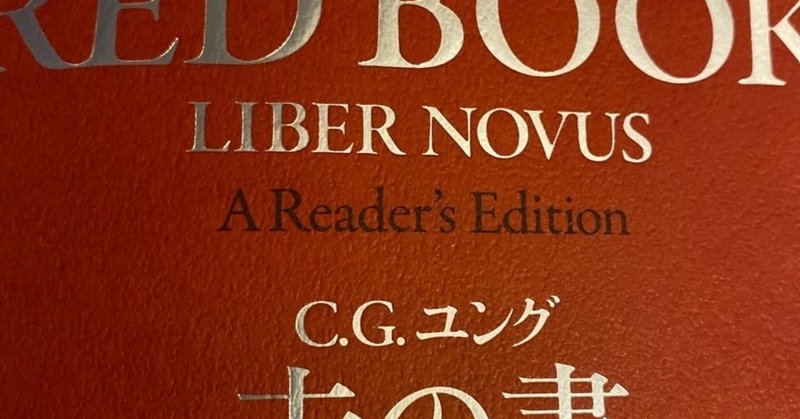
象徴という人間の自然が新しい神にー読書メモ:ユング『赤の書(テキスト版)』(1)
異なる複数の個人たちの間で、象徴を共有する、象徴の流れを同期させる。
そうすることで人類は、死すべき孤独な自分の目に映る世界を「他者たちのもの」にする。
自分より前に生きた他者と、自分の死後に生まれるであろう他者。そうした他者たちと同じひとつの世界を共有していると信じること。自分は確固たる世界に生まれ、たまたまそこで生き、そしてこの世界は当面は続くのであろうと一応信じる。そうすることで、この生をやり過ごすことも悪くないと、思いたいのである。
象徴の共有、象徴の流れの同期化。
それを生身のひとりひとりの肉体の間で実行しようなどとは、大それたことである。
その橋頭堡の、さらに基礎は、ユングのいう「集合的無意識」にある。
私たち一人ひとりが遺伝によって受け継いだ神経ネットワーウの構造。
この基礎のさらに基礎には、分子の形と動きをパターン化する力が隠れているが、そこまで降りるともはや人間と動物、動物と植物の区別さえ無効になる。
生身の声
集合的無意識に覆いかぶさり、そこに深く根を下ろして寄生するのが言語システムである。
言語システムというのは抽象的なものではなく、そもそもは誰かしら特定の喋る他者の生身の身体として迫りくるものである。その目、表情、声、四肢の筋肉のこわばり。
おそらく数万年前から、私たちの祖先である子どもたちは、生まれもった神経ネットワークに、目の前の大人の身体のあらゆる表面から立ち上がる「記号」を介して、言語システムを擦込まれてきた。
擦込まれた記号が織りなす体系は、今度は神経ネットワークの一部となり、外界を外界としてシミュレートして認識する「意識」の挙動を支え、方向づける。そうして記号によってシミュレートされた世界が、感覚器官に捉えられるあらゆる外観の向こうに「読み込まれる」ようにもなる。
文字は声の主を遠隔化・一方的に、つまり神にする
数千年前の文字の発明に至り、記号は記号そのものとして自立した。
口と耳、その他あらゆる生身の身体を介した擦込みは、二次的なものとなり、そのはるか彼方に、「神」と呼ばれるような単一の発声元かつ文字を刻み込む者が永遠不変に立ちはだかるようになった。
言語システムは、あらゆるものの名とあらゆる言葉は、その最初に発声し、文字を刻んだ者のところで、完全に完成済である。というように。
近世に至っての印刷技術の発明は同じ文字を機械的に大量生産し世界中にばらまくというやり方で、ますます言語システムを、「神のもの」という外観に接近させた。
その力はあまりにも強力で、それまで「神」だと信じられてきた沈黙する声の主をさらにはるかに遡り、数式で記述される自然そのもの、宇宙そのものの法則性と運命という新しい神のところまで、神観念を遠隔化した。
神と身体の情動
そして現在に至る電子メディアの、リアルタイムに同期したパーソナルな記号交換回路は、二つのかけ離れた極限へと、私たちの言語システムを、言語システムに憑依された神経システムを、引き裂こうとする。
一方の極限は、文字の登場以来の彼方の神の方である。すべての言葉はそこで生産され、完成品として合格印を押され、整然と並んでいる。
他方の極限は、意識にとっての最凶の他者である「自己の身体」、その激情とともに蠢き、揺らめく、生身の肉体そのものとしての声、あるいは叫びである。
神が貯蔵する完成した文字と、言葉にならない、言葉以前の叫びや呻きのような声。神の文字があまりにも遠くへと飛び去ってしまった現代において、しばしば私たちは、自分自身の生身の身体の呻きを、タンパク質の集合体そのものを生み出した「自然」という神が、その神聖な文字を読み上げる聖なる呪文だと、想うようになる。
情動の爆発こそ、人間と世界の間で、予め書き込まれた通りのパターンで確実に進行するプロセスである。
象徴の激流の中で吹き飛んでしまいそうな言語システムを結びつけておくことができる錘は、神によって書かれた文字が並ぶ聖典ではなくなる。新しい錘は、人間の身体における信号の流れ、神経伝達物質の動きの方である。
そうして人類は、情動を神として、その命じるところに従うことこそが、より自然に、新しい神の命じる処に、叶っているように想う。
象徴との対話
ユングが『赤の書』に記したものは、自分自身の意識の表層に浮かび上がる、象徴たちとの対決の記録である。
死すべき運命の中で、一直線に解体への坂道を転がり落ちる生の過程と、そこで湧き上がり続ける象徴たち。それに対して、意識=意味は、一体どう折り合いをつけることができるか?
もし今、何十億というひとのひとりひとりが、自分自身の象徴と対峙し、それを意識にとどめ、パーソナライズされた『赤の書』を記すことができるならば。
人間はおそらく、文字の発明以降最大の発明をすることになるだろう。
その発明は、記号を文字という囚われの姿から解放しながらも、生身の身体に送り返すことなく、象徴それ自体として保ち、象徴から象徴への変容の余地を確保し、そうしてその変容を日常の言葉に翻訳する口ぶりを許す。
そうして身体であり、そこに憑依する言語システムである「わたし」は、一人の死すべきタンパク質の集合的流体としての運命に戦慄する。そして、その集合的流体が、象徴が永遠に変容し続けるプロセスを進行させる歴史を超えたネットワーク状の配管の一部として、永遠に生き続ける可能性の前に、私は言葉を失う。言葉を失いながらも、一つ一つ、自分自身が初めて出会う象徴たちが通り過ぎるところへ、一言二言、なにか声をかけてみようとするのである。
おわり
関連note
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
