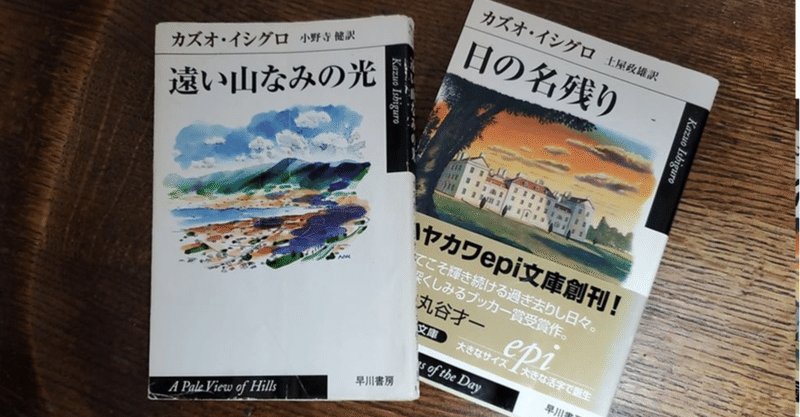
カズオ・イシグロに最適の年齢 ①「遠い山なみの光」
カズオ・イシグロに最適の年齢 はじめに
日本において、日本人が考えると、出世作、英語圏で最大の文学賞、ブッカー賞を受賞した『日の名残り』における最大の謎は、「なぜ日本生まれの彼が、(国籍はイギリスであり、言語も英語がネイティブとはいえ)、最もイギリス的な、古い名家のお屋敷の『執事頭』という職業を題材・舞台にしたのか、」ということになりやすいのだが。
しかし冷静に考えると、『日の名残り』執筆当時、まだ三十代半ばであるイシグロが、なぜ、人生の終盤の、仕事においても愛情生活においても、もう取り返しのつかない年齢になった老執事の、様々な意味で、取り返しのつかない人生の失敗への後悔をテーマに選んだか、という方が、より不思議ではあるまいか。
ここで「題材・舞台」と「テーマ」という言葉を使ったが、イシグロの他の作品、最新作までまとめて眺めれば、「題材・舞台」は、バリエーションが極めて豊かである。戦後日本を舞台にした小説から、不条理小説・探偵小説、未来舞台のSFに、中世騎士ファンタジーとバリエーションが豊かだ。というか、一作ごとにそのアプローチを大きく変えること自体がその小説家としての特徴と見なされている。
一方、「テーマ」に関しては、「人生終盤における、取り返しのつかない後悔」をめぐるものが多い、ということは、漠然とイメージできる。(これについては後ほど詳細に検討する。)イシグロは一貫して「人生の終盤における後悔を、先回りして心配し続けてきた作家」と呼べるのではないか。これが、本稿で私が書きたいことの中心である。
イシグロの小説家としての「テーマ」ということでいうと、世間一般的には「記憶をテーマとして書き続けている作家」という定説が流布している。
ノーベル賞の選定理由では、もうちょっとややこしい言い方がされている。Wikipediaから「受賞理由として『壮大な感情の力を持った小説を通し、世界と結びついているという、我々の幻想的感覚に隠された深淵を暴いた』。
なんか、難しいけれど、記憶があいまいでよくわからなかったことが、物語が進むうちに、個人の深淵が世界と結びついていることが明らかになっていくということだ、平明に言うと。それを記憶のあいまいさを軸に書いた、ということだ、定番的評価で言うと。
天下のノーベル賞選考委員会に、私のようなものが文句をつけて申し訳ないが、私はこうした通説にはいささかの違和感がある。
記憶があいまいであることも、それが最終的に世界の深淵と結びついていることも、そういって置けば、それは概念が広くなるから、間違いにはならないけれど。僕がここで試みようとしているのは、もっと明確な、切実なある情緒・感情に紐づいた、明確なテーマについて、イシグロは、繰り返し繰り返し書かれているのではないか、ということを明らかにしていきたいのだ。
たしかに、ごく普通に読めば、どの小説も記憶のあいまいさ、無意識のうちに記憶が改竄されること。それを巡って展開される小説が多いことは誰でも異論がない。私にもない。
とはいえ、さきほど「題材・舞台」と「テーマ」という言葉を使ったが、イシグロにおける「記憶」というのは、果たしてテーマなのだろうか、そこに、私は疑問があるのだ。
私の仮説をまず、提示しておきたい。 私は、前述のとおり、イシグロ作品に通底するテーマは「人生の取り返しのつかない段階における、様々な意味での後悔」であると、考えている。すると、小説は、必然的に、すでに過ぎてしまった人生を、人生最終盤に入った主人公が「回顧」するという形をとることになる。そうすれば、必然的に「記憶」をめぐる、その不確かさや、自己正当化のための無意識的改竄や、都合の悪いことが意識下に押し込められる忘却といったことを通して叙述することになる。そうした記憶の特徴が、文学としての緊迫感やドラマ性を高めることになる。(いわゆる信用できない話者、というやつだ。)一人称小説であれば、主人公が回顧しつつ語ることになるのだが、それが本当に真実なのかどうかがよくわからない、という状態のまま小説を読み進むことになるからだ。
つまり、「記憶」というのは、「人生終盤における取り返しのつかない後悔」というテーマを描くことに付随して必然的に描かれる、「文学的な語りの装置」である、というのが、私の、とりあえずの仮説なのである。
「「テーマ」と「設定・舞台」と「文学的な語りの装置」 を意識して切り分けて分析することで、カズオ・イシグロの文学についての通説「日本出身でありながら英国伝統の世界をテーマにした」とか、「カズオイシグロは記憶をテーマにした作家である」というような曖昧な物言い定説の霧を晴らし、イシグロが一貫して描こうとしている「テーマそのもの」を、より詳細、精緻に分析していこうというのが、本論の狙いである。「人生終盤における、取り返しのつない後悔について、非常に若い時期から、先回りして心配し続け、作品にし続けてきた小説家」というのが、カズオ・イシグロである、ということについて、では、個別作品で、そのことを見ていきましょう。
『遠い山なみの光』
Amazon内容紹介
「内容(「BOOK」データベースより)
故国を去り英国に住む悦子は、娘の自殺に直面し、喪失感の中で自らの来し方に想いを馳せる。戦後まもない長崎で、悦子はある母娘に出会った。あてにならぬ男に未来を託そうとする母親と、不気味な幻影に怯える娘は、悦子の不安をかきたてた。だが、あの頃は誰もが傷つき、何とか立ち上がろうと懸命だったのだ。淡く微かな光を求めて生きる人々の姿を端正に描くデビュー作。王立文学協会賞受賞作。」
小説家を志したイシグロが、まず、日本における記憶を定着し、自らのアイデンティティを明確にしようと書かれた小説であると同時に、まさに「取り返しのつかない過去を回想する話」という、イシグロ小説の「型」が、ここですでに確立している。
イシグロ本人は、1954年生まれである。日本を離れた時、イシグロは五歳であり、父親が四十歳、そして、祖父が七十歳である。世代関係で言うと、『遠い山なみの光』で言えば、長崎で、語り手、悦子の体内にいる胎児が、イシグロの分身である。その後日本で生まれ、幼くして親に伴ってイギリスに渡って、小説冒頭時点では、何らかの理由で自殺したとされる景子が、立場としてはイシグロに重なる。
世代関係、境遇で言えば、自分にあたる人物は自殺している。その母親が、英国に住みながら、日本での、自分と、夫、義父、友人のことを回想するという小説である。
ひとつ、確認しておくと、イシグロは、1954年の生まれであり、実際は小説に描かれる敗戦後すぐの混乱時期には生まれていないのである。イシグロが物心ついてぎりぎり記憶のある1960年の日本というのは、高度成長期に日本が入ろうとする、戦後の混乱がほぼ収束した時期である。
ではなぜ、イシグロは、実際の自分の記憶、実人生より、もうすこし時代を遡った「敗戦数年後」という時代を、はじめの長編小説の舞台に選んだのであろうか。
それは、イギリスという国において、日本にルーツを持つ自分が小説を書くにあたっての、アイデンティティと、ある種「政治的立場」を小説の中に織り込む必要を感じたのではないか、というのが私の想像である。
話は少し遠回りするが、(そういう言葉は、当時、言われていなかったであろうが)、文学を書く意識の中に、「ポリティカル・コレクトネス」への配慮が侵入することは、現在でも多くある。いや、現在において、非常に強まりつつある。日本の小説の新人賞受賞作の多くに、設定的にそこには必然性があまりなさそうなのに、性的少数者や差別を受ける立場の登場人物やエピソードが挿入されていることが、よくある。そのこと自体をテーマにした小説ならともかく、そうではないサブの登場人物、サブのエピソードとして挿入されるのである。なぜだろう、現実にそういうことが増えているのかしら、とも思う。それもあるが、それ以上に、(これは二〇代で小説を書いている長男と話をするときにも常々感じることだが、)ポリコレに対して意識が高い、ということを、きちんと作品内で表明することは、文学者として生きていくうえで不可欠な要素、必要条件と彼やその同世代の文学者たちは思っているようだからである。私からすれば、それは個人としてそうであれば十分で、作品に必然性のないそうした要素を、新人作家たちがそろいもそろって小説に持ち込もうとすることには大きな違和感を持つ。「処女作」を書こうとしたときには、そのことを、小説内にきちんと表現しておくことが大切、という意識が働くようなのである。
先の大戦の戦勝国であるイギリスにおいて、これから小説家としてのキャリアを築いていこうというイシグロにとって、「日本出身である」ということ(この小説を書くときは、まだ帰化していないので、国籍としても日本人)は、魅力化という意味での差別化強みとして利用すべきであった一方で、日本人として、先の大戦への態度を表明しておく必要性、プレッシャーが無意識のうちに働いたのではないか。
日本人であるということは、当時はまだ、他の作家にはない魅力としての「差別化」(マーケティング用語としての差別化)要素であるよりも、リアルに政治的な意味で「差別」される要素として存在したのではないか。
米国などと較べると人種差別は強くなかったのかもしれないが、戦後の、まだ保守的な価値観も残る60年代のイギリスで、日本出身の少年として育ったイシグロは、(特にそうした体験を語ることも、文学の中に持ち込むことも、イシグロにはほとんどないが、) 全く意識しなかったとも思えない。東南アジアの戦線で、日本軍との戦争を直接体験した人たちも、当時のイギリス社会には、いたことだろう。イギリス人にとっての先の大戦は「主にナチスドイツと戦った」という意識が強いにしても、日本人というのは元・敵国の人間である。
初めの長編小説を書いて、イギリスの文学界に自らの存在を認めさせようと考えた時に、それを自らの個性、強みとして利用しようという思いと同時に、「先の戦争について、敗戦国にルーツを持つ文学者として、どのように考えているのか」を、作品内で表明しておく必要がある、という意識が、(どこまで明確に意識されたかは分からないが)存在したのではないか。
そのような意識が、小説の時代設定を、実際に持っている記憶、一九六〇年近くではなく、十数年遡った、戦中から戦後にかけての日本(それも、事実故郷ではあるが、長崎という特別な意味を持つ都市)を舞台にさせてたのではないか。時代をずらすことによって、そこに、「戦争責任、加害国、戦争の交戦国・敗戦国としての日本の責任というものをイシグロがどうとらえているのか」ということを、より明確に織り込むことが可能になるからだ。
(イシグロから見た世代呼称で分類すれば)「祖父・戦時中に戦争に加担した世代」「父・母 戦時中にはまだ戦争に責任は負っておらず、戦後にそれを批判した世代」「自分自身、戦後に生まれ、戦争自体の記憶がない、戦後民主主義の中で育った世代」と、一口に「日本人」といっても、そのような世代が重なっているということを、イギリスの読者に、知ってもらうこと。そしてイシグロという作家は、戦争について記憶がない、新しい世代(日本で生まれでイギリスに渡った景子と同じ)に属することを、イシグロはこの作品の基本構図として提示している。
戦後を舞台にすることで「戦中から戦後への価値観の大きな転換」の中で、「戦争に加担した祖父世代」と「それを批判する父世代」の間の葛藤が明確に浮かび上がる。祖父世代を中心に言えば、多くは悪意はなく、懸命にまっとうに生きる中で、結果として戦争に加担してしまった祖父世代の複雑な気持ち、というものが中心になっていく。
この『遠い山なみの光』でいえば、教師として戦中に、戦争や天皇を神とする教育をしてきた義父が「祖父世代。」。戦後になり、それをかつての部下に激しく批判、糾弾される。(語り手、主人公悦子から見て、作中、最も好ましい人物、好きな人物として描かれる義父が、その糾弾されて苦しむさまを、悦子は見つめるのである。)それを、家族の中の「父(祖父世代)と息子(父世代)」「義父と嫁」という、愛憎の複雑な感情として織り上げられていく。政治的後悔、葛藤と、個人生活の愛情が複雑に絡み合う。ここに、イシグロ小説、最大の特質が表れているのである。
のちの他の小説でも幾度も繰り返される「祖父」「実子(息子や娘)」「嫁や婿」「孫」の三世代のやりとり交流を通じて、複雑なその感情を描くという、イシグロ小説のひとつの特徴がここですでに生まれていることがわかる。
ちなみに、この「老父と嫁」「老父と息子」の会話劇というのは、イシグロ自身が小津や成瀬の映画などから影響を受けた「想像の中の、自分が創造した日本」である、と語っている。つまり、読者が「イシグロの日本における幼少時の記憶」として受け取っている小説の描写の中に、作家としての嘘、記憶とフィクションを織り交ぜる嘘が上手に塗り込まれているのだ。(日本を離れる当時五歳のイシグロに、そのような複雑な事情や家族の感情の機微が、明確に意識、記憶されていたと考えるのは無理があるだろう。)
繰り返しになるが、この小説における「取り返しのつかない人生の後悔」は、
①戦争への加担をめぐる義父(祖父世代)の後悔。それは、日本人がイギリスで文学を書く中で、「戦争責任の問題」に対する考え方を表明し、自分の世代がその中で、どのような位置にあるものなのかを語る必要があったというイシグロへの無意識的要請が、明確なテーマとして形作られたものだと私は思う。
②幼い子供を連れて英国に渡り、ある人生の時間が過ぎたのち、つれていった娘を自殺で無くすという、語り手の後悔。これは、政治的なものではない。家族関係の中での、人が人生の中で向き合う、愛の後悔に関わる問題である。こどもを自殺で亡くすという、取り返しのつかない人生の空漠。
戦争をめぐる、政治的立場と振る舞いについての、取り返しのつかない後悔と、愛するものを失うという、個人の生活の、人生終盤での、取り返しのつかない後悔。このふたつがイシグロの胸に、いつもいつも、のしかかってくるのだ。まだ若いのに、人生の終盤のそれを想像してしまうのだ。 イシグロという作家は。
第二回は『浮世の画家』です。下のアンダーライン部分をクリックすると飛びます。
カズオ・イシグロに最適の年齢 ②『浮世の画家』から『日の名残り』へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
