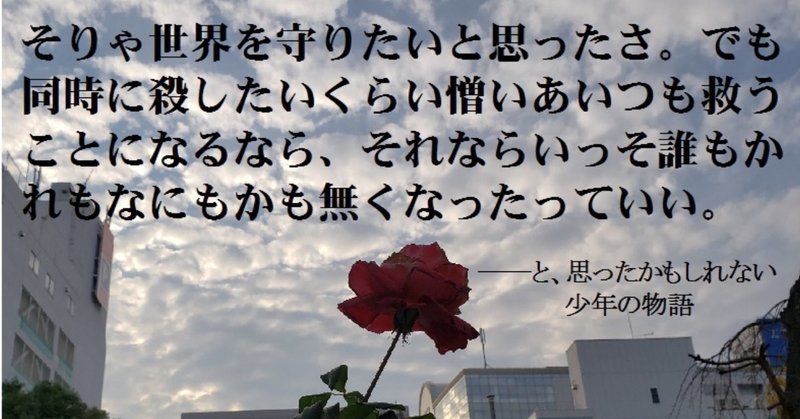
「四度目の夏」4
父さんとおじいちゃん
四年前のある日突然、父さんがかつて生まれ育った白雲岳に行くぞと言い出した時には「お父さんはちょっとホームシックにかかったのかもしれないわね」と母さんは言った。
だけど本当のところ、ぼくには父さんの気持ちがわからなかった。ただ、三年前に初めて白雲岳を見た時、その圧倒的な大きさとむきだしの岩肌に蔓延(はびこ)る野性の松の木と、長い歴史を見つめてきた本堂の焦がしたような真っ黒い木造建築に声がでなかった。
父さんは息子のぼくにこれが見せたかったんだと長い往路も納得した。
父さんの先祖代々が住職を務める白雲寺の歴史や、その宗派のことだって知らないけれど、ぼくはここにいたいと思った。それはこの寺を継ぎたいということではなくて、この景色がぼくの人生に大きく関わる、そんなイメージを持ったのだと思う。
「でもぼくはここが好きだよ。ぜったいこの夏休みはここで過ごしたいと思ってたんだ」
「朝のお勤めめもできるかい?」
朝のお勤めとは早朝の本堂での読経のことだ。
「うん、むしろすごく楽しみ。お経は覚えていないけれど、気分が清々しくなるもの」
「君の二番目のお母さんは、滞在中一度も起きてはくれなかったけど、君がそう言ってくれるとなんだか僕も嬉しくなるよ」
「いまでも修験者のひとたち来るんでしょ?」
「今年は今のところ予約ないね。毎日ネットとにらめっこしてるんだけど。一時は外国人も多かったんだけどなぁ」
「虹池の滝修行が厳しすぎるのよ。最近の若い人はあまり辛いことはしたくないものなのよ」
「にいやん、おれ、経典が読めるようになったんで!」
よっくんがご飯を頬張って得意げに言った。
「へぇ! すごいね」
ぼくは益司さんの読経のなか、目で文字を追うのが精一杯だ。
「義之は毎朝すごく眠そうだけどな」
よっくんは固まった笑顔をぷいとそらした。
ぼくも正直に言うと朝はものすごく弱かった。三年前の初めてのお勤めはあくびを噛み殺すのに必死だった。でも勤行を終えてお堂を出るときのあの朝日に当たる気持ち良さはなんともいえなかった。
「おれまだ鐘はつかせてもらえんのんよ」
よっくんが小声で言った。
「それはまだ手が届かないからだよ」
益司さんが言った。
「手は届くわ!」
「背伸びしてやっとね」
佳菜江さんが言った。
清掃を終えたら、朝の6時きっかりに鐘をつくこともお勤めの一つだった。
「今年は君が鐘を突いてみるかい?」
益司さんがぼくに笑いかける。
「いいの?」
急に心臓がドキドキした。あの鐘、朝の6時と夕方の6時に鐘を突くけれど、日中にも夜中にも鐘をつきたくてたまらない衝動にかられる。あの音はほんとうに不思議だ。
「なぁに? 将来はお坊さんになるつもり?」
佳奈江さんが笑いながら訊く。
「ちがうよ。よっくんが白泉寺の住職になるのを邪魔しない」
「あらやだ、子供らしくないセリフ」
佳奈江さんが言った。
「義之が住職になるのはまだまだ当分先のことだよ」
益司さんが言う。
ふと思った。
「おじいちゃんは? 寝室?」
最近は寝てばかりと聞くぼくのおじいちゃんだ。
「日中は寝ているけど、夕飯だけは起きて食べるのよ。もう食卓についてるわ。今日あなたが来ることは伝えてるんだけど、顔を見てもわからないかも……許してあげてね」
「うん。大丈夫、わかってる」
じいちゃんは認知症が進んで、去年のぼくのことだってわかってなかった。
それでも中学生になったことを伝えると「ほうか、大きくなったなぁ」と顔中皺だらけで喜んでくれた。
そして痩せた大きな手でぼくの頭を撫でた……叩いたわけじゃないと思いたい。力の加減がわからないのか、撫でているつもりだと思うけど、ぼくには痛かった。それからぼくはおじいちゃんが、なんとなく苦手になった。
食堂に入るとおじいちゃんが大きな8人がけのテーブルの一番奥に座っていた。痩せて細くなったおじいちゃんはグレーのスウェットを着ていた。去年までは着物だったり作務衣だったのに、きっと着替えがしやすいようにスウェットになったのだと思う。でもスウェット姿のおじいちゃんは威厳が10分の一くらいになって見える。
その横にみっちゃんが子供用の椅子に座っていた。ふたりとも食事用の前掛けをしてた。
みっちゃんはうさぎさんのイラストが入ったスタイを。じいちゃんは青いナイロン製のエプロンを。並んで座っているけど、じいちゃんのほうが体は大きいし、もちろんずっと年上なんだけど、小さなみっちゃんよりずっと弱々しく見えた。
「おじいちゃん、こんにちは。ぼくだよ、わかる?」
おじいちゃんに話しかけると、おじいちゃんは白目の濁った虚ろな目をぼくにむけて、「おお、おお、わかる、わかる」と顎をカクンと落とした。頷いたらしい。俯いたままおじいちゃんが言った。
「ようすけ、いつ帰ってきたんじゃ」
陽介は父さんの名前だ。
「この子は陽介じゃないわよ。陽介兄さんの息子。東京からわざわざ会いに来てくれたのよ」
佳奈江さんが言った。
佳奈恵さんの言葉にはっとしてじいちゃんがまたぼくを見た。
「ああ、そうか、そうか、そりゃすまんことしたのう」
そう言って、ぼくに向けて手を伸ばした。去年みたいに頭を撫でてくれるのかな、と思って思わずぼくは膝を折った――ら、いきなり後頭部を叩かれた。
「お前は―! よくも恥ずかしげもなくここに帰ったもんじゃ! 寺も檀家も捨ておって!」
「おじいちゃん! この子は兄さんじゃないってば!」
「もうほんにおじいさん、しっかりしてくださいよ! この子は陽介の息子だぁね。よう見てぇさいよ! まだこの子は中学生だぁね!」
おじいちゃんは驚いたように目を見開いてまた顎をカクンと落とした。
「ああ、ほうか。ほうか。ひと違いか。すまなんだ……」
「ごめんね、おじいちゃん最近認知症が入っちゃって……」
「あ、いや……大丈……」「ひっく、ひっひっ、ぅわあああああん」
みっちゃんがしゃっくりを二三度したと思ったら大声で泣き始めた。
じいちゃんの怒鳴り声と佳奈江さんの叫び声にびっくりしたんだろう。
佳菜江さんがみっちゃんを抱き上げてもなかなか泣き止まなくて、ぼくはその声にしだいに胸が苦しくなって、食欲なんかすっかりなくなってしまった。
「本当に大丈夫かい?」
益司さんが訊いた。
佳奈江さんがなにか言いたそうに口を開いたけど、とっさにぼくはそれをさえぎるよに言った。「大丈夫です。いい匂い。嬉しいな、ご馳走だ」
ぼくは空いている椅子を引いた。
おじいちゃんを見ると、目をつぶってまるで何かを食べているように頬の中で歯を動かしている。口の中にはなにもないはずだ。
「ほんとにごめんね」
佳奈江さんがまた言った。さっき言いたそうにしたのはこれだったんだ。結局聞くことになってしまった。ぼくは首を横に振った。
おじいちゃんが認知症なのは知っていた。
年に一度しか会わない孫だし、だんだんと忘れられるのは仕方がないと思う。だけど父さんと間違えられたのは今日が初めてだった。
父さんはここに帰ると決まって一度はおじいちゃんと口論になった。
おじいちゃんがここを出て行ってすっかり姿が成金らしくなった父に嫌味を言って、それに耐えられなくなった父さんが悪態をつく。それにおじいちゃんがキレる。さらに激昂する父さん。
楽しくない会話。楽しくない食卓。赤ちゃんだったみっちゃんは大泣きして、小学生低学年だったよっくんは青ざめていた。
ぼくは半泣きで父さんの袖をひっぱって父さんを制したけれど、母さんは黙ってふたりのやり取りを見つめているだけだった。なんで母さんは父さんを止めないのか不思議だった。
去年まで三年連続で夏の怒鳴り声と泣き声の大騒ぎ。益司さんと佳奈江さんはぼくら一家が一体なんのために帰ってくるのか、さぞかし困惑したことだろう。
ぼくに自分のルーツを見せたかった、と益司さんは父さんのことを言ったけれど、たしかにぼくは白雲岳を見てよかったと思ったし、白泉寺に住む父さんの家族に会えて嬉しかったけど、じいちゃんと父さんの口喧嘩だけは、ほんとうにもう、たまらなく嫌だった。
いくらなんでもそんな確執を息子に見せたかったとは思えない。父さんが理性を忘れて殴り掛かりそうなくらい誰かをののしっている姿をはじめて見た。いつだって豪快な、それがぼくの父さんだ。
どうして父さんが寺を継がなかったのか、想像できなくもない。
父さんは田舎暮らしができるタイプの人間ではなかった。派手なものが好きで、お金を稼ぐことが好きで使うことが大好きな人間なのだ。きれいなものに目がなくて女が好きで、食にもこだわる。
それでも父さんは毎年ぼくを連れてここに帰ってきたのは、ぼくを自分の両親に見せたかったこと、そして父さん自身も、父親には会いたくないにせよ、母親には、おばあちゃんには会いたかったのだと思う。父さんは、おばあちゃんにはとにかく優しかった。父さんも誰かの子供だったんだ、と知ったことも息子のぼくには新鮮だった。
父さんとおじいちゃんの口喧嘩に静かにつきあったのが母さんで、母さんは二人の喧嘩を心配そうに見つめるものの、口はしっかりと閉じて、絶対の信頼を寄せている、といったふうに見守っていた。「あれがふたりのコミュニケーションなのよ。おかしいわよね。でも親子にしか通じ合わないコミュニケーションがあるものなのよ」と母さんは言っていた。
ぼくには母さんの言っていることの意味がわからなかった。去年初めて父さんの新しい妻の前でもやはりふたりはいがみ合ったけれど、父さんの新しい妻は父さんの加勢をして、ますますこじれさせた。
母さんはコミュニケーションだと言い、あの女はおじいちゃんの失礼さに本気で怒っていた。
ぼくは、おじいちゃんに頭を叩かれたことをコミュニケーションだとは思えない。
今だって、鉛を飲み込んだみたいに気持ちが落ち込んだままだ。
父さんの奥さんは去年こそ一泊二日はつきあったものの、今年は白雲岳に行くのは絶対にイヤだと言い張って、父さんをキプロス島に連れて行った。
ぼくはぼくで、毎年おじいちゃんと父さんの喧嘩を見たくなかったし、そんな大人たちを小さないとこ達にも見せなくなかったから、父さんが来ないことになって正直ほっとした。
父さんと母さんが海外に出かけている間間、この夏休みのあいだじゅう、この白雲岳で過ごす計画だ。佳奈江さんも益司さんも快く受け入れてくれているし、よっくんとは仲良しだ。人見知りのちいさなみっちゃんともそのうち打ち解けるだろう。
おばあちゃんは――おばあちゃんは父さんが来ないことを寂しがっている。
それはこの山門をまたぐまでのおばあちゃんの背中でわかる。
香りのいい菓子だぁね、と言ったおばあちゃんの声のトーンでわかる。
甘いお菓子なんかよりも、父さんに会いたかったに違いないのだ。
最後まで読んでくださってありがとうございます! 書くことが好きで、ずっと好きで、きっとこれからも好きです。 あなたはわたしの大切な「読んでくれるひと」です。 これからもどうぞよろしくお願いします。
