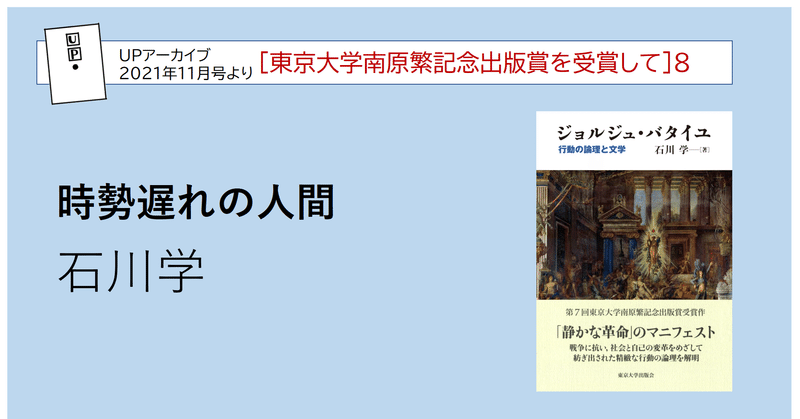
時勢遅れの人間/石川学
すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。其時私は明治の精神が天皇に始まつて天皇に終つたやうな気がしました。最も強く明治の影響を受けた私どもが、其後に生き残つてゐるのは必竟時勢遅れだといふ感じが烈しく私の胸を打ちました。私は明白さまに妻にさう云ひました。妻は笑つて取り合ひませんでしたが、何を思つたものか、突然私に、では殉死でもしたら可からうと調戯ひました(注1)。
夏目漱石『心 先生の遺書』(1914(大正3)年)
私が、東京大学大学院総合文化研究科に提出した博士論文『ジョルジュ・バタイユにおける行動の論理と文学』で第7回東京大学南原繁記念出版賞を受賞したのは、2017(平成29)年3月のことである。その後、翌18年3月に、『ジョルジュ・バタイユ―行動の論理と文学』という題で、刊行の運びとなった。受賞から4年半という年月は、それほど長いものとも言えまいが、この間、状況の推移があった。個人的な事柄に先だって、改元について書いてみたい。
私は1981(昭和56)年の生まれで、現在満40歳である。8歳から38歳までが、平成の年間に該当する。漱石は1867(慶應3)年生まれで1916(大正5)年に没しているから、明治の45年間が生涯とほぼ重なる。大漱石と己をかりそめにも比べようものなら、失笑やお叱りを受けるだろうし、そもそも激動の明治と停滞の平成(「失われた30年」なのだそうだ)を比較することには幾重もの留保がいるだろう。とはいえ確からしいのは、幼少期以来、数十年続いた元号が改まるとき、いかんともしがたい「時勢遅れ」の感覚にとらわれることである。近代以降、一つの元号が付される時代は、各人にとって、若さの喪失を含み込むのに余りある長さとなった。その意味で、改元とは「時勢遅れ」を可視化する制度だと言えるのかもしれない。
乃木大将と「先生」は死に、漱石は生きたが、その生が続いたのは4年だった。享年49歳。大正への改元時に45歳だと思うと、1925(大正14)年に生まれ、昭和(1926-1989年)とともに歩みを進めた三島由紀夫の行年が45歳だったことも想起される。今度は大三島と比べるのかと打擲されそうだが、自分がそうした年齢に近づいてきたことは、事実として感慨がある。
無論、改元が「時勢遅れ」を可視化するにしても、その感覚自体が突然に襲うのではない。乃木大将(1849(嘉永2)-1912(大正元)年)は、西南戦争(1877(明治10)年)で軍旗を失って以来、死に場所を探しながらも機会を得られずにいたと遺書に書いた。62年の生涯のうち、35年間である。これは「時勢遅れ」とは別の感覚だろうし、だいたい乃木大将の心情を云々しては打擲だけで済まなかろうから控えるが、いわばこの持続が「先生」をして、「それから二三日」のうちに自死の決意を固めさせたのである。「先生」もまた、自らの決意を暗黙のうちに追求し続けていたのだろう。天皇の死は、代替のないその契機である。
卑小な私の話に戻ると、南原賞の受賞論文を2018(平成30)年に刊行していただき、翌19年に慶應義塾大学商学部に専任教員として着任した。それまでは任期のある特任教員として生活の糧を得ていたから、個人的に大きな変化である。同年の4月をもって平成は終わり、時代は令和となった。7月には南原賞での刊行作が第36回渋沢・クローデル賞(日仏会館/読売新聞社)奨励賞を受賞するという望外の栄誉を得た。受賞者講演の機会を与えられ、原稿は活字になり、また後日、読売新聞社でのインタビューもあるとのことだった。少しは世に問いかけるような内容を話さなければならないという、柄にもない願いが生じた。そこで、平成の終盤に発せられた、ある政府通達への見解のようなものを談ずることにした。国立大学の「教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院」について、「組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組む」ことを求めた、2015(平成27)年の文部科学大臣通達である。
各界の識者たちが議論を重ねているこの問題について、浅見の委細をここで繰り返そうとは思わない。バタイユが「文学」に見てとろうとした、「行動」(=有用性)の一元支配に抗う力を、今日の文学、さらには人文学に期待することが可能か、また、文学や人文学の側にいかなる決意が必要となるかを、今後の検討課題として提起したということだけ、言及しておきたい。本稿の論点は、「時勢遅れ」の感覚にある。人文学を研究教育の生業にする者として、研究教育を主管とする文部科学省からのこうした否定に接し、それへの抵抗を試みながらも、内なる心情として、「生き残つてゐるのは必竟時勢遅れだといふ感じ」が拭いがたいのである。令和元年=2019年は、私にとって新しい始まりの年だったが、年来の「終わり」の感覚がついに浸透し、分かたれなくなるのを意識せずにはいられなかった。2020年には首相が交代し、一息ついたのも束の間、今度は日本学術会議の任命拒否問題が起こった。その1年後には、件の首相が辞任することになるのだが。
無力に興じているつもりはない。乃木大将の35年を持ち出さずとも、「先生」もまた、死を10日以上先延ばしにして、「私」に「長い自叙伝の一節」を書き残す熱意を持たずにはいなかった。「先生」はこのように言う。
私に乃木さんの死んだ理由が能く解らないやうに、貴方にも私の自殺する訳が明らかに呑み込めないかも知れませんが、もし左右だとすると、それは時勢の推移から来る人間の相違だから仕方がありません。或は箇人の有つて生れた性格の相違と云つた方が確かも知れません。私は私の出来る限り此不可思議な私といふものを、貴方に解らせるやうに、今迄の叙述で己れを尽した積です(注2)。
「時勢遅れ」の人間が、新しい世代の人間のために、理解されないことを覚悟のうえで、理解を得るために力を尽くすこと。無力さの覚悟と、無力への沈滞とはまったく別物であり、己の無力を引き受けたうえで、あくまで伝達の可能性に賭けること。若き「私」に対し、黙って消えゆく自己満足を排した「先生」の誠実さは、文学者漱石の誠実さそのものであり、おそらくは、かつての教育者漱石の誠実さそのものである(注3)。『心』に五年先立つ『それから』(1909(明治42)年)の末尾で、代助は、職業を探すべく街へ飛び出し、「『あゝ動く。世の中が動く』と傍の人に聞える様に云」い、「自分の頭が焼け尽きる迄電車に乗つて行かう」と決意する(注4)。狂気とも絶望とも取れようが、この決意は確かに、「それから」に続いていくのだ。『心』にもまた、「それから」がある。「時勢遅れ」の「先生」が残した言葉に対峙しながら生きていく、若き「私」の「それから」が。
教育者としてのこうした責務を、自身のものとしてあらためて自覚できたのも、令和元年のことであった。渋沢・クローデル賞授賞式での講演内容を考えていたとき、私は教養課程のセミナー形式の授業で、フランスのドレフュス事件(1894(明治27)年)に際しての文学者たちの反応と、日本のいわゆる大逆事件(幸徳事件。1910(明治43)年)に際しての文学者たちの反応を対比する文献を扱っていた。「私は弾劾する」のエミール・ゾラ(1840-1920年)は、日本にはありうべくもなかったが、文学者たちがみな、ただ押し黙っていたわけではない。一高で有名な「謀叛論」の講演を行い、幸徳らを敢然と擁護した徳冨蘆花(1868(明治元)-1927(昭和2)年)は例外にしても、やむなき沈黙に「自ら文学者たる事について甚だしき羞恥を感じ」、「自分の藝術の品位を江戸作者のなした程度まで引下げるに如くはないと思案した(注5)」と『花火』(1919(大正8)年)に書いた永井荷風(1879(明治12)-1959(昭和34)年)は、やはり無力さという「時勢遅れ」の感覚、生誕以前の「江戸」への回帰すら強いるこの感覚に打ちのめされながらも、その無力さを伝達したことにおいて、後代の人々の心を打つのであり、そこには教育者荷風の意地を見てよいように思う。大逆事件はちょうど、荷風が慶應義塾文学科に着任した年の出来事であったのだ。私はといえば、荷風も蘆花も漱石も仰ぎ見る以外にないが、ただし、彼らについて、彼らが書き残した無力について、語ることはできるだろう。こうした自覚を、学生たちと接するなかで、得た気がする。「彼ら」とはもちろん、これらの固有名には限られない。
専門研究に関しても、教育の場から課題を見出す機会を与えられた。「アカデミック・スキルズ」という、学術的な発表の作法や論文の書き方等を指導する授業があり、学習意欲の高い学生が幅広い学部から集まる。1、2年生ということもあろうが、開講まもなく、理性的であることがすなわち倫理的であり、社会問題の解決を導くという素直な信念にしばしば出会った。20世紀の歴史が経験した、合理的思考の帰結としての破局―科学知の極みであり、圧倒的勝利の卓越した手段である原爆がもたらす破局はひとつの典型である―に衝撃を受け、理性の「度外れ」を見据える「至高な感性」の倫理を主張したバタイユ(1897-1962年)の思索を、若き人たちに伝えたいという勝手な思いが頭をもたげた。バタイユの観点を時代的変遷も踏まえつつ検討し、ハンナ・アーレント(1906-1975年)による「悪の陳腐さ」の主題と、ジャン=ピエール・デュピュイ(1941年-)による「賢明な破局論」とに結びつけて論じた文章を、『理性という狂気―G・バタイユから現代世界の倫理へ』(慶應義塾大学出版会、2020(令和2)年)というタイトルで出版することができた。学生を想定読者とした新書サイズの本だが、新しい考察を提示できた部分があると思っている。また、本年9月には、第二次世界大戦期にモーリス・ブランショ(1907-2003年)が『ジュルナル・デ・デバ』紙に寄稿した文芸時評の翻訳を、『文学時評1941-1944』として刊行した(郷原佳以・門間広明・伊藤亮太・髙山花子との共訳。水声社、2021(令和3)年)。訳者のなかで唯一ブランショを専門にしない者として恐れ多くもあったが、ちょうどブランショとバタイユの出会いの時期にあたる時評を担当し、両者の思想交流の端緒について、間々思い至ることがあった。いっそう深め、文章にできればと考えている。
バタイユの言うところでは、ヘーゲル(1770-1831年)は晩年、同じ講義ノートを用い、同じ内容の授業を繰り返していたらしい。ヘーゲルがナポレオン(1769-1821年)に「歴史の終焉」を見たというのが本当なら、歴史以後という不易な「時勢遅れ」のなかで、生そのものの終焉に近接したヘーゲルが、静的な完成というある種の無力を進んで体現したと受け取るのも、イメージとしては魅力的である。だが、バタイユによれば、「老ヘーゲルの顔立ちに現れる荒廃した和らぎは、見る者を打ちのめし、かつ落ち着かせるのだが、それは、始まりをなす不可能性の忘却ではまったくなく、むしろその似姿である。すなわち、死と完了の似姿である(注6)」(「実存主義から経済学の優位へ」(1947-1984年))。細かい議論は抜きにして、何やら「時勢遅れ」の人間も、ひっそり隠居するどころでは到底なく、とんでもない葛藤を内包しながら、真の終焉までを生き抜かねばならないようだ。毎年のノートは新たにしつつ、その責を担っていくつもりである。
(注1) 夏目漱石『心 先生の遺書』、『漱石全集』第九巻所収、岩波書店、1994年、297頁。
(注2) 同書、298頁。
(注3) 妻への秘匿は、措いてはいけない問題だが、ここでは措かせていただきたい。
(注4) 夏目漱石『それから』、『漱石全集』第六巻所収、岩波書店、1994年、343頁。
(注5) 永井荷風『花火』、『荷風全集』第一四巻所収、岩波書店、1993年、256頁。
(注6) Georges Bataille, « De l’existentialisme au primat de l’économie », Œuvres complètes, t. XI, Paris, Gallimard, 1988, p.287.強調は原文。
(いしかわ・まなぶ フランス文学・思想)
初出:『UP』589号 (2021/11)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
