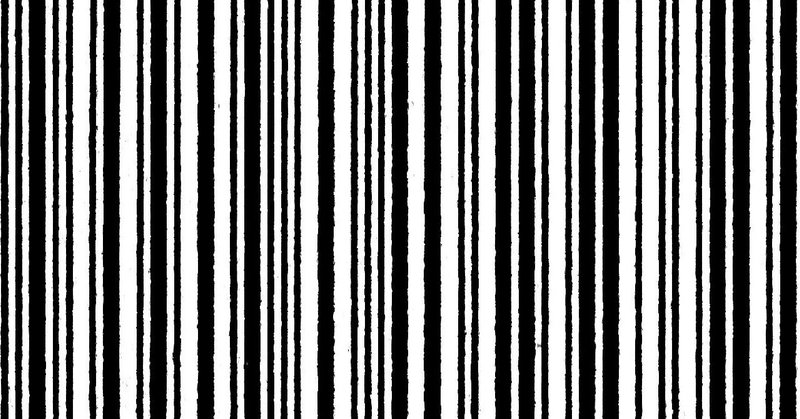
何も書きたいことがありません
鳥の鳴き声と薄明るさで目を覚ました。いい朝だな、5時か6時くらいかなと思って時間を見たら12時間違った。とたんに泥っぽい気だるさがこう、だってさっき沈んだばかりの日がもう1度昇ってくるまでの半日を、飯を食うとか煙草を吸うとか、おのれのナニをアレするとかして時間を潰さなくてはならないのだ。
近所に日高屋があるのがありがたく、日が変わるころ財布と煙草を抱えて店に向かった。特に腹が減っていたわけではない。途中、横断歩道の上で1匹のネズミが車に轢かれて死んでいるのを見つけ、私は下世話な好奇心からレンズを向けた。1匹の動物の死をどの距離から撮るのが最適かをいやらしく考え、何枚か撮ったあげく「死を写したいならちょっと離れすぎるくらいがいい」との結論に至って再び歩き始めたところで結局、これから何かの死体を食べに行くのだと思うとどんな顔をしていいか分からなくなった。店に入るとさっそく演技が始まったようで、痩せきったじじいが立ち上がって飯はまだかと吠えていた。応対する中東系の若い男性店員には話が通じていないのか、じじいにはそれを凌駕する迫力もなく軽くあしらわれていた。今、pcの前で私はじじいの一挙一動を書きつけるのさえ億劫で、気づくと、俺が帰るころじじいは床に倒れて死んでいた。来た道を戻って再び横断歩道に差し掛かると、さっきのネズミはもう1度か2度、さらに轢かれて白線の上を滑っていた。私は今になってなんてネズミの尊厳を踏みにじっているんだろうと感じたがあー、ネズミは全く、象徴してくれているようだった。街の中で写真を撮るということは本来こうも乱暴なことなんだとアラーキーもたしか本の中で言っていたから。で、それをこそ俺は趣味にしているのだと無理に納得して開き直り、家に帰ると溜飲を下げるように自慰行為などをした。酒が回ってぼんやりしている俺は、気が狂ったようなアクロバティック的体位の映像と無機質これ限りない喘ぎ声にめまいがした。それはこちら側の虚無感をいっそう際立たせているようで、私に何の興奮も与えなかった。
そのくせ、真似したくない、父親譲りの妙な神経症のきらいがある。観るまでもなく飛ばした動画の最後の数秒や、踏み飛ばした階段のほんの一段が、回りまわって自分に降りかかる不幸の元凶になるような気がすることがある。もしも私がその「踏み飛ばされた最後の一段」だったとしたら、自分だけ相手にされなかったことを根に持つような気がするからだ。気でしょ?だったら気にするまでもないと思いたいのだが、思い込もうとするほどそれはかえって頭の中で大きくなり、どうせならできるうちに消しておこうとわざわざ階段まで戻ってしまうのだ。踏み飛ばした一段をしっかりと見極め、両足でしっかりと踏み、しまった、すると今度は全ての段を両足で踏まなくてはならないのだ。ため息をついてわざわざ片足で一段ずつ踏んで降りる。するとまたしまった……もう一度階段を上らなくては自分の部屋にたどり着けないのだ。今両足で踏んできたということは、また両足で上らなくては余ってしまった片足が心細くなり、俺に対して恨みを抱くんじゃないかと思うのだ。で、そんなことをしているうちに平成が終わってしまったのである。

実体のない幽霊なんかより生きてる人間の方が怖い、と、私思うんですけど、何より怖いのは自分自身に恐怖を感じる瞬間だろう。夜、暗い部屋の中で鏡と向き合い、笑いかける自分の顔が見慣れないものに変わる瞬間ほど恐ろしいものはない。自分自身に恐ろしさを感じたのは、あれはおそらく私がまだ小学校に入る前の歳だろうと思う。その時の体験はどうも記憶から離れない。
その頃横浜に住んでいた私のいとこ家族は、毎年夏になると祖父母の家に遊びに来ていた。私と両親の家は祖父母の家の隣にあったから、いとこが遊びに来ると毎日祖父母の家でいっしょに遊び、夜になると2階の座敷でいっしょに眠った。普段は灯りを消せばすぐに眠ってしまうものだったが、その夜はどういうわけか目が覚めた。時刻は分からなかったが、すぐ横でいとこの母親が息子たちを寝かしつけているのが分かった。彼女は子守唄を口ずさみながら、端から子供たちの寝顔を眺めているようだった。
私は身体を動かさなかったし、彼女も私が目を覚ましたことには気がついていなかった。順番に、ゆっくりと私の顔も見た。私も目を開けて彼女の顔を見た。灯りのない暗闇の中では顔がよく見えず、私は目を合わせようと相手の顔をよく見た。それは相手も同じだったろう、どれだけの時間か私たちは互いの目を探してじっと待った……すると口ずさんでいた子守唄がぴたっと止まった。ふいに私の名前を呼んだ彼女の声と、ようやく見えてきたその顔ははっきりと驚きの表情だった。私には、私を見下ろしたその表情もまず怖かったのだが、その時私は頭の中で、彼女になり代わって自分を見下ろしていたようだった。すやすや眠っていると思っていた子供が、身じろぎもせず両目をがっつり開いてこちらを見ているのだ。今思えば彼女が怖がるのも無理はないのだが、その時の自分にとって、意図せずに恐怖された自分がいたことに自分自身が恐ろしくなったのを覚えている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
