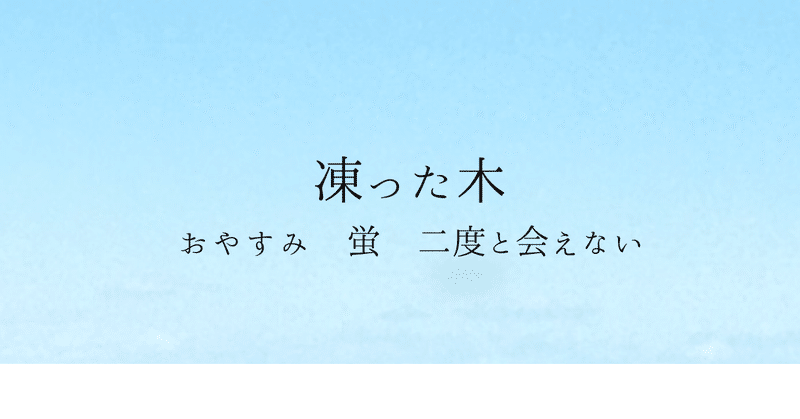
凍った木
おやすみ、となにかが世界に囁いたように、雪が降り続け、無秩序に公平に分け隔てなく、文明も大地も生命も、すべてが凍てついた。
その惑星がたいらかに氷に閉じ込められてから幾千年。氷の下で凍てつくような海が広がっていることなど誰も想像はしない。海で新たな生命が息づいていたとしても氷上の世界が気付くことはない。同様に、氷上に息吹く存在があったとしてもまた海は知りえない。氷という明確な境界線は、互いが二度と会えないよう、強固なまでに惑星を上下に分割した。
水平線という言葉は死語になり――そもそも言葉自体が死滅したが――氷平線ともいうべき、白く半透明な世界が遙か遠方まで延びている。
白を輝かせるまっさらな青空、あるいはすべてが鈍く白くなる曇天、氷に反射するほどの星の海、大気と一体となり自然は日々なにごともなく凍ったまま移ろいでゆく。
そんな惑星に辿り着いた、空飛ぶ生物。かつてペンギンと呼ばれていたものに形状が近いため、仮にペンギンと呼称する。
空飛ぶペンギンは宇宙から飛来し、死した惑星に到着する。凍り付いた星はさほど珍しくはない。しかしその中にも見覚えの無い生物が棲んでいる場合もある。旅するペンギンはぺちぺちと平らかな足で硬質な氷を歩く。氷は空から見下ろすとなんの変哲もない白い壁でしかなかったが、地に足を着けてよく目を凝らしてみれば、薄い罅や僅かなおうとつが重なっており、色もただ白いだけではなく複雑なゆらめきをしている。光と影の入り具合にも、氷の密度にも左右されるのだろう。単純なようで複雑に透いている。しかしここには何も無いし、氷の下の世界にも想像は及ばない。ペンギンはてちてちと歩く。広い世界をたった一匹で歩く。
比較的小規模な惑星である。
無限に膨張する宇宙に点在する銀河系もその銀河を形成する星も規模はそれぞれだ。塵やガスが密集して生まれる星たちは、ペンギンと同様飛来するものもあれば、何も無い空間に凜として留まるものもある。その地上に生命が誕生するかは、さまざまな偶然が折り重なって奇跡の平衡を得た際にしか起こり得ない。
その点、この星は恐らくその奇跡が起こり得たはずである。であれば、どこかに命は生じる。
ペンギンは歩き続ける。
白く輝く恒星が氷平線の下へ落ちてゆこうと傾くと、光が乱反射し、真っ白だった世界は夕景へ転換する。青からオレンジ、紺のグラデーションがなんの邪魔も無く空に広がり、ちょうど氷の上に寝転んで眺めていると、あらゆる色彩の移ろいがペンギンに与えられる。一辺倒な色ではない。じっと展望していると、微細な情報が入ってくる。これと定められるものではないのだった。光は大気の塵にぶつかり乱雑に動き回り、決まった動きをするわけではないからだ。惑星を覆う氷もまた、恒星の輝きを受けて蛍光を発するよう。ペンギンは背中に氷のつめたさを感じながら、恒星がやがて沈み、暗闇となった世界をまた歩き始めた。
太陽が隠れると、今までも存在していた彼方の星が見えるようになる。見えていないだけで、本当は存在するものばかり。元々存在していたものを明らかとした時、発見と呼ぶ。この星で得る発見を、ペンギンは探す。何も遮るものがなく、足下の氷の感覚はどこまでも変わらない。硬質で、なにものも寄せ付けようとはせずに在り続ける。
ペンギンは自分の立ち寄ってきた星について思いを馳せた。点在する星の輝きについて、きっとあれがついこないだ行ったもので、そこからずっと遠くに在るようなあの星にも行った。一つの星から見上げると、星々は隣り合っているようで、位置関係は複雑だ。
何度もまばゆい恒星が昇っては落ち、繰り返される時間を過ごしていると、なにものも不在であった静謐な星に、ぽつと浮かぶかぼそい線が見えた。
目を丸くしたペンギンは、しかし急ぐことなく、細い線へ足を運ぶ。
一本の木であった。
枝は生長を止め、葉の一枚もついていない木は、とうに死滅している。幹の中にも生命の循環は感じられない。ただ一本、特別背が高かったのか、吹雪にも冷気にも負けなかったのか、立ち続け、樹氷として凍り付いた星と一体化してしまったのだろう。
ペンギンはそのかぼそく凍った木を撫でる。表面に感じられるのは氷のつめたさだけだ。白透明の奥で枯れた木が薄らと此の世から消えた色を携えている。それは空の色と似通っている。定められる色ではなく、光の加減によってかたちを変える、しかし確実に木そのものの色が凍った表層の奥に存在している。褪せてゆこうとも、そこに存在していた生命の証拠。
ペンギンは虚ろとなった木を背にして、座り込んだ。今まで一切遮るもののなかった視界に、止まったまま動かなくなった枝が浮かんでいる。
この根の下に、生命が宿っているのかもしれない。
ペンギンは考える。
将来、この木は風に吹かれて塵と化し、跡形もなく氷の世界にちりばめられてゆく運命なのかもしれない。
されど、いつか根の這う隙間を通じて、氷の下に眠るなにかが空のもとに顔を出すだろう。
白くつめたい世界を突き抜けて、忘れていた豊かな色彩に目を醒ますだろう。
ペンギンが飛び立った後の、いつか遠い未来で。
了
「凍った木」
三題噺お題:おやすみ、蛍、二度と会えない
たいへん喜びます!本を読んで文にします。
