
人間失格(済み)|自己紹介:序

父と母が駆け落ちした。
わたしが生まれる前のことだ。
駆け落ち先は、実家から100m下った父の先輩の家の納屋であった。
わたしが何かと納屋に縁があるのは、これが理由かもしれない。
ふたりは親を説得し、実家へ戻った。
後に、わたしの父と母になるふたりは、こうして結ばれた。
わたしが生まれる。
母は心を病み、入院することになった。
_わたしは、残された。
退院後、弟が生まれる。
母はまた心を病み、入院した。
弟は、遠方の親戚に預けられた。
_わたしは、残された。
わたしが三歳の時、母は宗教に狂って、家を出た。そのまま戻ることはなかった。
父と母は、離縁した。
_わたしは、残された。
祖父は次第に酒に溺れていった。
気苦労の多い人生の憂さを晴らしたかったのだろう。
普段は気の優しい寡黙で不器用な男だった。
翌年、祖父は酒が仇となり、身体を壊してぶっ倒れた。
肝臓がやられ、糖尿病もあり、壮絶は闘病生活の末、血を吐きながら、この世を去った。
_よくわからぬままに、わたしは、残された。
幸いなことに、残されたわたしには祖母がいた。
苦労の数が皺に刻まれたような風貌のひとであったが、そのぶん、いや、その何倍もやさしいひとであった。
寡黙で、静物のような佇まいをしていた。
静かな祖母が笑うと、殆ど歯のない口元に広がる闇があり、そこには、悲哀(もしくは銀歯)という名の星が、光を放たずにくすんだまま輝いているように見えた。
「ばあちゃん、入れ歯買えし。」
こどもながらに、祖母のそんな姿を哀れに思ったわたしがそういうと、祖母は哀しげな笑顔を浮かべながら、静かに言った。
「ばあちゃんは、へえ、死ぬだから要らんだよ」
毎回、そう言って、わたしを諭した。
その祖母は、心臓の病気で入退院を繰り返しながらも、わたしをおぶって、急な坂道を上り下りして、わたしを育ててくれた。
さぞ、身体に堪えたであろうに。
ごめんよ、ばあちゃん。
父は大癇癪持ちであった。
父親は、年中、怒鳴っていた。声も手も上げた。
小さな部屋のなかを、ガラス製の灰皿が何度も横切って飛んだ。UFOみたいに。
ゴルフクラブで粉砕された窓ガラスと玄関。
祖母がテープで補修した。
夜は、酔っ払った父の怒号が鳴り止まず、祖母は毎晩罵られていた。
布団のなかでそれを聞きながら、わたしは、ただ、震えた。震えながら、父を憎み、祖母を助けられない自分を憎んだ。
だから、わたしは父が大嫌いであった。
こんな父親になるものかと決意したのは、わたしがまだ8歳のときであった。
わたしの実家はボロ屋であった。
これは以前にも書いた。
(『洞穴』と呼ばれたぼろ屋暮らしに興味がある方は、拙著『夜明けの夜明けの、ペロペロ』をお読みください。)
農家であったから無駄に広い土地。
そこに、朽ち果てた木造平屋建てと納屋、プレハブ小屋があり、あとは六畳二間の隠居部屋が、ぽつんと建っていた。
六畳二間の隠居部屋には、仏壇と神棚。
加えて、生前の祖父が難病におかされた父の命を救うために半年間修験道を通い詰めて霊験し、狛犬の命を受けた神を祀る大きな祭壇があった。
それらが、生活空間のほとんどを占めた。
便所は、ぼっとん便所で、年中、家のなかには溜まった排泄物のくせえ臭いが立ち込めた。
風呂は、離れの朽ちかけた平屋の土間にあった。風呂といっても、コンクリートを打って、浴槽を置いただけのものだった。
板は腐って穴があき、風呂場の床には、百足やゲジゲジを始めとした見たこともない節足動物たちの通り道であった。
時折、こおろぎや鈴虫が姿を見せることもあったが。
多くの者にとって、安らぎの場となる家も風呂も、わたしにとっては、脅かされる場所であった。

わたしは中学生になると毎週のようにリンチされた。現代の陰湿ないじめとは様相が異る。当時は、主に直接的な暴力だ。
当時のわたしは色々と目立った存在だった。
それが気に入らなかったようだ。
殴る蹴るは当然のこと、竹刀や木刀、メリケンサックにバット、何でもありだった。
理不尽な暴力に対する怒りと、頑固な負けん気が仇となり、それはエスカレートした。
わたしにとって学校という空間(厳密には、その周辺の空間も含める)は、常に、襲撃に備えなければならない戦場であった。
仲間や友だちはいたが、巻き込むわけにはいかなかった。
家には話の通じない父と、心配をかけてはならない祖母がいる。だから、わたしは耐えるしかなかった。
_わたしは、ひとり耐え抜いた。
何度も挫けそうになっり、
何度も逃げ出したくなり、
何度も消えてしまいたくなった。
そりゃ、そうだろ。
しかし、しなかった。
わたしを支えていたものがあったからだ。
それは、
早く大人になり、ばあちゃん孝行をしたい。
自分にできるすべてをばあちゃんにしてやる。
その気持ちだけが、当時のわたしを支えた。
わたしが十五の時、再び入院した祖母は、それから家に戻ることなく、その年の秋に亡くなった。
_わたしは、また、ひとり残された。
弟はグレて、家出をした。
全国各地の警察署から家に連絡が来た。
その度に、父は怒り狂いながらも、事後処理に奔走した。
弟は、その後、姿を消した。
そして、日の当たる道を外れ、裏社会の一員となった。
わたしは、ひとり、日の当たる道を歩いた。
わたしは、祖母を喜ばせるためだけに、日の当たる道を歩いてきた。
わたしは、祖母に育てられたからという理由で無条件に可哀想な目で見てくる心ない大人共を見返す、など諸々、どうでも良かった。
ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、祖母に親孝行するためだけに頑張って生きていたのだった。
その祖母は、もう、いなかった。

爆弾のような父とのふたりきりの生活が始まった。
わたしの家からは言葉が消えた。
自然の音だけが、ただ、季節の移ろいに合わせて、鳴っていた。
さらりさらさら、
ごうごうごうごう、
ひゅうるりひゅるりら、
どっどどどうどう、
ぴるぴりぴるるり、
ざわざわざわ。
そんな生活のなか、野良猫がわたしの家(という名の小屋)に棲みついた。
わたしは、その野良猫に名前をつけてやった。
いつしか、その野良猫だけが、わたしに生のぬくもりを与えてくれる唯一の存在となった。
その野良猫は、車にはねられて死んだ。
亡骸は梅の木の根元に埋めてやった。
そうして、また、
_わたしは、ひとりになった。
立て続けに支えを失ったわたしの心は、とうに限界だったのかもしれない。
ある日、なにかの糸が、切れた。

息が、出来な、くなった。
呼、吸の仕、方、を、忘れ、た。
パパパパパパパパパパパパパパパパニパニパニック発作で、ああああった、あった、あたたたたたたたたた。
|つい で| に|
解 離| も|
|現
れ
た。
わたしは、呼吸と身体と心を失ったのだ。
県内の一番大きい総合病院で、あらゆる検査を受けた。わたしの身体と心は、現代医学によって、解体され、分析されていった。
「ストレスでしょう。心因性のものです。若いから大丈夫だと思いますが、念のためにお薬を出しておきましょう。」
(「ストレスでしょう。心因性のものです。若いから大丈夫だと思いますが、念のためにお薬を出しておきましょう。」)
わたしは言われたことを頭のなかで繰り返した。そして、家に帰る途中、
処方された薬を、すべて投げ捨てた。
わたしの、ひとりでの戦いが始まった。
いや、わたしは、生まれたときからずっと、ひとりで戦っていたのかもしれない。
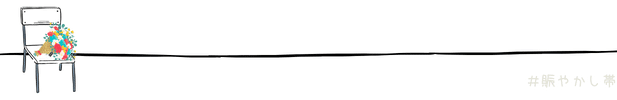
わたしは進学のため、上京した。
あたらしい部屋で、
あたらしい生活が始まったのだ。
その部屋のアパートの近くには、寺があった。
奇しくも、そこは、
太宰治が眠る場所であった。
(縁起でもねえな、先生)
わたしは、心のなかで呟いた。
当時は、まだ、
SNSなんてものはなかったからね。
そういえば、同じように、太宰治に引き寄せられるように上京した芸人がいたな。
太宰治に憧れた彼は、後に作家となり、太宰治が獲れなかった芥川賞を受賞した。
(縁起でもねえな、先生)
わたしは、今度は、SNSで呟いた。
それを、いま、ここに書き留めている。
それを、いま、あなたが目にしている。
これは、
病を抱えながらも残りの人生のすべてを捧げて、わたしをまもり育ててくれた祖母に恩返しすることも叶わなかった、矮小な男の話である。
まあ、ひと言でいえば、
その男、人間失格(済み)。
これが、わたしの人生の、序である。
玉川上水沿いにある
銀河鉄道サザンクロス逝きの列車は、まだ、
来ない。
ー了ー
『人間失格、済み|自己紹介:序』


つづきは、こちら↓
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
