
【有料記事】 絶望と希望の映画変革史(2010年代編)
長きにわたる映画の歴史は、僕たち観客の「絶望」と「希望」によって紡がれてきた。
心を強く震わせられる作品に出会うたびに、「もう、こんな映画体験は二度と味わうことができないかもしれない」と途方に暮れてしまうような気持ちになる。そうした、ある種の「絶望」にも似た感情を抱いたことがある人は、きっと少なくないはずだ。
それでもまた、「こんな映画を待ち望んでいた」と心から思わせてくれる作品が次々と生まれていく。そうした、映画シーンの新たなる「希望」として、それぞれの時代を彩り、その後の映画史を不可逆的に変えてしまう作品たちのことを、僕たちはマスターピースと呼ぶ。
もう、その作品がなかった世界へは戻れはしない。幾度とない「変革」を重ねながら、映画界は、かつては誰も想像もできなかった次元へと突き進み続けている。その必然として、10年も経てば、僕たちの映画観は決定的に変わってしまう。そうした映画史の流れの速さには、時代の節目ごとに、いつも本当に驚かされる。
今回は、テン年代、つまり、2010年〜2019年に生まれたマスターピース30本をランキング形式で紹介していきたい。
「絶望」に次ぐ、「希望」。
この記事が、あなたの映画観が変わる、一つのきっかけになれたら嬉しい。
【30位】
『her/世界でひとつの彼女』(2013)

SFの要素を大胆に取り入れた未来の寓話である今作が、テン年代を生きる僕たちに伝えてくれたこと。それは、他のどんな恋愛映画でさえも到達し得なかった「愛すること」の本質だ。
恋には、数え切れないほどの形がある。
今作が描いたのは、妻と別居中の主人公・セオドアと、人工知能型OS「サマンサ」の間に芽生えた、全く新しい恋の形だった。
《I think anybody that falls in love is a freak. It's a crazy thing to do. It's kind of a form of socially acceptable insanity.》(恋に落ちたら誰だって変人。クレイジーなものなの。社会的に許容された狂気の形象の一種ね。)
未知なる恋愛に悩み苦しむセオドアに対し、彼の親友がかけたこの言葉は、あらゆる恋の形を、優しく包み込み、そして肯定してみせた。
「社会的に許容された狂気」とは、まさに言い得て妙である。そう、今作は、それまでの他のどんな恋愛映画よりも鋭く、真っ直ぐに、「恋愛」の本質を射抜いてしまったのだ。
【29位】
『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017)

ギレルモ・デル・トロ監督は、ずっと「人間ではないもの」を描き続けてきた。異形の怪物へのフェティッシュなまでの強いこだわりは、『ヘルボーイ』シリーズ(2004/2009)で存分に発揮されていたし、『パシフィック・リム』(2013)において執念的に造形されていたのは、ロボットよりもむしろ「KAIJU」 の方だった。
そして今作において、ギレルモ監督の「人間ではないもの」への温かな眼差しは、ラブストーリーと最も相性が良いことが証明された。
『美女と野獣』(1991)といった例を挙げるまでもなく、種族を超えたラブストーリーはいつの時代も人々に求められ、愛されてきた。しかし、皮肉めいた見方をすれば、それらの物語は、美しい「在るべき」フォーマットの中に規定されていた。ベルは若くて美しい処女だし、野獣は結局はハンサムな王子様だ。
ギレルモ監督が「アンチ・美女と野獣」を表明するように、彼はその既存のフォーマットを破壊し、新しい物語の形を創り上げた。そして、この「混沌の時代に贈るおとぎ話」が生まれたのだ。
あまりにも刺激的な形で「多様性」の在り方を突き付けた今作が、第90回アカデミー賞において作品賞を受賞したことは、やはり、テン年代の映画史に刻まれるべき重要なターニングポイントであったと思う。
【28位】
『万引き家族』(2018)

是枝監督が、映画作りを通して行なってきたこと。それは、「家族」という概念の再定義だ。
親は子どもを選べないし、子どもは親を選べない。それでも、いや、だからこそ、お互いに絆を育み合いながら「家族」になるしかない。
是枝監督は、血縁という絶対的な繋がりの意味を問い直し、そこに新しい価値を見い出してきた。そして、これまで「無条件の愛」とセットで語られてきた「家族」という枠組み(および、その誤解)を一度取り払うことで、逆説的に、「家族」になることの幸せを説いてきた。
そして、是枝監督は、今作『万引き家族』において新しいテーマに挑戦している。それは、親と子どもの関係を「選択」する、ということ。つまり、血の繋がりを超えて、「家族」になろうとする試みだ。
いろいろな生き方があって、いろいろな価値観があって、いろいろな愛の形がある。しかし悲しいことに、この社会にはまだ、その全てを許容する余裕はない。(劇中で深く言及されることはないが、この物語の前提となっているのは、児童虐待、年金問題、雇用問題といった、現実社会の構造的な負である。)今作が投げかける問いかけに、この社会が正面から答えるには、まだ時間がかかるかもしれない。
是枝監督は今作で、カンヌ国際映画祭の最高賞であるパルム・ドールを受賞する。彼が再定義した「家族」の在り方が、一日でも早く世界のスタンダードの一つになりますように。そうした透徹な願いが、カンヌを通して全世界に共有されたことは、テン年代の映画界においてあまりにも深い意義のある出来事だった。
【27位】
『Mommy/マミー』(2014)

カナダから現れた若き俊英、グザヴィエ・ドラン。彼は、2014年公開の監督作『Mommy/マミー』によって、その名を世界へと轟かせる。
目の逸らしようのない「1:1」の画面アスペクト比は、観客と登場人物の間に抜き差しならない関係性と緊張感を生み出す。そして、斬新にして大胆なポップ・ミュージックの引用は、登場人物が抱く感情の起伏をありのままにトレースしている。特に、中盤、オアシスの"Wonderwall"を背景としながら「世界」が開けてゆく演出は、圧倒的に、美しく、鋭く、エモーショナルなものだった。
当時25歳だったグザヴィエ・ドラン監督は、第67回カンヌ国際映画祭において審査員賞を受賞。当時83歳の巨匠・ジャン=リュック・ゴダールと並ぶW受賞が実現したこの時、映画界に新しい時代が到来したといえる。
ドランは、新世代のクリエイターたちへ向けて、次のようにスピーチした。
「僕と同世代のみんなへ。誰もが自由に表現する権利があるにもかかわらず、それを邪魔する人たちもいる。でも、決して諦めないでください。世界は変わるのです。僕がここに立てたのだから。」
その言葉に奮い立たされたクリエイターは、きっと少なくないはずだ。次の時代を牽引するトップクリエイター・ドランは、これから、どのような表現の地平を切り開いていくのか。彼が抱くビジョンに、期待が止まらない。
【26位】
『ブラックパンサー』(2018)

この映画が「MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)」という枠組みを超え、広く世界に受け入れられ、称賛され、アカデミー賞・作品賞にノミネートされたこと。それは、テン年代のポップ・カルチャー史に刻まれるべき美しい奇跡である。
それは、今作が「黒人」や「女性」といったマイノリティーな存在にフォーカスを当てている作品だからではない。むしろ逆で、「黒人」や「女性」が、「白人」や「男性」と対等(もしくは、優位)な関係性であることが、今作で描かれる世界における絶対的な共通認識となっているからだ。
そう、ブラックパンサーやオコエ、ナキアの活躍を描く上で、何も特別な理由はいらないのだ。この認識のもとで紡がれたストーリーが、全世界で記録的な大ヒットを記録したことは、まさに新しい時代の必然だったのかもしれない。
今や、全世界の一大テーマとして掲げられている「多様性」という概念。2018年、そこに、最も美しくリアルな輪郭を与え、その可能性を堂々と証明してみせた今作の功績は、やはり、あまりにも大きすぎる。
【25位】
『悪の法則』(2013)

『ノーカントリー』(2007)の原作者である米ピュリッツァー賞作家・コーマック・マッカッシーが脚本を書き下ろした『悪の法則』。今作はまさに、この世界の本質についての深淵なる考察である。
『ノーカントリー』では、圧倒的な「個」としての悪であるアントンシガーが、その存在感を奮っていた。一方、今作で描かれるのは、「システム」として存在する悪である。そこには、全体もなければ、中心もない。その意思決定の仕組みは、この世界の末端として生きる今作の登場人物(そして、僕たち観客)には分かりようもない。
それでも、確かに存在する悪の在り様を、この映画は、あまりにも鮮やかに描いている。不都合な真実から目を逸らし続ける僕たち観客に、真っ直ぐに突き付けられる対話不能な存在。その脅威は、全ての観客にとって、極めて普遍的なものだ。
今作が暴いてしまったこの世界の真実を、もう誰も覆い隠すことはできない。
【24位】
『スパイダーマン:スパイダーバース』(2018)

まさに、映像表現における新次元の革命。
今作に用いられたCGと手書きのタッチを融合させた新たな表現スタイルは、これまでのアニメ業界の常識と慣例を一瞬にして覆してしまうものだ。
プロデューサーのクリスティーナ・スタインバーグはこう語る。
「狙ったのは、映画を、命を得たコミックのように見せること。それと、映画の最終バージョンは、最初のコンセプトアートのようにしたいとも話し合ったわ。そういう絵はとてもダイナミックで新鮮で見ていてワクワクするから、それをきちんと画面で表現したかったの。」
今作では、通常の照明の代わりに、コミックで利用されているハーフトーンスクリーンを取り入れ、動き、空間、光や質感の映像表現に、"印刷技術"的なメソッドが転用されている。そして実現したのが、強くエッジの効いたグラフィカルなルック、そう、まさに「動くアメコミ」だ。
ポップ・アートとしてのアメコミへの愛と敬意を爆発させながら、アメコミ映画に特有のダイナミズムとスピード感も有している。その映画体験は、とにかく圧倒的に新しいものだった。
【23位】
『君の名前で僕を呼んで』(2017)

2010年代の半ばから、『キャロル』(2015)、『リリーのすべて』(2015)など、LGBTを主題とする作品のヒットが立て続けに起こった。そしてそれは、単なる一時的なムーブメントではなかった。当時の映画界における一つの潮流を、新たなジャンルとして決定付けたのが、この『君の名前で僕を呼んで』だ。
特筆すべきは、そのアートワークをも含めたビジュアルの美しさである。これほどまでに、どのシーンを切り取っても「画」になる映画は珍しい。
しかし、この映画は決して「画」の力に逃げていない。この時代に発信しなければならないメッセージを、臆することなく、堂々と言葉にして伝えている。
愛と理解、そして最大限の敬意。その先にしか、真の「多様性」は実現し得ない。そう訴える今作のラストシーンは、混迷を極めるこの時代における道標となるだろう。
いつか、この世界の「LGBT」の問題が全て解決される日が来るとしたら、きっと「LGBT」という言葉はなくなるはずだ。その時、『君の名前で僕を呼んで』は「LGBT映画」ではなく「恋愛映画」の金字塔になる。この映画が、真の意味で世界中で受け入れられ、愛されるということは、つまり、そういうことなのだと思う。
【22位】
『グランド・ブダペスト・ホテル』(2014)
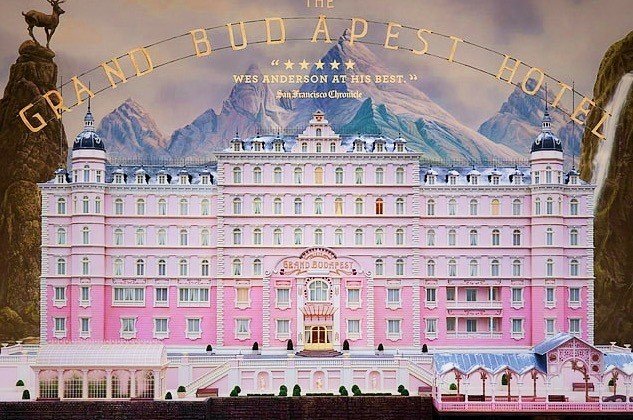
これまでウェス・アンダーソン監督は、潜水艦、列車、島など、限定された空間における寓話を描いてきた。その意味で、ホテルを舞台とした今作は、彼の集大成にして一つの到達点といえるだろう。
混沌としているようで徹底的に統制されたビジュアルイメージ。リアリズムからの解放を謳うような破天荒なストーリー。そうしたウェスが創り上げる世界で、精一杯に躍動するキャラクターたちは、いつだって懸命に、そして上品にチャームを輝かせている。
奇想天外なアクション、ピリッとした風刺の効いたコメディ、一瞬の油断さえ許さないサスペンス、そして、ハートウォーミングなドラマ。その全てが渾然一体となった時、あらゆるジャンルの差異を超越した「映画」そのものが豊かな実体をもってして立ち上がる。
「映画」の原初的な存在意義を、これほどまでに過激に、美しく、そして華麗に証明できる監督は、特に2010年代においては、あまりにも稀有である。
【21位】
『ムーンライト』(2016)

インディペンデント体制で製作された今作が、見事にアカデミー賞作品賞に輝いた事実は、テン年代の映画史に刻まれるべき鮮やかな革命であった。(授賞式の作品賞発表時において、はじめに『ラ・ラ・ランド』の名が誤って発表された事件も忘れられない。)
原案となったのは、劇作家タレル・アルヴィン・マクレイニーによる『In Moonlight Black Boys Look Blue』。そのタイトルが示しているが、今作で描かれる幻想的な「青」の世界は、言葉を失うほどに美しい。そして、シビアで凄惨な現実社会から浮遊するような、主観的にしてファンタジックな映像表現は、主人公の孤独な魂、そのフラジャイルな在り方を丁寧に映し出している。
そう、今作は、たとえこの世界がどれだけの絶望に満ち溢れていようとも、それでも「この世界は美しい」と信じさせてくれるような、微かでも確かな肯定性で満ちている。この映画を観た観客であれば、きっと誰もが、今作が秘める深淵なる可能性を感じ取ることができるだろう。
静的にして詩的な映画の力。あらゆる孤独を包括し、慈しむ、極めて眩い可能性を誇る傑作だ。
【20位】
『ヘレディタリー/継承』(2018)

長きにわたるホラー映画史における新たな金字塔にして、究極の到達点。長編デビュー作である今作によって、アリ・アスター監督は、一気に現代ホラー界の頂点に君臨した。
この世界そのものを呪い倒すような狂気的な執念が、全てのシーンから放たれている。そして、僕たち観客は、アリ・アスター監督が、あらかじめ定めた筋書きの駒に成り下がり果てる。この映画の1カット目に足を踏み入れた瞬間から、観客の「運命」は決まりきっていたのだ。だからこそ僕たちは、ただただ身を委ねることしかできない。(この諦念にも似た感覚は、次回作『ミッドサマー』にも通ずるものがある。)
何より恐ろしいのは、今作が「家族」の物語であることだ。その極めて普遍的なテーマから、逃れることができる観客などいないだろう。過去に何かしらのトラウマを抱える人は、今作から耐えきれないような壮絶なプレッシャーを与えられることは間違いない。
はっきり言ってしまえば、今、これほどまでに絶望的な世界を描くことができる監督は、他にいない。全てのホラー映画を、「ヘレディタリー以前/以降」に二分してしまう、まさに歴史的快作である。
【19位】
『ウルフ・オブ・ウォールストリート』(2013)

新進気鋭の映画人によって、次々と新たな変革が巻き起こるテン年代のシーンにおいても、やはり、巨匠・マーティン・スコセッシの存在感は絶大的であった。
テン年代版『グッドフェローズ』(1990)とも称するべき今作は、金とドラッグとセックスにまみれた、一言でいってしまえば最高に破天荒な人生訓だ。映画だからこそ描くことのできる人生があるとして、そこから僕たち観客が学ぶべきことは、やはり、あまりにも多過ぎる。
スコセッシ監督が映画に懸ける熱量は全く衰えることを知らない。それどころか、演出は更に過激に、手数は更に増えており、もはや、この華麗にして狂乱的な物語を、誰も止めることができない。(今作は、劇映画史上、最も「FUCK」を連発する作品という名誉ある記録に輝いた。)
そんなスコセッシが、テン年代の最後に、『アイリッシュマン』(2019)によって、品性のある成熟さを見せつけてくれたことも、この10年の映画史のハイライトであったと、ここに合わせて書き記しておきたい。
【18位】
『1917 命をかけた伝令』(2019)

まず、何よりも特筆すべきなのが、「全編を通してワンカットに見える映像」だ。縦横無尽に宙を舞い、銃撃や砲撃を避けながら地を這うカメラワークは、狂気的なまでの執念に満ちている。それでいて、あらゆる画が、背筋が凍るほどに荘厳で、美しい。
その過程で生まれる未知なる没入感は、客席とスクリーンの境界を無化してしまう。そう、今作は決して、単なる「2人の兵士を追いかける映像」ではないのだ。110分間の戦争体験を再現した撮影/編集の技術は、はっきり言って過去作とは比にもならない。その意味で、今作が『プライベート・ライアン』(1999)以降初めて、アクション映画のクオリティの絶対水準を不可逆的に引き上げてしまった作品であると言える。
ただ、語弊を恐れずにいえば、今作の真価は、そうした映像の技術を超えた先にあるように思う。
この映画は、大義や自由のために、自身を犠牲にした全ての軍人へ向けたリスペクトの表れである。そして、彼らの意志を未来へ引き継ぐための揺るぎなき決意であり、透徹な祈りであり、そして深淵なる願いである。
「映画」は、哀しみの歴史を変えることはできない。「映画」は、現在進行形の悲劇を止めることはできない。「映画」は、いつまでも消えることのない傷を、痛みを、トラウマを、決して癒し切ることはできない。それでも、「映画」は「戦争」を超えることができるのか? あえて無防備な言葉で表してしまったが、今作は、その果てしなき問いに対する、サム・メンデス監督による偉大なる回答である。
彼が「映画」に託した想いの全てが最も美しい形で結実したラストシーン。どれだけの言葉を綴ったとしても、決して紡ぐことのできない「命」のドラマは、テン年代の映画史における最後のハイライトとなった。
【17位】
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)
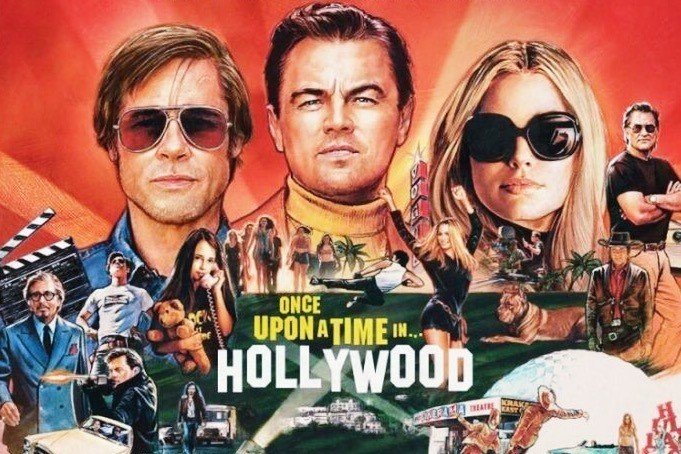
これまでタランティーノ監督は、映画を「武器」にして、悲惨な「史実」に対して戦いを挑み続けてきた。
『イングロリアス・バスターズ』(2009)では、ユダヤ人による、ヒトラーとナチス幹部への前代未聞の復讐劇を。『ジャンゴ 繋がれざる者』(2012)では、黒人奴隷出身のジャンゴの破天荒な完全勝利を描いた。そう、彼は、映画だからこそ実現できる「歴史改変」という荒唐無稽な破格技によって、クソみたいな「史実」に中指を突き立ててきたのだ。
それでは、今回、タランティーノ監督が成し遂げた「歴史改変」とは、いったい何だったのか。それは、1969年8月9日に起きた壮絶な悲劇から、女優・シャロン・テートを救済することだ。
「あの事件」の被害者として定義され、記憶され続けたシャロンだが、言うまでもなく、彼女にも、かけがえのない人生があった。そして、それこそまさに、映画が真に語るべき美しい物語であることを、タランティーノは訴える。
そう、この映画は、シャロンへの愛そのものである。彼女の人生を讃えたラブレターであり、現代へと語り継ぐべき可憐なおとぎ話である。この映画の愛の魔法によって、シャロンは悲しい史実から解放され、救われるのだ。
映画の可能性、存在意義、使命、その全てが眩い光を放ち続ける鮮烈な159分。今作こそが、タランティーノ監督の最高傑作であると、ここに断言する。
【16位】
『ズートピア』(2016)

『アナと雪の女王』(2013)において、往年の「ディズニー・プリンセス」シリーズに革新を起こしてみせたディズニー、その次の一手が、この『ズートピア』だ。
特筆すべきは、あらゆる差異を認め、肯定し、受け入れる、まさに究極の理想郷として描かれる都市「ズートピア」の描写である。特に冒頭、あらゆる種族の共存を目指して設計された街並みが紹介されるシーンには、思わず息を飲む。
そして、真の「多様性」を表現するためには、アニメーションの力が必要なのだと気付かされる。今作のアニメ表現を担保しているのは、一人ひとりのクリエイターの想像力であり、未来への意志であ李、そうした眩いクリエイティブの力に、とにかく圧倒される。
もちろん、アニメーションだからこそ描くことができる差別や偏見の寓話も、一切の容赦なくエッジーに描かれているから油断ならない。さすがディズニー、1mmの隙すらない、完璧といってもよいストーリーテリング術に痺れる。
何重もの意味で、2010年代におけるディズニー作品の最高傑作と断言できる。
【15位】
『スリー・ビルボード』(2017)

業火の如く燃え盛る怒り。無軌道に暴発し続ける執念。相克する被害者意識と加害者意識。そして、静かな風のように吹き抜ける諦念。喜怒哀楽を超越した究極の感情があるとして、そこに、これほどまでに鮮やかにリーチした作品は、はっきりと言ってしまえば、非常に稀有だ。
そして最後には、もはや善悪の価値基準をも無化した先に到達する、壮絶にして、悠々とした至高の人生観。その眩い輝きに、ただただ魂を揺さぶられてしまう。
この映画は、僕たちに何かしらの答えを提示したりはしない。この物語の続きは、観客である僕たち一人ひとりに託され、そして、その先の人生に伴走し続けていく。まさに、ヒューマンドラマという映画ジャンルにおける、一つの歴史的到達点と呼ぶべき破格の大傑作だ。
【14位】
『インセプション』(2010)

新しいディケイドの幕開けに、クリストファー・ノーラン監督は、極めて複雑な階層を持つ映画を「設計」してみせた。
喪失、葛藤、そして、輪廻。ノーランが長年にわたり追求し続けてきたそうしたテーマが、彼の矜恃であるリアリズムの中で溶け合い、単純な一本の筋が存在しない未知の物語が生まれた。
夢と潜在意識をテーマとした今作。人間の深層心理に深く潜り込む展開は、これまでの映画文法に則るのであれば、おそらく、どこまでも内省的になりがちであっただろう。しかし、この映画においては、非常に高い次元で、アクション、サスペンス、ミステリー、そして豊潤なヒューマンドラマの共存が実現している。そう、心の奥へ、奥へと入り込む過程が、誰も観たことのないエンターテインメント作品として結実したのだ。
テン年代、映画の新しい地平を切り開いてみせた、稀代の傑作だと思う。
【13位】
『ラ・ラ・ランド』(2016)

『セッション』(2014)によって、全世界を震撼させた若き新鋭・デイミアン・チャゼルの次回作。原作も既存曲の使用もない、全く新しいミュージカル映画に、全世界が恋をした。
しかし、ラストシーンにおいて、僕たち観客は気付く。そうか、今作は単に、彩り豊かで華麗な恋愛映画などではない。まさに『セッション』がそうであったように、人生を懸けて在るべきステージを目指す人々の魂の物語なのだ。
僕たちは、その目指すべきステージを、時に容易く夢と呼ぶ。そして、それがこの現実世界において、いかに儚く切ないものであるか痛いほど理解している。あまりにも鋭い切れ味を放つラストシーンは、前作『セッション』にも通じるが、今作『ラ・ラ・ランド』が誇る壮絶な余韻は、それでも夢を追う全ての観客の魂を強く揺さぶる。
そのラストシーンに託されたメッセージは、「絶望」か「希望」か。いずれにせよ、今作は、現実世界を生きる僕たちにとって、何ものにも代え難い作品となったことは間違いない。
往年のミュージカル映画への愛と敬意を爆発させながら、同ジャンルを全く新しい次元へと導いた、まさに革新的一作である。
【12位】
『ゼロ・グラビティ』(2013)

『アバター』(2009)から、たった4年。3D映画の新たな可能性が、まさか、これほどまでに鮮烈な形で提示されることになるとは、誰も予想しなかっただろう。
アルフォンソ・キュアロン監督の一つの代名詞ともいえる驚異の長回しのシークエンスは、今作で「宇宙」という広大なステージを得て、その破壊力を増した。特筆すべきは、約13分間にわたる一繋ぎのオープニングシーンであある。3D映像による空間の果てしない広がりは、とにかく圧巻であった。
「映画を観る」という受動的行為を遥かに超越した、まさに、「映画に没入する」という能動的行為。そして究極のライド感が最後に観客へもたらすのは、「映画と一体化する」という未知なる体験である。
尊ぶべき重力の重みを受けながら、大地を踏みしめて立ち上がる。その渾身のラストシーンで、壮絶な輝きを放つ生命の力。僕たち観客が、そうした至極のカタルシスに至ることができたのは、3Dの技術革新と今作のメッセージが確かにリンクしていたからだ。
次の10年、3D映画の可能性は、いったいどのように開かれていくのだろうか。
【11位】
『トイ・ストーリー3』(2010)

ゼロ年代から、怒涛の快進撃を続けてきた稀代のアニメーション制作会社・ピクサー。『ウォーリー』(2008)、『カールじいさんの空飛ぶ家』(2009)に続く今作は、同社にとっての永遠のマスターピースの一つとして、いつまでも愛され継がれていく作品になるだろう。
ピクサーが長年にわたり挑み続けてきた、CGキャラクターに命を授けるための試み。その一つの到達点である今作は、おもちゃの生き方を通して、僕たち観客に、人生を生きることの意義そのものを突き付けてくる。寓話と言ってしまえばそれまでだが、歪さや苦い諦念までも含めた今作のメッセージの深度は、はっきり言って過去作の比ではない。
そして、至高のラストシーン。ウッディやバズが、再びおもちゃに戻る時が訪れる。それは、シリーズ3作品を通して一貫して紡がれてきた渾身のメッセージが結実する瞬間だ。そうだ、これは「トイ・ストーリー」なのだ。いわゆる実写映画では決して味わえないような怒涛の感情が一気に押し寄せて、涙を堪え切れなくなる。
アニメーション技術を通してこそ、語ることのできる物語が、そして人生訓がある。それこそがクリエイティブの存在意義であり、今作は、全てのクリエイター、そしてエンターテインメント界における究極の指針である。
《30位〜11位 タイトル一覧》
【30位】『her/世界でひとつの彼女』(2013)
【29位】『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017)
【28位】『万引き家族』(2018)
【27位】『Mommy/マミー』(2014)
【26位】『ブラックパンサー』(2018)
【25位】『悪の法則』(2013)
【24位】『スパイダーマン:スパイダーバース』(2018)
【23位】『君の名前で僕を呼んで』(2017)
【22位】『グランド・ブダペスト・ホテル』(2014)
【21位】『ムーンライト』(2016)
【20位】『ヘレディタリー/継承』(2018)
【19位】『ウルフ・オブ・ウォールストリート』(2013)
【18位】『1917 命をかけた伝令』(2019)
【17位】『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)
【16位】『ズートピア』(2016)
【15位】『スリー・ビルボード』(2017)
【14位】『インセプション』(2010)
【13位】『ラ・ラ・ランド』(2016)
【12位】『ゼロ・グラビティ』(2013)
【11位】『トイ・ストーリー3』(2010)
ここから先は
¥ 300
最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。 これからも引き続き、「音楽」と「映画」を「言葉」にして綴っていきます。共感してくださった方は、フォロー/サポートをして頂けたら嬉しいです。 もしサポートを頂けた場合は、新しく「言葉」を綴ることで、全力でご期待に応えていきます。
