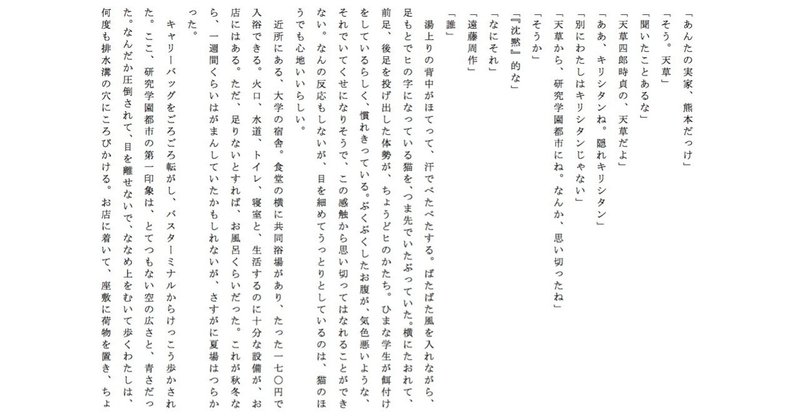
落下傘ノスタルヂア(2)
「あんたの実家、熊本だっけ」
「そう。天草」
「聞いたことあるな」
「天草四郎時貞の、天草だよ」
「ああ、キリシタンね。隠れキリシタン」
「別にわたしはキリシタンじゃない」
「天草から、研究学園都市にね。なんか、思い切ったね」
「そうか」
「『沈黙』的な」
「なにそれ」
「遠藤周作」
「誰」
湯上りの背中がほてって、汗でべたべたする。ばたばた風を入れながら、足もとでヒの字になっている猫を、つま先でいたぶっていた。横にたおれて、前足、後足を投げ出した体勢が、ちょうどヒのかたち。ひまな学生が餌付けをしているらしく、慣れきっている。ぶくぶくしたお腹が、気色悪いような、それでいてくせになりそうで、この感触から思い切ってはなれることができない。なんの反応もしないが、目を細めてうっとりとしているのは、猫のほうでも心地いいらしい。
近所にある、大学の宿舎。食堂の横に共同浴場があり、たった一七〇円で入浴できる。火口、水道、トイレ、寝室と、生活するのに十分な設備が、お店にはある。ただ、足りないとすれば、お風呂くらいだった。これが秋冬なら、一週間くらいはがまんしていたかもしれないが、さすがに夏場はつらかった。
キャリーバッグをごろごろ転がし、バスターミナルからけっこう歩かされた。ここ、研究学園都市の第一印象は、とてつもない空の広さと、青さだった。なんだか圧倒されて、目を離せないで、ななめ上をむいて歩くわたしは、何度も排水溝の穴にころびかける。お店に着いて、座敷に荷物を置き、ちょっと休憩したら、すぐにあたりを探検にまわった。奈津美から聞いてはいたが、すれちがうのは、研究者と、公務員と、学生と、中国人ばかりだった。その四種族がはっきり見分けられたわけでもなく、あやしいのは、だいたい学生に分類してしまう。あるものといったら、大学、役所、研究所以外には、畑と田んぼだけ。そして、がっちり塀にかこまれた役所や研究所とちがって、なぜか、ここの大学は門も入口もないのだ。完全に街と溶けこんでいて、いつのまにか、わたしは敷地のなかに足を踏み入れている。全国二位の面積をほこるキャンパスだそうだが、たっぷり一時間かけて大学を縦断したあと、さらに一時間かけて、南端の学生宿舎にもどってきた。共同浴場はそのとき見つけ、知らん顔して入れないかな、とだめもとで挑戦したが、あっけないほど簡単に入浴できてしまった。実は、夏場でも毎日お風呂に入ることなどなかったが、これは活用しなければ損。
「遠藤。誰」
「なんでもない。そういう小説があるだけ。まあいいや。そう、それで、あんたの妹も熊本なわけね、当然」
「そうだよ」
電話のむこうで、奈津美はおかしでも食べている。鼻声の合間合間に、くちゃくちゃ口を動かしている。
「熊本で浪人生するのは、いやだったわけ」
「まあ、そんな感じか」
「なにそれ」
「あんまり、お母さんと、なかよくないのでね。わたしが上京してから、ふたり暮らしになってね。うん、けっこう、がまんしてたんじゃないの」
「ああ、そうなの」
「高校卒業したら家出るって、ずっと言ってたから。大学は受からなかったけど、約束どおり、出てきたわけね」
「分かった、分かった。そういうのはプライバシーにしときなよ」
「なに、いま、大学の宿舎にいるんだっけ」
「そうだよ、風呂上り。目の前に広場があってね、ダンスサークルの人たちでしょうか、なんか音楽に合わせて激しく踊っています。ベタな酔っぱらいが通りました。まだそんな時間でもないのに、ひどい状態です、大学の校歌かなんかを歌ってますよ。あ、いま、お風呂から出てきた子、ちょっとかわいい。HNKの、連続テレビ小説、あの子に似てる」
「実況しなくていいよ」
「ここの大学受けたんでしょ。うまくいかないもんだね。あんまり頭よさそうなやつ、いないけどな」
「もっと馬鹿なんでしょ。受かるわけないんだよ。知ってんだ、そんなこと。おばあちゃんの家から近いでしょ、そこ。その大学」
「いや、でも、受かるといいじゃん。来年こそ」
「どうだろ」
「なにが」
「ラジオ体操ねえ」
「早起きできて、いいじゃん」
かわいい、と口々にさえずりながら、女子大生ふたりが、わたしの足もと、猫をかこんでしゃがみこむ。はっとして、足を引っこめるが、その場を去るタイミングは、すでに逃してしまっている。柵にひっかけておいたお風呂セットを、そっと取り上げる。猫は、わたしがいたぶるよりも、いっそう恍惚とした表情で、女子大生になでられている。後足のあいだに、男の子のしるしを見つける。いやらしい猫だと思った。わたしは、少し小声になる。
「あんたがお店出すからじゃないの」
「なにが」
「泰子ちゃんが、熊本から出てきたのは」
「どちらかと言えば、そっちに出てきたって聞いて、あわててわたしが駆けつけたような感じ。で、おもしろそうな場所だから、ちょうどいいや、って、お店を開くことにした。わたしが養っていかないといけないんでね、これからは。だから、あんまり大学に行ってほしくはないんだ。学費が」
「まあ、どっちでもいいや。結局、なかよしなんだ」
「そうでもない」
食堂につながる通路へ、ギリシャの神殿を思わせる柱が、残像のようにならんでいる。まっ白な、ボール状の明かりが、そのまんなかあたりに、いちいち行儀よく浮かんでいる。影すらつくれないかすかな光は、かろうじて歩道のタイルのでこぼこをふちどるだけのものでしかなかった。夕焼けの残照にまじって、立ちこめる湯気が黄色く、青く、呼吸するように点滅しながら、女子大生たちと、猫をつつむ。猫は、もうどうにでもしてくれ、と、あおむけに寝ころんでいる。
「なんて名前かな」
「さあ、なんだろ」
金髪に近い、くるくるした髪の毛と、ハスキーな酒やけしたような声には、覚えがある。体を洗っているときに、リンスを忘れた、切れたと言って、となりのわたしに声をかけたふたりだった。番台のおじさん以外で、誰かと話すのははじめてで、多少あせり、あやしまれないようにと思ったのか、妙に高い声で、いいですよ、とリンスを渡した。少しでも若く見られよう、というつもりだったらしいが、よけいなことだった。
「あの、なんて名前ですか」
くるくるのほうが、わたしを見上げて聞いてくる。とっさに奈津美との電話にもどろうとしたが、しばらくあいづちを返さなかったせいか、もう切れていた。頭に血がのぼり、腕は冷たくなってくる。風呂場のやりとりが伏線となり、これ以上会話をすると、知り合いくらいにはなってしまいそうで、こわかった。くるくるは、わたしをじっと見つめている。もうひとりもやがて顔を上げ、
「名前、ないんですか」
と、やはりハスキーな声で言う。確実に、わたしをリンスの人だと認識し、目をきらきらさせている。わたしは、耐え切れずに、
「さあ、わたしの猫じゃないんで」
とこたえてしまう。
「よく見ますよね」
「え。ああ、猫がね。そうですね、よく、いますね」
「名前ないなら、つけましょうよ」
「いいんじゃないですか。ノラ猫だろうし。多いですよね、犬とか猫とか、カラスとか。みんな人間をなめてるから、ヒの字で寝てる」
「ヒの字。ああ、本当だ」
くるくるが笑い、ハスキーも顔を見合わせて笑う。いまいちその波に乗れないわたしは、ただ、ぼけっと突っ立っていた。首すじに痛みを感じ、お風呂セットを持ちかえ、手のひらで思い切り打った。はっきりと、血のたまった腹が破裂する手ごたえを感じる。このあたりの蚊は、服の上からでも刺してくる。刺されたときに、かゆいよりも、針を立てられたような感触にびっくりしてしまう、凶悪な蚊。手のひらの上で、ごちゃごちゃした、わけの分からない黒い塊になった蚊の死体を、わたしは軽く人さし指ではじいた。
奈津美に電話をかけたときは、葉桜の枝ごしに横たわる雲が紫ににじんで、夏の夕暮れはまだまだこれからだったのに、いまはもう、夜のはじまりと言ってよかった。まんまるな明かりが、湿気の多い空気のなかで、やわらかいレースのような輪をまとう。やがて、自販機の前に、巨大な蚊柱が浮かび上がる。もぞもぞ、そこらじゅうから虫たちが集合してくる気配に、鳥肌が立つ。もう開きなおって、このふたりと気持ちよく交流することを考えていたのに、わたしは、そろそろ切り上げて帰りたくなっている。
「じゃあ、なんか、三人だけの名前をつけましょうよ」
ハスキーが、提案する。三人にわたしが入っているのが、うれしいような、まずいような気がする。できれば学部とか名前とか、自己紹介し合うような流れにはなってほしくないが、なんのうたがいもなく同じ女子大生だと思ってくれているのは、素直に、うれしい。いくつに見えるのかだけ、うまく聞き出せたら、奈津美に自慢してやろうと思う。
「なんだろう。スージー」
「男の子だから」
「そっか。ジョン」
「ジョージ」
「ダニエル」
「太郎」
「パパイヤ」
「かば」
「コレステロール」
「悪玉」
「おにぎり」
「パン」
「もち」
「でぶ」
ひどいことを言う。わたしを置き去りにして盛り上がるふたりを見て、若いっていいな、と思う。と、またすねを蚊に刺されている。体育会系らしき男子学生が、浴場に入っていく。入口で携帯をいじっていた女の子が、出てきた彼氏らしいのと一緒に帰っていく。南こうせつの顔が、目の先に浮かぶ。みんな平和そうに、太った猫をながめながら通りすぎていくが、わたしはひとりでひやひやしている。そんなわたしの気持ちも知らず、猫はもだえつかれて、軽く肩で息をついている。うとうとしている表情まで、やけに人間くさい猫だった。
「なにがいいですかね」
猫を抱き、くるくるが立ち上がった。きたないからやめたほうがいい、と思ったが、言わなかった。
「ドラえもん」
と思いついたままに、わたしはこたえる。泥棒が手ぬぐいをかぶったように、両目と両頬、あごの下を結んだ線で色がかわっている。内側が白で、手ぬぐい部分は灰色だが、この暗がりだと、青みがかって見えないこともない。
またうけた。若いものにちやほやされるのは気持ちいいが、こうしているうちにも、着々と親しさは増していっている。メーターでも見ているように、はっきりと分かる。
「似てる、似てる。丸顔だし。そういえば、ドラえもんは、猫だ」
「じゃあ、そういうことにしておきましょうかね」
「ドラちゃんって、呼びましょうか。ドラちゃん。あ、なんか、しずかちゃんになった気分」
完全にふたりに心を開かれ、自己紹介されてしまう。くるくるが、山本、ハスキーが、佐藤だった。下の名前は言わなかった。ふたりとも、社会学部の一年生ということだった。
わたしもしょうがないので、苗字だけ言う。当然のように、学部を聞かれてしまう。
「どこだと思います」
「さあ。文系かな。じゃあ、比較文学」
「あたり」
われながら、さえていた。学年も、同じ手をつかう。もう、ふたりの素直さ、純粋さはいままでのやりとりでしみじみと感じている。それだけに、ふたりの宣告は、どんな結果であっても、そのまま受け入れなければならない。
「え、同じ学年じゃないんですか」
「そう思いますか」
「思います」
「あたり」
もう奈津美には、イグアナなどとは言わせない。ここ数ヶ月で一番興奮している。その興奮を表現できないのが、じれったい。
夏休みは帰省しないからひまだ、とか、てきとうに話を合わせ、別れる間際の、最後の最後で、リンスのお礼を言われる。くるくるの手から地面に下ろされたドラちゃんは、放心したように、ぐったりとヒの字に寝転び、どう見ても口もとがにやにやしているようで、女子大生になでられた感触を反芻しているとしか思えない。
すっかりかわいた髪を指ですきながら、宿舎と宿舎の谷間を、縫うように歩いていく。芝生を囲むそれらの棟は、昆虫の巣に似た無機質さで立ちつくし、ひっそりと幼虫のように生息する学生たちの、しずかな呼吸が聞こえてきそうだった。裏にまわって窓をながめると、明かりがついているのは、ひとつ、ふたつ、帰省しているのか、遊び歩いているのか知らないが、完敗のオセロみたいに悲惨な光景だった。じっと見ているわたしの頭のなかまで、シンプルに白と黒で整理されていく気がする。わたしも、ここが気に入ったようだ。若く見られたのがそこまでうれしかったのか、と言われれば、それもある。でも、もっと、なんとなく、なんとなくいいと思う。それをがんばって言語化するなら、たぶん、このテンポと肌ざわりがなつかしい。つまり、田舎なのだ。研究学園都市なんて言うから、それこそドラえもんの世界、タイヤのない自動車がパイプのなかを走っていたり、宇宙人みたいな服を着た人がいたり、日本の科学技術が集結している、夢のような未来都市だと思っていた。
なんのことはない、田舎で土地が安いから、大きな研究所、役所なんか、みんなここに集まってくるだけだ。どこに行っても、こやしのにおいが、鼻をむずむずさせる。原始のようなクモがそこらじゅうで網を広げ、窓枠を渡るアリまでが、わたしの常識を越えた巨大さだった。これで研究学園都市も、未来都市もないものだと思う。そこが、なんとなくおもしろい。おもしろい場所だ、とは奈津美も言っていた気がするが、だんだん分かってくる。奈津美も熊本生まれの田舎ものだから、新潟の寒村に生まれたわたしと、似たような感受性を持っているのかもしれない。
早くお店を開きたい。友達ができてしまった。宿舎のお風呂に通わなくてすむようになれば、山本と佐藤のふたりに素性を明かして、客になってもらう。来年、泰子の先輩になるのかもしれない。年齢的には同い年だし、きっとなかよしになれると思う。こうして、ひとつひとつの想像をつなげていって、大きな想像にするのが、一番たのしい妄想のしかただと知っている。サンダルでリズムをとって、あんなこといいな、できたらいいな、と口ずさみ、長い、長いまっすぐな道を歩いていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
