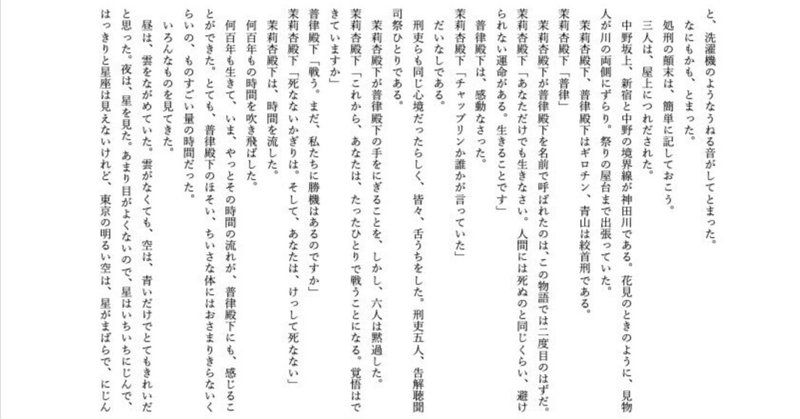
不死王曲 (28) 終
茉莉杏殿下「これから、あなたは、たったひとりで戦うことになる。覚悟はできていますか」
普律殿下「戦う。まだ、私たちに勝機はあるのですか」
茉莉杏殿下「死なないかぎりは。そして、あなたは、けっして死なない」
茉莉杏殿下は、時間を流した。
何百年もの時間を吹き飛ばした。
何百年も生きて、いま、やっとその時間の流れが、普律殿下にも、感じることができた。とても、普律殿下のほそい、ちいさな体にはおさまりきらないくらいの、ものすごい量の時間だった。
いろんなものを見てきた。
昼は、雲をながめていた。雲がなくても、空は、青いだけでとてもきれいだと思った。夜は、星を見た。あまり目がよくないので、星はいちいちにじんで、はっきりと星座は見えないけれど、東京の明るい空は、星がまばらで、にじんで五倍、十倍くらいにふくらんだ星が、夜空をうめつくして、プラネタリウムよりもきれいだった。それは、普律殿下にしか見えない空。
走馬灯、というのがあるではないか、人が死ぬ直前に、いままでの記憶が、映画の早送りみたいに見える、らしい。それが、いまの普律殿下なのだ。
見てきたいろんなものは、でも、ほとんどが空ばかりで。早送りすると、夜空と、青空と、朝焼け、夕焼けが、全部まじってしまって、それはもう、絵にも描けない、ことばにもならない、ものすごい色になって、ぐるぐるめぐる。普律殿下にしか分からない、景色で、色で。だってそうだろう、ずっと空だけをながめて生きてきた人なんて、いないじゃないか。
きれいなだけではない、たぶん。
夜空の黒は、まっ黒な黒ではない、絵の具の全部をしぼりだして、まぜたみたいな、淡い明るい黒で。だから、青くも、赤くもなる。想像してみるがいい。絵の具を全部まぜたまっ黒のなかで、ひとつひとつの絵の具の色が、それぞれに見えてしまうようになったら。
気づいたとき、普律殿下の手は、茉莉杏殿下の手をにぎっていた手は、からっぽだった。
誰もいない。
神田川水上警察署はさびつき、雑草のおいしげる廃墟となっていた。
赤い夕日が、あるいは朝日が、川と桜を染めていた。
普律殿下は、そのまま、ぼんやりしていてもしかたないので、神田川水上警察署の壁をつたっておりていかれた。蔦がからまる城壁は、思いのほか、おりていきやすかった。川の水はかれていた。
川の底を、普律殿下は太陽にむかって歩いていかれた。
万亀橋の下、机があった。灰色の事務机である。私がそこに背中を見せてすわっていた。
普律殿下「おい」
ふりかえって、
私「はい」
普律殿下「みんなはどこだ。姉上は」
私「いません」
普律殿下「いない、とは」
私「死にました。千年もすれば、それはそうでしょう」
普律殿下「馬鹿な」
私「しかし、真実です」
普律殿下「ここを行くとどうなる」
私「さて。やはり、荒野でしょう。私のように物語を書いている人間も、もしかすると、いるかもしれない」
普律殿下「書きなおせ」
私「私には無理です。殺されたって、無理です」
普律殿下「ならば、行く」
かくして、(と私は書く)普律殿下の物語は終わり、はじまった。
円盤である。
見あげると、円盤が光り、回転し、視界のなか、どんどん大きくなっていく。
普律殿下の冒険は、宇宙へと飛びだすのか。
ああ、円盤である。
円盤である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
