
「物語」にしばられ、しがみつく。為末大さんの白状
逆境に耐えて勝つ、弱点を克服する、仲間と助け合う——。
アスリートの「物語」には、王道のテンプレートがあると、元プロ陸上競技選手の為末大さんは言います。
小柄な日本人が技と知恵で世界を舞台に戦う「侍ハードラー」。自分も、そんな「物語」のなかで生きる心地よさと苦しさをともに経験した、と。
「『物語』に苦しんでいると分かっても、自ら書き換えることは難しい。その人自身がその『物語』にしがみついている面がありますから」
為末さんに、「物語」と向き合うことを話してもらいました。

僕は自分をずっと観察していないとダメ。
——Twitterのプロフィールの一文が気になっています。「人間を理解したい」と。
為末:自分のことが一番よく分からない。だから、自分の枠組みである「人間」を理解したい、と思ったんですが。
ーーなにかきっかけが?
為末:一つ理由をあげるなら、陸上競技の経験です。
陸上競技は、敗因が「自滅」以外にないんですね。他人の影響を受けないから、思ったような成績が残せない原因は自分のミス。だから自分をよく観察して特性をつかみ、いいパフォーマンスの出せる環境に自らを置くことが大事です。
僕でいうと「音」のコントロールがカギでした。小さな音でも集中が途切れ、試合前も、話しかけられるとだめ。だから、フードを深くかぶり、ヘッドホンをして、「音」を遮断していました。
2001年、為末さんは世界陸上で3位となり、陸上スプリント世界大会で日本人初のメダルを獲得する。その3年後、大阪ガスを退社。現役時代の後半はコーチをつけなかった。
為末:途中からコーチをつけなくなったのも「音」と同じような理由です。他人とうまくやれないタイプだったので。でも、コーチはいたほうがいいです、絶対に。客観的に見るには限界がありました。
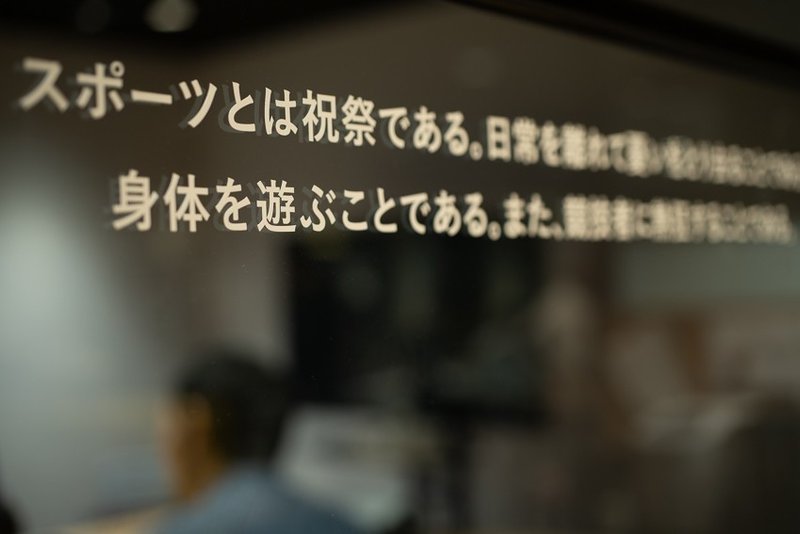
為末:僕は失敗しながら学んできたのですが、さすがに失敗しすぎて遠回りをしたと思うことがあります。
例えば、高校時代からアスファルトの坂をかけ上がる練習を続けてきました。だけどあの練習でアキレス腱と膝を痛め、引退も早めてしまったかな、と。
もう一つは、アテネ五輪の競技本番の数日前、あえて負荷のかかるメニューで筋肉を強化し本番にピークをもっていく練習に臨んだ時のことです。
練習を始めたとき、いつもより疲れている気がしたんですね。「やめたほうがいいかな」と迷いながらも最後までやったら結局、本番でも5%くらい疲れが残った。それで、準決勝で100分の1秒差で負け、決勝に進めませんでした。身体が絶好調になったのは、試合の2日後でした。

為末:あの時、疲れを自覚しながらも練習をやめられなかったのは、大事な試合を前に、ただ不安だったからです。自分の身体感覚を信じずに「決まっている練習」を選んだ。不安になると冷静に判断できません。
そんな自分の判断が正しいと思い込むために、いろんな人の話をつぎはぎしてロジックをつくってしまう。
もし経験豊富なコーチがいたら、アスファルト上での負荷が身体にどんなダメージを与えるかを僕に伝えたでしょうし、本番前の練習もズバッと「やめよう」と言ったでしょう。
そうやってミスをコーチに拾ってもらいながらいろいろな実験ができていたら、もうちょっと上に行けたかもしれません。後悔は多いです。
失敗を重ねるうち、僕という人間は自分をずっと観察していないとダメなんだと分かってきました。
例えば、カーッと頭に血が上っているようなとき、僕のものの見方はたいがいゆがんでいます。深夜に書いたラブレターと同じです。朝読み返すと恥ずかしい、みたいな。だから時間軸で考えます。1年後、1週間後に自分の思考を振り返って、恥ずかしくないかな、と。
「物語」にしがみつき「物語」にしばられる。

ーー1人でやってきた選手時代の姿と、Twitterなどで多くの人と交わる姿が正直つながりません。
為末:僕には、ふたりの「自分」がいると思っています。「世捨て人」な自分と「社会とかかわりたい」自分。選手時代は「世捨て人」でした。速く走れることだけを求めていた。自分以外の存在は世の中にいないし、いなくて構わないとすら思ってました。
いまは反対に、社会や他者とかかわり何かしらの価値を還元したいと思う自分に寄っています。大きなこと、仕組みを変えることは絶対に1人では無理ですから。
——変えたい仕組みがある?
為末:今の社会は、人の可能性が閉ざされてしまう仕組みのようなものがあるように感じているので、どうしたら人の可能性が開かれるのかに興味があります。
可能性を最も狭めているものは、偏見と思い込みだと思います。偏見は外から、思い込みは中から、それぞれ自分を縛ります。
特に「自分はこういう人間だ」という「物語」が思い込みとなって人を縛っている気がします。「物語」に苦しんでいると分かっても、自ら書き換えることは難しい。その人自身がその「物語」にしがみついている面がありますから。

ーーどんな「物語」が人をつらくさせると思います?
為末:怒り、もしくは自分を蔑む「物語」にとらわれている人が、特に苦しそうに見えます。
例えば、何かにつけて怒る指導者がいますよね。どうしてそんなにいつも怒るのかと考えるうち、もしかしたらあの人たちは、怒りを通した行動しか経験してこなかったのでは、と思うようになりました。
少年向け漫画などで、「男子」が変わったり、成長したりする瞬間として「ぉぉぉおーー!!!」と怒るシーンが描かれることが多いなと感じています。自分が変わるときに、社会的に一番安全なアプローチが怒りなんです。「男子らしさ」から外れなくて済むというか。
言いかえれば、怒る以外の立ち上がり方を許されなかった人たちともいえます。タテ社会のなかで、別の感情で自分が変わることが許されないまま、威圧という表現でしか他者と関われない。
共感、寄り添いというアプローチを許されずにきたのだろうか、と切なく感じるときがあります。
「アスリートの物語」の心地よさと苦しさ
——アスリートにも「物語」はありそうですね。
為末:確かに、心理学者の河合隼雄さんが日本の童話から見つけたような心理構成が、日本のスポーツ界の物語にもありますね。
逆境に耐えて勝つ、弱点を克服する、仲間と助け合うーーといった「王道」のテンプレートがあると思います。
僕で言うと、現役時代は「侍ハードラー」と呼ばれていました。所属事務所のマネージャーが考えてくれた呼び名です。小柄な日本人が技術と頭脳を駆使して世界の舞台で並みいる選手たちと対等に戦う。さしずめ「一寸法師」の世界ですね。
——その筋書きはしっくりきました?
為末:気持ちいいですよ。分かりやすいストーリーにはまる心地よさがありました。
でも、「侍の物語」と自分が完全に一致していると思っていた間だけです。途中からズレに気づいて苦しくなりました。「侍ハードラー」としての自分は、弱かったり、不安を抱えたりする人に否定的なレッテルを張っていた。
でも、自分だってそんなに勇ましくないし、「日本人」ぽくもないじゃないか、と。

為末:「あきらめない」物語を生きてきた選手にとって、「引退」はとても難しいことです。ずっとあきらめない、あきらめない、あきらめない——という「物語」でやってきたから。
全力を出しきらないことへの罪の意識が強く、周りの人も「物語」に巻き込んでいるから、自分だけでは閉じることが難しい。
五輪経験のある選手から相談を受けたことがあります。もう一度五輪に出られると思うが、本当は迷っている、と。年齢を考えると、もう一度競技者として出るより、引退してビジネスの分野で五輪に臨んだほうがいろいろ経験できるかもしれない。本人はそう考えていました。
こんな考え、日本では軽々しく言えないでしょう? けれど人生は五輪後も続くと考えたら、一つの選択肢だと思いませんか。
「引退後」を悩んでいるアスリートは少なくありません。でも、関係者が多い分、表立って話せることが少ない。そういう選手は安心できる空間だと、本当によくしゃべります。
今は仕事として、アスリートや起業家と対面で話すことがよくあります。「こうすべきだ」ではなく「この人はこっちの方に進みたいんだろうな」と探りながら話します。
自分自身が「物語」に苦しんだ経験があるので、「物語」に苦しんでいる人がいたら、その人にあう新しい「物語」を提供できる人間でありたいです。
「物語」から逃れられないのなら自在に書き換えたい。

——「物語」にとらわれている人に、どうアプローチするんですか?
為末:「白状」ですね。「僕はこんな感じで『物語』にとらわれてるよ」と先にさらけ出す。そうすると「そこまでは出していいんだな」という空気になります。その中で自分で自分を分析して、自分を物語ることで、少しずつ別の「物語」と自分を一致させていく。その繰り返しだと思います。
もう一つできることがあるとすれば、「あなたの今がこれまでの『物語』からズレていても、私はがっかりしないよ」と伝えることだと思います。本人が一番おびえるのは、今の「物語」から降りてしまった自分を、周りが失望して見放すことです。だから、今の「物語」にしがみついてしまう。
「物語」に苦しんでいる人に正論をぶつけても、何も解決しません。自分を縛りつけている「物語」から距離を取れるようになるには、本人が納得しないと始まらない。他者ができるのは、聞いて、聞いて、聞くことです。
こう話す僕自身も、実は「物語」にとらわれています。客観的な場所から「自分は『物語』から逃れている」と眺めているつもりでも、そんな自分もまた別の「物語」にとらわれている。
阿波踊りで「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々」とうたいますよね。人間として、「物語」から逃れられないのなら、もっと自在に書き換えて生きていきたいと思っています。
縛られている自分自身を笑ったり、楽しんだりするしかないですよ。どうせ縛られてしまうのならば。

為末 大(ためすえ・だい)
1978年広島県生まれ。男子400メートルハードルの日本記録保持者(20年3月現在)。2001年、世界陸上エドモントン大会で3位となり、陸上スプリント世界大会で日本人初のメダルを獲得する。その3年後、大阪ガスを退社。賞金とスポンサー収入で生計を立てる「プロ選手」の道を選ぶ。05年の世界陸上ヘルシンキ大会でも再び銅メダル。3度の五輪(シドニー、アテネ、北京)に出場、12年に引退。現在はスポーツとテクノロジーに関するプロジェクトを手がける株式会社Deportare Partners代表、アスリートの社会貢献をめざす一般社団法人アスリートソサエティの代表理事。
文:笹島康仁 写真:西田香織 編集:錦光山雅子
【Torusの人気記事】
未来食堂・小林せかいさんが向き合う 「正しさ」への葛藤
「貧困の壁を越えたイノベーション」。湯浅誠がこども食堂にかかわる理由
「当事者のエゴが時代を変える」。吉藤オリィが参院選で見たある風景
人気ブックデザイナーが考える 「いい装丁」とは?
イタリア人医師が考える、日本に引きこもりが多い理由
「僕は楽しいからそうする」。大学の外で研究する「在野研究者」たち
「性欲は、なぜある?」が揺るがす常識の壁
Torus(トーラス)は、AIのスタートアップ、株式会社ABEJAのメディアです。テクノロジーに深くかかわりながら「人らしさとは何か」という問いを立て、さまざまな「物語」を紡いでいきます。
Twitter Facebook
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

