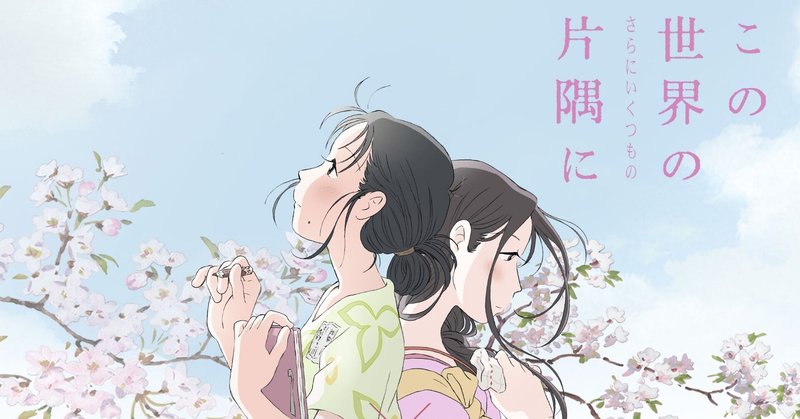
3月27日 片渕須直監督について思うこと。作品の読み方について、創作について。
Netflixに『この世界の片隅に』に関するドキュメンタリーがあるのだが、この中の片渕須直監督のインタビューがやたらと面白い。
例えば『この世界の片隅に』には「テルちゃん」という女の子が出てくるのだが、テルちゃんの方言から九州地方の出身であることはすぐにわかるのだが、片渕須直はちょっとした台詞の一つから、テルちゃんの出身地を飯塚かあるいは田川と特定。筑豊で炭鉱をやっている村の出身ではないか……というところまで推測する。
え? この人、探偵なの? なんでそこまでわかるの?
同じく『この世界の片隅に』では橋の上ですずさんと周作が語り合う場面がある。このすずさんと周作が語り合う場面は実は「出会いのシーン」にもなっていて、作中、非常に重要な場面だ。しかし、この橋が具体的に“どこ”なのか、漫画の中で詳しく描写されていない。
橋の上ですずさんと周作は“何か”を見ながら語り合っている。ではこの橋がどこで、2人は何を見ながら語り合っているのか?
アニメを見た人は答えがわかっているはずだが、すずさんと周作の目の前にあったのは原爆ドーム。その原爆ドームの背景に広がる焼け野原。
しかし漫画は具体的な「場所」を特定しなかった。そこで片渕須直監督は作中で描かれている橋から70年前の広島の地図を比較し、そこが原爆ドームの目の前だと特定した。原作こうの史代がこっそり仕込んだ「秘密」を解いてから、アニメの制作に当たっていたのだ。
最近、YouTubeでコントレールのアカウントを発見し、片渕須直監督の埼玉工業大学での講義映像があったので、作業の傍ら聞いているが、これもすごかった。
主題となっているのは次回作として準備している「清少納言」についてだが、その清少納言の書き残した随筆『枕草子』から、それがいつ書かれたものなのか、どういった経緯で書かれたものなのか、徹底的に調査していた。正確に何年何月何日なのか、ということを明らかにして、この時京都でどんな事件が起きていたのか照合し……(その時雨が降っていたのか雪が降っていたのか、まで特定している)。それで「清少納言が何を思ってそれを書いたのか」という心理的動機まで推測しようとしている。
次回作準備のためにやっていることなのだが、やっていることがほとんど学者。ひぇーそこまでやるのか……と驚いた。いや、恐れ入った。
片渕須直監督は「何となく雰囲気で」という作り方をしない。その時なにがあったのか、どうして人々がそう思ったのか、そこまで作り込んでアニメを作る。
『この世界の片隅に』でも呉が空襲を受ける場面でも、「どの地域にどの程度爆弾が落とされ、どの程度被害があったか」ということまで調べて描いている。「なんとなくこんな感じだっただろう」みたいな雰囲気で作らない。すずさんの住む家にも爆弾が落とされてくるが、おそらくは「あの辺りに爆弾が落とされたことがあった」ということを調べた上で描いたのだろう。
何となくの雰囲気で……では描かない。その時、何があったか、社会はどうであったか、それを掘り下げてから作品を作る。よくある「戦争ドラマ」ではガラスが飛散しないように窓ガラスにテープなんか貼ってたりするんだけど、実際にはあれはほとんどやってなかった……とか。戦時中は男性が戦地に行って人手不足になったので女性が色んな場所で勤めていた……とか(これは『この世界の片隅に』でも描写されていたそうだ。気がつかなかった)。
片渕須直監督という人は探偵なのか学者なのか……。そのいずれでもあって、アニメ監督でもある。
片渕須直監督の話を聞いていた思ったことが2つ。
1つは作品の読み方。
私はよく、「ほとんどの人は物語の一番美味しいところは食べていない。匂い(フレーバー)を嗅いだだけで、「面白かった」と言って帰ってしまっている」という話をする。物語に描かれていることは本当にごく“表面”に過ぎない。そのシーンがどうしてそのように描写されたのか、その意図は、経緯は……? そういうのを掘り下げていくと、物語はどんどん面白くなっていく。
私は「物語をしっかり読むのに教養が必要」といつも語っているが、なぜそれが必要なのかというと、より楽しむためである。ほとんどの人は表面に載っている匂いを嗅いだだけで満足しちゃっている。そんな受け身で楽しむ立場から、自分から一歩二歩と進み出て、物語の内面に掘り下げて読んでいくと、どんな物語でもどんどん面白くなっていく。「なんでそんな面倒なことしなくちゃいけないんだ」と思われるが、そうしたほうが絶対に楽しいから推奨するのである。
作家が物語の表面上に描くもの……というものは本当に表面でしかない。必ず裏がある。あえて描かなかったもの、というものもある。実はそういうものの中に、作品の本当のメッセージ、作者の本音が隠されている。
それが表面上に描かれないのは、「大人の事情で書けない場合」。あるいはそのテーマが非常に複雑で、ある程度以上のステップを踏まないと伝えられないものである場合。そういう難しいテーマの場合、作り手は「配慮」として「わかりやすく噛み砕いたテーマ」をフレーバーとして表面に載せていたりする。そういうメッセージが理解できた時、その物語の真価、本当の感動を得ることができる。
私も作り手として、むしろそういう裏のメッセージを読もう読もうと思って物語と向き合っているのだけど、しかし片渕須直監督の読み方を接すると「私はまだまだだったな……」と思ってしまう。レベルがぜんぜん違っていた。「そこまで読み込むのか……」と茫然とした。
読み方がほとんど探偵か学者か、というレベルで、作者が描き込んだ裏の裏まで読み取ろうとする。
これまた私がよく書くことに、「芸術家と評論家の仕事とは?」というものがある。「批評家の仕事は芸術を言語化することだ」「芸術家の仕事は言語化されたものを飛躍させることだ」。芸術は言語化を越えること、つまりその社会にすでに知られていること、考えられていること、の向こう側を描くことが本当の仕事である。
世代を代表する文学作品になる条件一つに、クオリティ問題を別にすると、その時代の精神を言い当てることにある。その同時代の人がまだなんとなくモヤモヤとしていて、そのモヤモヤ感を言語に言い表せていないような感情や感覚。それを「物語」という形にして言い当てたものが、その時代を代表する文学になり得る。人々が「どうして僕の気持ちがわかったの?」という気持ちにさせる文学だ。
しかしこういう「言語化を超えた作品」を目指そうとした場合、作家自身も自分が描こうとしているものがなんなのかわからない……ということが往々にしてある(「言語化を超えた作品」だから、作者もその作品について言葉でそうそう表現できるものではない。言語化できるなら「言語化を超える作品」とは言わない)。というか、わかっちゃったらその作品をもう書こうという気持ちにならなくなる。作家は自分でもわからない、というものに対して強烈な創作意欲を抱くものだ。書いてから数年経ってから、ようやく自分が描いたものがわかってくる……という感じだ。作家は時として自分の身幅を越えた作品を作ってしまうものなのである。
これを読み解き、言語化するのもやっぱり良き読み手の仕事。評論家は時として作家が言語化できていないものを言語にしなければならない時が来る。
そしてその作品を、原作として映像作品にする場合、作者が想定を越えているものを読み解き、解体し、再構築しなければならない。こういう場合、映像作家は評論家と芸術家の仕事を同時にこなさなければならなくなる。
この作業を、片渕須直監督は完璧にやりこなしている。評論家として原作を徹底して読み解いて分解して、さらに再構築する。ただ単に「原作再現しました」というだけではなく、原作に描かれている場所は、時間は、というところまで特定して、その周辺の空間を描き出す。この作業を経ているから、アニメ『この世界の片隅に』はなんともいえない奥行きを感じさせる映像になっている。
もう1つは、「物語とは?」というテーマについて。
片渕須直監督はほとんど学者のような目線で、その時何が起きていたのか、細かな事件をどんどん掘り下げていく。それこそ何年何月何日何時何分というレベルで事象を掘り出して検証する。実際に『この世界の片隅に』では何日何時何分に空襲が起きて、どの地域が燃やされた、というデータを手に入れてから、作品に反映させるというところまでやっていた。
でもここまでやっていて、片渕須直監督は学者ではなく、「作家」なのだ。どういうことかというと、「事象」以上に、その時、体験した人はどんな気持ちになったのか……ということを一番に考えるからだ。
物語とは結局のところ、「感情」を他人の伝える仕事だ。事象を本にしてまとめて伝えるのが学者の仕事。その事象から「感情」や「情景」を掘り起こすのが作家の仕事。その人がどんな経緯を持って、怒ったのか、悲しんだのか……。その感情を強く残せた作品が、名作になる条件を得ることができる。
片渕須直監督の場合、圧倒するようなデータを積み重ねて、その上でこの人はこういう考えに至ったのではないか、こういう行動に出たのではないか。歴史物を描く場合でも、単に教科書的な歴史事実を書きました……というのではなく、そこに至るまでの「心情的経緯」を重視する。
そこで「なんとなく雰囲気で」というやり方をしないから、通俗的な表現に陥ることはない。なんとなく雰囲気で、というやり方になると、作り手側の意図が入り込んでしまう。このシーンで怒らせてやろう、悲しませてやろう……そちらを先に出して、そのために周囲の事象を作り込んでしまう。むしろこういう作り方の方が多い。
そうではなく、片渕須直監督の場合、かなりフラットな視点で、何年何月何時何分なにがあったか、というデータを積み上げて、それで「この人はこういう感情になった」という物語を掘り起こそうとする。
次回作はどうやら「清少納言」を主人公にした物語になるようだが、どうやって清少納言の物語をひねり出そうとしているのかというと、ありとあらゆるデータを引っ張り出してきて、「清少納言はこの時○○をした」「清少納言はこの時○○と思ったはずだ」という事象を集めて、そこから物語を引っ張り出そうとしている。歴史検証はほとんど学者のようなやり方だが、物語を引っ張り出そうとするところに作家としての意識が現れてきている。ここから果たしてどんな物語が生まれるのか、私には全く見当がつかない。
学者のような思考方法で、作家として物語を組み上げている。こういう作り方をする作家、といえば片渕須直監督のごく近しいところに1人いることに気付く。高畑勲監督だ。高畑勲監督といえば『かぐや姫の物語』で学者的目線で平安時代を徹底的に調べ上げ、かぐや姫が実際いたらどのような生活をしていたか、というところまで掘り下げ、そのうえで心情を描き出した。高畑勲監督は『かぐや姫の物語』に限らず、『アルプスの少女ハイジ』の頃からずっとこのアプローチ法で物語を作り出している。
どこか作風が似ている……。似ているが違う。高畑勲監督の場合、作品のイメージとは裏腹にどこまでもドライ。むしろ情緒や感傷を避けて描く。高畑勲のエピソードを聞いていると、「この人には感情はあるのだろうか」と思うほどにドライ。
片渕須直はもう少しふわっとしたところで人の心情を描く。宮崎駿監督のような活劇やビビッドな感情はさすがにない。そうではなく、ある時にふわっと出てくる人の感情。
『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』で、ある瞬間、すずさんが周作とケンカを始める印象的な場面がある。私のお気に入りシーンだ。あのケンカを経て、やっとすずさんと周作が「ちゃんとした夫婦」になるのだ。『この世界の片隅に』ではすずさんがそういった心情になるまでの経緯を一つ一つきちんと描いて、やっとある瞬間、ふわっと心情が描かれていく。
高畑勲と手法は似ているが、出てくるものが違う。片渕須直的な人情……というものが作品に現れている。
データを徹底して重視して、その上で人の心情を考えるから、通俗的に陥らないし、その経緯が非常に精密になっていく。片渕須直監督の講演を聴いていて、「ああ、そうか、物語とはそうやって作るものなのか」と改めて発見した。究極的には「感情」を描けるか。感情がなければ物語は物語になり得ないんだ。それを再認識しだのだった。
でも、片渕須直監督のメソッドにはすごい感心したけれども、私はあんなふうに作れないなぁ……。何かとんでもなくレベルの違うものを見せられた感じがしていて、自分の創作に活かすことはできそうにない。
とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。
