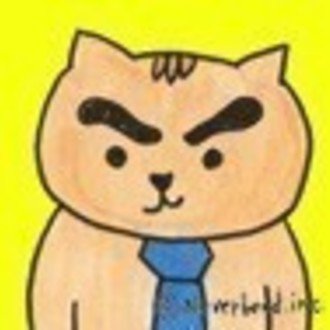♯018 精神科病院を退院後の受療中断をいかにして防ぐか(約束やルール決めをする)

退院後、本人が受診や服薬をやめてしまうことがあります。主治医の判断で徐々に投薬を減らしているのでないかぎり、自己判断で治療を中断してしまうことは、症状の悪化にもつながります。
家族からの相談を受けていると、「過去に通院(入院)したことはあるが、途中でやめてしまって、そのまま何年も経ってしまった」と話すなど、受療中断した際に、家族も対応をとっておらず、結果として、病気の方を長年、放置したことになってしまっています。
そもそも、本人とのコミュニケーションがとれておらず、通院や服薬を自己管理に任せているケースもあります。当然、受療中断したことによる状態の変化にも気づかず、病状がひどくなってから受療中断の事実を知るのでは、あまりに遅すぎると言えます。
退院後に受療中断しないための環境を整えることはもちろん、受療中断となった初期の段階で、いかにして対応をとれるかが重要です。
退院前を前提とした面会で、ルール決め
受療中断した方を再び医療につなげることは容易ではありません。とくに、もともとの親子関係、家族関係が希薄なケースでは、第三者が介入・訪問(受診勧奨)しやすい環境にしておくことが重要です。
よって入院中から、「退院後に受療中断した場合、家族の力だけでは服薬管理や受診につなげる自信がない」と不安があるのであれば、病院のカンフレンスでそのことを伝え、そうならないようないくつもの手段を講じておくことです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?