
スパジャー誕生物語 #3
①創刊への道のり
②なぜバイリンガルにしたのか
③“スパイス”がテーマの媒体を考え付いた背景
③“スパイス”がテーマの媒体を考え付いた背景
本の名を『スパイスジャーナル』に決めたのは2009年から年が変わる頃でした。でも、周囲からは思いっきり反対されました。
「スパイスなんて言葉はマイナーすぎる。いくらカワムラがそういう思いをメッセージしたとしてもそれは世間一般では浸透していないし、たぶん今後も広がらない」
「スパイスもインド料理も、大衆は特別な思いはもってない。どのみちカレーマニアのための本になる」
「ジャーナルというのは報道のニュアンス。季刊誌では記録の感じになってしまう。もっと本の名を熟考すべき」というインテリ?な意見もありました。
本の判型も反対されました。当初の僕の計画ではタブロイド版、またはA2二つ折りを考えていました。イメージはアメリカやヨーロッパの売店にあるようなゴシップな感覚だけど、その実は専門紙というもの。
これについては結局A5サイズに。今ではすっかり当たり前のように見る判型ですが、フリぺでなく商業雑誌としてはけっこう斬新な判型だったのではないかと思います。
でも『スパイスジャーナル』という本名については何の迷いもありませんでした。中身も文字通り一貫として「スパイス」をテーマにしています。
ただ、これは決してマニア向けではないと考えていました。一見マニア志向に見えてもその実は逆で、あくまで普通の生活を送る一般層に向けたもの、と。
おおげさかもしれませんが、強い使命感のようなものもあったのです。今まで長いあいだ飲食の現場一筋で生きてきましたが、中でもやはり三重・松阪時代の『THALI』(1998~2001年)は決定的でした。
毎日のように同じような質問や一方的な発言が飛んでくるんです。
「日本のカレーって西洋から伝わったんでしょ?」「本場インドのカレーってもっと辛いよね?」「インドでは手で食べるんでしょ?」などと歴史や文化からはじまり、徐々にややこしいのが飛んできます。
「もっととろみが必要。シャバシャバなカレーが本場風というのはわかるけどここは日本だ」「カレーというものは黄色じゃなく焦げ茶色じゃないと。黒いカレーだってあるくらい。もっと勉強したほうがいい!」「カレーはコクが命。これじゃ物足りない」「もっと日本式のカレーを作れ!」「名古屋の〇〇というインドレストラン、あれこそ本物だ」などなど。
ひどいときは「僕は私はあの人は、とんでもないほどのカレー好きで食べ歩きなら誰にも負けない。この店の一番自信のあるカレーを出して!」なんていうのも。
うちのどこに「カレー屋」と書いてあるのか?
・当店はインド料理店
・主な人気メニューは日替わりのターリー
・できれば自家栽培の野菜
・ブレンドスパイスはすべて自家配合
・パウダースパイスはできるだけ挽きたて
・ベジとノンベジの2種類あり
発信していたメッセージは以上です。

(写真は2000年頃の雑誌BRUTASにて)
もちろん、時間と共にポジティブに興味を持つお客さんも出てきます。
「インド人はカレーを手で食べる?」
「インド料理はルーやブイヨンは使わない?スパイスだけで作る?」
「スパイスってなに?野菜?植物?」
「このスパイスはどの国の何科?何属?」
「どんな薬効がある?」などなど。
中には熱烈なインドファンのお客さんもいて、この層も一長一短でした。SNSやネットはないので、現代のように一気に人が集まってくる、という状態ではなく、少しずつ口コミで広がっていくんです。
例えば関東圏の本場のインド料理やネパール料理を食べ歩き続けている、数名のグループははるばる駆けつけてくれてうれしかったです。今でこそ東海道・山陽道なんて楽に移動するし、三重県と言えば伊勢神宮参拝に誰もが行くような時代になっていますが、当時は東海道新幹線の駅を持たない三重県がどこにあるかわからない人が東京にも大阪にもいて、伊勢神宮へ参るなんてちょっと変わった人、という感覚でした。
しかも当店は松阪駅の「駅裏」と呼ばれたエリアで、さらに袋小路となる路地にあるわけで、地元の人でも普通に迷うような場所に店はあったのです。

彼らは色々提案してくれました。10人分単位のスパイスキットや冷凍カレーも彼らからの相談で始まりました。同時に、地元客の主婦層向けに、5人分単位の小サイズのスパイスキットもこの時誕生しました。
中にはインドに長年住んでいるという人、30年にわたり60回以上渡航しているという雑貨商の達人もいました。よく考えたら、僕が大阪箕面でやっていたエスニックなバー「P・AGE・BAR」(1991~2007)のスタッフの一人も、インドに一年住んでいたっけ。
このようにディープなインドラブな日本人の客も何人かいて、そういう方たちの話はとても興味深いのですが、時に問題を引き起こす人もいたのです。
それは、どっちが本場本物を知っているか論争です。日本人は好きですね。あんたよりも俺ワタシのほうが詳しい的な物言いが。
ある時、インドに住んでいた経験のある男性と、ご主人がインド人で向うに10年ほど在住経験のある日本人女性が、言い争いになったんです。
何が本当のインドカレーで、どんなものが本場式なのか論争。
ほかのお客さんもいたのですが。実質5坪ほどの狭い店ですから大声で論争されてしまうと、みんな食事が不味くなる。僕は確信しました。本当にお客さんに喜んでもらうには、何が正しいかより、どれだけ快適かが大事だということを。
結局この二人は最後まで相いれることなく物別れに終わったわけですが、二人ともインド通ならあの国が多様性の極地であることを誰よりも熟知しているはずなのに、日本人同士では多様性を受け入れられなかったのでしょう。
本場のことをよく知る人から、本場の話を聞くことはとても面白いことなのですが、あくまでここは不特定多数の人が共存する小さなお店ですから、時に限度があるし、マナーは不可欠ですよね。
ま、僕自身もいつまでも話を聞き続けられる状況ではなかったというのもあったのかもしれません。当時の僕の生活リズムはこんな感じです。
朝8時頃~仕込み。11時半から開店。早ければ1時過ぎ~品切れ。まかない(週に5日は残り物のダールやベジとごはんとヨーグルトと漬物)。シンクに皿を突っ込んだまま買い出し。4時頃~店に戻り夜の仕込前半戦。6時頃~営業。夜は酒を飲む方が多く、アドリブでスパイスつまみを作ります。週1~2くらいのペースでご予約いただき10品ほど作る日もありました。
自分の夜ごはんはスーパーなどで買っておいた串揚げの盛合せなどを食べるのが定番でした。
さて、話を本題に戻します。
スパイスというワンテーマの本を創り出した最大の理由は、以上のことからたくさんの方々がインド料理やスパイスに興味を持っていることを肌で感じ取っていたからです。
でも、現実社会は離れている。少なくとも自分が関係していた雑誌の編集部などでは、「インドカレー」という言葉はおろか、「カレー」という言葉さえも人気のない言葉として信じられており、小さな記事さえも書かせてもらえない状況でした。「インド料理」という言葉もほぼ無視状態。
そんなだから僕はある頃から「スパイス」という言葉を意識して使うようになり(当時は香辛料と拮抗していた)、誰も相手にしてくれないなら自分で創ってしまおうってことで「スパイスジャーナル」という言葉生み出したのです。
『スパイスジャーナル』のコンテンツはみんなお客さんが投げてきた球から生れたものです。本当に、それくらい多くの人が「インド料理」と「スパイス」に強い興味を示していたわけです。
今では、カレーだけがインド料理じゃないことや、辛いばかりではないこと、インド料理の多様さ、いろんな国にスパイスを使った料理があること、体調とスパイスの関係性、などなどかなり広くに知れ渡っているように感じます。
「スパジャー誕生物語」おわり
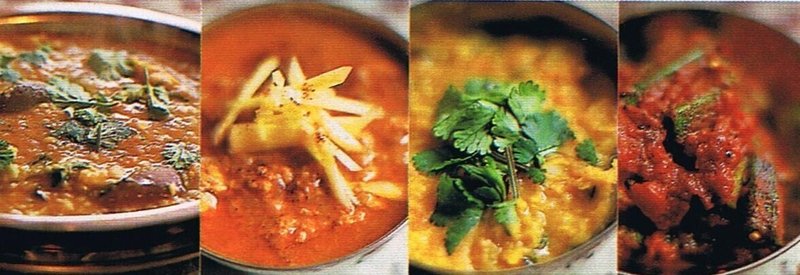

三重松阪『THALI(ターリー)』(1998~2001)の料理例
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
