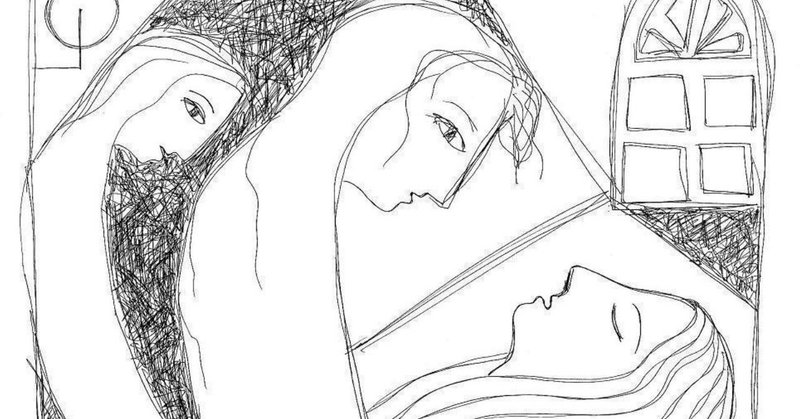
安楽死に関するNHK番組 それでも制度としての導入には慎重であるべきだ
NHKが放映した「彼女は安楽死を選んだ」が話題になっている。重い神経難病を患った50代の女性が、安楽死するためにスイスに渡り、実際に処方された薬物を投与することで安楽死するまでを撮影したドキュメンタリーだ。この番組へのネット上の反応を見ると、自己決定による「死ぬ権利」を認め、日本でも積極的安楽死ができるようにするべきだという意見が目立つ。自己決定権を重んじるということのようだ。だが、性急な議論の展開には慎重であるべきだと私は思っている。
番組の意図は議論の喚起か
日本では積極的安楽死は認められていない。というか、議論もほとんどなされていない。治療の不開始や中断などによる消極的安楽死(これを日本では尊厳死と呼ぶことがある)は、各種のガイドラインがあり、現場で選択されることが増えているといわれる。鎮静も採用されることがある。
スイスでは民間団体が、自殺幇助の形で安楽死を手伝っている。医療者が処方した致死性の薬物を本人が自ら用いることによって死ぬのだ。スイスの一部の団体は外国人を受け入れており、今回NHKが取材した団体の代表者は「日本人が急に増えている感触がある」と述べていた。「潜在的ニーズ」が日本にもあるということを番組は示し、議論の種にしてほしかったのだろう。
自殺・自死を防ごうとしていながら積極的安楽死は認めるのか
確かに、病気になった本人にしかその本当の辛さはわからない。だから、外野が余計な口を挟むな、といわれるかもしれない。生きることを強制する権利など誰にもない、と糾弾されるかもしれない。だが、積極的安楽死を社会制度として導入することには、やはり危惧がある。
例えば、自殺・自死のことを考えてみる。日本では現在、年間2万人以上が自殺しており、自殺対策が社会の重要な課題として取り組みが進められている。自殺の理由は様々だろう。病気を苦にしてとか、経済的な苦しみを抱えてとか、人間関係に悩んでとか。積極的安楽死には医師が直接、致死薬を体内に入れるなど医師の手による方法もありうるが、スイスではこの方法は殺人にあたる。おそらく日本で積極的安楽死が万々一、認められる事態になったとしても、自殺幇助の形になる可能性が高いと考える。だとすれば、一方で自殺防止を社会が課題として対策を進めながら、他方では社会が自殺を推奨することになる。
だれが「希望がない」と判断するのか
「いや、あくまで苦痛が激しく、不治かつ末期の状態の病人だけを対象にする」という反論がすぐに返ってくるだろう。だが、借金などの経済苦の人の自殺は防ぎ、病気の人には認める区分けの根拠があるのだろうか。苦痛の大きさは身体的なものだけが特別に重視されるのだろうか。「精神的な苦痛だって病気にはある」といわれれば、経済的苦しみや人間関係の悩みに伴う精神的な辛さと一体、どのような違いを見出せば良いのか。
「病気は医師が判断するし、治る見込みが無かったり、死期が迫っていたりするから希望がない。でも、経済苦などは助かる手段がある、希望を見いだせる」という理屈によるとすれば、病気にだって希望を見出す種はあり得ないと断言できるのか。いま不治の病だとしても、明日、新たな治療法が発表される可能性だってあるのだ。「不治=希望がない」は性急な前提だろう。例えば今回の番組でも、安楽死を選んだ女性と同じ病を患う別の女性に取材していたが、その女性は「人工呼吸器をつけでても生きる」選択をしていた。口がきけなくなっても、家族との何気ないやりとりが生き甲斐だと感じられるからだと言う。誰が「この人には希望がない」と断言し、判断するのか。それは本人の選択だとすればまた最初に戻ってしまう。では、なぜ経済苦など病気以外の苦しみでは自殺という選択肢を認めようとしないのか、と(なお誤解を招くと困るのでここで断言しておくが、そうだからといって私は決して「じゃあ、どんな場合、どんな理由でも社会が自殺を認めて幇助すればいいじゃないか」などというつもりは全く、微塵もない)。
「滑りやすい坂」への危惧
もう一つ、社会制度として積極的安楽死を認めることになれば、よくいわれることだが「滑りやすい坂」に足を踏み込む危険がある。積極的安楽死を認めている国でも、当初は耐え難い苦痛や不治であることなど要件が厳しかったにも関わらず、徐々に未成年も対象にしたり、認知症患者までも対象にしたりとその適用範囲を広げようとする動きが出て来る。一度、足を踏み入れれば、滑り始めてしまい、止まるに止まれない坂。特に日本のような「場の空気」が支配する社会では、滑りやすさは他の国以上になる危惧がある。障害ある人間は不幸だから、といったような本人の意思とは無関係な圧力が怖い。本人の意思と言いながらもその実、周囲の都合・空気を押し付けてしまいかねない怖さがある。
自己決定に判断力の有無を問うとしたら
本人の意思決定、自己決定権が絶対大切だと考えるとしても、その意思決定とはおそらく「判断力がある」と考えられているからこそ認め、尊重しているはずだ。例えば、認知症や精神を病んで判断力に疑問がある場合、たとえ本人が主張したことでも周囲は認めないことがある。契約行為でも実際、そうした理由で無効と判断されて破棄されることがある。病気で苦しむ人の中には、苦痛から判断力が低下する場合だってある。そんな状態の中で判断したこともまた本人の意思決定、自己決定として認めることができるのか。それとも、重い病気、苦痛がひどい病気の時には、「判断力」の基準が引き下げられてしまうのだろうか。「本人の判断力の有無は医師や周囲が判断すれば良い」とするならば、もはや自己決定を尊重するという根本が揺らいでいる。それは周囲が判断することとほぼ同義になっている。周囲の都合・判断に合わせて自己決定が成立するかしないかになっている。
誰も見捨てない社会であってほしいと思うからこそ
他者に対して、生きることを強制はできない。それは当たり前だろう。説得には限界がある。苦痛緩和の方策や精神的ケアにも限界はある。それでも、たとえ偽善だといわれても、本人の苦しみがわからない冷血漢だといわれたとしても、やはり社会は社会制度として死の選択肢を提示するのは可能な限り避けるべきだと思う。ギリギリまであらゆるケアを提示し、寄り添う。生きている意味を語りかける。生きているだけで社会のリソースを使ってそのように可能な限り寄り添うことをこの社会が示してくれるとしたら、そのことを顕在化させるという一点において、多くの人に「この社会はどんな人も見捨てない社会なのだ。生きることを受け入れる社会なのだ」と示す意義はある。生きるための意味や希望が必要だとするなら、その種になりうるかもしれない。
これは本人のためというよりも社会のためにではないか、生き方を強制していると指摘されるかもしれない。それに、書きながら辛いのが「この社会は本当にそうした社会的包摂を実現している誇るべき状態なのか」と自問自答するとき、一瞬言葉に詰まる自分を発見してしまうことだ。その現実を含め、それでも、否、そうだからこそ、絶望の淵に佇む人に対し安易に死の選択を提示する社会ではなく、死なせない努力をする社会であってほしいと思うのだ。その可能性を引き出すためにも、いきなり死を提示する社会であって欲しくないと思っている。生きているだけで意味があると、だれもが感じることができる社会を諦めたくはない。一人一人の「生きる権利」さえまだまだきちんと確立しているとは思えないこの社会で、「死ぬ権利」が唱えられるのはシュールだ。
苦しむ人の「線引き」
いま新出生前診断で陽性反応が出ると、9割以上の夫婦は中絶を選択している。この社会はそういう社会だ。まるで、障がいがあることは不幸であり、障がいのある子どもを育てることは不幸だといわんばかりの、無言の社会意識・空気がそうした選択の背景にないと断言できるだろうか。制度として積極的安楽死が導入されるとすれば、「苦しむ人は不幸なのだから、本人の自己責任・選択で死を選ぶことは当然の選択だ」という無言の社会意識・空気が広がりかねない。それは「誰か」がその「苦しむ人」を選択し、線引きする危険性を常に伴うことを意味している。だから、制度にすることは怖いのだ。
自分は弱いからこそ
「それは苦しむ本人には無関係なことだ」といわれてしまうと、もはや口ごもるしかないかもしれない。私はそれほど強い人間ではない。だから、目の前で苦しむ本人からそういわれたら、「でも、でも、モゴモゴ…」となってしまいそうな自分を知っている。だからこそ、最初から建前をかなぐり捨ててしまい、感情的同調を優先することには与したくない。繰り返しだが、社会の基底には他者への共感・同情が当然にあるべきだと思う。それでも、それだからこそ、死という選択肢を社会が制度として提供することには、慎重の上にも慎重を重ねる必要があると思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
