
McCoy Tyner Trio featuring Michael Brecker / Infinity
今回はMcCoy TynerのトリオにMichael Breckerがフィーチャーされた作品「McCoy Tyner Trio featuring Michael Brecker」を取り上げて行きましょう。タイトルの割には編成はカルテットないしはパーカッション奏者が曲により加わり、クインテット編成です。
1995年4月12~14日録音 Recorded and mastered by Rudy Van Gelder
Recorded at the Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey
p)McCoy Tyner ts)Michael Brecker b)Avery Sharpe ds)Aaron Scott perc)Valtinho Anastacio
1)Flying High 2)I Mean You 3)Where Is Love 4)Changes 5)Blues Stride 6)Happy Days 7)Impressions 8)Mellow Minor 9)Good Morning, Heartache
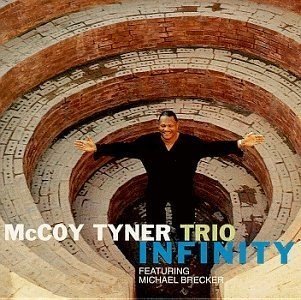
この作品は1995年にリリースされ、1996年のグラミー賞Best Jazz Instrument Performanceに輝き、また収録されているJohn Coltraneの代表曲Impressionsの演奏でMichael Breckerが同じくグラミー賞Best Jazz Instrumental Soloの栄冠を獲得したという、大変な栄誉あるアルバムです。
レーベルもColtraneの一連の作品をリリースしたあのImpulse!で、60年代当時McCoy自身の作品もImpulse!から6作リリース〜いずれも大変素晴らしい作品ですが1枚挙げるとすると「Reaching Force」でしょうか〜されており、古巣に戻った形です。そのためかどうか、本人かなり力が入っていて自筆で1曲ずつ丁寧に解説を書いたライナーノートが添付されています。結構癖のある文字であまり読み易くはありませんが(笑)、作品に賭ける情熱と意欲が文面から伝わってきます。
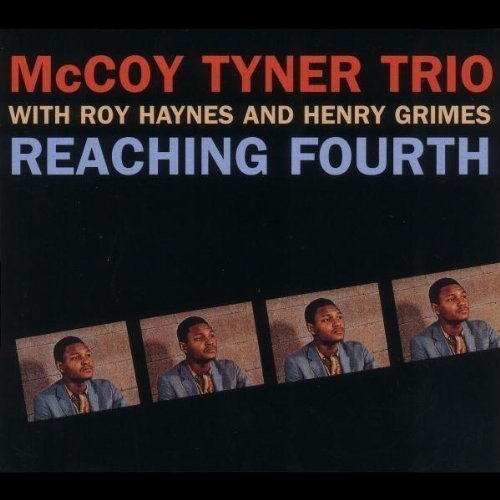
このレコーディング・メンバーでかなりの本数のワールド・ツアーを行いました。ただ残念な事に来日公演は果たしていません。youtubeにその映像が幾つかアップされているので、こちらで我慢しましょう。
ベーシストAvery Sharpeは80年代から90年代にかけてMcCoy Tyner Trioレギュラーを務めています。McCoyの70年代の名盤「Song Of The New World」「Enlightenment」「Atlantis」でベースを弾いているJuni(もしくはJoony)Boothに実によく似たタイプのプレーヤーです。最初に聴いた時にはてっきりJuni Boothだと思うくらいにベースの音色やラインのウネウネ感がそっくりでした。50年代から活動していたアルト奏者Clarence Sharpe(同じ苗字ですが血縁ではないと思います)はCシャープと呼ばれていますが、Avery Sharpeも当然Aシャープとなりますが、B♭ではありませんね(爆)McCoyはこういうビート・タイプのベーシストをレギュラーとして起用するのが好みなのかも知れません。
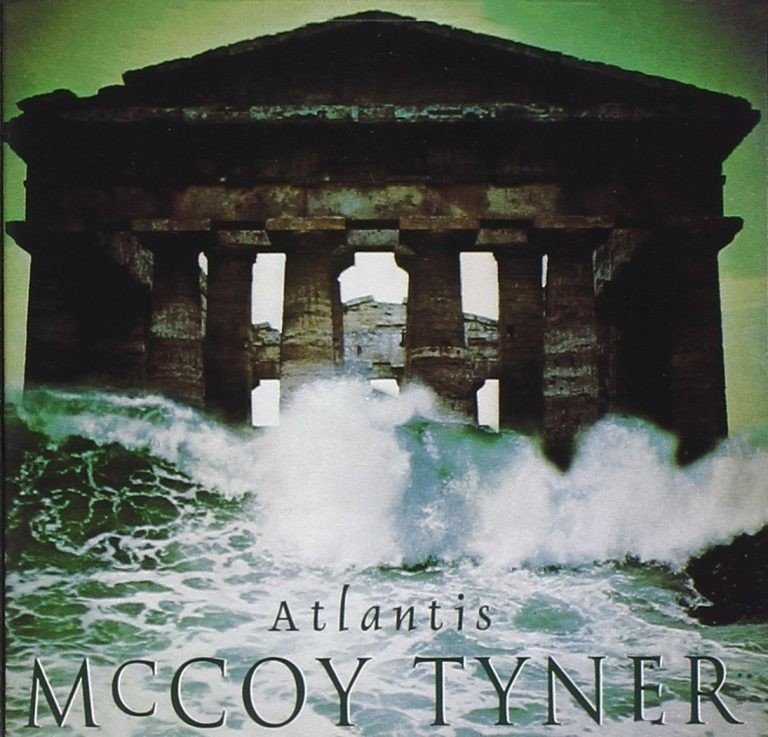
この作品で素晴らしいドラミングを聞かせるAaron ScottはBerklee音楽院出身で89年から96年の本作まで計5作、McCoyの作品に参加しています。AaronとはBerklee同期だった僕の友人ドラマー曰く、見た目や雰囲気から来ているのでしょうか、彼は「ラクダ」と言うあだ名だったそうです。一卵性双生児の兄弟がいて母親が間違うほどソックリだそうですが、Michael Breckerが「Aaronは僕に対抗意識(competition)を持っている」と話していました。いつも会うたびにMichaelにちょっかいを出すらしく、多少のことには動じないMichaelも”うざったさ”を告白していました。同じ楽器を演奏する者同士なら対抗意識を持つのも分かりますが、逆に同じ傾向、同方向の物の考え方を持つもの同士なら楽器が違えど対抗意識を持つことがあるのでしょうか。そういえばSteve Grossmanが「Bob Bergはオレに対抗意識を持っているんだ。アイツは面倒臭い奴だよ」と言っていました。この事にはしっかりと頷くことが出来ます。18歳でWayne Shorterの後釜としてMiles Davisのバンドに大抜擢、一世を風靡した天才サックス奏者には努力の人Bob Bergは対抗意識むき出しで当然だと思います。Randy Breckerも「Bobはコンプレックスの塊だ」とも発言しているのを読んだ事が有ります。でもBob Bergは87年頃にMilesのバンドに参加、「You’re Under Arrest」をレコーディングしてロードにも出ました。New Yorkで60年代末から70年代初頭にかけて青春時代を過ごした、いわゆるロフトでジャムセッションを繰り広げ、お互いに切磋琢磨しあった間柄のColtraneスタイル・テナー奏者たちSteve Grossman、Dave Liebman、Bob Berg、 Michael Brecker、Bob Mintzer達は全員ユダヤ系アメリカ人です。特にGrossmanとLiebmanは2人とも70年代を代表するバンド、Miles Davis Groupの他Elvin Jones Groupにも参加、70年代にはその音楽性を見事に開花させました。Michaelは実はジャズジャイアントと共演の機会が少なかった事に引け目を感じていたように感じます。こんな話があるのですが、Charles Mingusのラストレコーディング、名盤「Me, Myself An Eye」のレコーディングについて僕がMichaelと話をしました。


膨大な人数のミュージシャンが参加したラージアンサンブルなのですが、僕の「レコーディンの時のことを覚えてる?」と言う質問に「あまり覚えていないけれど、Charlesの他Lee Konitzが居たのは覚えているよ 」Michaelと同じくジャズシーンだけではなくスタジオミュージシャンとしても活躍して居たバリトンサックス奏者Pepper Adamsの参加を思い出し、「確かPeppr Adamsも一緒だったはずだよ」と言うと急に色めき立ち「えっ、本当?Pepper Adamsがあの場に居たのかい?」「そうだよ。ライナーの写真にもPepperが写っているよ」自分が参加したアルバムにあまり興味のないMichael、当然ジャケ写も見ていない事でしょう。「僕はPepper Adams(何故かPepprではなくフルネームで呼んでいました)と共演していたんだ…」遠い所を見つめる様な感じの目付きをしながら呟いていたのが印象的でした。ジャズジャイアントとの共演歴が彼の中でその時もう1人増えた訳です。
盟友Grossman、Liebman達の華々しい活躍を尻目に彼自身はHorace Silverのバンドに参加したことがある位で、ひたすらスタジオミュージシャンとして活動を続けていました。多分MichaelもGrossman、Liebman2人にはcompetitionを持っていた事でしょう。でも外にその感情を出さずその分のエネルギーを自分がやるべき事の精進のために凝縮して費やす、むしろそう言うことが出来る事に長けている、いやその点に関しては天才的なのがMichael Breckerです。驚異的な楽器の習熟度、進歩、誰も成し得なかったサックスの奏法開発、まさに不言実行を絵に描いたような人でした。
Chick Corea、Herbier Hancock、Elvin Jones達ジャズジャイアントと演奏を展開し、この作品でMcCoy Tynerとも共演を果たしました。さらに96年には自己の傑作アルバム「Tales From The Hudson」でMcCoyをゲストに迎えてPat MethenyのオリジナルSong For BilbaoとMichaelのオリジナルAfrican Skiesをレコーディングし、96年この自身の作品でもMichaelはBest Jazz Instrument Solo(収録曲Cabin Fever)とBest Jazz Instrument Album2つのグラミー賞2年連続受賞と言う快挙を成し遂げました。
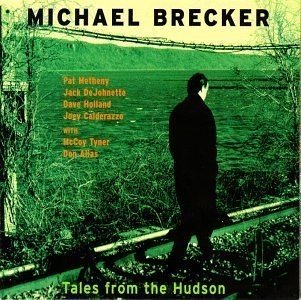
「McCoyは僕にとても良くしてくれているんだ」と嬉しそうに話すMichaelの笑顔を忘れる事が出来ません。Milesとの共演だけは果たす事が出来ませんでしたが、Michaelはありとあらゆるジャズジャイアントとの共演を実現させました。
最後に「Infinity」のレコーディングの音質について触れて見ましょう。前述の通り名エンジニアRudy Van Gelderによる、彼のNew Jerseyのスタジオでの録音なので本来なら悪かろう筈がないのですが、実は僕にはあまりピンと来ていません。というかMichaelのテナーの音色が彼らしくないのです。96年の来日時Michaelに会い一緒に石森楽器に同行した時の話です。お店の従業員の方がMichaelが来店したので気を利かせてこの「Infinity」CDを掛けました。すると「うっ、このCDのテナーの音は苦手なんだよ」とMichael呻くように呟きました。「このレコーディングはRudyがエンジニアなのだけれど、どうしてなのかこんな音色で録音されたんだ。Tatsuyaはどう思う?」「確かに僕もこのMichaelの音色はいつもと違うと思っていましたよ」「そうなんだよ…」Rudy Van Gelderは既に何度もMichaelのレコーディンを経験していて、彼の音色の本質を把握している筈ですが、Rudyは常々レコーディングのクオリティを向上させるべく新しい事にチャレンジしていたようです。この作品はひょっとしたらチャレンジが裏目に出てしまった例なのかも知れません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
