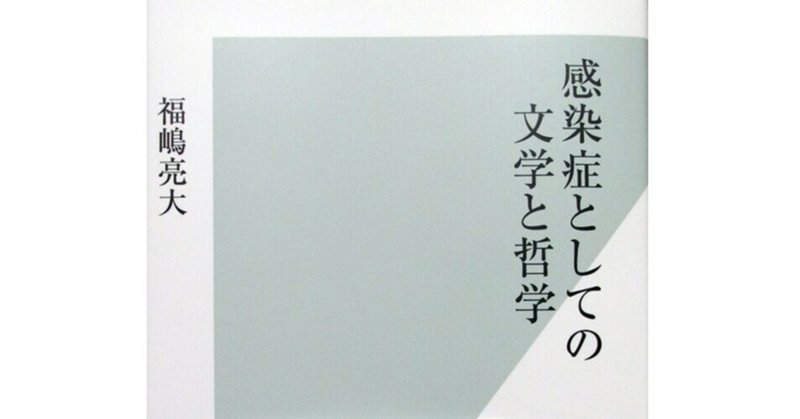
『感染症としての文学と哲学』(福島亮大・光文社新書)
2022年2月の発行。著者は中国文学科卒業だというが、そんな気配は少しも感じられない。西洋文学中心かと錯覚していた。文章が巧い。読ませる力があり、それはまた、読者がすいすい読めていながらちゃんと内容が把握できていくということである。一読して何が言いたいのかが伝わり、また少し複雑なところは、ただ読めば説明が即座になされるというようなスタイルで、読者に悩ませる暇を与えないのである。
もちろん、2020年からの新型コロナウイルスによるパンデミックの中から生まれた本である。過去の歴史の中にも同様のことが起こっていたことを、人類は知っていた。だが、今の時代にそんなことはない、と誰もが思い込んでいたほどに、パンデミックなどは過去のものであった。もちろん、鳥インフルエンザやSARSのような話が時折舞い込む。しかし、それは世界の中でも局所的なものであるとしか理解されない。自分とは関係のないものだ、という思い込みが、私たちの中には確かにあった。
それが、世界へのこの蔓延である。特にヨーロッパでは、忌まわしいペストの記憶が蘇ってきた。日本では、その代わりにコレラがあった。百年前のスペイン風邪の影響は、今回の新型コロナウイルスとの比較がなされる。
人が移動することが、こうした感染症を拡げる要因であるということは、よく言われるようになった。事実、緊急事態宣言で人の動きを抑制していたときには、拡大させない一定の効果があったと言えるだろう。しかし、それだけのものなのか。人間は、経済基準でしか物事を捉えられないのか。過去のペストなどの時に、人類は何を考え、精神的な何を遺してきたのだろうか。
本書は、宗教的な癒しから入る。となると、イエスの癒しも話題になる。山形孝夫氏の強調する治癒神という考え方に偏っているのは、仕方がないかもしれないが、人間の精神的な営みの中で宗教をきちんと捉えておく準備は悪くない。そこから今度は哲学に中心が動いていく。そのときカントが繋ぎ役になっているのは、少々意外だった。カントは、健康というものが、感じることはできても、知ることはできない、と言っているという点を強調してきたのである。カントの認識の捉え方は間違いなくそうである。いま私たちは健康を、まるでモノのように扱っていはしないか、そうではないコトとして捉える、そこにきっと文学の力が見えてくるのだという気もするのだ。
哲学は、古代からきっちりと辿る。探し出してくると、様々な人が、ちゃんと疫病のことに触れている。このコレクションは、私も確かに知らないし、そんなものがあるのだろうかと不思議に思っていた。パンデミックの2年間で、当然出てきてもよさそうなものであるが、そうした本が出て来たようには聞いていなかったからである。単に私が知らないだけかもしれないけれども。
時代時代で、様々な疫病が出ている。残念なのは、旧約聖書の例が取り上げられないことである。資料性に乏しいからだろう。神はしばしば、疫病を人間に与えているし、預言者の書にもよく出てくる。やはり人類史上、疫病というのは常にありうることだったのだ。それは最後に日本のことについて、清少納言と紫式部の時もまさにそうだったという指摘にも驚かされたことから改めて思い知らされた。但しこの二人は、文学において疫病に対するアプローチが違うというのだが、それはどうぞお読みになってのお楽しみとしておく。
哲学史の中では、哲学が医学をどのように捉えていたか、というのが大きなテーマである。たとえば外科医が元来非常に蔑視された存在であったことは有名である。その時代において医師がどういう社会の位置づけであったのか、それはまた医学技術の有効性にも関係したことだろう。日本では加持祈祷というのも医学の一部であったことがあるはず。病になれば神仏に祈るというのがまずすべきことであった。医学の歴史を繙けば、西欧でもさほど事情は変わらないことが分かる。
章を改めて、今度は文学が疫病をどう描いていたかという議論が始まる。やはり古代からだが、やはりあのヨーロッパのペストは注目に値する。私はこのパンデミックの中で、デフォーの『ペスト』を非常に関心をもって読むことがあった。もちろんそれも扱われる。そしてコレラも実はヨーロッパ文学において大きな要素となっている。『ヴェニスに死す』や『ボヴァリー夫人』にしっかりそれが描かれている。その他、私は時折無性に文学作品に首を突っ込むことがあり、それがこうした説明を見るときに実に活きてくるのだということを強く感じた。もちろん知らない本も多々出てくるが、結構、読んだものが扱われるので個人的に読みやすかった。
ただ、エイズは、この文学に描くということから、少し外れてくるものがあるという。かつて文学こそが、感染症を描く本丸と見られていたのが、この新しい時代では、どうもそうではなくなってきたらしいのである。
すでに長く紹介してきたが、本書の味わいはここからである。次は、文学が如何にして医学を描いてきたか、という問題である。ここでラブレーの大きさを私は知った。これは作品としては読んだことがない。解剖医だったラブレーの描写の、えぐいこと。それが弟子たるフローベールに流れたり、ウェルズなどにいくとまた面白い展開を見せる。シェイクスピアやロシア文学へも言及し、この社会そのものに病院という意味を見るようになってくると、文学が如何に人間のものの見方のために大きな存在であるのかを思い知らされる。
ソラリスが取り上げられと、よく知らないものだから乗っていけなかったが、それでも読んだつもりにさせてくれるような文章に助けられる。感染と衛生との対比は、少し疑問も感じたが、いまの情況においても考慮すべき大切な視点があると思った。衛生を重んじることは、一見合理的で正論のように見えるのだが、まるで社会というものの命を保持するために、個人を殺すような仕打ちに向かう危険性があるのではないか。その衛生に、人は苛立つ。政府が規制しようとすればするほど、反発を覚えるという場合がある。かといって感染は怖い。だが怖いながらも、自由とは何かという点を大切にしていく精神力をそこに有している。
新型コロナウイルスは、従来のペストやコレラのように、文学を呼ぶのだろうか。それには著者は否定的である。ペストやコレラのときには、「死」の姿が、ありありと人々に感じられた。直接の死者にも触れていたし、文学もそれをよく描いた。しかし、新型コロナウイルスにおいては、死者は数値になり、どのように苦しむのかという「死」の姿は、明らかにされない。これだけ情報が伝わっていても、情報化してはならないという暗黙の了解があるためかもしれないが、人々は勝手に自分の思い込んだイメージを、さもこのウイルスについての情況にも当てはまるようなものとして、知ったような顔で話しているばかりなのである。だからかつての思い込みを言葉にしているだけであって、かつて世界をペストなどが変えたようには、このコロナウイルスは世界を変えることはできない、というのである。都合良く「ポストコロナ」の考えが飛び交うが、それも思い込みに過ぎないかもしれない。だが、奇妙なことにそれを信仰している。
著者はここのところに、一番力強く、楔を打ち込んでいるのだと私は思う。この点は、大いに賛同の意思を示したい。
本書の題の意味は、多分「あとがき」で納得するだろう。そして、哲学と文学は希望を与えるだろうという展望を見せてくれる。著者はその新しい道の、パイオニアであるような仕事をしてくれたように思う。各章毎の豊富な参考文献が、その重みを伝えている。そして私たち読者に、たくさんの味わうべき作品を、紹介してくれている。好著である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
