
【夜はなにいろ】浅倉透の感想
感覚と純粋

浅倉透の思考は、感覚と純粋のあいだでおこなわれる。色が見える人間と、色が見えない天使のあいだ。経験と形式のあいだといってもよい。
非感覚の世界に属する天使が、感覚世界を見下ろしている。映画『ベルリン・天使の詩』の冒頭、開いた目のクローズアップが挟まれる。天使のまなざしを表すその印象深いショットに対応するように、【夜はなにいろ】では、カメラレンズのクロースアップの画面がなんども挿入される。
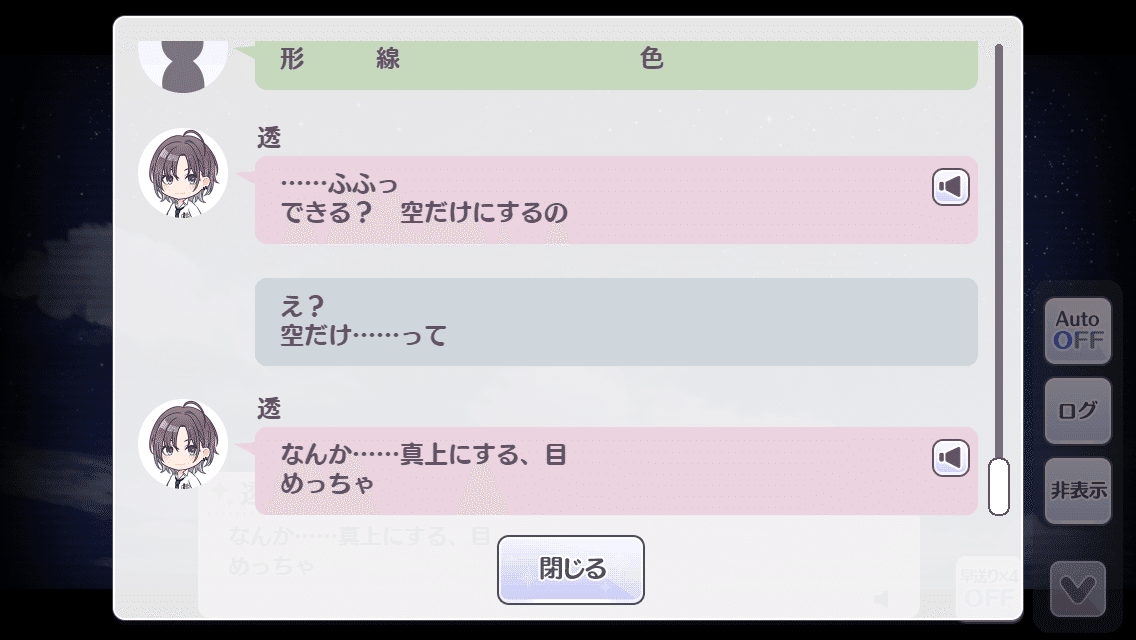
さて、『夜の器官としての僕ら』での「空だけにする」という透の試みは何を意味するのか。浅倉は、視界に夜空以外のものや鼻と前髪を入れない遊びをして、自分の肉体から束の間 逃れようとする。黒一色の夜空で視界のすべてを覆うことは、不完全な地上の世界のうちで純粋なモノクロの景色を手に入れるすべのひとつだったはずだ。しかし、浅倉は躓いてしまう。その目が純粋なカメラになることは不可能だった。浅倉の目は肉体的な器官でしかありえなかったのだ。
プロデューサーの目もまたひとつの感覚的な器官であった。浅倉が躓くのを前にして、プロデューサーは黒い空と白い息が覆っていると感じられた夜に、感覚的な赤色を見出したからだ。ハートのシールの赤、人間の生を象徴する血の色。この出来事がこのコミュのエッセンスだと言える。白黒映画の画面の「色」や、雪の「味」の記憶が、生の実感のもとで一つに結ばれた。
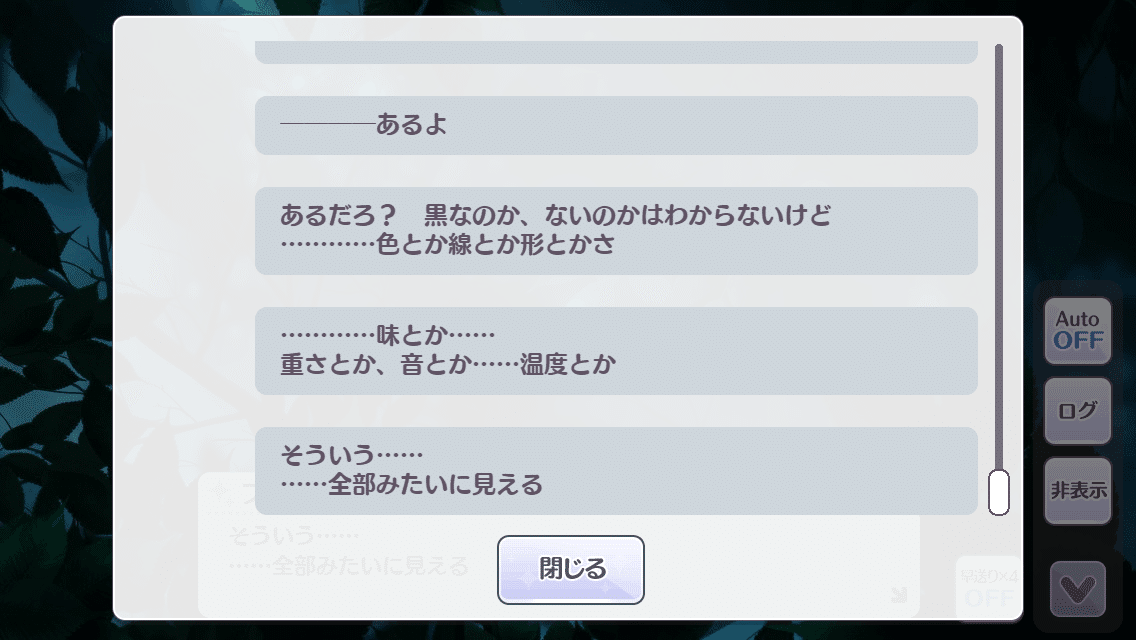
この出来事に裏打ちされてこそ、『ある』におけるやりとりにてプロデューサーの言葉が可能になったのだろう。浅倉は問いかける。黒は黒があることなのか、何もないことなのか。それに対して、プロデューサーはあることとないことも似ているという境地まで行きつく。そのくぐもった声から毛布をかぶったと思われる浅倉は「……じゃ、私は?」「黒?ない?」と問う。プロデューサーは、これまでの記憶を想起することで、色、線、形、味、重さ、音、温度とかの全部みたいに見える、透は「ある」のだと答える。
『世界封切り』で浅倉が倉庫で再現しようとした「映画館」は人間世界において「暗やみ」に包まれるありがたい場所のひとつであり、『夜の器官として僕ら』での夜空もその純粋な黒色で視界を埋め尽くし、『ある』で事務所の灯りを消して毛布を被る浅倉は黒色のなかに溶け込むのであった。このあとに続く存在にまつわる二人の問答を聞くと、光のもとの立ち現れにではなく、すべてを包む夜のうちに存在を見出す現象学者への連想に誘われもするが、これという意味づけは避けよう。ただ、【夜はなにいろ】の生命の物語が純粋さを象徴する暗闇のなかで進んでいたことを確認するだけにとどめたい。
落下する子ども
「元ネタ」に飛びついて【夜はなにいろ】と『ベルリン・天使の詩』とをばかまじめに突き合せたとき、何を言えるのか。それは次のようなものではないだろうか。
天使はアイドルにはなりえず、人間だけがアイドルになることができる。このことを落下という観点から考えてみよう。アイドルは落下しうるゆえにアイドルであるのだ。
『ベルリン・天使の詩』をもっぱらシャニマスのことを念頭に置きながら見たときに興味深いのは、いわば天使はスペクタクルをなしえないことが描かれているところだ。それはなぜかといえば、端的に人間の目から天使の姿は見えないからという理由に尽きるのだが、むしろその単純さは反対に、アイドルは「見られる」存在である、といういささか手垢のついた命題をあらためて新鮮に理解させてくれる。
この映画のなかには二つのショーのシーンがある。サーカスでの空中ブランコのシーンと、ロックバンドのライブ会場のシーンだ。
主人公の天使・ダミエルは、一人の人間に心を寄せる。解散間際のサーカス団の一員、ブランコ乗り・マリオン。ダミエルは、マリオンの最後の空中ブランコのパフォーマンスを見とどける。このとき、ダミエルは、マリオンがブランコから「落ちて」しまうのではないかと気が気でない。彼女の腕は震えていて、あわやその手を放してしまいそうな瞬間がある。
ダミエルと観客が「落下」の予感に苛まれるのは、この空中ブランコのシーン以前に、いくつかの「落下」のシーンが配置されているからだ。スタントマンがスタジオセットの高所から緩衝マットへと落ちていくシーンと、高層ビルの屋上からイヤホンをつけた若い男が身を投げるシーンだ。安全な落下と致命的な落下を、すでに観客は見ているのだ。この二つの可能性のあいだの宙づりを味わいながら、人の行いに干渉するすべをもたない天使は空中ブランコにつかまるマリオンを仰ぎ見るしかない。
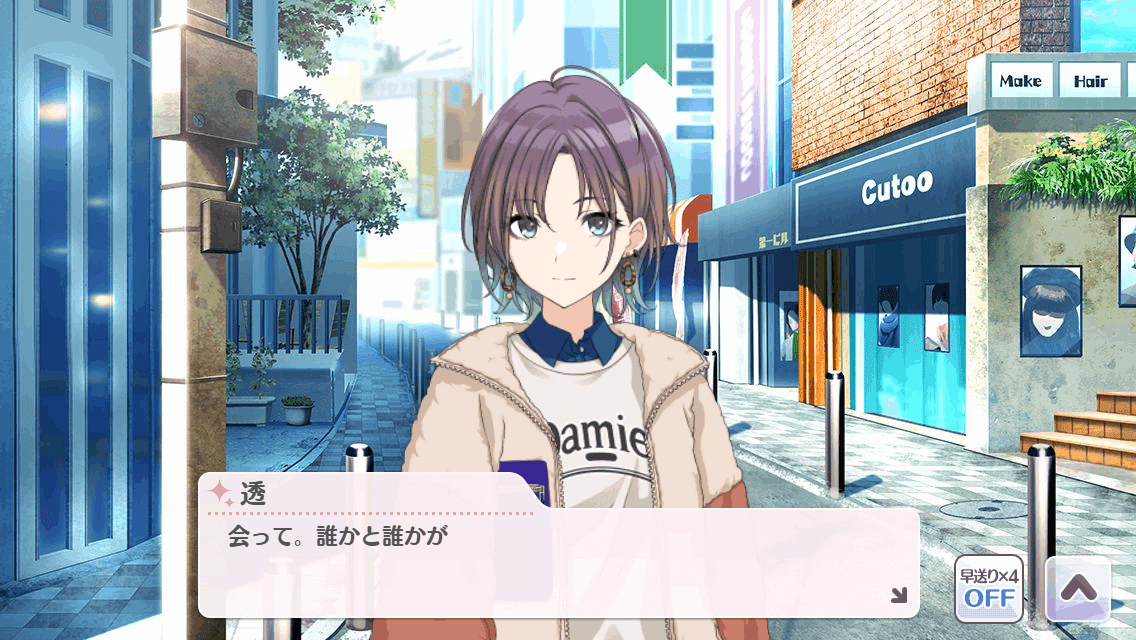
さて、ダミエルとマリオンの恋はライブ会場で実を結ぶ。ダミエルは、天使であることをやめ、人間の生を手に入れてマリオンに会いに行ったのだ。このとき二人は、ともにバンドライブの観客である。二人が言葉を交わすとき、画面は二人の顔を真正面でとらえたクロースアップの切り返しになる。もはや天使として人間を見下ろしたり、観客としてステージの上の演者を見上げることはない。視線の高さが同じになったのだ。
『いろする』でのプロデューサーと浅倉の待ち合わせはこの出会いに呼応する。プロデューサーが街のなかに浅倉の姿をみとめて「モノクロの画面に色がつ」き、浅倉が「誰かと誰かが」会うシーンを思い出す。天使のなかに人間くさいリビドーが表れはじめ、二人はロマンスへと向かうかのようだ。
もちろんと言うべきか、プロデューサーと浅倉にそのようなロマンスは起きない。問題は落下だ。映画のなかでもっとも強烈な落下のシーンは、天使カシエルの落下である。若い男が投身自殺するのを間近で見ていた天使カシエルは、そのあと男にならって戦勝記念塔のうえから身を投げてしまう。しかし、天使であるから落下にはならない。ただ、ベルリンの街頭と人と戦争などの怒涛のイメージを浴びるように見るだけだ。天使の落下は達成されず、見ることへとずらされてしまう。
高所からの落下。【国道沿いに、億光年】での落下の危険と庇護のあいだの緊張関係、【つづく、】のイメージを想起してもよいだろう。浅倉透もまた高いところにいる人間にほかならない。つまり「てっぺん」あるいは頂点捕食者の地位へと昇ろうとしている人だ。捕食と被食はもっぱら人間の世界に属するものであって、天使は何も食べなければ食べられることもない。天使はてっぺんから落ちる可能性が皆無だ。
姿を見せず、翼(!)をもった落下とは無縁の天使が、飾りの翼を背負い、あるいは翼をもたずに落下の可能性に曝される空中ブランコ乗りを仰ぎ見る姿。シャイニーカラーズと照らし合わせながら『ベルリン・天使の詩』を見たときに記憶に残るのはこのイメージだ。もちろん、赤色を見出したプロデューサーは天使ではないのではあるが。ただ、アイドルが視線を勝ち得るのは、アイドルが落下するかもしれないからだとしたら?
*
浅倉透の置かれた環境の厳しさは、これまでのコミュでも描かれてきた。その厳しさが、新たな側面から照らされたように感じる。もちろん、厳しい環境のなかで浅倉はなおも「強い」。たとえば『いろする』で、浅倉は、映画のなかの天使の目を見つめ返すシーンを覚えている。
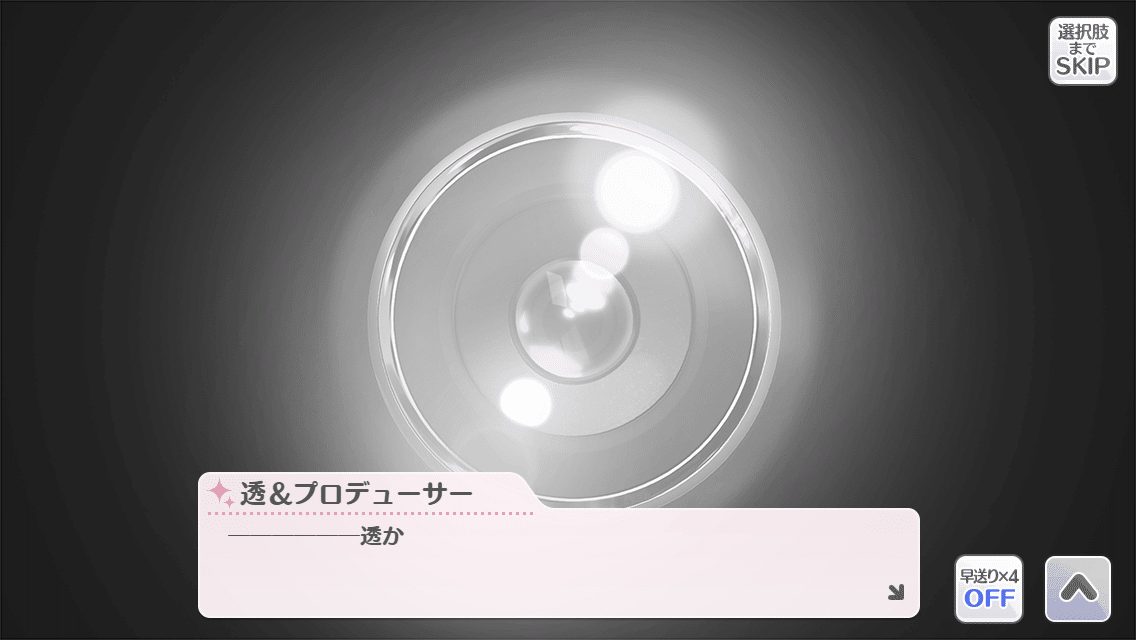
音声では「それで、見つめ返す」と台詞が重ねられている
『ベルリン・天使の詩』に登場する天使は、ふつう地上の人にはその姿が見えない。しかし子供だけは時折その存在を察知して、じっと天使のいるであろう方向を見つめる。浅倉もまた、ビルのうえにいる天使をさらに見つめ返す感触を覚える。ここに浅倉の変わらぬ強さを安心して見ることができるだろう。
(しかし、このとき浅倉は子供の立場にいるのだ。浅倉透がわれわれの前に立ち、われわれを見返す以上、彼女は子供でしかありえないのではないか?
「大人としての彼ら[=天使]はあらゆる経験を経ることができますが、唯一できないのが幼年時代を持つことなのです」と、ヴィム・ヴェンダースは言う。天使が幼年時代をもたない存在であるのとは反対に、少なくともわれわれが知ることのできる浅倉透は、幼年時代しかもたないのではないか?)
引用:『天使のまなざし』フィルムアート社、280頁
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
