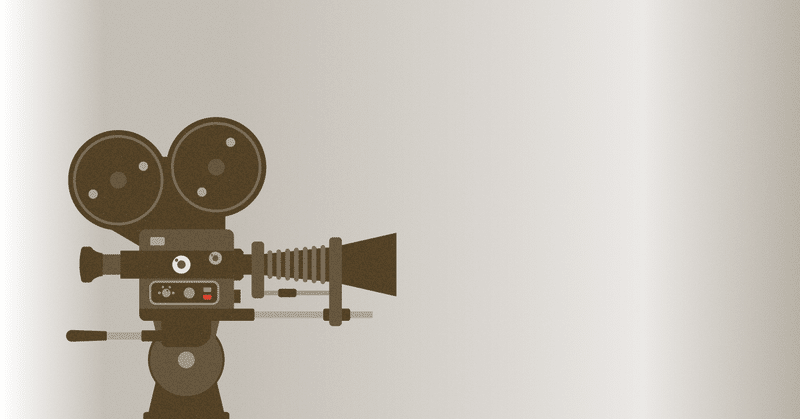
『祇園囃子』:1953、日本
祇園南側四部に暮らす芸妓の美代春の家を、彼女に入れ上げて勘当になった若旦那の小川が訪れていた。美代春は、三ヶ月もお茶屋の支払いを溜めながら未練たらしく遊びに来た小川を批判した。
小川は「僕は君と結婚するつもりだ」と言うが、美代春は「私は結婚する気なんか、あらしまへん」と冷たく告げた。腹を立てた小川は捨て台詞を吐くと、美代春の家を荒々しく出て行った。
小川を見送った男衆の助次郎は、外に16歳の娘・栄子がいるのに気付いた。栄子は、美代春がひいきにしてもらった元芸妓の娘である。
栄子は美代春に、母が亡くなってから伯父に嫌なことばかり言われることを話した。そこで舞妓になろうと考え、家を飛び出してきたのだという。栄子の母を水揚げしたのはメリヤス問屋の沢本だが、商売に失敗して落ちぶれ、葬儀にも顔を出さなかった。
男衆の幸吉は沢本の元へ使いに行き、栄子の保証人になるよう求めた。しかし中風で右手に麻痺が残る沢本は、「自分のことで精一杯だ」と断った。
保証人が無いと、妹分として引き取ることは難しい。しかし栄子が「どんな苦労でも辛抱します」と言うので、美代春は彼女を舞妓として仕込むことに決めた。栄子は美代春の家で家事をしながら、女紅場に通って太鼓や踊り、生け花などを学んだ。
栄子が修業を始めて1年が経とうとする頃、美代春はお茶屋「よし君」の女将・お君に「そろそろ座敷に出してみたい」と申し出た。お君は承知するが、「衣装は立派にせなイカン」と注文を付けた。立派な着物でなければ、良い座敷には出られないのだ。
「出すからには、出来る限りのことはしてあげたい」と考える美代春だが、そのためには30万円もの大金が必要だった。美代春が工面を頼むと、お君は自分もそんな大金は持っていないと告げた上で、何とか手はずを付けることを約束した。
見世出しの日が訪れ、栄子は髪を整えてもらい、着物に着替えた。彼女は美代栄という名前を貰い、美代春と共にお茶屋の挨拶回りに出向いた。よし君を訪れると、お君は楠田車輛の御曹司・楠田が来ていることを美代春に告げた。
楠田は重役の佐伯と共に、役所の課長を務める神崎を接待していた。美代春は栄子を連れて座敷に出向いた。楠田は栄子に、神崎は美代春に目を付けた。
女紅場での稽古の帰り、栄子は仲間の舞妓から「旦那を取るって、何のことや知ってる?一人前の女になることや。ウチ、旦那はん取らなアカンねん」と打ち明けられた。相手が62歳の老人だと知り、栄子は「断ったらエエやないの」と言う。
しかし仲間の舞妓は「そんなわけにはいかへん。お母ちゃんに言われたんやもん」と告げた。嫌だと思っても、それが祇園の仕来たりなのだ。
美代春はお君から、楠田が栄子の旦那になりたがっていることを聞かされた。「まだ座敷に出たばかりなのに」と美代春が困惑すると、お君は「そんなこと言うてたら、時代に乗り遅れるよ」と言い、見世出しの衣装代が楠田から出ていることを明かした。さらに彼女は「大体な、旦那も持たんと妹を引いてるのが間違いや。一人で無理せんと、誰かのお世話になったらどうや」と勧めた。
後日、美代春と栄子は楠田の指名を受け、よし君に赴いた。美代春はお君から、「15日の藤間の会、東京に行くつもりやったら楠田さんが連れて行ってもいいって言ってはる」と告げられた。美代春は離れの座敷に呼ばれ、行くと神崎だけがいた。
栄子はお君に、楠田が旦那になりたがっていることを聞かされた。栄子は「よう見てから、お返事します」と勝ち気な態度で言うと、楠田が待つ2階の座敷に向かった。楠田から藤間の会へ一緒に行こうと誘われ、栄子は喜んで承諾した。
美代春と栄子が東京行きの寝台列車に乗っていると、沢本が現れた。途端に栄子は不機嫌になり、コンパートメントから出て行った。沢本は美代春に、借金取りに追われて逃げるように京都を出て来たことを話した。
美代春と栄子は踊りの会を堪能し、旅館に戻った。栄子は楠田から、銀座へ連れて行ってもらうことになっていた。楠田は神崎に電話を掛け、旅館へ読んだ。
楠田は美代春に、「神崎さんと今夜、付き合ってくれ」と持ち掛けた。困惑して断ろうとする美代春だが、座敷で神崎と2人きりにされてしまう。楠田は栄子を抱き寄せ、強引に関係を持とうとする。しかし栄子は激しく抵抗し、大声で悲鳴を上げた。
その声を聞いた美代春が部屋に行くと、栄子は楠田の唇を噛んで怪我を負わせていた。楠田はしばらく入院することになった。
見舞いに訪れたお君に、楠田は佐伯を通じ、栄子の抵抗よりも美代春が神崎を袖にしたことに激怒している旨を伝えた。そのせいで神崎から8千万円の発注の返事が届かず、会社の経営が危うくなっていたのだ。
お君は「何とかして話をまとめますから」と約束し、よし君に美代春を呼び付けた。美代春は栄子のことで詫びを入れるが、お君は「アンタも悪い」と注意した。
お君は美代春に、「神崎さんの顔を立ててくれるんやったら、今までのことは水に流してもらうよう頼む」と告げる。しかし美代春は、「好きでもない人と、そう簡単に」と難色を示した。
お君は「それはな、お金のある人間の言うことやで。お金も無いのに生意気なこと言わんとき」と叱り付け、「ほんなら貸した30万円は返せるんか」と尋ねた。美代春が「何とかします」と答えると、お君は「その決着が付くまで、ウチには出入りせんといて」と言う。
お君は祇園で顔が広いため、他のお茶屋も彼女に遠慮して、美代春と栄子を座敷に呼ばないようになった。仕事が無くなって落ちぶれた美代春の家に、小川が芸妓2人を連れて現れた。商売が繁盛している彼は、美代春に嫌味な態度を取った。
小川が去った後、沢本が訪れた。東京でのアテが外れた彼は、美代春に金を無心した。身勝手な要求に腹を立てた美代春だが、指輪と簪、時計を渡した。
佐伯はお君を訪ね、木屋町の茶屋「中西」まで神崎を連れて来てきたことを告げた。佐伯はお君に、美代春を呼ぶよう求めた。栄子はお君を訪ねて詫びを入れ、楠田の元へ連れて行ってほしいと願い出た。
お君からの電話でそのことを知った美代春は、慌てて「困ります、すぐ美代栄を帰して下さい」と頼む。お君は神崎が中西に来ていることを告げ、それについて話があるから出てくるよう持ち掛けた。美代春は悩んだ挙句、「中西へ行きますから、美代栄は帰して下さい」と返事をした…。
監督は溝口健二、原作は川口松太郎、脚本は依田義賢、企画は辻久一、撮影は宮川一夫、撮影助手は田中省三、編集は宮田味津三、録音は大谷巌、照明は岡本健一、美術は小池一美、音楽は齋藤一郎、和楽は望月太明吉、筝曲は萩原正吟。
出演は木暮実千代、若尾文子、河津清三郎(第一協団)、進藤英太郎、菅井一郎(第一協団)、田中春男(新東宝)、小柴幹治、石原須磨男、志賀廼家弁慶、伊達三郎、浪花千榮子、毛利菊枝、岩田正、牧竜介、大美輝子、橘公子、柳恵美子、小松みどり、小林加奈枝、小柳圭子、前田和子、種井信子、三田登喜子、上田徳子、不二輝子、久松京子ら。
―――――――――
川口松太郎の小説を基に、『雨月物語』の溝口健二が監督を務めた作品。先に映画の企画が決まっており、それに合わせて、製作開始前に「オール読物」で川口の小説版が発表されている。
美代春を木暮実千代、栄子を若尾文子、楠田を河津清三郎、沢本を進藤英太郎、佐伯を菅井一郎、小川を田中春男、神崎を小柴幹治、幸吉を石原須磨男、助次郎を志賀廼家弁慶が演じている。
見世出しの日、楠田に促されて酒を飲んだ栄子は、泥酔して家に戻る。「飲まな座敷が務めらんと思って」と言うと、美代春が「アンタはアプレや」と告げる。すると栄子は「お姉ちゃんはアヴァン・ゲールや」と言い返す。
アプレとは無責任で無軌道な若者を示す言葉で、アヴァン・ゲールとは昔からの価値観を守ろうとする面々のこと。いずれも第二次世界大戦後に流行した言葉だ。
「姉貴分と妹分の芸者が辛い目に遭う話」という大枠は、ちょっと1936年の『祇園の姉妹』を連想させる(『祇園の姉妹』は本物の姉妹だったが)。
ちなみに本作品で、小川に「結婚するというのは嘘だったのか」と言われた美代春が、「芸者の嘘は、嘘にならへんの。商売の駆け引きや」と言うシーンがあるが、それと同じようなセリフを、溝口監督は『祇園の姉妹』でも言わせていた(脚本は同じ依田義賢)。その芸妓のルールを、監督は気に入っていたようだ。
美代春は神崎と寝るよう要求され、最終的に承諾せざるを得なくなっているが、祇園の芸妓が全て愛人のような商売をしていたわけではない。かつての祇園は甲部と乙部に分けられており、「格上は甲部、格下が乙部」という住み分けがあった。そして乙部には娼妓(金で体を売る芸妓)が多く暮らしていた。
この映画で描かれているのは、たぶん乙部なんだろう。溝口監督はステータスの高い人間が遊びに行くような場所よりも、庶民的な乙部を好んだらしい。
溝口監督では、ロクでもない男ばかりが登場し、女性が辛い目に遭わされるというパターンが多い。この映画でも、登場する男は総じてロクデナシだ。楠田は栄子を手篭めにしようとするし、沢本は娘を見捨てておきながら都合のいい時だけ利用する。佐伯は取引のために美代春の肉体接待を要求し、神崎は取引をエサにして美代春を差し出させる。
男だけでなく、美代春と栄子にとっては、浪花千栄子演じるお君も自分たちを苛める相手だ。彼女のせいで全てのお茶屋に出入り禁止となり、落ちぶれてしまう。
女紅場の教師は生徒たちに、「祇園の舞妓は日本の誇る生きた芸術作品だから、日本の美しさの象徴としての誇りと自尊心を持ちなさい」と説く。だが、そこからは、舞妓や芸妓たちを取り囲む醜い現実、哀れな現実が描かれていくことになる。
実際の祇園の世界は(この映画で描かれる限り)、そんなに美しいものではない。女たちの誇りや自尊心など、男や金の前では簡単に打ち砕かれてしまう。
見世出しの後日、女紅場の教師は生徒たちに「憲法の定めた基本的人権によって、あなた方の自由は保証されている」と語る。栄子が「座敷でお客さんが強引に口説いたら、それを無視したことになるんですか」と訊くと、「理論的には、そうなります」と答える。
しかし法律や理論など、お茶屋では通用しない。そんなものより、男の理屈や金の力の方が、遥かに強い世界なのだ。
ラスト近く、栄子は「みんな嘘つきばっかりや。京都の名物も、世界の名物も、みんな嘘や。お金で買われるのが上手な人が出世して、下手なのがウチみたいにボイコットされるんやないか」と喚き、そんな世界なら辞めると言い出す。しかし美代春は彼女を諌め、「そんな生一本では通らないのが芸妓の世界なのである」と説明する。
所詮、売春モドキの世界なのである。
ただし前述したように、祇園の全てがそうだったわけではないので、『祇園の姉妹』の時と同様、溝口監督は祇園の関係者から抗議されたらしい。
ただ、これまでに複数の溝口作品(具体的には7本)を観賞して感覚が麻痺してしまったのか、「意外に優しいな」という印象を受けた。溝口監督のことだから、もっとサディスティックに美代春と栄子を苛めるんじゃないかと思ったのだ。
しかし栄子は大して不幸な目に遭遇していないし、美代春にしても「他に好きな男がいて、それでも神埼と寝なきゃいけない」というわけでもない。他の作品と比べるとクランクアップが早かったらしいし、「軽い小品だから」と、溝口監督は肩の力を抜いて撮ったのかもしれない。
(観賞日:2010年7月30日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
