
異常を排除した通常という異常
善と悪は表裏一体である。
いや、順番的には、悪が先なのだろう。悪いものがどういうものなのかが明らかになることではじめて、結果として良いものとはどういうものかを表せるようになる。『ドラゴンボール』でピッコロ大魔王が切り離されてようやく神様をつくることができたのと同じことだ。
人は、たいてい愚痴や不満をいうほうが、何かを褒めたり評価したりするよりも、やりやすい。それも同じことなのだろう。愚痴や不満はほっといてもどんどん出てくるが、で、どうなるといいの?と訊ねると案外答えはない。
褒めたり評価したりできる場合もたいていはすでに褒め方や評価の仕方がわかってるときだけで、それまで誰かが褒めたり評価したりしたことがない点の良さを新たに見つけて褒めたり評価することはむずかしい。逆に、悪いものであれば初見でも非難したり嫌がったりできるというのに。
悪いもの、汚いもの、いかがわしいもの、病んだもの、自分と考え方や価値観の異なるものを、外へと追いだす。その追いだし行為によって、善や正しさははじめて形を成す。消去法的に。
社会を良くするだとか、改善だとか、イノベーションだとか、言っても同じこと。異物を排除することで、それらは成り立つ。だから、それらが本当に手放しで立派なことだと言えるといえば、かなりあやしい。
なのに、世の中の風潮は、そうした方向での活動を手放しで称賛する傾向があるのだから、相当危険なにおいがする。それらがかつての魔女狩りとさほど変わらないのだということに気づく必要があるはずだ。
話の本筋と脱線と
ここ最近、道化やスケープゴートの話を書くことが多いが、そうした境界に位置する存在の犠牲の上でしか、「良いもの」は成り立たない。良いものは何かを形づくることはできない。少なくとも良いものは道化とタッグを組んで現れる必要がある。
山口昌男さんが『道化の民俗学』で、道化とヒーローの関係について、次のように書いているのも、そうした側面を思い浮かべながら読むと意味を取りやすい。
日常世界の規範の肯定的な部分を延長して投射されたヒーローは、それゆえに、日常世界的アイデンティティの前提たる一貫性および禁制という制約のなかで(時によってはその外延に接近するとは言え)、物語またはプロットの時間を先に進めなければならない。従ってヒーローの開示する世界は限られている。それに対して「道化=からみ役」は日常世界の規範としての禁制から解放されている。彼には一貫性といったアイデンティティの証しは要求されていない。どのような状況にも高い可塑性をもって自由に対応できる。従ってヒーローならば対応できないような状況、通り過ごすような状況に対しても、感受性を働かしてそれをプロットの中に組織する。
道化とヒーローが登場する舞台や物語では、ヒーローの側はストーリーを前へ前へと展開する動きをするが、道化の方の動きはといえば、むしろ、ストーリーとは無関係な動きをしたり話をすることで、物語の流れを脱線させる。現代のテレビドラマなどに登場するコメディエンヌたちの役割も同じだろう。

『道化と笏杖』でウィリアム・ウィルフォードがこう書いている通りだ。
喜劇的人物がフールな力を帯び過ぎてくると、ちょうどフォールスタッフがシェイクスピア史劇から追放されたように、彼は完全に追放されねばならないのである。こうして17世期の終りにかけて、コンメーディア・デラルテのクラウン役となっていたハーレクィンは、劇本体から分離されて、実に様々な芝居に挿入される幕間狂言に姿を現わすようになっていた。畢竟、意味ある行為の表現としてのドラマはフールのものではなく役者のものなのである。
しかし、その本筋とは外れた領域を道化が見せることにより、話の本筋が消去法的により浮かび上がってきたりもする。しかも、本筋しかない語りより、はるかに道化による脱線があったほうが物語そのものが豊かになる。
異常を排除した通常という異常
山口昌男さんはこう書いている。
このような言い方は、なかなか理解されないとは思うのだが、結局私の言いたいのは、日常世界の道徳という基準をしばらく停止してみると、世界の活力の源泉または光源は、むしろ「周辺」の側にあるという点なのである。人が悪の魅力と言う場合に、そういった視点は暗黙の前提となっていると思われるし、ルドルフ・オットーのごとき宗教学者も「聖なるもの」をそういった「境界」性として考えているように思われる。
いや、これは理解できる。
道化が、ああでもない、こうでもないとDon'tの例を挙げてくれるからこそ、何がDoなのかが明確になる。ヒーローと道化の関係は、Do/Don'tの対比を明らかにするのだが、ここでも順番を間違えてはいけない。
異常な非日常があることで正常な日常が可能になるのだ。
逆ではない。間違えてはいけない。
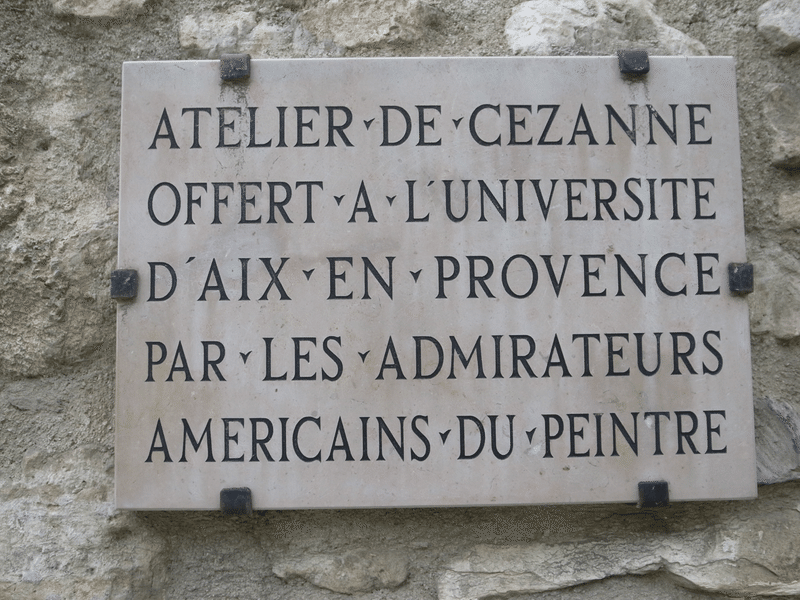
それと同じことだ。善でないものを描けるからこそ、善についても論じることができる。
だから、そのことに気づかぬまま、悪を最初から排除して善のみを追いかけようとするのは、本来であれば異常とさえる言えるはずだ。
異常を排除した通常という異常。
しかし、いまの非寛容な社会では、本来は社会の健全な循環に必要悪的に存在した道化的なものの存在すら許されなくなってしまっている。道化的ないたずら、道化的な両義性を許容する余裕を社会が失ってしまっている。非日常時代が日常を作るというのに、それを排除すれば日常がどんどんおかしなものになるという理屈がこんなにもわからなくなってしまったのは何故だろう。
「異形の者」が家を経めぐって、グロテスクな形姿かつくり声で、関係を確立する。それで暴力的な身振り言語によって聖なる力を導入する。このような「よりしろ」に物を施すというのは物に添えて、日常の生活では好ましくない災悪を託して持ち去ってもらうことを意味する。
ハロウィンのおばけや秋田のナマハゲのように、祭の際に社会へと侵入して、ちょっとした悪事をはたらき、その後に追放を通されるという流れのなかで、裡にたまっていた悪いものを彼らといっしょに社会の境界の外に追いだすという、定期的な浄化の社会浄化の機能を失ってしまったがゆえに内部がどんどん澱んでいくしかない。そして、外部に流すことのできなくなった悪いものを、互いに蔑み、文句を言うことだけで、澱みを解消するどころか、それをどんどん増やしていく方向でしかなくなれば、そりゃ持続可能性などなくなって当然だろう。
バタイユの低級唯物論
イヴ=アラン・ボワ+ロザリンド・E・クラウスという人の美術評論家が同名の展覧会にあわせて著した『アンフォルム 無形なものの辞典』という本では、ジョルジュ・バタイユの思想から、いくつかの概念をコンセプトとして借りていてタイトルにもなっている「アンフォルム」のほか、以下の引用にもかかわる「低級唯物論」というコンセプトもバタイユ経由で展開されている。
「異物(異質なもの)という観念を用いれば、汚物(精液、経血、尿、便)と、聖なるもの、神的なもの、あるいは驚異的なものと見なされ得るすべてとが、主観的に見れば基本的に同一である、と示すことが可能になる」。神が聖なるものであるのは、糞が聖なるものであるのと同じ根拠によるにすぎない。
この汚物と聖なるものが区別なく同一視された状態が、道化とヒーローがまだ未分化な状態だということになる。動物と人間、自然と文化が未分化な混沌の状態である。
この低級唯物論という考え方は、今年の最初にも紹介したジョルジュ・バタイユの『ドキュマン』での小論「低級唯物論とグノーシス」で表されているものだ。バタイユはこの低級唯物論という考えを、初期キリスト教の異端思想グノーシス主義における「物質」の捉え方を参照しながら、展開している。

その一文を引いてみよう。
実際のところ、物質を自律的な永遠の存在をもつ積極的原理と考えている点を、グノーシスの中心思想とみなすことができる。その存在は暗闇の存在であり(それは光の不在ではなく、その不在によって露わとなる怪物的な執政官たちであろう)、悪の存在である(それは善の不在ではなく、創造行為であろう)。物質についてのこの考え方は、古代ギリシア精神の原理そのものと完全に相いれないものであった。後者は根本的に一元論的であり、物質と悪をおもに高級な原理からの頽廃として捉える傾向にあった。おぞましくも愚かしいわれわれの騒乱が生じる大地の創造を、恐ろしいまったく不法な原理に帰することは、ギリシア的な知的体系の観点では、吐き気を催すような許しがたい悲観論、是が非でも確立して全面的に明らかにすべきことのまさに反対物を、明らかに意味していた。
この引用中に語られるとおり、グノーシス主義が展開された3-4世紀の地中海世界を代表する、ギリシアの思想においては、プラトンのイデアを想起するとわかるとおり、物質的なものを悪同様に、低級なものと考える傾向があった。
プラトンは芸術も含めて現実世界で物象化されたものを低級にわけることで、理想的なイデアという高級なものを導いているという点では、ここまで述べてきたような善悪の表裏一体のしくみを理解した上でそれを行なっていることがわかる。
プラトンは、それらを低級に分類しても排除するつもりはなかったということは大事なポイントだろう。
絶対悪と悪の仮象としての道化
とはいえ、グノーシス主義が低級なものとして見出したものは、芸術のように人間の思想を物象化したものというより、さらにその背後に隠れた物そのものだ。
それは、後のカントなら人間には触れないものとした物自体であると言えるような、人間世界からはどこまでも遠く離れた場所に追いやられた低級な物だ。そうした物に、グノーシス主義もバタイユも、暗闇の存在、悪の存在として価値を見出しているのだ。
文中にあるとおり、このグノーシス主義やバタイユが低級唯物論で展開する絶対的な暗闇=悪は、光の不在でもないし、善の不在でもない。
だから道化のような境界線上にあるものではなく、境界の向こうで、人間の目には触れない悪そのもの、物自体である。悪そのものと悪の化身としての道化。この違いは見落とせない。
言い換えれば、人が道化とヒーローにタッグを組ませることで、境界の外に追いだしたいのは、この悪であり、その運び手こそが道化なのであって、彼自身は決して悪そのものではない。絶対的な暗闇すぎて人の目に触れない悪そのものを目に見える形でイミテーションの悪として表象する役割が道化やトリックスターなのだ。芸術の役割に近いということに気づくだろうか。
なのに、この悪の仮象的な存在である道化やトリックスターまで悪そのものといっしょくたにしてしまい、排除してしまうから、本当の悪を追いだす仕組みがなくなってしまう。
目に見えやすい仮象の悪をとにかく躍起になって外へと追いだして、目に見えにくい本当の悪が蔓延る環境をつくってしまうのだから厄介だ。「あなたの体は9割が細菌」が現実だというのに、過剰な清潔意識がなんでもかんでも殺菌して必要な微生物まで排除してしまって、病気に罹りやすくなったり身体に必要な機能を失ってしまっていることもその象徴的な出来事の1つだろう。
そして、それが現代の問題であることにもなかなか気づけない。
むしろ、それを何十年も前に気づいていたのがバタイユだったのだと思うと、考えさせられる。
絶対悪でも絶対善でもない
ふたたびウィルフォードの『道化と笏杖』から引く。
フールたちの未開性なり魔術は、しばしば彼を特徴づける他の性質同様、フールと動的な関係にあるノン・フールたちの態度と行動と相関的なものなのである。普通フールたちが未開、魔術的な存在として現われるのは、自分は合理的、現実的であると考え、少なくともそういうふうに見えるはずと考えているノン・フールたちとのコントラストに於いてなのである。何をもって「合理的」で「現実的」と言うかは勿論、何を「フーリッシュ」と言うか次第なのだが、ともかくそれらと「フーリッシュ」はコントラストの関係にある。こういうわけで、魔術的儀礼の重要な社会にはクラウンたちがいて、そうしたクラウンたちが魔術を行い時には、それはクラウンならざる僧侶、魔術師たちのもっと「合理的な」魔術とコントラストを形づくる――ここで「合理的な」というのは、その社会とその成員の生活の継続に不可欠と考えられている諸価値の構造に準拠している、というほどの意味である。
悪と善はセットで見ないといけない。コントラストが必要なのだ。
だから道化とヒーロー、フールとノン・フールの並置によるコントラストは欠かせないのだと思う。善と悪のコントラストだけでなく、合理的であることと未開であること、現実的であることと魔術的であること。
とはいえ、どちらにせよ、それは仮象なのだ。人間の理解のための像なのだ。
いずれも絶対悪でもないし絶対善でもない。仮象なのだからそこまで断罪する必要もないし、褒め称える必要もない。物自体ではなく、人間が触れられる物のイメージと同じなのだ。
つまり、そう見えているだけだという面がある。
すくなくとも、悪と見るにしても善と見るにしても、そう見ている人自身の参与がある。見られる側とみる側の両方の関係において、悪だとか善だとかが決まっているのに過ぎない。絶対ではなく、相対なのだ。
そもそも良いと思うものだって、完全に良さだけしかないものなんてない。だって、相対的な善悪しか、人間には触れることができないのだから。
良いと自分で信じているものだって、自分ではそれに気づくことができなくても、他人から見たら問題はたくさん見つかっておかしくない。
もし、それで他人がその問題点を罵倒しはじめたら、どうだろう?
価値観の違いで喧嘩になる。
まったく何のための戦いかわからない揉め事がそこからは発生する。
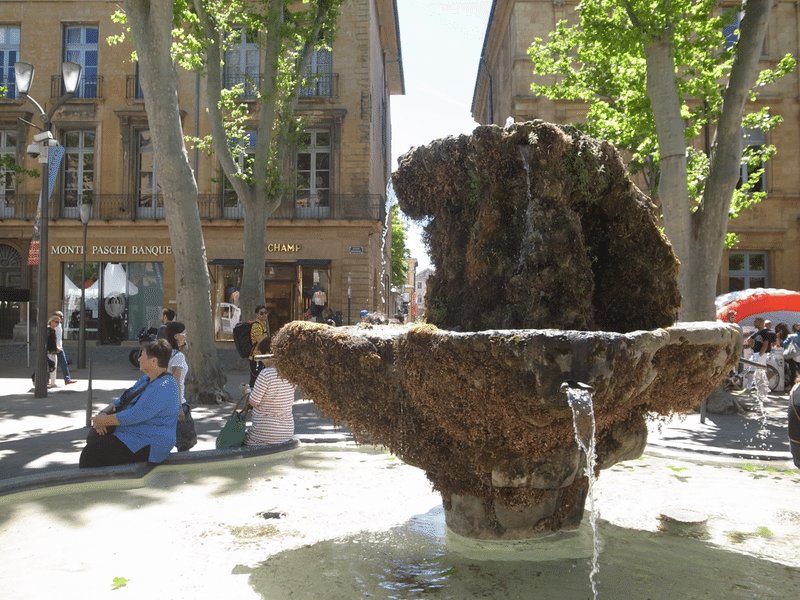
なのに、ちょっとでも気に入らなければ自分から見て悪だという以上の絶対悪であるかのように激しく文句を言い、それを完全に息の根が止まるまで罵倒してしまうケースは少なくないだろう。ほんのささいな過ちですら、2度と戻ってこれないくらい遠い外の世界へと追放する。あんまりである。
そんな不寛容な世の中では、とにかく普通に生きていくための免疫すら失われていく。抗生物質が腸内の必要な微生物の生きる環境も破壊して、宿主の体調を悪くしてしまうことがあるように。
モートンのダーク・エコロジー
いまの世の中、とにかく良くしよう、便利にしよう、楽に生きられるようにしようとして、免疫が失われた状態がいまの持続可能性を欠いた環境なのではないだろうか。
ここで話は環境問題にもつながっていく。
「私たちは粘着性の汚物の中にいるというだけでなく、私たち自身が汚物なのだが、私たちはそこにひっつくやり方を見出すべきであり、思考をより汚いものにし、醜いものと一体化し、存在論ではなくてむしろ憑在論を実践すべきである」なんてことを書くティモシー・モートンが提唱するダーク・エコロジーという考え方が僕は大好きなのだが、そのモートンが『自然なきエコロジー』で、19世期末に書かれた小説『フランケンシュタイン』を参照しながら、昨日は外側にあったものが今日には内側になる、というとき、そこで想定されているのは道化やトリックスターなど現代においては境界の外へと追いやられた者たちの内側――といっても正確には内外の境界線上――への回帰だろう。
『フランケンシュタイン』が示す前兆は、ディープエコロジーの反対物である。なすべき課題は、不快で不活性で無意味なものを愛することである。エコロジカルな政治は、エコロジカルなものについての私たちの視野を、たえまなくそして容赦なく再設定しなくてはならない。昨日は「外側」であったものが今日には「内側」のものになるだろう。私たちは奇怪なものと同一化する。私たち自身が、ガラクタの小片と細片でみすぼらしくつくられている。もっとも倫理的な行為は、他者をまさにその人工性において愛することであって、その自然さや本来性を証明しようとすることではない。
バタイユが「低級唯物論」というコンセプトを掲げることで、その方向を指し示した、どこまでも暗い絶対的な暗闇がその存在をほのかに漂わせる、僕らのコンフォートゾーンの外側の世界が、次の日になれば内側に入り込んでくる、というそんな不快さも伴う提案をモートンはしているのだ。
「ダークエコロジーは、対象を理念的な形式へと消化するのを拒絶する、倒錯的で憂鬱な倫理である」と定義するモートンは、バタイユほどの絶対的な暗闇までは想定していないものの、フランケンシュタインレベルの化け物性は社会に必要だと考えている。
モートンは、そうした汚れを伴っているのが当然である自然からそれを取り除き、安全に消費可能なものに変えてしまったという容疑で19世期のロマン主義の罪を指摘する(「消費主義の誕生はロマン主義の時代と一致している」)。自然は殺菌消毒された真空パック状態で売られるようになった。そこにすこしでも微生物でも混入していたら、とたんにクレームの対象になるようなものに。
しかし、その自然の異質な加工が、いまなら遺伝子組み換え食品同様の、フランケンシュタイン的な怪物性を秘めていることを誰も気づかなかったりもするわけだ。異常である。
19世期のコレラの大流行
ところで、このロマン主義が流行した19世期といえば、イギリスで言えば、ヴィクトリア朝の時代とも重なっている。
ここで高山宏さんの『アリス狩り』からも引いてみたい。ここまで書いてきたことが、なぜ今語るべきことなのかのイメージができるのではないかと思う。そう思うので、いくつか続けて引用する。
公衆健康法が1848年に出て、医療も良くなり環境も清潔になってきて、事態は上向きになったものの、例えば1865年から翌年にかけての大コレラ禍の如く、時々には大流行もあり、そして何よりも過ぐる時代の病禍の残した原―記憶がヴィクトリア朝全体の感性と行動のパターンを決定していたのである。
1854年、ブロード・ストリート事件と呼ばれる、医学においては大事な出来事が起きている。
1854年の8月、ロンドンのブロード街周辺でコレラ患者が多量発生した。それまで空気感染するとされたコレラの感染原因を疑っていた医師のジョン・スノウは、患者発生状況の調査を行い、感染経路を追うことで、ある井戸が汚染源と推測した。その結果「汚染された井戸水を飲んでいる人は罹る」と結論。行政が問題の井戸を閉鎖することで流行の蔓延を防ぐことができた。疫学のはじまりだ。
しかし、こうした画期的な発見があったにもかかわらず、引用にあるとおり、1865年になってもかつての大禍の記憶から人々は右往左往し、疫学的な発見も役立たず、またもやコレラの大流行を引き起こしてしまう。つまり、19世期のなかばのこのコレラの大流行はそれまでの自体の流行とは意味が違ったのである。
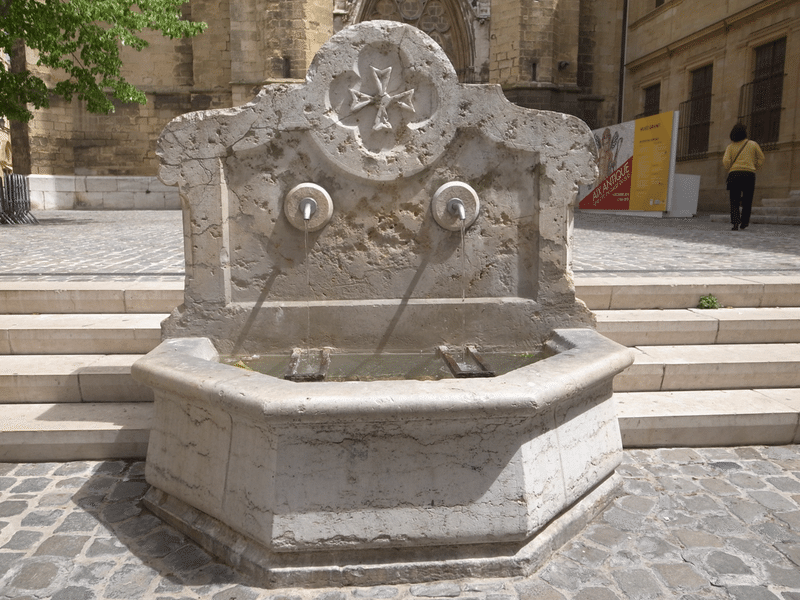
問題は病気そのものだけではなかったのだ。
19世期は大事なものをすでに失ってしまっていたのである。失われたものは道化的なさかさまの世界が展開されるカーニヴァルであり、宮廷道化とともにあった王政である。都市の風通しをよくしてくれていた境界的な祭りと存在の両方がともに失われていたのだ。
一方でこうして死と病が外に瀰漫しているのに、これを象徴的に祓うための社会的制度―祝祭―を世紀末は欠いていたのである。かくて死の意識との和解をめざさず、これをひたすら外のものとして拝することによって自立したのが、有名なヴィクトリア朝の室内崇拝であった。
生と死を自由に行き来することで、スケープゴートの役割を担って悪いものを外へと連れて行ってくれる道化はいない。悲しみも苦しみも癒してくれるものがないまま、都市の内側に残る。そうなれば人はもっと内へと逃げこむしかない。室内へ、そして、利他的な考えを捨てて利己的な個人の裡へと。
そんな引きこもり状態で、小さな窓から外を覗くヴィクトリア朝の時代の人々の楽しみ、心の癒しはなんだったのか?
女毒殺者マデリン・スミスの公判を見に大衆が集まった図がある。制度としての祝祭を失った大衆は、もっぱら裁判所と絞首台の周りに陰鬱な擬似・祝祭を繰り広げたのである。彼らは犯罪小説を渇望していた。「本を読むというヴィクトリア朝大衆の習慣そのものが、不変に興味のある話題としての殺人事件の存在によって明らかに助長された」というのだから、「文化」とは実に始末の悪いものではないか。
フランケンシュタインの話や吸血鬼ドラキュラの話が小説となって展開されるようになるのもこの時期だ。さらに殺人事件に光を当てるシャーロック・ホームズのシリーズを、コナン・ドイルが手がけるのも。
死が登場する、怪奇小説や推理小説が道化たちの生きる場所が失われたあと、あちらの世界とこちらのせかいをつなぐ境界の役割を担うようになったのだろう。
赦すことは、根本的にエコロジカルな行為である
ここまでみて、もう一度、モートンがフランケンシュタインと絡めて書いた文章の引用を見返そう。そこにはこう書かれていた。
私たちは奇怪なものと同一化する。私たち自身が、ガラクタの小片と細片でみすぼらしくつくられている。
人工と自然はフランケンシュタインの身体と同じようにいっしょくたになって分けようがない。どこが悪でどこが善なんてことなくいっしょくただ。「あなたの体の9割が細菌」であるように、私の身体もどこが自分でどこが細菌、どこがウイルスだなんて分けようがない。いや、空気と自分の身体だって境界近くではもはやあやふやだろう。
なのに、いったい何を隔離しようというのか、こんだけ善も悪も一心同体、いっしょくたのフランケンシュタイン的状態で日々生きている人々がいまさら何を避けようというのか。誰を罵倒し、何に文句を言い、どんな奴らを自分たちの手の届かないところへ追放しようというのか。なぜ、そんなにまで不寛容になる必要があるのたろう。
モートンは書く。
かくして赦すことは、根本的にエコロジカルな行為である。それは、エコロジカルななものにかんして確立された概念の全てを超えたところでエコロジーを再定義する行為であり、他者と徹底的に一緒にいようとする行為である。そして、ここにいること、つまりは文字通りこの地球において存在するということ(現-存在)は、赦す必要があるということをともなうが、それはつまり、あそこにいるなにものにも私たちには責任があり、究極的には「私たちの落度」であると考えるのと同じくらいに徹底的に考えてみることを意味している。
なぜ赦すことができないのか。
なぜ私たちの落度でもあると認められないのか。
ちゃんと自分たちの責任を引き受ける必要がある。
かつての道化たちのように。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
