
都市の祝祭
「自然は自分自身の美しさに徹底して無関心だ。ここには人間を途方に暮れさせてしまうような何かがある」。
畠山直哉さんの撮る東京の地下を流れる川の暗渠の写真に写る、ドブネズミの糞の上に生えた「溶かしたガラスを空中に何度も引き伸ばしたようた細い糸状のカビ」が光を浴びてキラキラと美しく光る様に対して、『都市の詩学』の著者である田中純さんは、そう述べている。

人間は古くから自然を眺めてきた。ミメーシス(模倣)を根本原理においたルネサンス絵画以降は、自然は眺められる対象(客体)となった。
それに異を唱えたのが、印象派以降の近代絵画だろう(いや、正確にはマニエリスム以降、主体と客体をめぐる闘争は何度も繰り返されている)。近代は、見られる客体をどう描くか?という問題から、どう見るか(あるいは見ているのか)?という主体の側に問題を移した。
一方で、写真という方法が登場すると、見る主体という存在意義も揺さぶられた。見る者と見られる者の関係をめぐる問題は、主体とも客体ともつかない機械(写真機)が介在することで複雑化した。
けれど、そんな見る者と見られる者との関係などとは無関係である、自然が写真に入り込む。
それが、写真家、畠山直哉が、東京のただなかにある暗渠の真っ暗闇の世界で光を必要としているのが自分ただひとりだけであることに気づかされることになる写真集『Underground』の撮影において起こったことだ。
だが、『Underground』でこの写真家は、「自然」の「無関心」を前にした挫折と無力感を通して、自然が人間などまったく見ていないこと、人間によって見られようが見られまいがどうでもよいこと、つまり、「見る者と見られる者の関係」などという問題それ自体がきわめて人間的な関心ごとでしかないことを示しえたように思われる。自然の「無関心」の前では、人間自身が括弧に入れられてしまうのである。
関心が無い。
そう言えば、何かあるべきものが存在していないかのような錯覚をうける。
けれど、自然の側からすれば「関心」というもの自体があまりに人間的すぎるものだということになる。
そんなものはそもそも存在しない。
「意味」というものが人間にとってのみ意味あるものであるのと同様、「関心」はあくまで人間だけが関心を示すものでしかない。
だから、自然が自分たちに対して無関心だと気づいて無力感を感じるのも人間だけである。
美しい自然が自身の美しさに無関心であることに気づいて途方に暮れるのも極めて人間的な感覚でしかない。
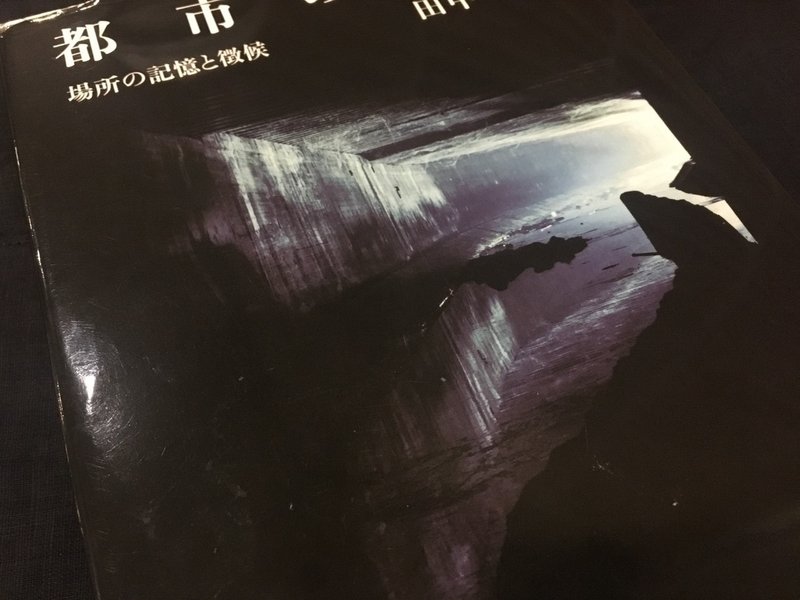
バタイユなら途方に暮れたりせず、いや、そもそも、それを不意撃ちだなどと感じることなく、楽観的に受け止めるであろう。
美しく思えた当のものが同時に「ドブネズミの糞に生えたカビ」であるということに、人間的な意味の裂け目を明らかにするアンフォルムの操作が行われたことを認めて、喜びはするのかもしれない。
けれど、バタイユ的な思考においては、人間的に高級なものと、人間的に低級なものよりさらに低いものは同居している。高級なもののベールの下に、非人間的な自然=獣的なものが見出されることがバタイユのいうアンフォルムではない。
ジュリア・クリステヴァが『恐怖の権力』という著書の中で、アブジェクション=おぞましさという概念を用いているが、バタイユのあらゆるものを踏み潰してガラクタ化するという操作としてのアンフォルムはそれとは違う。クリステヴァのおぞましさはベールの下に隠れたものを暴き出すように見えて、ベールの下から現れるのは、その暴き出しの行為自体によって止揚されたアブジェクションという別の価値を帯びさせる。バタイユのアンフォルムは、この弁証法的意味化を徹底して避ける。

この観点において、冒頭の「自然は自分自身の美しさに徹底して無関心だ。ここには人間を途方に暮れさせてしまうような何かがある」という見方は、自然の無関心さを止揚してしまっているようなところがある。それは元の畠山さんの写真自体にあるものというより、この読解の方にあるものだろう。
人間に無関心な自然は美しくもあれば、おぞましくもある。それは元よりそうなのではなく、人間がそこに意味を見出そうとするから、そうなのである。
バタイユが見るのは、そうした意味化が同時にガラクタも生み出しているということだ。意味の生産には無意味の生産が付きまとっている。
そして、バタイユは最終的には、無意味が意味を凌駕すると考えた。どんなに掃除婦が頑張って埃を掃き捨てようと頑張っても、最終的には埃まみれになるのは避けられないと。
また、『アンフォルム』から引いてみる。
ついで彼は、「掃除婦たち」のシシュフォスめいた闘いに触れる。毎朝羽箒と掃除機とで武装して、彼女たちはこうした日々に押し寄せる誇りに立ち向かう。最後に、この闘いは不公平であり、勝ち目はないと彼は結論する。「[……]いつの日か埃は、残存する以上は、おそらく家政婦たちに対して勝利を収めはじめ、うち捨てられたばかでかい建物やさびれたドックを莫大な費用量の屑で一杯に満たすだろう」。
その意味では、バタイユがいまのサーキュラーエコノミー的な考えを知ったらどう思うのだろう?と考えてみたくなる。
現代はとにかく、この埃の生産をひた隠そうとする。だから、余計に塵は積もって山になる。
中世までは、それを避けるために祝祭を置いた。上と下、高貴なものと下賤なものが逆転する祭。精神的なもの、宗教的なものが、肉体的なもの、色欲や食欲的なものに取って代わられるカーニバルの時間。そこで意味あるものも、無意味なものも一切合切、消尽された。
その祝祭はルネサンス期までは生きながらえたが、その後社会から排除され、19世紀には完全に姿を消す。産業革命が人間社会から自然を追い出していったのとほぼ時を同じくして。
畠山直哉さんの写真は、そんな祝祭を失った都市における祝祭的な役割を担うものではないだろうか?
写真とは石ころである。蹴られた石ころがどこに転ぶか、撮影者である写真家にもわからない。それは行く先を占う護符なのだ。片足立ちで石蹴り遊びをしながら、よろめくように歩く写真家は、跛行の神々に似て、さまざまな異界を遍歴巡行してゆく。その石ころが転がった先に、都市の「自然」が思いもかけぬ姿で出現する。
異界への遍歴を可能にする石ころとしての写真。それはかつての祝祭が担っていた異界との接触を可能にする。
もちろん、それが異界であるためには、僕らはそれを止揚して回収することを避けなくてはならない。
そんな止揚が起こらないようにするためにも、かつての祝祭は、決まった祝祭の期間を過ぎれば何もなかったかのように終えられたのだろう。消尽の時間が終われば、またいつものように意味の生産の時間が開始された。意味あるものも、無意味なガラクタも同時に生産された。
そうした祝祭によるリセット機能を失った現代の社会で何がたまり続ける埃を消尽する役割を担うのだろうか。
戦争? テロ? あるいは……。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
