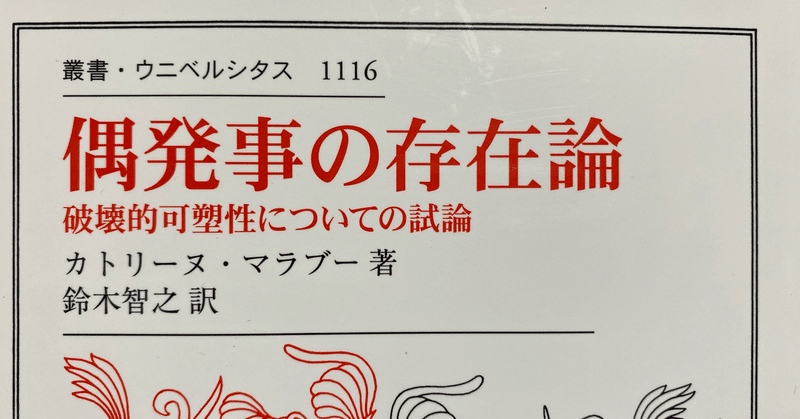
偶発事の存在論/カトリーヌ・マラブー
なんともオリジナリティのある本だ。
ほかの本と交わる感じがしない。孤立している。
そんな印象を受けた。
まさに、この本でテーマにされている「破壊的可塑性」そのものだ。
本書でいうところの可塑性とは、主体が外部からなんらかの作用を受けつつ、それを内部での変化へと変換することを通じて自らを作り替える様を示す概念だ。
そこに「破壊的」という形容が加われば、取り返しのつかない形で主体が上書き更新されることを指していることになる。
つまり、破壊的可塑性が作動したのち、主体はかつての主体であるとは主体自身も気づかないほど変化してしまうのだ。
その孤立が、この本『偶発事の存在論』そのものと似ている。
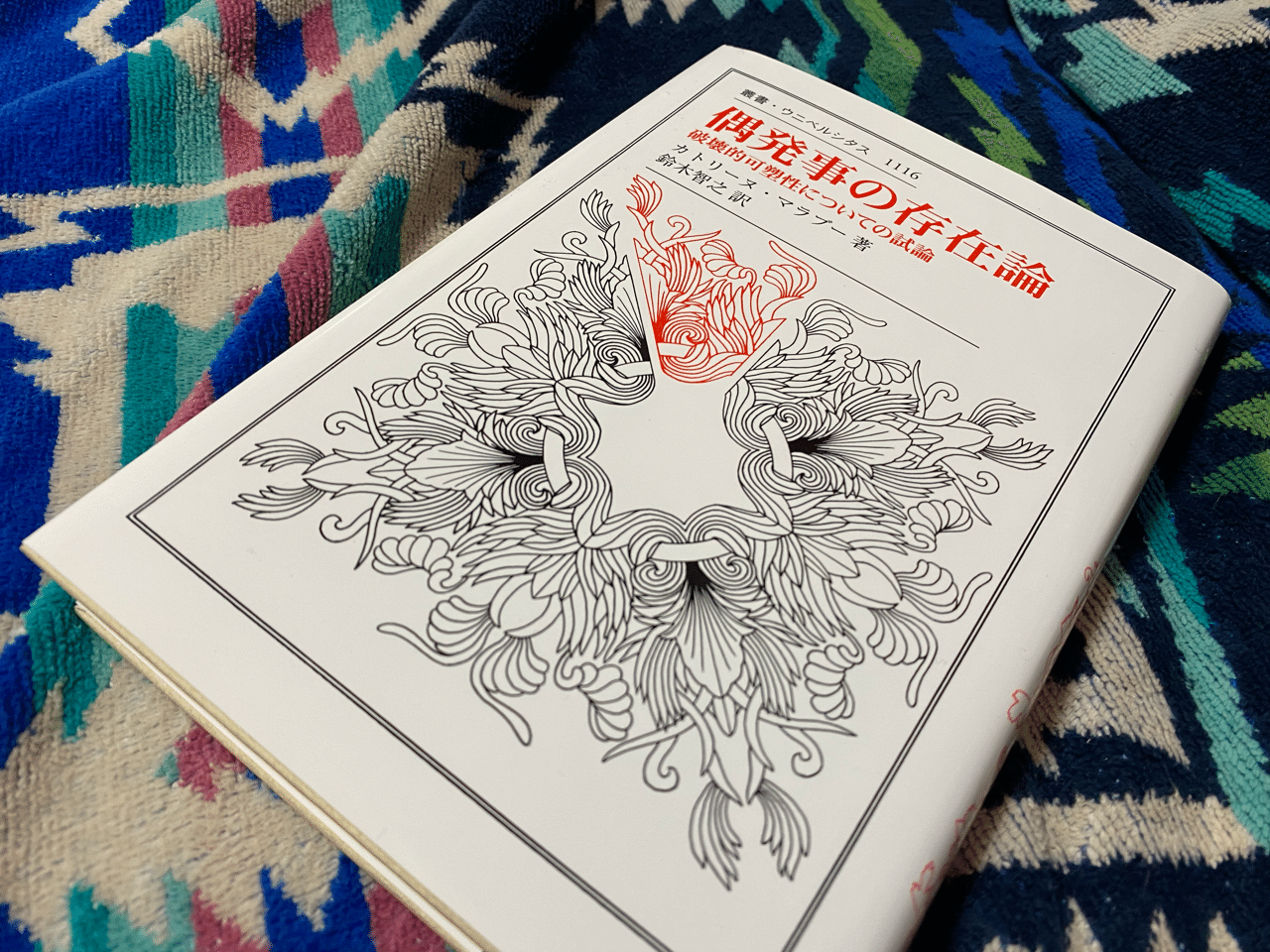
コロナ禍という破壊的可塑性
この本が対象にしている個人の可塑性とは違うけれど、今回のコロナ禍を境にした社会の変化もある意味、破壊的可塑性だ。
実際、僕はそうしたことに言及されているのかと思い、自粛期間中にこの本をAmazonで購入したくらい、個人のことと社会全体のことという違いはあれど、似ている。
ある唐突な変化によって、その前と後がまるで異なるものになる。
これまで親しんでいたものにアクセスできなくなり、これまで普通にしていたことが急にできなくなってしまう。
何故そうなったのか、コロナウィルスの流行のせいだといえばそうなのだけど、何故それによって美味しいものをみんなで集まって食べたり、外国に旅行に出かけたり、好きなアーティストのライブに行けなくなるのかといえば、なんとも理不尽なものを感じなくはない。
頭で理由はわかっていても、変化が唐突すぎて、起きていることを承認することがむずかしいのが、いまのこの状況ではないだろうか。
分割された同一性
著者のマラブーが破壊的可塑性という言葉で想定しているのも、そうした唐突な変化だ。
何故、そんな変化が自分の身に訪れ、いままでの自分とはまったく切り離されてしまうような理不尽としか思えない境遇に見舞われなくてはならなかったのか。
そこにちゃんと承認できるような理由は見出せず、運命の悪戯としか思えない偶発事に巻き込まれたとしか、考えることができない。
マラブーが対象にするのは、そんな破壊的事象である。
私はこれまでにもずっと、この破壊的可塑性の現象、分割された同一性について、アルツハイマー病者の突然断ち切られ打ち捨てられたような同一性、ある種の脳損傷患者や、戦争で外傷的経験を負った人や、自然あるいは政治がもたらした破局的な出来事の犠牲者たちの、感情的な無関心について論じてきた。確認しておかなければならないこと、知っておいていただかなければならないこと。それは、私たちの誰もが、ある日別人に、まったくの別人に、それまでの自分とは決して折り合いをつけることができないような何者か、贖いも償いもなく、遺された意志ももたず、劫罰を受けて時間の外へと突き落とされたかのような何者かになりうるということである。
この引用中、「分割された同一性」という言葉があるとおり、破壊的可塑性の前後では人は同じアイデンティティを持ちえない。
マラブーが例に挙げるフランツ・カフカの短編『変身』である日、虫に変身していた主人公のように。
過去の自分から切り離されて誰も自分を、かつての自分と同じようには扱ってくれない。
いや、場合によっては自分自身さえそうだったりするケースもある。
そのときには、もはや過去の自分ではなくなったことにすら、本人自身が気づかない可能性がある。アルツハイマーなどはそうした例だろう。
誰も考えたがらない変化
この理不尽な出来事が訪れる可能性は、「私たちの誰も」が共有していると言えるだろう。
しかし、このことをテーマとして哲学はこれまでない、とマラブーはいう。
誰も、破壊による可塑的な造形については、進んで考えたがらない。しかし、破壊もまた形を与える。殴られても歪んでいても、それは顔である。四肢の切断は、ひとつの体形をもたらす。外傷的経験を負った心も、ひとつの心であり続ける。破壊はそれ自らの彫刻刀を備えている。
破壊的可塑性について考える気にならないのは、ある意味、それが死よりも残酷だからではないだろうか?
破壊的可塑性の場合、変化のあともなお、それまでとはまったく不連続ながら、別の形で身体や心が残る。巨大な虫になってきまった自分、もはや他人のことも自分のこともわからなくなった自分、昨日まであって四肢がなくなってしまった自分。
どんなに変わってしまっても、生はまだ続く。
いままで生きてきた土台だけを奪われた形で。
死んでしまった本人はもちろん、まわりの人にとっても喪失ではあっても、死はまだ受け止めることができる(もちろん、それがあまりに唐突だったり、死因が不可解だったりすれば別だろう)。
しかし、破壊的可塑性のように、唐突な変化があった上、別の形で身体や心だけが残り続けるというのは受け入れるのがさらにむずかしそうだ。
すべての可能態が尽きたとき
心がそのままで身体がまったく別ものに変わってしまったり、その逆にアルツハイマーや記憶喪失のように身体はいままでのままなのに心が別ものになってしまったり。
破壊的可塑性は同一性を暴力的に分割する。
そこには一切の許しがないように思える。
何かを拒絶したり否認したりする可能性さえ残されておらず、ただ変わり果てた別の形だけを断ることもできずに受けとるしかない。
破壊的可塑性は、すべての可能態が尽きてしまったところから、作動を開始する。一切の潜在性がとうに失われてしまった時、大人のなかにあった幼年期が消えてしまった時、全体のまとまりが破壊され、家族の精神が消え去り、友情が失われ、絆が消失してしまった時、砂漠のような生はその冷淡さを強めてゆき、そのなかで破壊的可塑性が作動する。
まさに砂漠だ。
あらゆる可能性を欠いた渇ききった荒野だ。
人為的な破壊的可塑性を憂う
この本を読んでいて考えたのは、いまの世の中、こうした破壊的可塑性が、SNSなどを通じたり誹謗中傷や度を超えた批判によって簡単に起こってしまうということだ。
何か問題ある行動をした人が完膚なきまでに叩きのめされ、それまで持っていたものをすべて奪われるどころか、その後の社会復帰すら危うくなるくらいに、人生を別ものにされてしまうことが頻繁に起こっているように思う。
しかも、何か問題ある行動を起こした人だけでなく、まわりの人まで巻き込んで、それまでの暮らしを奪いとってしまう。
こんな暴力的なことが人為的に、かつ日常的に起こってしまう社会はこれまであったのだろうか?
そして、こうした人為的な破壊的可塑性まで偶発事として考察しなくてはいけないのだろうか?
これはまぎれもなく持続可能性の問題のひとつである。
その意味でも、破壊的可塑性というテーマは今後大きく取り上げられるものになっていくのかもしれないと感じた。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
