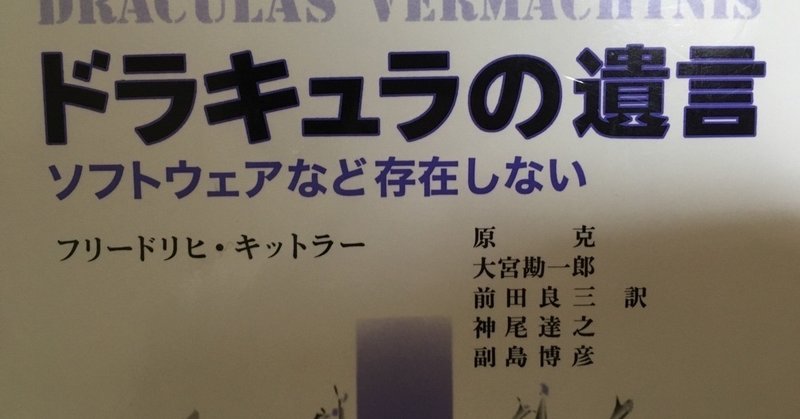
ドラキュラの遺言/フリードリヒ・キットラー
大事なのは、教えてもらうことではなく、学ぶことだ。
だから、自分がどうやって学ぶのかを自ら身につけないとどうしようもなくなる。自分が何から学びを得られるかを知っているかどうか。
その意味で、今回ここで紹介する、そして、僕のnoteではすでに何度も紹介している、ドイツのメディア評論家フリードリヒ・キットラーの『ドラキュラの遺言』は本当に学びの機会を多く与えてくれる本だった。
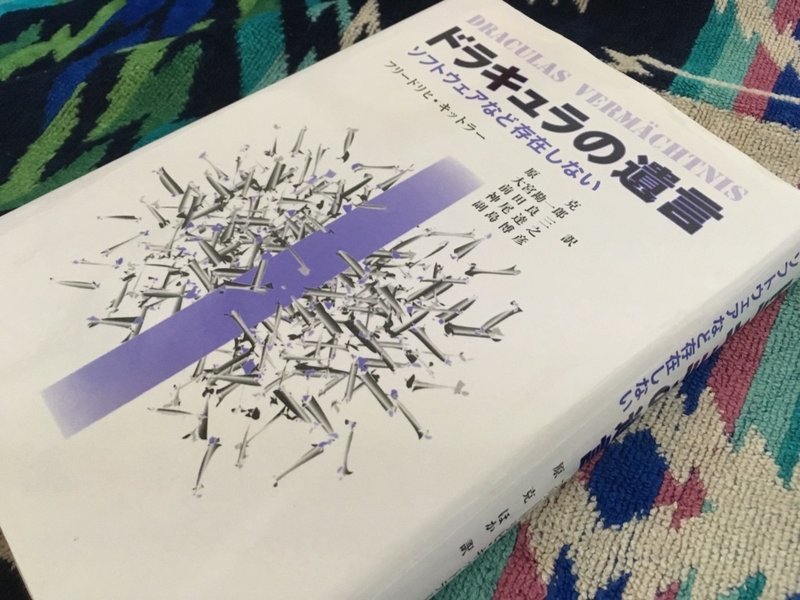
普段読んでいる本よりむずかしさを感じたが、その「むずかしさを感じる」こと自体、学びが得られることを気づかせてくれるサインだ。むずかしいのは、僕自身がそこに書かれていることに対して無知(あるいは既知が少ない)だからで、つまり、そこにはたくさんの学びのチャンスがあるということにほかならない。
よくむずかしく感じる文章を前に、文章の側のせいにしているひとがいるが、そんなことをしてたら学びの機会はどんどん失われるだけだ。これまでわからなかったこと、対処できなかったことを、わかったり対処できたりするようになるのが学びだろう。それは間違いなく対象の側の問題ではなく、自分の側の問題なのだから。
キットラーは、コンピュータにおけるGUIの登場について、こう書いているが、これと同じことだ。
ユーザー・インターフェイス、ユーザー・フレンドリー、あるいはまたデータ保護といったキーワードで、産業界は昨今人間に、人間のままでいるべしという運命を押しつけている。
自分の側(人間の側)が変わるのではなく、対象の側に自分に「わかりやすい」よう譲歩させること。それは自分の側(人間の側)に変わらないまま、成長のないままでいろという運命を押し付けていることにほかならない。
ある意味、人間の文化の歴史は、この人間が変わるか? 対象の側が変わるか? あるいは、その両方なのか? の変遷のプロセスだといってよいのかもしれない。そして、キットラーがこの本で扱うのも、タイプライターや蓄音機、映画や通信技術、そして、コンピューターの登場とそれらから人間の思考や文化が何を学んで自らを変化させたかということだ。
ストーカーは1893年に心理学研究協会において熱狂的に受け入れられたフロイトのレポート『ヒステリー現象の心理的機制に関する暫定的報告』から着想を得たという。実際これはそうである。人々を、たとえそれがただの事務職員であろうと小説の登場人物であろうと、「森林の向こうに隠れた土地」トランシルヴァニアへと送り込むなどということは、エスのあったところに自我が生じる、ということを聞いたことがなければ思い付くはずがないのである。
そう。キットラーのこの本、ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』(書評noteはこちら)を読み終えたすぐあとに読みはじめたのだった(買ったのは同時)。『吸血鬼ドラキュラ』を読みつつ、ここでキットラーが指摘している精神分析との関係は感じていた。同時に、その精神分析の発展とは無関係ではない人類学的な意味でのトランシルヴァニアとロンドンという関係もこの小説にはありありと現れている。そして、音声あるいは筆記文化と蓄音機やタイプライターによる機械的文化の対比も『吸血鬼ドラキュラ』を支えるものだ。
1874年、アメリカ南北戦争の終結以来生産過剰で経営が悪化していたレミントン兵器工場は、最初の大量生産可能型タイプライターを発売した。しかし、奇妙なことに商業的成功はその何年か後のことであった。すべてのジョナサン・ハーカーたち--主人のディスクールを同時速記し、清書に起こし、場合によってはインクを湿らせるか何かして社内資料用に写しを取る、といったことを仕事とする、これら男性秘書たち--が、この新しいディスクール機関銃を侮蔑的に拒否したのである。ひょっとすると彼らは単に、その長い就学期間をかけて習得したこの手書き文字という持続的で文字どおり個別的な、すなわち彼らをそれぞれ独立した諸個人として結び合わせ、狂気から守ってくれる紐帯に、過度な誇りを抱いていたのかもしれない。いずれにせよ、ハーカーがトランシルヴァニアへ旅行用タイプライターを携行しなかったのは、レミントン・タイプライターの技術的後進性のせいではない。彼が後に妻とするマリー嬢が5ヶ月後に同じ目的へと旅に出た時には、その旅行用タイプライターはとうに発売されていて、彼女はそれに胸を躍らせていたのである。
タイプライターによってオフィスに女性が進出するようになる。代わりにそれまで男性に独占されていた地位が失われることになる。
ストーカーの小説から20年とすこし経った1920年には、フリーマン・ウィルス・クロウツが『樽』という探偵小説で筆跡の残らないタイプライターをアリバイの道具として使っている(しかし、このアリバイが覆るのもタイプライターの活字の摩耗のせいなのだが)ように、タイプライターというテクノロジーは、筆跡とともにあった個人のアイデンティティ、男性秘書のスキルを無効化していった。
だから、その同じ時代に、「自己消失」の恐怖としてのドッペルゲンガーが日常に数多く登場するようになったのも偶然ではないのだろう。ドッペルゲンガーの報告を初期の段階でしていたのは、文学者である。彼らは彼ら自身の書斎のなかで、自分に似た者の幻像をみた。
そして、その自身と同一の幻像を生み出す力はさらにモータリゼーションによっても増幅される。
ドッペルゲンガーたちが、よりにもよってバスや急行列車に出現するのには、それなりの理由がある。自我という名のドッペルゲンガーが、つまり詩と哲学による幻像が、中部ヨーロッパの読み書き教育の普及に由来したとすれば、マッハやフロイトの前にも現れたみすぼらしい人物は、中部ヨーロッパに普及したモータリゼーションの産物である。このことについては、『感覚の分析』も「不気味なるもの」も、口をつぐんで語らない。だが鉄道とオットーエンジンが登場した後になってはじめて、動く鏡面や、滑走するパノラマや、道路使用者という名の無数のドッペルゲンガーが出現することになるのだ。
筆記ではない機械的な記録によって、アイデンティティが喪失され、動く映像によって幻像が日常にあふれ出す。
1895年以降、道が2つに枝分かれする。一方は、真面目な文学と称される映像を欠いた活字崇拝、他方は、鉄道や映画のように映像をモーターで可動化する純然たるテクニカルなメディアだ。文学はいまさら、娯楽産業が生み出した奇跡の数々と競い合おうとはしない。文学は魔法の鏡を機械に譲り渡すことになるのである。
タイトルの「ドラキュラの遺言」という小論からはじまり、サブタイトルの「ソフトウエアなど存在しない」という小論で終わる、10編の小論から成るこの本を、キットラーは19世紀後半のタイプライターや蓄音機の時代から、映画などの時代を経て、20世紀の半ば以降のコンピューティングの時代の技術へと時間を進めていく。
そして、コンピューターが登場するころには、ついにこのような宣言がなされる気配が充満する。
今日われわれの誰もが承知していながら、決して口にだしては言わないことがある。書くのはもはや人間ではないという事態がそれである。
タイプライターは、書く行為を男性から女性へと移したが、コンピューティングはもはや人間を直接書く行為の現場からは排除する。コンピューターの登場以降は『樽』でアリバイを解く鍵となったような活字の磨耗も存在しなくなる。書く行為は完全に人間の手に負えるような場所には存在しなくなるのだ。
しかし、記述を計算へと置き換えるには、そのオペレーションの技術を整理し、発展させておく必要があった。
ギリシア初期の銘文や中世初期の写本には語間に区切り記号がない。だが、文字変換をしようとすると口語の発話と全く同じように、どうしてもデータの喪失や忘却が生じるかそれに脅かされることになる。そこでは、つねに間違う可能性を孕んだ人間の記憶だけが一時記憶装置として何とかことを運ばせていたのである。それに対して、語間や文の両端にスペースを置けば各々の文字すべてが、チューリング・マシーン上でのように操作可能になる。文字は区切り記号を備えていれば、交換、複写、消去という基本的なコンピュータ操作が可能となる。シャノンが指摘したクロスワード・パズルから回文にいたるまで文字を使うすべてのゲームはこうしたオペレーションに基づいているのである。詩は、おそらくこうしたオペレーションを最大限にしたものにほかならない。
区切り記号のなかった初期ギリシアや中世の写本の記述に対して、区切り記号や引用記号、あるいは数学の記述における代数記号などの登場が記述と思考のバリエーションを増やしていく。
そうした過程を経て、命題をあやつることを演算的なデータ処理へと変換することが可能となる。
文学=文献とは、その内容が何であれ、とりあえずデータ処理なのである--それは情報の受信、保存、演算処理、伝達を行うのだ。コンピュータのそれのようなロジックは「思想」あるいは哲学に関わることのいっさいを自動化によって処理し、「文学を音に変換する」という彼のラジオ美学の不可能とされた望みをいともたやすく実現するばかりではない。そればかりか、サイバネティクスはデータ、アドレス、指令をエレガントな形式で実行するので、歴史的な意図においても、あるいはまさにそのような意図で、文学を回路モデルによって記述することが可能かもしれないのだ。
このあたりはエドガー・アラン・ポーやギュスターヴ・フローベルら19世紀後半の文学者が気づいて取り組んでいたこでもある。
ほとんど技術主義的といっていい繊細さで、ポーは「目的はその達成のために最も適した手段によって達成されねばならない」という原理にのっとって、作業する。
と書くのは『文学とテクノロジー』のワイリー・サイファーだ。
「19世紀的世界観によって、方法は計画的たることを得、その限りで技術主義的たることも得たのである」とサイファーは書くが、これは単に文学者のみを指してではなく、「19世紀は企業、科学、芸術すべての世界において、なんでも方法論を発明せずにはおかなかった時代である」というように、あらゆる分野においてそうであったのである。それが産業革命的な新たなテクノロジーが次々に生まれてくることに対する人間側の学びであったことは間違いないだろう。
そして、そのテクノロジーの発展と人間的な学びの先に訪れたのはこのような事態だ。
長いが引用する。
ヒルベルトの意味においてすべてを形式化すると、理論というものはおはらい箱にされてしまうことになる。というのと「理論はもはや有意味な命題の体系ではなくなり、語の連なりとしての文章の体系にすぎず、そして語自体もまた字母の連なりにすぎない。したがって、いかなる語の組み合わせが文章であるのか、いかなる文章の組み合わせが公理であるのか、そしていかなる文章が他の文章から直接的な帰結として得られるのか。これらを決定するのは、ひとえに形式のみによる」からである。意味が文章に収縮し、文章が語に収縮し、語が字母に収縮すると、ソフトウェアもまた存在しないということになる。あるいは言いかえれば、コンピュータシステムがこれまでのように日常言語の言語環境のなかにいる必要がなければ、ソフトウェアは存在しなくてもよいであろう。しかしこの言語環境とは、よく知られていることだが、古代ギリシアで考案されて以来、字母と貨幣--証書と籠--のことである。こうした経済的に十分な理由があったため、コンピュータ開発の石器時代に、十進法よりも二進法のマシン記号を読んでいたアラン・チューリングの謙虚さは、その後すっかり一掃されてしまった。コンピュータ協会なるもののいわゆる「哲学」は、チューリングを継承するどころか、必死でハードウェアをソフトウェアの背後に隠し、電子的記号表現を人間と機械のインターフェイスの背後に隠そうとしてきた。高水準のマニュアルでは人間を大切にするためと称して、三角法機能をアセンブラーで書く時、精神的混乱が生じるかもしれないと注意を呼びかけている。そして、「基本的なハードウェアを操作する具体的な手順を、ユーザーのプログラムから取り除く」役割は、ご親切なことにBIOSの手引き(そして専門の著者たち)が引き受けている。こうして考えていくと、中世における天使の位階が漸進主義だったのとあまり変わらず、まずCOMMAND.COMのようなオペレーティング・システム機能がBIOSをカバーし、次にワード・パーフェクトのような応用プログラムがオペレーティング・システムをカバーするという具合に、カバーの連鎖がつづくことになる--その結果、先年、コンピューターデザインに(あるいは米国防総省の科学観に)2種類の根本的な変更がなされ、この隠蔽システムがめでたく完成するはこびとなったのである。
そう。新たなテクノロジーという対象が、ヒューマンインターフェイスの名をもつ古い記述体系の下に覆い隠されてしまい、人間が新しいテクノロジーそのものを学ぶ機会が失われたのだ。
そして、現代の深層学習するAIの前ではもはや人間は彼らが何を考えているかは分からず、せいぜい学習モデルの構築に関われる程度だろう。
僕らはこうした環境において新たに学んでいく必要があるのだ。
それは間違いなく過去の自分を否定し、壊していくことが含まれる。
もちろん、それを自らしようとしなくても、このテクノロジーの発展のなかで、それまで依ってたってきたものは勝手に崩壊していく。そのとき、新たな依拠の対象について学べているか、古い対象にしがみついて気がつけばその対象自体を失うかは、学びに対する姿勢次第だろう。
キットラーのこの本はそんな現実を見つめなおさせてくれるきっかけを与えてくれる良書だと思う。ぜひ一読をおすすめする。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
