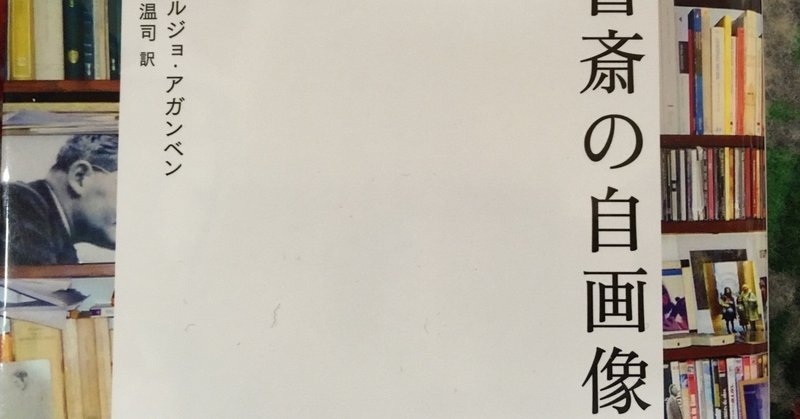
書斎の自画像/ジョルジョ・アガンベン
アガンベンが書くものが好きだ。
なんというか意味が溶解するところ、理性的な人間を超えたところにあるものを見つめる視点に惹かれる。
この本も含めて4冊目になるが、どの本にも心を動かされてきた。
いままで読んだ4冊のうち『スタンツェ』(書評)と『ニンファ』(書評)の2冊は主に芸術に関しての思考を集めたものだ。『事物のしるし』はなんと要約すればいいか、むずかしいが、言うなれば思考の方法論について考察されている。
そして、この『書斎の自画像』は、シンプルに言ってしまえば、アガンベンの自叙伝となる。
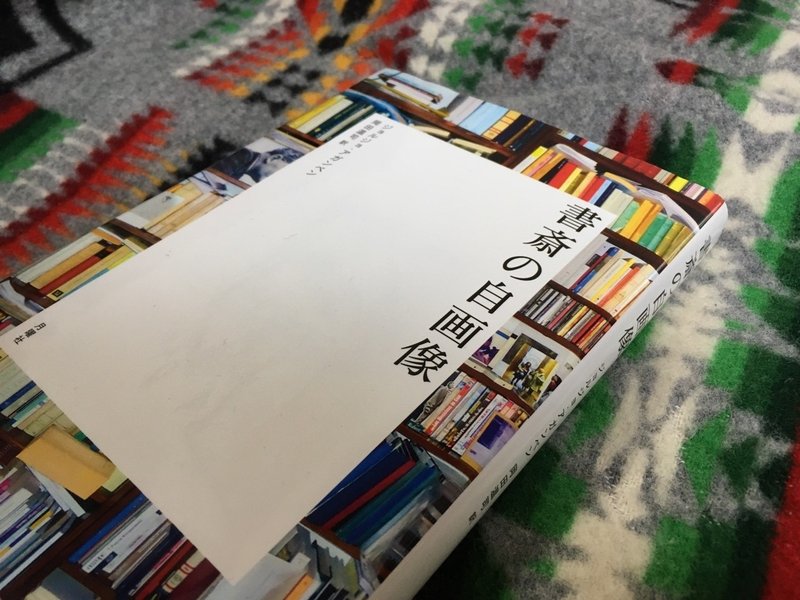
出会いの連鎖
この自叙伝は、アガンベンとさまざまな哲学者、美学者、詩人、作家、古典学者、画家、映像作家、批評家、編集者、音楽家などとの出会いが、彼の人生のいろんな時期にいろんな場所にあった書斎に飾られた写真を辿りながら語られる。

たとえば、1966年、彼がまだ24歳の若き頃にハイデガーと過ごしたプロヴァンスの日々は、「ローマのジリオ通りにある書斎で、左にハイデガーの写っている写真は……」と語り出される。

この「プロヴァンスでのハイデガーとの出会いは、わたしにとって何だったのか」とアガンベンは問い、「温和であると同時に厳格でもある顔つき、鋭くて妥協のない面、それは夢のなかなか以外では見たことなないようなものだった」と、50年以上前の出会いを回想する。
あるいは、1968年のフランスの五月革命にも影響を与えた運動、アンテルナシオナル・シチュアシオニストのリーダーでもあったギー・ドゥボールとの1980年代後半の出会いについても「カフェ・ルテシアでギーとアリスにはじめて出会ったことはよく覚えている」と書いている。
会話はすぐに盛り上がり、政治状況のあらゆる局面にわたって、予想されていた合意が得られた。わたしたちは、同じ明晰さに達したのだ。ギーは芸術的アヴァンギャルドの伝統から、わたしは詩と哲学から出発して。
と。
そして、この出会いからはじまったドゥボールとの関係の中で、アガンベンは、「ギーが解明できなかったもの」である「親密な内秘性」の政治的な意味を見いだす。
いかなる伝記もいかなる革命も、その秘法のもとでは難破せざるを得ない。純粋に政治的な要素は、私的な生の内秘のうちにある。だが、それを捕まえようとしても、伝達不能で退屈な日常性のみがわたしたちの手中に残るだけである。まさに当時のわたしが問いはじめていたのは、この内秘なもの――ゾーエーという名でアリストテレスが都市から排除することで、同時に都市に包摂したもの――の政治的な意味であった。
ゾーエー。
前に紹介した、ロージ・ブライドッティが『ポストヒューマン』のなかで「生気的唯物論の一部門として、ポストヒューマン理論は、人間中心主義の傲慢や、超越論的カテゴリーとしての〈人間なるもの(ヒューマン)〉という「例外主義」に異議を唱える。そのかわりにポストヒューマン理論は、ゾーエー、すなわち非-人間的な諸側面における生命の生産的で内在的な力と手を組むのである」という文脈で用いたときにも、僕は、その概念に着目したが、アガンベンがドゥボールの文脈において、その概念に触れるのを読んで、この一冊が僕にとっても良い出会いとなるであろうことを確信した。
秘密の観相学
だから、問題は、この生における内在的な力についてだと言える。
内在的であり、内秘的である、
所謂、人間的なという意味では、非―人間的な生。
人間性をむしり取ったあとに残る生の残余。
そんな生であるゾーエーが実はこの本全体に横たわっているように僕は感じた。
本書の後半、アガンベンは、人生において出会ってきた人々について思い出しながら、こんなことを書いている。
わたしが愛した友人や人物に思いを馳せるなら、全員にどこか共通のところがあったように思われる。それは、次の言葉でしか言い表わすことができない。すなわち、彼らのうちにある不滅のものとは、彼らの脆さ、壊れるかもしれないという彼らの無限の能力である、と。
この脆さ、壊れるかもしれないという無限の能力。これこそが内秘的な生としてのゾーエーとつながっているように思う。アガンベン同様に、僕自身、そうしたものに惹かれ、それゆえにアガンベンの書くものにも惹かれるのだと思う。
アガンベンがこう続けているのを読めば、その思いは確信にいたる。
だが、おそらくこれこそは、人間についてのいちばん的確な定義である。ダンテによれば、「いとも不安定なる動物」、それこそが人間なのだ。変化と破壊をどこまでも生き延びることができる、人間はこれより他の実質を持たない。この残余、この脆さは、まさしく一貫して残るものであり、個人の歴史と集団の歴史の変わりやすい栄枯盛衰に対抗しうるものである。そしてこの残余こそ、秘密の観相学なのであり、人間の流転する顔のなかに認めるのが困難なものである。
変わりゆく表情をもつ顔のなかにではなく、個人や集団の移ろいゆく歴史にも抗い、残余するものとしてのゾーエー。その秘められた生の観相学へと向かうアガンベン。
そんな彼ゆえに、同じような意味で、スイス人のドイツ語詩人であったロベルト・ヴァルザーの病に、そして、彼の詩の現実世界での救いのなさと裏表にある「彼の聖性」について書くのだろう。
たしかにヴァルザーには、回復されるべきものも救われるべきものも何もない。だが、彼の聖性――聖性について語りうるとして――は、癒されることのない病気に自分が付きまとわれているという確かな見通しが立たないから帰結する。カフカもまたそうだったように、彼はこの病気と徹頭徹尾うまく付き合っていくことができた。だが、また別の面もあった。かつてヘルダーリンに起こったように、ヴァルザーは、世界が自分にとってまっまく生きづらいものとなったことを、はっきり感じていたのだ。
世界は生きづらく、だが、みずからの病についてはうまく付き合うことができる。ヴァルザーが生きたのは、表面的な生ではなく、内秘的なゾーエーとしての生だったのかもしれない。
そんなブァルザーと、ヘルダーリンを重ねるアガンベン。
「病室は居心地がいい。伐採された樹木のように、そこにいる者は、まったく肢体を動かす必要はない。遊び狂って疲れ果てた幼児のように、すべての欲望は眠っている。修道院か死の控えの間にいるように感じられる。[……]文学の教授たちが描くのとは違って、わたしはら晩年のヘルダーリンは決して不幸ではなかった、と確信している。絶え間ない要求を満たす必要なく、質素な片隅で夢を見ることは、たしかに殉教者にはできないことだ。だまされてはいけない」、完璧な明晰さでヴァルザーはこう記していた。1926年(ヴァルダウに収容される3年前)の短い散文には次のようにある。「人間が理性を失うということは、人に勧めうることであると、つまり機転にあふれることだと、40歳のときヘルダーリンは考えた……」。
「人間が理性を失うということは、人に勧めうること」。
理性をもってしては届かぬところにゾーエーがあるのだとしたら、理性を失ったヘルダーリンも、ヴァルザーも、なるほど不幸ではないだろう。
アガンベンは、そんな理性を失った人々の秘密の観相学に惹かれている。
プルチネッラ
僕がなんとなく、このヘルダーリンやヴァルザーに惹かれるアガンベンのことがわかる気がするのは、以下の引用中にあるような道化の身振りが思考の糸をつないでくれるからだ。
ヴァルザーの文体、わけてもそのマニエリズムは、深淵に宙吊りにされているため、誰にも真似できないものである。それは、この間に誰もがニヒリズムという小アパートに生きるようになったからである。だが、この深い裂け目の淵にあっても、ヴァルザーの登場人物たちは、ある種の超越的なバランスを保ちながら、ほとんど踊るようにして通り過ぎることができる。彼らの流儀は、無の身振り、パントマイムやサーカスのそれであり、あらゆるパントマイムがそうであるように、通過儀礼的な要素を含み、語の純粋な意味で神秘的なものである。だが、この通過儀礼には、いかなる啓示のための場もない。つまり学ぶべきことは何もない。それゆえ、無との共犯関係は、カフカにおけるのと同じように、どこか滑稽なものがある。
ここでは道化の身振りとしてのパントマイムやサーカスの身振りが、「マニエリスム」と重ねられる。
それは意味の空疎な滑稽として重ねられる。
それはどちらも表面的な意味を超えて笑いを誘う。
意味は口を開いた深淵な空疎の上で宙吊りにされる。
カーニヴァルにおける上下の反転、フールの反対行動だ。
この空疎な身振りは、コンメディア・デラルテにおけるプルチネッラのそれにほかならない。
アリストテレスの言うように、悲劇において人間は、役を模倣するために演じるのではなくて、役を引き受け、責任をとるのだとすれば、反対に、喜劇の登場人物は、ただ役を模倣するためだけに演じ、その行動には最後まで無関心で、決してかかわりを持つことはない。そのため、その行動はパントマイムへと転じるのだが、このことが意味するのは、あらゆる責任の糾弾から役をひたすら解放する、ということである。プルチネッラは、彼を紛糾させようとする生の出来事やエピソードを決して生きることはない――彼はむしろ、その身振りが行動の彼岸に、その言葉があらゆる意味の伝達の此岸ないし彼岸に永遠に留まるように、ただひたすら生きることの至福の不可能性を生きているのだ。
生きることの至福の不可能性。
むしろ、ヘルダーリンやヴァルザーがそうであったように、幸福は、理性を失った先の生にこそある。その生を生きるのがプルチネッラであろう。
そのプルチネッラの姿は、アガンベンの書斎の写真のなかで棚の上のラジカセの横で佇んでいる。

ところで、身振りはまた、プルチネッラ[コメディア・デラルテに登場する道化師]の発する鶏のような声でもある。それは、声というよりもむしろ、イギリスの手遣い人形師たちがそう呼ぶように、「未知の言語」であり、ブルーノ・レオーネが見せてくれたような、ナポリの人形芝居の遣い手が口蓋深くまでピヴェッタ――1本の糸で結えられた2つの真鍮片からなる一種の小さなリールで、呑み込んでしまうことすらある――を突っ込んで発する、人工的な音である。プルチネッラの声――身振り――は、もはやしゃべることができなくなっても、まだ言うべきことはあるということを示している。ちょうどそのおどけた仕草が、どんな動作も不可能となったときでさえ、まだやるべきことはあるのだということを示しているように。
このプルチネッラの「しゃべることができなくなっても、まだ言うべきことはある」こと、そして、「どんな動作も不可能となったときでさえ、まだやるべきことはある」ということが、内秘的なゾーエ−にほかならないだろう。
意味が笑いの発生とともに無意味へと溶けていくのちにはじめて、ゾーエーの次元が現れてくるのだと思う。
アガンベンのノート
さて、本書も終わりに近いところ、アガンベンはこんなことを書いている。
私はしばしば[大文字の]本、つまり絶対的で完璧な本を発見することを夢見てきた。それは、わたしたちが全生涯で、大なり小なり意識的に、どんな場所や書店や図書館に行っても見つけようとするものである。夢のなかで手にとり、喜びを募らせながらページをめくるのは、わたしのコレクションにある古い児童本のような、挿絵入りの本である。こうして休みなく何年も探しつづけるのだが、ついには、そんな本はどこにもなくて、見つける唯一の方法は自分でそれを書くことだと、悟ることになる。
絶対的で完璧な本が見つからないから、それを見つける唯一の方法として「自分でそれを書く」ことを悟るアガンベン。ローマ、ヴェネツィア、そして、パリなど、各地を転々としたアガンベンの書斎は、まさにその本を書くための場所である。
そして、その書斎という場所の意味を象徴的に閉じ込めているのが、アガンベンのノートかもしれない。
ジリオ通りの書斎の机の上に、いろんな色に製本された8冊のノートが見える。思いつき、所見、読者録、引用、そしてごくまれに夢、出会いや特別な出来事を書きとどめたノートである。つまり、わたしの実験室の本質的な部分であり、将来の本や進行中の本の最初の萌芽や素材を含むものである。(中略)たしかに、完全した本とくらべると、たどたどしい筆跡の走り書きのようなこれらのノートは、ありえたりありえなかったり、また別な風にありえたかもしれない可能性を保管している、潜勢力の忠実なイメージである。その意味では、これらのノートこそがわたしの書斎である。
「潜勢力」というのも、アガンベンの用語のひとつだ。それも内秘的なゾーエーとの関係性が強い。顕在的になっている日常の意味、日常の生とは異なり、潜在的な状態に留まりつつも、たしかな勢いをもつ生命の力、身振り、そして詩的な言葉。そうしたものに常に惹かれ続けているのがアガンベンであり、彼のノートには、その思いが完成された本にならないものも含めて潜勢力として残されているのだろう。
自画像といえば画家のアトリエで描かれるものだ。であれば、自画像と名付けられたこのある種の自伝が、作家にとってのアトリエと言える書斎とともに書かれているのは、とても自然だと感じた。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
