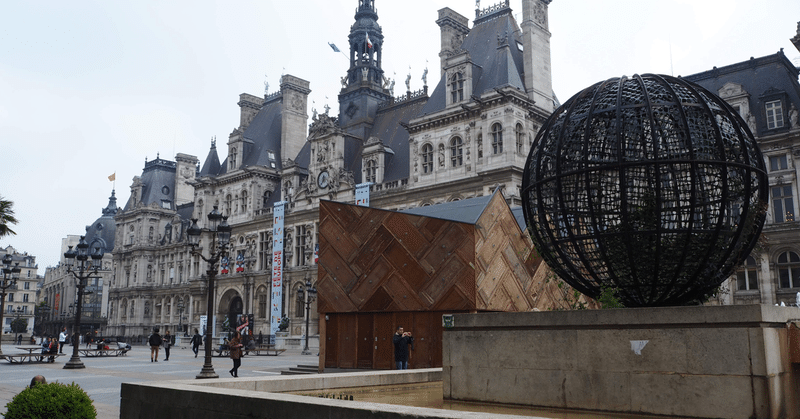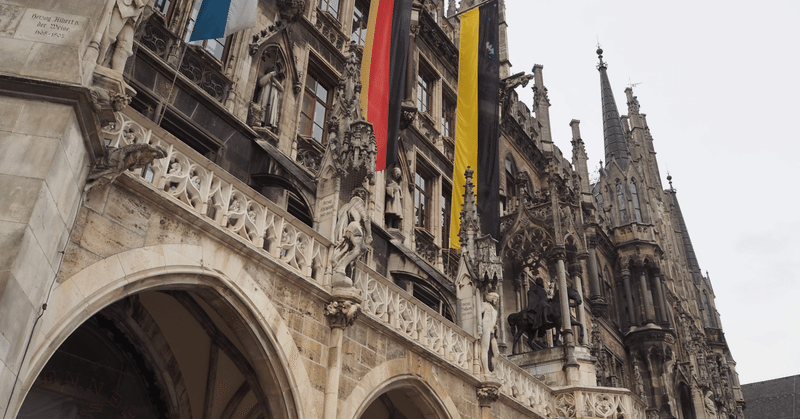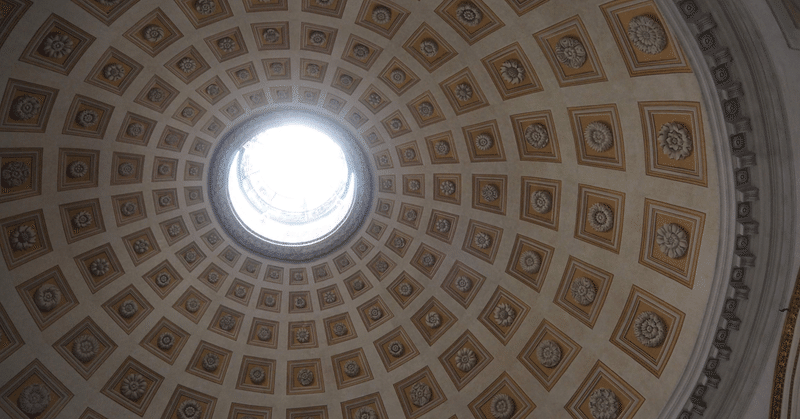- 運営しているクリエイター
#歴史
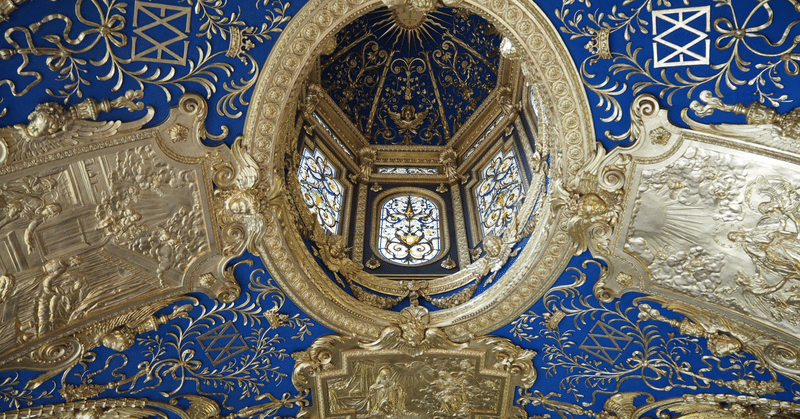
わたしたちは各方面からわたしたちのところにやってくるさまざまなニュースの間断なき喧騒から身を引き離すよう努めなければならない
久しぶりにテレビのニュースを見ていて、唖然とした。 緊急事態宣言の発効を伝える内容なのだけど、中身がほとんどない。いろんなものが削られてまさに換骨奪胎。まったくコミュニケーションになっていなかった。 アナウンサーの喋っている言葉も、映像や音声の切り取られ方も、テロップなどで出される文字情エッセイ報も、このたくさんの命に関わる状況を改善するために、それを見ている人が正しい判断をし行動をとるための一助となるような有益な情報を何も伝えていないように感じた。 いや、何も伝えていな