
Books, Life, Diversity #24
実はそれほど深く考えて付けたわけではないこのマガジンのタイトルですが、多様性、意外に外していなかったなと、いまさらながら感じています。本は多様でなければ生き残れないし、生きてこないメディアです。そしてまた、本に触れることによって、この私という個人の内面も、また社会も多様になっていきます。多様でなくても良いと嘯けるのはしょせん強者でしかありませんし、しかもそれは脆弱な強者です。そんなこんなでささやかな抵抗としての第24回。
「新刊本」#24

柴田邦臣『〈情弱〉の社会学 ポスト・ビッグデータ時代の生の技法』青土社、2019年
タイトルだけを見ると、売れるためにセンセーショナルにしたように思えてしまうかもしれませんが、まったくそうではありません。現代的に非常に意義のあるテーマを追った研究書であり、最後まで読んでみると、著者が(悩みつつも)挑戦的に、攻める覚悟を持ってこのタイトルを選んだことが理解できます。
そもそも、なぜ私たちは「情弱」という言葉を見ると、何か軽いなあとか、見下しているよなあと思うのでしょうか。あるいは逆に、では「情強」であればそれは良いことなのでしょうか。著者は次のように言います。
ここで確認しておきたいのは、「情弱」であったりそう呼ばれたりすることを、徹底的に嫌悪し強迫的に回避すべく、必死にスマホを叩きディスプレイを見つめ続ける、私たちについてである。もしそんな自分を、まったくまっさらな感覚をもった、別の世界線の自分が客観的に見ることができたら、そしてその別の世界線の自分が精神科医だったら、「この世界の自分は、「情報強迫性障害」を患っている」と診断するのではないか。「情弱」とラベリングされることを強迫的に嫌悪する私たちは、ワーマンの言う「情報不安症」が、三〇年経ってさらに進んだ、「情報強迫性障害」とでも呼ぶような存在になってしまっているのかもしれない。(p.19)
情報に依存している人々は、情報が限られたり、変質したり、悪化したりすることで簡単に、その〈生〉が左右され、変質され、さらには奪われることにもなる。そもそも入手できる情報に制約のある〈情報弱者〉だからこそ、そのような変質や悪化に対して抗して生き残る力を蓄えることができる。ポスト・ビッグデータ社会における〈情報弱者〉とは、アーキテクチャそのものの本質的問題を自覚できず、生きることが追いつめられる私たちすべてといってもよい。だから私たちすべてが、先人としての社会的弱者から、その〈生きるわざ〉を学ぶ必要があるのだ。自らが〈情報弱者〉となってはじめて、マイノリティとしての経験・知恵の重要性に気がつくことができるのである。〈情報弱者〉のリテラシーとその蓄積の戦略は、〈生きることの情報化〉が急速に進展する中で、私たちが私たちとして生きるために必要な技法と戦略を、教えてくれるのである。(p.197-198)
少しでもこのような著者の問題意識に共有するものがあるとお思いであれば、本書はとてもお勧めです。いま、性善説でも性悪説でも、あるいは技術の価値中立論でもない、技術が本質的な次元で日常となったなかで私たちの生の在り方を問う新しい波が、同時多発的に起きているのを感じます。いや、そんな議論はこれまでもあっただろうとお思いかもしれませんが、私の感覚としては、単なる議論ではなく「技術が日常となった」というリアルな感覚ななかでリアルを問うということは、いまようやく様ざまなジャンルで生じてきているものです。そしてネット上に溢れる情報の大半が、いかにその情報を表層的に使いこなし「強者」の立場に自らを置くかということに偏重しているのかを見る限り、恐らく、このような問いが可能であるのも、それほど長くはない時間でしかないのかもしれません。
柴田氏自らが書いているように「ネガティブにもほどがある、しかもだいぶ時代遅れ感がつきまとうバスワードで、どういう議論ができるのか」とお思いになってしまうかもしれませんが、それはあまりもったいない良書です。タイトルに違和感を覚えた方にこそ、お勧めします。
なお、美しい装丁は#21でも触れた今垣知沙子氏によるもの。
うっかりしていましたが、この方の装丁なさった本はこれを含めて4冊持っていることになります。どれも素晴らしいですね。
「表紙の美しい本」#24

荒金直人『写真の存在論 ロラン・バルト『明るい部屋』の思想』慶應義塾大学出版会、2009年
タイトルにある通り、バルトの『明るい部屋 写真についての覚書』(花輪光訳、みすず書房)の注解書です。バルトの写真論を深く知るために最適な一冊。私自身『明るい部屋』は非常に影響を受けた本で、〈それはかつてあった〉というどうしようもなく切実な狂気を通して、初めて写真というメディアを、多少なりともかもしれませんが理解できたと思っています。そんな私にとって、バルト読解の心強い先達としてあったのが、本書です。
今回「表紙の美しい本」区分でこれを挙げているのは、先に紹介した「断片的なものの社会学」(岸政彦、朝日出版社)と同様、この装丁もまた、ここで語られている思想を見事に表現したものであるためです。そしてまた、これは『明るい部屋』の表紙(私は新装版しか持っていないため、それ以前の版がどうかは分からないのですが)に対する見事なオマージュでもあります。

どちらも窓にカーテンがかかり、その向こうに光が透けて見えています。亡くなった母親への追悼の書であることを知っている私たちには、それはあたかも、誰か大切なひとが亡くなってしまった後のある朝、部屋でふと目覚めたときに見る光景のように思えます。『明るい部屋』の写真はDaniel Boudinet氏の作品(残念ながらオフィシャルなサイトは見つけられませんでした)。『写真の存在論』は写真がEnrico Policardo氏の"Homage a Daniel Boudinet"とのこと。装丁は鈴木衛氏。
「読んでほしい本」#24
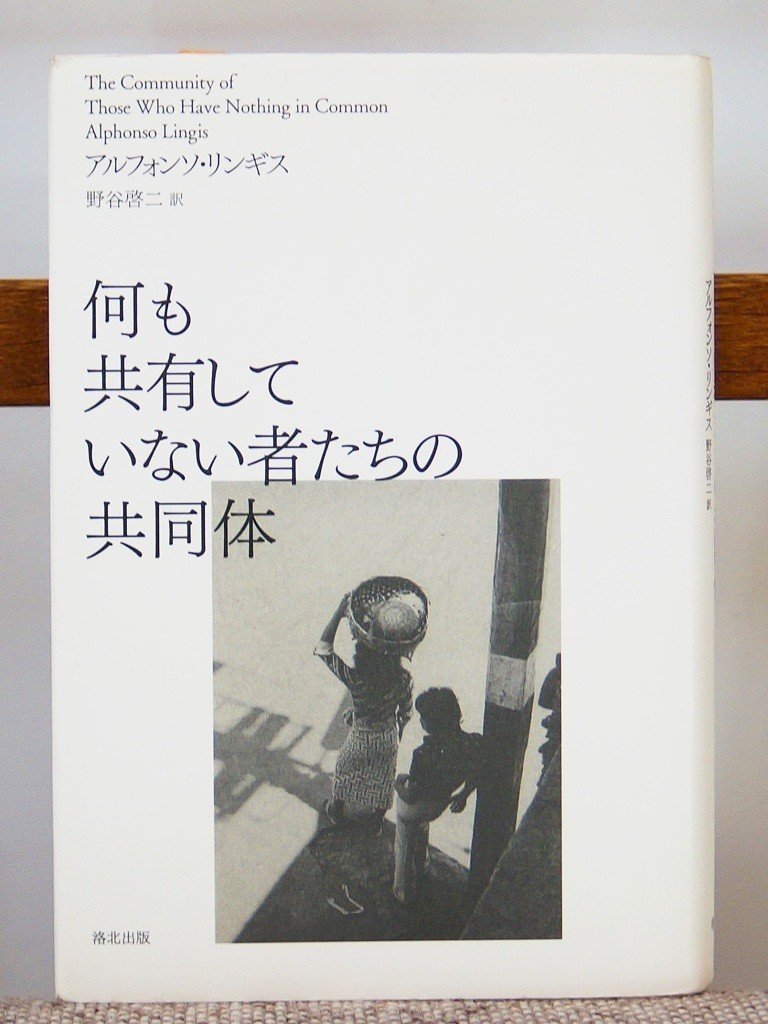
アルフォンソ・リンギス『何も共有していない者たちの共同体』野谷啓二訳、洛北出版、2007年(3刷)
共同体とは普通、何かを、たとえば言語やものの見方や考え方を、共有している人びとが形づくっているものだと考えられている。また、一つの民族、都市、制度といったものを共に作っている集団によって形づくられると思われている。けれども私は、すべてを残して去っていく者、すなわち、死にゆく人びとのことを考え始めた。(p.11)
この言葉によって、リンギスは、死者とのコミュニケーションについての類をみない倫理的かつ詩的な論考を始めます。
通常、共同体はあるコミュニケーション形態を共有しています。そのコミュニケーションにおいては、他の誰でもないこの私が語るということによって生じる不透明さ(特有の抑揚、口ごもり、言い間違い等々)、そして私たちがコミュニケーションを行っている背景に存在する様ざまなざわめきは、すべてノイズとして捉えられます。そして透明なコミュニケーションは、いかにそれらのノイズを取り除けるかにかかっています。「コミュニケーションの理想都市とは、最大限に雑音が除去された都市」(p.30)なのです。コミュニケーションとはすなわちノイズとの戦いであり、そのようなコミュニケーションによって形づくられた共同体は、「みなが同じ側に立ち、お互いどうしが〈他者〉ではなく、全員が〈同じ人間〉の別形にすぎない対話者たちの同盟、押しよせる雑音汚染の流れを押しとどめるという共通の関心によって結ばれている、対話者たちの同盟」(p.112)です。けれども本当にそうなのだろうか、とリンギスは自問します。ノイズを完全に除去するということは原理的に可能なのか。そもそもノイズはコミュニケーションではないのか。そうしてリンギスは、コミュニケーションには二つの側面があると考えます。
一つは、自分の目にするものと考えることを客観化し、それを共通の合理的な言説によって言い表わし、語られるべき内容の代表者ないし代弁者として、他者と同等かつ交代可能な人間として語る方法である。そしてコミュニケーションへのもう一つの入り口は、本質的なのは、きみ自身、きみが何かを語ることだという状況である。(p.151-152)
きみが彼あるいは彼女に語るとき、咳き込み、言い間違え、言い換え、同じことを繰り返す。その場で、きみにしかできない唯一の形で語ること。それが透明なコミュニケーションからノイズとして排除されてきた、別の、そして先行し、対となるコミュニケーションなのです。合理的な共同体(そしてそこで行われる透明なコミュニケーション)においては、語られる内容こそが本質であり、誰が語ろうと、どのように語ろうと、それは問題とはなりません。むしろ問題になるべきではない。そしてその場において、私たちは他人と置き換え可能になります。この私が語ることが重要なのではなく、他の誰が語っても同じでなければならない。私の位置はきみの位置と交換可能であり、きみの位置は他の誰かさんと交換可能です。それでもコミュニケーションには何の変化もなく、同一の内容が語られ、それは交換可能な部品の無限の連なりのなかを伝達されていきます。
けれど私たちは、そのとき、交換可能な自分がけっきょく誰でもないということに気づかざるを得ません。交換可能な誰かが抜けたあとに入り込んだこの私は、要するにこの私であることを放棄することによってこの私としての位置を占めているに過ぎないのです。だから、私たちは不安になります。私はいったい、どこに存在するのか。私とはいったい何ものなのか。透明なコミュニケーションによっては、私たちはその確証を得ることはできません。だから、私たちは自分の手を眺めます。
人は、自分が自分であると確認される自分の手を見る。そして、自分の指にある、四十億の人間の右手の、どれ一つにも見いだせない数十本のしわを見る。人は、この自分が自分であることと、この手だけが触ることができるものに他者の手が触っていないことに、気づくのだ。(p.209)
だからこそ、私たちは「この私の手」でしか触れることのできない誰かを求めて、旅に出るのです。交換不可能な、世界に唯一のこの手で触れることのできる誰か。
自分の感受性のなかにだけある力、他の誰にもできないように愛し、笑い、涙を流す力への関心は、世界中の裏道や小路に、自分のキスと抱擁を待っている人びとがいるという確信、そして、自分の笑いと涙を待ち望んでいる湿地や砂漠があるという確信においてのみ可能となるのである。(p.211)
そのとき初めて、私たちは他の誰でもないこの私として存在し、そして他の誰でもないこの私の死を理解できます。代替可能であるかぎり、それは私ではなく、死も存在しません。けれどこの私となったとき、死が私たちの前に現れ、この私にとってのみ可能なことと、代替可能性による無限の可能性との間にはっきりとした境界線を弾きます。そしてまたその境界線こそが、この私に、他の誰でもない、交換不可能な他者の存在を教えてくれるのです。だからこそ私たちは、他の誰のものでもないこの私の手で、他者に触れるために他者のもとへと向うのです。そしてその他者は、交換不可能な唯一の誰かであり、従って死にゆく誰かです。傷つき、怯え、苦しんでいる誰かです。
他者のほうへと差し伸ばされた手は、他者の傷つきやすさ、疲れ、苦しみに触れ、他者が死に行く場所へと人を向わせる。触れようと伸ばされた手は、見知らぬ命令に従う。この死が、私と関係するのだ。人には、他者の死を正当化する自由などありはしない。自分の役割が課す命令や、文明社会の共同事業が課す命令によって、他者の死を正当化し、他者の死を彼あるいは彼女にまかせて立ち去る自由などないのである。(p.218)
そしてきみは、他者が、一つの生が持ちうる美徳と力の限界にあるとき、そしてその根源にあるとき、その場に立ち会うように求められ、そこできみは、言語の力が果てる極限に立っていることに気づく。
看護士たちは、「よく来て下さいました」と言う。彼らは、きみが彼らにはできないこと――死にゆく者に何かを言うこと――ができ、また言わなければならないということを、知っている。だが、何が言えるだろうか。何か言おうとしても、すべて空疎でばかげたことのように聞こえてしまう。[中略]だが、もしきみが少しだけ勇気をだして出かければ、きみはその場にいて、何か言わなければならないことを確信するはずだ。要請されているのは、きみがそこにいて語るということである。何を語るかは、結局のところ、ほとんど重要ではない。きみはどんなことでも口ばしってしまうだろう。たとえば「大丈夫だよ、お母さん」と。きみはこんなふうに言うことは愚かなことだと知っている。母親の知性にたいする侮辱ですらあることも分っている。母親は自分が死ぬということを承知しているし、きみよりも勇敢なのだから。母親はきみが言ったことを責めたりはしない。結局、何を言うかは大して重要なことではないのだ。要請されていたのは、何かを語るということだけであり、それは何でもよかったのである。きみの手と声が、彼女が今しも漂いゆく、何処とも知れぬ場所に付き添って伸ばされること。きみの声の暖かさとその抑揚が、彼女の息が絶えようとするまさにその時に、彼女のもとに届くこと。そしてきみの目が、何も見るものがない場所に向けられている彼女の目と出会うこと。このことだけが重要なのである。(p.142-144)
それはコミュニケーションが遂に果てる情景なのでしょうか。死という究極の沈黙を前に、私たちはただ絶望し、断念するしかないのでしょうか。死にゆく人に差し伸べるぼくらの手に、彼あるいは彼女に触れるこの私の手に、いかなる力もありません。けれど、そうではない、とリンギスは言います。むしろそこからこそ、コミュニケーションが始まるのです。私たちは、死にゆく人のもとへ出かけていきます。ただ付き添うためだけに。ただともに苦しむためだけに。
人が出かけていくのは、そこに行くように駆り立てられるからだ。人は、他者が、彼または彼女が、ひとりきりで死んでいくことのないように出かけていくのである。敏感さとやさしさと共に動かされる人の手の動きのすべてが、他者を感受する力によって、その人に向けられた命令を感知する。人は、他者のために、そして他者と共に、苦しまずにはいられない。他者が連れ去られてしまったときに感じる悲しみ、いかなる薬も慰めも効かなくなったときに感じる悲しみは、人は悲しまずにはいられないということを知っている悲しみなのである。(p.223)
死に向うのは、勇気のいることです。そして同時に、死にゆく人のもとへと出かけていくのもまた、勇気のいることです。私たちは、その勇気を持ち得るのでしょうか。あのとき私たちは、その勇気を持ち得たのでしょうか。恐らく、答えはありません。答えがないまま、それでも問い続けなければなりません。透明なコミュニケーションの向こうにある、癒す力を持たない手を差し伸べることによってのみつながることができる共同体のなかで。そしてまた、きょうも、明日も、私たちは出かけていかなければなりません。いつか誰かがこの私のところに出かけてくるその日まで。
リンギスは先にも紹介しましたが、メルロ=ポンティやレヴィナスの翻訳で知られる一流の研究者であると同時に、独特の感性によって彼の旅してきた世界を切り取った素晴らしい文章を書く作家でもあります。彼の撮影した魅力的な写真とあわせて語られる「きみ」を主語とした小さな物語。本書は、名づけようのない唯一の文学ジャンルを成したとさえ思える名著です。詳細な解説もついていますので、リンギスに興味をお持ちの方は、ぜひお読みください。
この一連の記事では、出版支援として以下のプロジェクト/情報へのリンクを毎回貼らせていただきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
