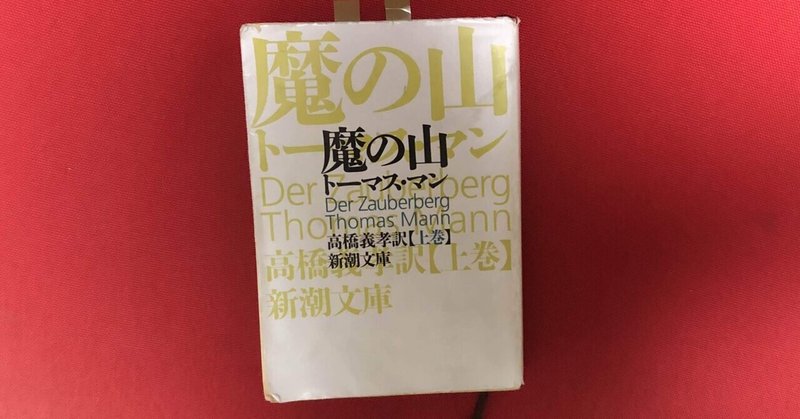
トーマス・マン「魔の山㊤」
この本を読もうと思ったきっかけは「ノルウェイの森」だ。僕が初めてノルウェイの森を読んだ時、この「魔の山」がどんな本なのか全く知らなかった。ノルウェイの森を初めて読んだ頃はまだ外国文学に興味がなかった。どれくらい興味がなかったかと言うと、「ライ麦畑でつかまえて」を読んでも「なんかずっと一緒やな」と思っていたくらい。
それから何年か経ち、僕もとうとう自分から「魔の山」を読みたいと思うようになった。いつか読みたいとは思っていたのだが、本屋で分厚い背表紙を見るたびに「読む意味があるのか...」と避けてきたのだ。5月のある日、具体的に読みたい本がない時期に入った。その時に思い浮かんだのが「魔の山」だった。
魔の山、、、文量のわりに抽象的なタイトルだ。梅田の紀ノ国屋で買い、電車に座ってその長い物語の1ページ目に手をかける。長編小説をやめられないのがこの瞬間のためだ。分厚くて難解だとしても、少なくとも読み続けるだけで「魔の山を読んだことがある状態」になれる。
さて、どうやらこの本は「健康な青年が旅行気分で山奥の精神病院にステイするうちに、自分もどんどんラリってくる話」みたいだ。序盤では主人公カストルプといとこのヨーアヒムが思想的な会話を繰り返すだけだから、この本がどうしてこれほど長いのか見当がつかない。そしてカストルプとヨーアヒムの性格もそれほど大差ない上、三人称がどちらも「彼」のため、どっちが喋っているのか分からなくなる。村上春樹はこんな本を20歳の時に読んでいたのか、と思う。
登場人物はどんどん増えていく。この手の小説は、主人公が誰を尊敬しているかを辿ることで本の方向性を確認できる。まあ大体の場合は「前衛的」か、「寡黙」かのどちらかだが。セテムブリーニ先生が今回のそれだ。作者トーマス・マンはこのセテムブリーニを身代りにして自分の言いたいことを言いまくっている。その攻撃的な姿勢にカストルプは惹かれだす。こういう作者と登場人物を絡める読み方をするようになったのは、村上春樹のおかげ(せい)だろう。本の内容が面白くなくても、どういう気持ちで作者がこれを書いているのか、いつでもそちらにシフトチェンジできるのだ。
途中まで僕がずっと気になっていたこと。というか、初めて魔の山を読む人が必ず思うこと。「なんでこの本はこんなに分厚いんだ?」である。
というのも、カストルプの滞在期間は当初3週間だった。そして3週間目に入るのが上巻の半分ほどの地点なのだ。あと1000ページもあるのに、残りでいったい何を書くのか?と不安になる。
心配は無用。ちゃんと「滑らかなつなぎ目」が用意されていた。恋愛である。
僕はここで「きたきた」と読む速度を上げた。はっきり言って前半はかなり説教ぽい本で、長く感じた。カストルプの「ありきたりな性格」は理解できるのだが、アルプスの情景描写と思慮深い心理描写のラリーじゃ飽きてくる。トーマス・マンの知識が豊富なため教科書として読めなくもないが、スリルとは程遠い。しかしクラウディア・ショーシャの登場によって、一気に誰でも共感できる話になってくる。好きな女の子がいるから家に帰りたくない、という気持ちが自然だろう。
肖像画のくだりなんかは良い。「誰か別の男によって描かれた好きな女の子の肖像画」という状況が不快なのは、どの時代でもそうだろう。ここで読者はカストルプの恋愛が本気であることに気づく。トーマス・マンはこのシーンをいつ思いついたのだろう?
そしてもう一つ共感できたのが、ショーシャが異国風の(アジア風)の顔立ちをしているという点。トーマス・マンはドイツ人。欧米人がアジア人の顔立ちにどこか魅力を感じるのは、僕たちが欧米人に魅力を感じるのと一緒だろう。ここに作者の好きなタイプが現れているのが面白い。
上巻を読むのに結構かかってしまった。本当はこういう長編を読む時は一本に集中するべきだ。でも魔の山の哲学的、教科書的な地の文が永遠に続くように思えてきて、ちょっと休憩に日本の短編を読んだりしている。なんて読みやすいんだろ、もういっそ魔の山は断念してやろうか、、とも思う。
でも、この本が下巻でどうなっていくのか、知りたい。この本はトーマス・マンが11年をかけて書いた本。どこでペンが進まなくなったのか、最終的にこれだけの登場人物、エピソードをどうまとめるのか・・・下巻を読んだらまた書こう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
