
社会福祉家 大原裕介 越境の物語
「社会をよくすることをしたいなら、株式会社より社会福祉法人を経営するほうがおもしろい。僕は、そういう時代がすぐそばにきていると思っています。」
大原は、この言葉を身を以て証明する先駆者だ。
北海道医療福祉大学の4年次に北海道医療福祉大学ボランティアセンターを立ち上げ、3年後にNPO法人化、さらに8年後に社会福祉法人にした。創業から20年で売上 約8.5億、スタッフ286人の組織に育て上げ、今も変容と成長を止めない。
創業の地である北海道当別町と隣町の江別町で13箇所、東京・品川で2箇所の障がい者福祉施設を運営するが、これらはひとつひとつ、障がいやこまりごとを持つ人びとに向き合った結果として生み出されてきた。事業展開のあり方は、「ひとりの想いを文化にする」という法人理念に表現されている。
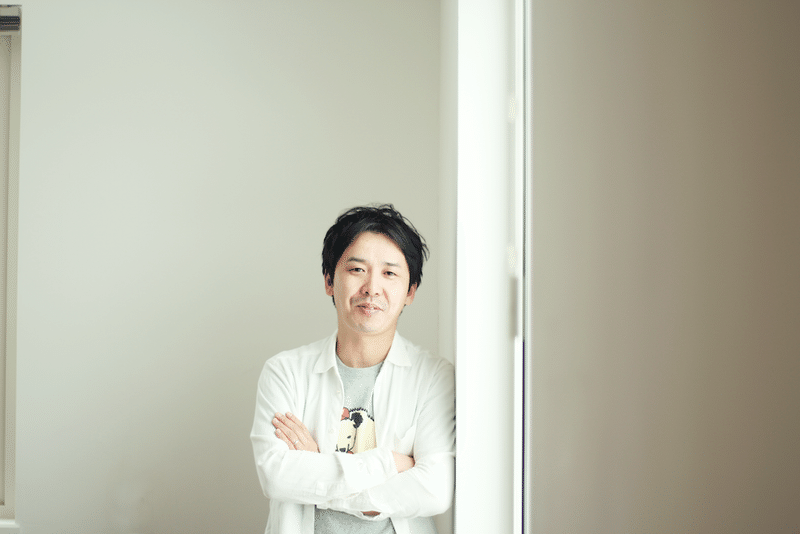
大原裕介
1979年札幌生まれ。社会福祉法人ゆうゆう創業者・代表理事。北海道医療福祉大学客員教授。NPO法人全国地域生活支援ネットワーク代表理事。一般社団法人 FACE to FUKUSHI 共同代表。

2019年に開設した「social apartment 大麻こばと」。利用者の子どもたちが成長し、家庭からの自立を求める年齢になったことから始めた暮らしの場だ。広い開口部で外部とつながるコミュニティスペースは、利用者の食事をするほか、「みんなのひろば」として地域に解放している。

美術の専門教育を受けていない人による表現活動「アール・ブリュット」の機会を障がいをもつ利用者に提供。社会福祉法人当麻かたるべの森と協働して北海道アール・ブリュットネットワーク協議会を設立し、北海道内のアール・ブリュット推進のため調査・発信活動も行っている

2020年2月、法人初の営利事業として東京大学の学食U-gohanの経営をスタートさせた。

U-gohanで提供する米とかぼちゃは、当別町でゆうゆうのスタッフと障がいをもつ利用者がつくっている。畑は、耕作放棄地を譲り受けた。
大原は、福祉の行為や営みの価値をさまざまなかたちに編集し、ひろく私たちの目の前に届けてくれる越境者だ。
Episode1 |原点| 生まれて初めて人のために必死になった
大原の物語は、ひとりの男の子との出会いから始まった。
「僕はもともと、福祉学科に在籍していながら福祉ってつまり何をする仕事なのかわからない。実習も必修だからしかたなく、家が近いところを選んで初日に遅刻して怒られるような学生でした。」
「極めてダメダメだった」と振り返る大原を変えたのは、実習先で訪れた一人の男の子との出会いだった。
「実習先は母子生活支援施設といって、 DVとかを受けた母子家庭のかたがたが寮生活をしながら自立を目指すシェルターでした。そこで僕は、自閉症の男の子に出会いました。といっても、当時は自閉症という言葉が意味するところもよくわからず。なんだか変なやつだな、という感覚でした。でも何かその子に惹かれるものがあって、『担当になっていいですか』とお願いして担当にしてもらいました。」
男の子は、すすきので生まれた子だった。母親は住所不定で妊娠中も病院にかかることなく、父親もわからない。そして、おそらく母親にも何かしらの障がいがあり、子どもに対する依存性から視界から外れた瞬間に発狂してしまう状態だったため、10歳なのに学校にも行っていなかった。大原はなにかに突き動かされるように、土日を問わず親子に関わるようになり、ふたりが暮らしている居室に入れてもらって一緒に過ごし、勉強を教えた。
そんなある日、さらなる転機が訪れた。
「あるとき、お母さんが『郵便局に行く間、この子を見てて』とおっしゃいました。『一緒に来て』という意味だと思ったら、郵便局にはお母さんひとりで行くという。信じられない思いで『いいんですか?』って聞き返したら、『あなたなら大丈夫だと思うから』と。僕は驚いて涙がとまらなかった。そして今度は、『10年間ずっと横にいたお母さんがいなくなったときどうなるんだろう』と彼を見ていると、見たこともない笑顔でキャッキャとグラウンドを走り回ったんです。」
わずか2、30分ほどのできごとだった。だが、親子の生きる世界が「大原がいない世界」から「いる世界」に変わったことをはっきりと実感できた。大原にとっては、困りごとを抱えた人に人として関わることで、彼らの環境を変えることが生涯の仕事になった瞬間だった。
「それまで僕は、人との距離感が遠めで、どこか斜に構えたり、関係性つくることに慎重になってしまう人間でした。やることなすこと、人からの見え方や見返りを気にしたり、価値や意味を考えていました。それが生まれて初めて、人のために必死になった。理屈抜きに、その子と過ごすことに充実を感じた。それがきっかけとなり、それまでのていたらくな学生生活を変えようと、チャラチャラつるんでいた友達と距離を起き、真剣に学べるゼミを選びました。同じゼミ生からしたら、『なんでここに大原がいるんだ』って感じだったと思います。」
Episode2 |越境する感性| 福祉を地域にひらく
変容した大原は大学4年生のとき、地域のボランティアセンターの立ち上げに参加した。きっかけは、またも目の前に現れた、こまりごとを抱えた人だった。
「ダウン症の男の子を育てるお母さんに『医療大学があるから当別町に引っ越してきたのに子どもが使えるサービスがない。期待も希望も持てない。できるなら、この子にわたしより長生きしてほしくない』と言われました。『どうしてこんなに辛いを思いして生きていかなきゃならないんだろう』と、またしても初めての感情を味わいました。身内が理不尽なことをされているといったこととは違う、赤の他人に対してのなんともいえない、義憤にも似た感情でした。」
心に奮い立つものを感じたとき、恩師からボランティアセンター立ち上げを手伝うよう打診があった。そこから大学院修了までの3年間、きっかけとなった親子を支えるレスパイトサービス(※)をはじめ、あらゆるお困りごとに対応した結果、0歳から96歳の生活を支える事業体に成長した。
※レスパイトサービス : レスパイトは息抜きの意。介護を要する高齢者や障害者を一時的に預かって、家族の負担を軽くする援助サービス。(大辞林第三版)

当別町のまちなかに建てられたボランティアセンター(当時)
同時期に、地域の一員として町内イベントの企画や運営にも参加した。「福祉の文脈だけでは、話が通じないことが多かった。まちを構成するさまざまな立場の人びと、それぞれの文脈に福祉を調和させていくものの考え方や話のしかた、仕事の進め方を、このころに実践から学びはじめました」と、大原は振り返る。
学生時代のボランティアセンターでの体験は、大原の越境者としてのあり方、実力に大きく寄与している。のちにNPO法人、社会福祉法人を立ち上げてからも、さまざまな方法で福祉をまちに開き、まちに参加するプロセスで大原自身が福祉のもつ無限の可能性に気づいていった。

「福祉の行為や営みは、目の前のひとりを起点に始まるので、そのひとの生きづらさの属性のインパクトに目が行きがちです。でも、ひとをケアする行為とか営みを地域社会にひらくと、違う人たちにつくれるインパクトって無限にあります。」
たとえば、こんなことがあった。
80歳のおばあちゃんがボランティアにきました。学校の先生としてずっと教える側にいた人です。彼女が、障がいのある青年たちと一緒に作業をして、「80にして自分は人から学ぶことができた。彼らのできないところばかりみていたけど、できるところに注目したらすごく優れている。自分が教員生活で立ってきた見地は正しかったのか、考えさせられた」とおっしゃったんです。
そこに生まれたのは、ケアを「する」側と「される」側をわける一方通行のサービスを超越した、ともにあることで互恵する人と人の関係だった。
大原は、「福祉業界ができることの限界に閉じて、限定された福祉をやりこめばやりこむほど、業界の外にいる人たちの違和感がますます増幅されていく。福祉の現場と地域を交叉させることは、福祉のこれからに必要不可欠」と話す。
こんなこともあった。
自分の子供の障がいを受容できていないお母さんがうちにきて、「スーパーで買い物をしていたら、知らない人が近づいてきて、『大きくなったね』って言って息子の頭をなでられた。知らないけど、『ありがとうございます』って言いました」と報告してくれました。特徴を聞いたらすぐ人物が特定でき、「そのかたは、僕らがいつも一緒に散歩に行く道すがらでお会いする人ですよ。」と答えたところ、お母さんがなんともいえない表情をされたんです。福祉の世界だけなら、専門家がお母さんと対話しながら障がいを受容させていくことが定石なのですが、そうではなくて。お母さんが自らつくったり、つくられたものとして感じてきた壁が、まちなかでの出会いとコミュニケーションで溶けていった。心が整地されたというか、そんな表情に見えました。
地域内で互恵する人と人の関係を生み出す営みが、福祉サービスを利用する当事者の心に新たな地平を拓いた。

大原の福祉を地域にひらく営みは、生産年齢人口の減少と高齢化が同時に進み、社会保障財政が極めて厳しい局面を迎えるこれからの福祉、ひいては社会・経済を、持続可能なありように創りかえていく意志のあらわれでもある。
だからこそ、ボランティアの人びとのはたらきを地域経済に還流させる試みも実施した。
「『ボランティアさん』と呼ばれる方達の地域貢献がすごく尊いのに、社会的評価が薄いことに課題を感じていました。このかたたちに光を当てたいと思って、社会的な活動をしたらうちの街でしか使えない地域通貨(ポイント)を発行してほしいとお願いしました。もともとポイントを発行・管理していた組合も、ボランティアさんたちも最初は『なんで?』という反応だった。『自分たちは報酬がほしくてやってるわけじゃない』という反発もありました。でも、『目の前の人を助けることの奥にある、まちの経済をよくするために』と説明したら賛成してくれました。同じポイントを学生の実習やボランティアに対してもつけるようにして、札幌に流れがちな消費を域内に促しました。」
Episode3 |戦略| 別解を導ける異分子人材の採用
福祉の可能性を拡張してきた大原は今、越境人材の採用に挑戦している。
株式会社が営利を最重要目的に福祉領域の制度ビジネスを手がけることもできる事業環境において、大原は社会福祉法人を「制度ビジネスが届かない、地域の中で狭間にいる人びとを発見したり支援する事業に投資をしていく存在」と定義する。自身が経営判断として社会福祉法人を選んだことで、それまでのNPO法人と同じ事業をしても免税措置が受けられるようになった。免税で生まれた余剰リソースは、制度の手が届かないこまりごとを発見し、苦しんでいる人を救う働きに投じられるべきだという。
この考えは、たとえば「わたなべストアー」具現化している。生活介護事業所「よるのにじ」と放課後等デイサービス事業「kaede」が入居する建物の1階にキッチンを備えたフリースペースを用意し、地域に解放しているのだ。

空き店舗をリノベーション。商店街に開き、誰でも入ってこられる通路には利用者のアール・ブリュット作品がならぶ。
「不登校の子どもを抱えるお母さんたちが集まって、お茶を飲んだりしてくれているようです。個々のかたがたとゆるくつながってお困りごとへの肌感覚をもっておくことで、いざというときの心の拠りどころになれるのではないか。そうした思いでつくったスペースなので、意図に沿うかたちで使っていただいているのはありがたいです」
また、全市民参加型の研修づくりも実施している。主婦、子育て中のママ、子ども、アクティブシニアといった非専門人材でも福祉に参画できるようになる学習プログラムを設計。当別町の総合計画づくりにも参画している。
「こうした仕事を担当してもらっているのは、5年前に初めて採用した、異領域からの新卒スタッフです。大阪大学の大学院で日本政治学を専攻していた彼女は、とある採用イベントに、『消滅自治体を福祉で変える』というテーマに興味を持って参加していました。学習プログラムの設計や総合計画づくりは、外からの目線で福祉の仕事を相対化・構造化する仕事なので、社会福祉を専門に学んできた人にはしにくいことです。」
制度としての福祉を学び、目の前の人を助ける技能を身につけたプロフェッショナルであればあるほど、柔軟なアイデアの着想や実現がしづらいと、大原は考えている。行政に「制度的にやっちゃいけない」と言われたり、上司に「報酬の対象にならないからやるな」と言われると、そこで終わってしまう。
「そこに別の分野の知識や発想、あるいはソーシャルな起業家精神があれば、『じゃあ寄付を集めてやったらいいんじゃないの?』と別解を導ける。今の福祉業界にはそういうふうに考えられる異分子人材が圧倒的に足りないんです。逆にいえば、経営や社会、工学の文脈で勉強してきた若者たちにとっては、活躍の余白が多く残された領域。福祉に参入すると、業界にとっても本人にとっても、無限のおもしろさがあるんじゃないかなと思っています。」
**********************
施設での対人支援からまちづくり、芸術、農業、東京での飲食業へ。アメーバのように領域を広げながら、交わることのなかった人と人がつながる結び目をつくり続ける大原。その結び目はやがて、人びとを、社会を底から支える目に見えないあたたかな網になるのだろう。越境する社会福祉家とともに網を紡ぐ働き方は、人口も経済も縮むこれからの社会において、よりいっそう輝きを増しそうだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
