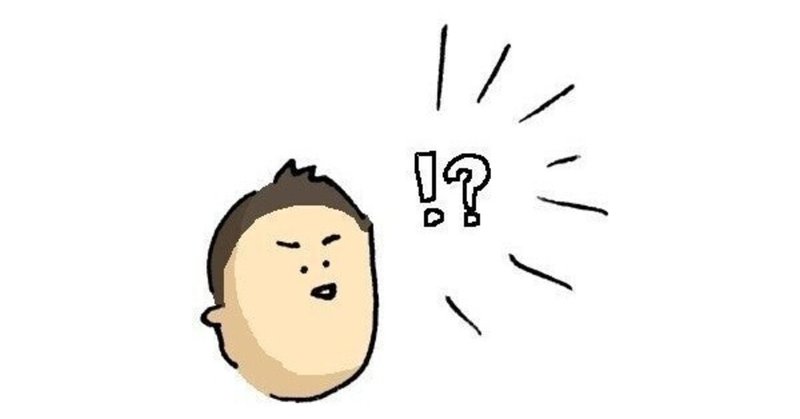
学生時代の「違和感」と社会化
昨日、金沢医科大学の医学生・看護学生向けに特別オンライン授業をおこなった。
タイトルは「地域医療のブリコルール(器用人)を目指して」。
金沢医大の一般教育機構講師の菊地建至先生が企画してくれたもので、参加してくれた有志学生は、いずれも地域医療や在宅医療に興味のある若者ばかりだった。みな真剣に話を聞いてくれて、質問も鋭いポイントを突いていたりして、講師冥利につきる講演だった。
企画者の菊地さんとは、数年前からのお付き合いだけれど、もともとニーチェ思想が専門の哲学者であり、現在では医学部でクリティカルシンキングの授業を担当されたり、「おんころカフェ」という患者・当事者をめぐる哲学カフェを開催されたりしている活動の幅の広い方だ。
私の講演は、自分の医師としての活動と経歴を振り返りながら、地域でのさまざまな実践が、対話やコミュニティ形成といったところを軸にして、今に至るということ。そして「ブリコラージュ(器用仕事)」的な実践、つまり余白や遊びを大事しながら、手持ちの道具や材料、そこにある人材や資源をうまく組み合わせることが、結果的にうまくいくのではないか、そんな話をした。
学生さんの感想で「大学病院で実習をしていて、医療のあり方に違和感を感じた。何となく、効率性を求めているというか、人間を治そうとしているというより、病気を治すということに終始しているように感じた(だから、全人的医療を目指す総合医に親和性を感じる)」という感想を言ってくれた人がいた。「よく分かる」と感じるとともに、その感覚・違和感はどんどん薄くなっていくんだよなぁとも思った。
私がまだ二十歳だったころ、医学部の三年生にあがる前の春休みに、ある病院に自主的な実習に行った。医療の現場を見るのはほぼ初めてだった。そこで強烈に違和感を感じた、医師のある一言を今でもはっきりとおぼえている。医局で医師同士のこんな会話が展開されていた。
医師A「今日の外来も、患者さんが多くてなかなか大変でしたよ」
医師B「外来はね、サクサクみないと駄目だよ。後ろが詰まっちゃうと大変だからね」
医師になった今となっては、もう慣れてしまった感覚だ。患者一人一人を大事にしたいと思いつつ、一人に時間をかけすぎるとそれはそれで大変なことになる(後ろの順番で待たされる人たちの気持ちも分かる)。だから、ある程度「まわしていく」あるいは「さばいていく」という感覚も求められる。
しかし、二十歳だった当時の私は、この医師Bの言葉に内心、強烈な反発を感じた。むしろ、怒っていたと思う。そんな「さばいていく」感じでみられる患者の側の気持ちはどうなるのだと。患者である限り、真剣に、一生懸命みてほしいと。
医学教育において、医師の職業的なアイデンティティが形成される理論をPIF理論(Theory of Professional Identity Formation)という。PIF理論によれば、学生は学校教育に加えて現場での学びや学外での学び、ロールモデルの影響などさまざまなプロセスを経て、現場での医師としての意識が形成されていく。そのプロセスは一種の「社会化」である。
社会化(socialization)とは、社会学の用語で、子供やその社会の新規参入者が、その社会の文化、特に価値と規範を身に付けることを指す。
学生時代の違和感が薄れてしまい、今では「さばく」ことに慣れてしまった私は、ある意味、医療の世界の価値観と規範になじみ、「社会化」されてしまったのだ。それがプロフェッショナルということでもあるのかもしれないが、一抹の寂しさを感じる。
医師になっても忘れたくない感覚がある。それは学生時代に感じたこうした「違和感」である。本当のプロフェッショナルとは、現場の複雑で不確実な状況に対して最大限機能するような実践をしつつも、そうした「違和感」も大事にしたいと葛藤し続ける存在なのではないか。そんなことを、学生さんの一言で感じた。
参考文献:
Cruess, R. L., Cruess, S. R., Boudreau, J. D., Snell, L., & Steinert, Y. (2014). Reframing medical education to support professional identity formation. Academic Medicine, 89(11), 1446-1451.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
