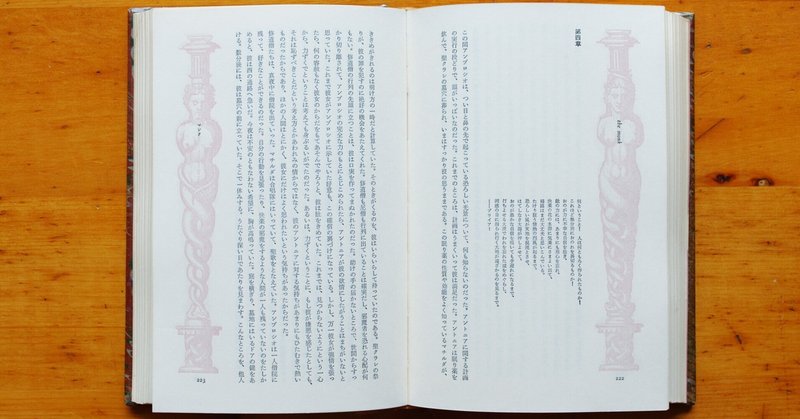
【連載】エピグラフ旅日記 第4回|藤本なほ子
「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉
ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年2月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。
出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子さんによる「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。
エピグラフ旅日記(9月)
9月某日(3)午後──太宰治、宮沢賢治、向田邦子、夏目漱石
午前中に文庫目録の分冊をとりあえず6冊つくり、あわてて昼食をとって、駅前の図書館へ。『太宰治全集』全13巻(筑摩書房、1998-1999)の続きを第4巻から見ていく。
太宰治は、初期の作品(1930年代後半から1940年頃)には凝った印象のエピグラフが結構あったが、戦中から戦後にかけてのよく名の挙がる作品群では、「津軽」に見えるだけだった。
津軽の雪
こな雪
つぶ雪
わた雪
みづ雪
かた雪
ざらめ雪
こほり雪
(東奥年鑑より)
(「津軽」★1)
初期作品には、タイトルの左下方に短い文句が添えられているものがぱらぱらとある。それらは、ほかの作家からの引用である場合もあれば、太宰の口から漏れ出たつぶやきのような文句もある。
思ひは、ひとつ、窓前花。
(「HUMAN LOST」★2)
──こんな小説も、私は読みたい。(作者)
(「古典風」★3)
──(生れて、すみません。)
(「二十世紀旗手」★4)
これらは、作者の「声」に近いと感じる。エピグラフというより「ちょっと付け足したコメント」風である。副題だろうか?と思うものもあったが、文の形になりすぎていて不自然だ。
自作のエピグラフだと言えなくもないけれど、作品や作者自身との距離があまり感じられないというか、……世の多くのエピグラフは、作品から少し離れた場所(次元)に独立して掲げられている感があるけれど、それらとは異質であるように思われる。
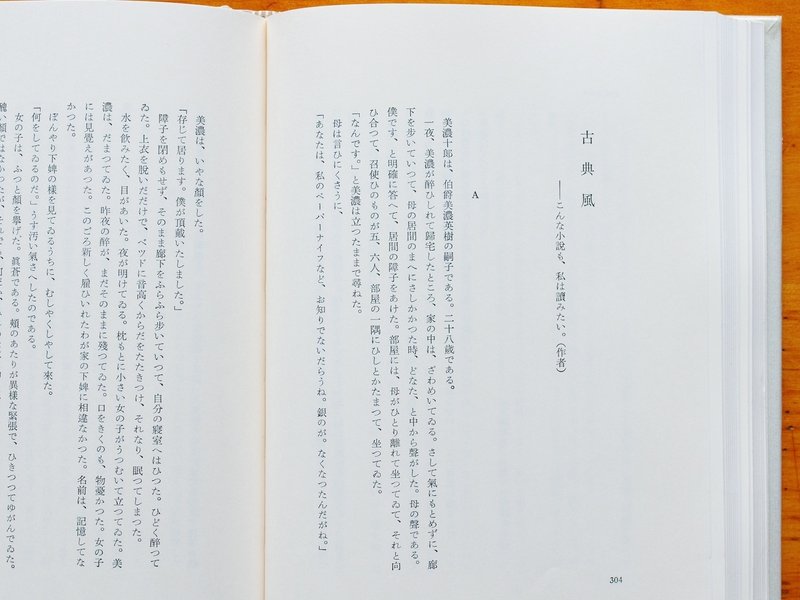
……そうだ。山本貴光さんによるとエピグラフとは、だいたいにおいて「異世界をつなぐもの」であるはずだが、太宰の置くこれらの文字は異世界へのつながり感が弱く、この作品自体、そしてそれを書いている作者自身と同じ場所にあって、それらとのみつながっているように感じられるのだ。
このような、タイトル脇という位置につぶやきを装った風の文字を置くふるまいは、ほかの作家にはあまり見られないものではないかと思う。とはいえほかの作家でも、とくに詩歌の作品では、タイトルの脇に添えられた言葉──エピグラフや献辞、作品成立の背景を伝える前置きや詞書の類──が「声」に近いというか、書き手が軽く漏らしたつぶやきか、ため息といった風情に感じられることがある。実際には周到に練られ、作為されたものなのかもしれないけれど。
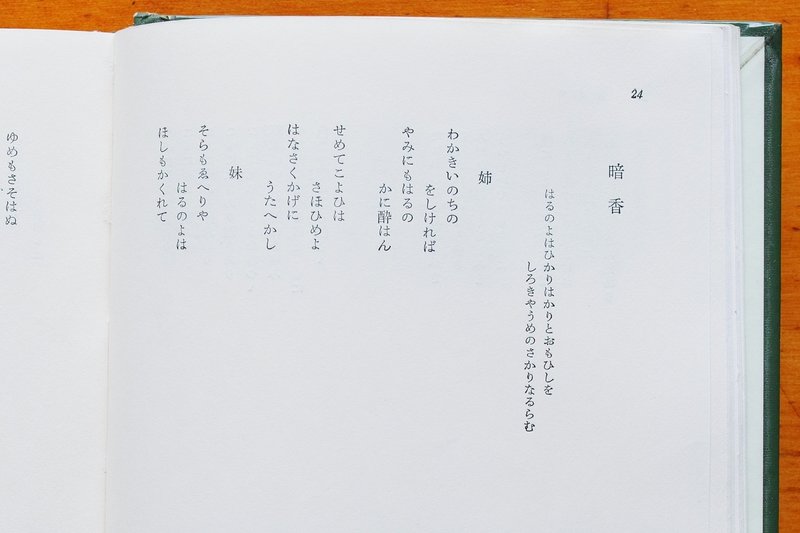
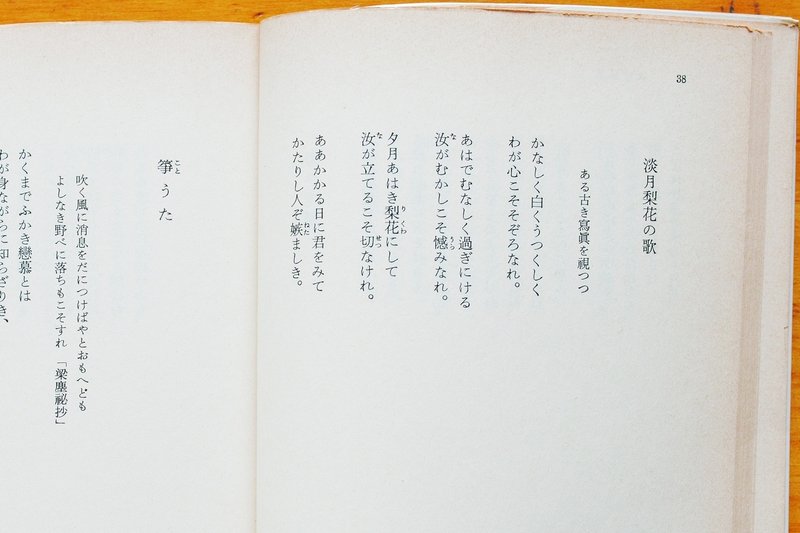
こんな、「つぶやき系」「ため息系」とでも名づけられるようなタイトル脇の文字たちが存在する気がする。それらの文字は、本文への誘い水として機能する。私の中では、水の連想からか、タイトルと本文のあいだの地面に文字という水が落ちてつくったしみの視覚イメージとなっている。
それにしても、太宰治のつぶやきの味わいは格別である。この水はなにか粘っこく、ずっと乾かずに地面に残っているのではないか。
棚になかった第6巻を残して『太宰治全集』を終え、『新修 宮沢賢治全集』全16巻+別巻1(筑摩書房、1979-1980)へ。12巻と15巻は抜けている。1巻からずうっとページをめくっていくが、エピグラフは見あたらない。しかしところどころで手をとめて読んでしまう。古い全集で、なんだか落ち着くサイズ。紙面の広さと文字のバランスが私には心地よく、自分の体に対して作品の世界がちょうどよい大きさの比率で現れ、向かいあえる感じがする。これなら宮沢賢治を読めるかもしれない。あとで古書を探そう。
続いて『向田邦子全集〈新版〉』全11巻+別巻2(文藝春秋、2009-2010)を、遊び心でめくりはじめる。予想どおりエピグラフは皆無だが、なんとなくのんびりした心持ちになり、エッセイを幾つか拾い読みする。各巻の口絵は向田邦子のスナップ写真が一枚ずつ載せられている。青山のマンションでくつろぐ姿やタクシーの中、直木賞の受賞時など。つい見入ってしまう。
さらに『漱石全集』全28巻+別巻1(岩波書店、1993-1999)へ。大物に手を出してしまった。しかしここにもエピグラフはまったくなさそう。いちおう全ページめくっていく。22、23巻は書簡集につき省略(他の作家の全集では書簡もだいたいチェックしているが、漱石全集ではきっと徒労になると見込んだ)。例によって、月報をつい読み始めてしまう。
第1、6、10巻は欠。そのほかの巻にはエピグラフは見あたらなかった。夏目漱石はきっとエピグラフを書かない派。
9月某日(4)──「世界幻想文学大系」、そして作戦変更
島崎藤村全集、高浜虚子全集などを確認。これで、この図書館の開架にある文芸領域の個人全集はひととおり見終えたことになる。さて。こんなに真面目に方針どおり進めてきたのだから、ここでひとつ、楽しみに走ることを自分に許そう。と「世界幻想文学大系」(国書刊行会、1975-1990)に手を出す。「あ、あそこにあるな」と視界の端にとらえ、ずっとねらっていたのだ。
第1巻はジャック・カゾット『悪魔の恋』(渡辺一夫+平岡昇訳)。エピグラフは見あたらない。最後に奥付を見ると「昭和五一年一一月一〇日印刷 昭和五一年一一月三〇日初版第一刷発行」とある。昭和51年ということは、1976年。そんなに古いシリーズだったのか!と今さらながら驚く。シリーズの責任編集は紀田順一郎+荒俣宏。造本は杉浦康平+鈴木一誌、印刷はセイユウ写真印刷株式会社+明和印刷株式会社と、印刷会社が2社クレジットされている。
第2巻のグレゴリー・ルイス『マンク』(井上一夫訳、1976)は上下二分冊。これがエピグラフ満載だった。作品全体の冒頭にあるほか、合計12章ある各章の冒頭にも置かれている。中には10行を超える長いものもある。その採集に加えて、ついつい本文を読んでしまったり(1796年発表の『マンク』は修道院の中でのめくるめく破戒と背徳、性倒錯や殺人を描く小説で、目に飛び込んでくる文字列にいちいち引っかかってしまう)、印刷や文字組みの様子をじっくり見てしまったりして、だいぶ時間をとられる。……これを続けていては、間に合わない。もちろんこれも必ず見なければならない叢書ではあるけれど、まずはもっと王道を、メジャー路線をつぶしてから「世界幻想文学大系」には戻ってくるべきではないか。
そう思い、名残を惜しみつつ第2巻でやめて、より広く知られた文庫・叢書からつぶしていく作戦に切り替える。大変残念ではあるが、進行管理としては冷静で分別ある判断といえるだろう、とひとりごつ。
9月某日(5)──「新潮・現代世界の文学」、ガルシア=マルケスなど
駅前での用事ができたので、少しだけのつもりで図書館に立ち寄る。
壁際の棚を、日本十進分類法95-番台「フランス文学」の途中から、99-番台「その他の諸言語文学」に向かって見ていく。岩波文庫など主要な文庫のチェックは必須とし、そのほか確認したい叢書もなるべくつぶしていく。
たとえば「スペイン文学」の棚には、スペインや中南米などのスペイン語圏の作品が収められている。ガブリエル・ガルシア=マルケスやマリオ・バルガス=リョサ、カルロス・フエンテスなどの作品を刊行した「新潮・現代世界の文学」シリーズ(新潮社)も何冊か並んでいるはずだ。1980年代から1990年代にかけて盛んだった古い叢書ではあるけれど、私を含め、ラテンアメリカの文学にはまずこの叢書で親しんだという読者は案外多いのではないか。あるいはジョン・アーヴィングやジョン・アップダイク、ジョン・バースなどのアメリカ現代小説や、ル=クレジオ、アラン・ロブ=グリエなどのフランスの小説作品でこの叢書にだけ収められていたものもある。シンプルで印象が強く、背表紙だけ見てもすぐにそれとわかる装幀で、「このシリーズだから読む」という読者も多かっただろう。
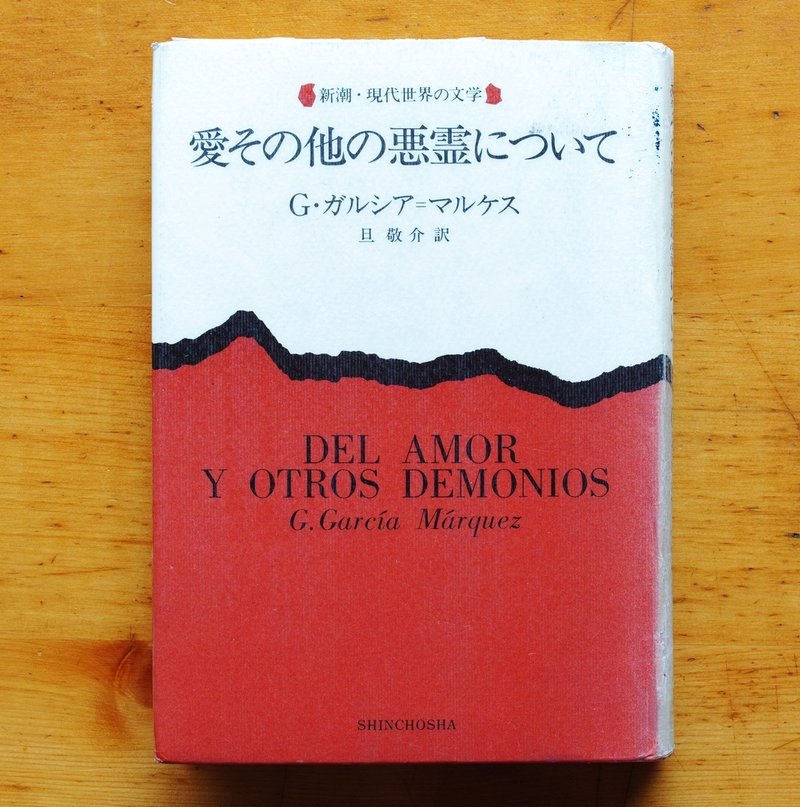
この図書館に収められた「新潮・現代世界の文学」シリーズの本では、ガルシア=マルケスやバルガス=リョサの作品にエピグラフがあった。
髪の毛は、体の他の部分よりもずっと生き返りにくいもののようだ。
──トマス・アクィナス「復活した肉体の完全性について」(問題第八十番、第五節)
(ガブリエル・ガルシア=マルケス「愛その他の悪霊について」 ★7)
ホルヘ・ルイス・ボルヘスも、岩波文庫の小説や講演録、集英社「現代の世界文学」シリーズの『砂の本』(篠田一士訳、1980)を確認(このシリーズにもお世話になった)。ボルヘスの小説はエピグラフの宝庫である。これについてはここで書き始めると脱線が過ぎるので、来るべき『エピグラフの本』(仮題)の紙上で(あるいはもしかしたら山本貴光さんの連載にて)ゆっくり、じっくり味わっていただきたい。
9月某日(6)──ロラン・バルト「パリの夜」
「スペイン文学」から「フランス文学」の棚へと少しだけ逆行。前回気になりつつ、当面の方針からは漏れるか……と思って調べなかった何冊かに、やはり手を伸ばしてしまう。
ロラン・バルト『偶景』(沢崎浩平・萩原芳子共訳)。みすず書房から刊行されているロラン・バルトの一連の著作の中には、ほかより文字が大きめで、一行の文字数も少しだけ少なめのものが何冊かあったと思う。この一冊もそれで、ひらいたとたん、あ、この感じ、と親しんだ感覚が呼び起こされた。
バルトはなんとなく、エピグラフが見つかりそうな気がしたのだが、まずは「パリの夜」という作品に付された次のエピグラフしか見つからなかった。
まあ、われわれは何とかうまく切り抜けた。
──ショーベンハウワー(死の直前、紙片の上に)
(★8)
「パリの夜」はその名のとおり、パリの幾つかの夜と週末の出来事を書いた日記風の作品で、冒頭にゴチック体で日付が記されている。原註に「ページの上の方に書き込み──書いている日の日付。原則としてその前夜のことを書く。」とある。カフェやレストラン、街路、メトロの中、訪問先でのパーティー、恋人らしい男性や「男娼」とのやりとり、自宅での就寝前の読書、夜中に目が覚めて覆われた気分など、バルトにとって日常的であっただろうこまごました光景や心象が綴られる。パリの街を移動してゆくバルト(「私」)の目に映るさまざまな事物、人びとの様子と、バルト自身の思ったことや心持ちの描写(多くはシニカルで、幻滅し、不快になり、いつも少し悲しげである)が絡みあって、読んでいる自分がバルトの中にいてパリの夜を見ているような、不思議な読書感覚がある。
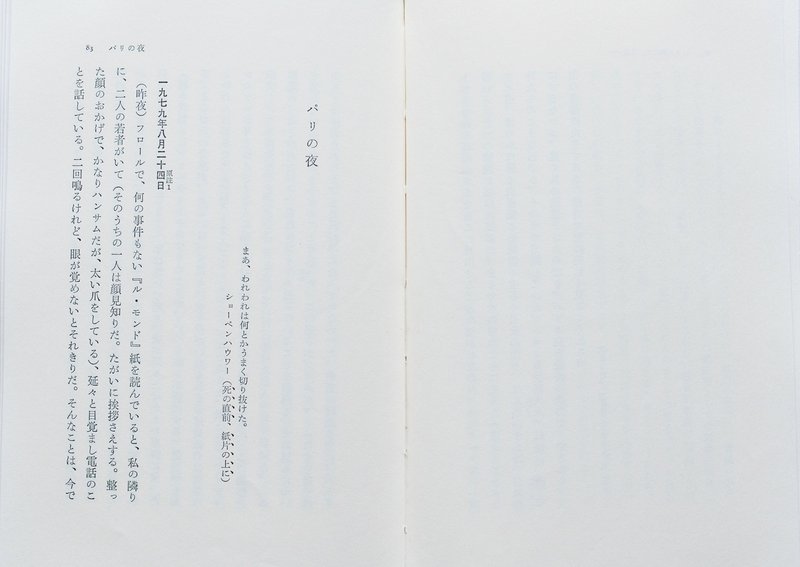
それにしても、このショーペンハウアーを引用したエピグラフ──死の直前の言葉!──にはどのような意味があるのだろう?と疑問に思い、巻末を見てみると、本文の後に置かれた花輪光「小説家バルト? ──解題に代えて」に解説があった。それによると、このエピグラフは「省察」というバルトが書いた別の文章(★9)の一部分に対応している。しかしその「省察」は、バルトが書いた日記の幾つかを載せるとともに、「「日記」というものに対する数々の根本的な疑問」を展開しているのだという。
「パリの夜」は、「省察」に発表されたその一日だけの日記のいわば続きのように見えるが、しかし「省察」においてバルトが展開したのは、「日記」というものに対する数々の根本的な疑問であった。自分が書いたこれらの日記(断章)をいくら読み返してみても、発表しうるものとは思われないが、しかしまた発表しえないとも思われず、要するに日記を発表しうるかどうかの問題は自分の手にあまる問題だ、とバルトは「省察」の最後の部分で言っている。
ところが、ヴァール(『偶景』の編者 *引用者注)を信用するなら、「パリの夜」は最初から発表するつもりで書かれているという。では、「省察」から「パリの夜」へかけて、バルトの「日記」観が変わったのか。
(中略)……発表を予定して書き始められた「パリの夜」は、「省察」の「実験的な」日記の断章(一九七九年四月二十五日付)と一見どれほど似ていても、その狙いはさらに遠くにある、と見なければならない。少なくともバルトは、「日記」を乗り越え、「反日記」に向かう可能性を信じて書き始めているのだ。
「パリの夜」の冒頭に掲げられたエピグラフ(ショーペンハウワー)はこの点きわめて意味深長である。「われわれは何とかうまく切り抜けた」(nous nous en sommes bien tiré)というのはどういう意味なのか。「省察」の最後のパラグラフはつぎのような言葉で始まっていた。「いいかえれば、私はどうしようもないのである(je ne m’en sors pas)。私がどうしようもないのは、私が《日記》にどういう《価値》があるのか決定できないのは、《日記》の文学的存在規定が私の指からこぼれ落ちてしまうからである」と。ここで用いられている「どうしようもない」(ne pas s’en sortir)が、エピグラフの「切り抜ける」(s’en tirer)に呼応するものであるとしたら、「パリの夜」のエピグラフは、とにかくあるめどがついたということを示しているのではなかろうか。
(★10)
1915年生まれのバルトは、1970年代以降、「ロマネスク(小説的なもの)」の執筆に向かっていたことが知られている。「ロマネスク」とはフランス語の「ロマン(小説)」から派生した語で、これについても花輪の「小説家バルト?」の中に簡潔な説明がある。
しかしバルトは、この語(=「ロマネスク」 *引用者注)によって「小説」でも「エッセー」でもない「第三の形式」を指していた。というよりも、たえず自己を更新するある「形式」、あるテクスト状態を指していた。もともと既成のあらゆるジャンルからはみ出す不定形な形式だった「ロマン」が、一つのジャンルに成り上がってしまった(というか、成り下がってしまった)ので、バルトは、「ロマン」本来のたえざる自己超出性をロマネスクという形で救い出そうとしたとも言える。
(★11)
そして1979年に書かれた「パリの夜」は、「「日記形式」によるロマネスク」の試みだったのだという(★12)。つまりバルトは、既成の「小説」でも「エッセー」でもない、たえず変容する新しい言説の一つとして、「日記」をモチーフとしつつそれを超えてゆく「反日記」を試み、「パリの夜」を書いた。そして、その試みをまずは何とかやりおおせた、日記をもとにしたこのテキストに一定の文学的存在規定を与え、発表に値するものに仕上げられた……と考え、「まあ、われわれは何とかうまく切り抜けた」というエピグラフを付したのではないか、というわけだ。
それにしてもこの「小説家バルト? ──解題に代えて」は読み応えがあり、収録作品やバルトのありようへの理解を大きく助けてくれる。続く萩原芳子「訳者あとがき」も、途中で逝去した沢崎浩平から訳業を引き継いだいきさつや、「偶景」というタイトルの説明(沢崎による造語だが、沢崎自身がこれをタイトルとするのをためらっていたという)が綴られ、短いながらも教えられることが多かった。冒頭のフランソワ・ヴァール「編者覚え書」も含め、隅々まで味読できる一冊。
バルトを離れ、ジョルジュ・バタイユ『ニーチェについて 好運への意志 無神学大全3』(現代思潮社、1992)を手にとる。さらにイタリア文学の棚も少し見ることができた。これについてはまた次回。
★冒頭画像
マシュー・グレゴリー・ルイス『マンク』下(井上一夫訳、世界幻想文学大系第2巻B、国書刊行会、1976)pp.222-223
★1 『太宰治全集 8』(筑摩書房、1998)p.4 以下、同全集からの引用はすべて旧字体を新字体に改めた。
★2 『太宰治全集 3』(筑摩書房、1998)p.57
★3 『太宰治全集 4』(筑摩書房、1998)p.304
★4 『太宰治全集 3』(筑摩書房、1998)p.31
★5 『島崎藤村全集 1』(筑摩書房、1981)p.24
★6 佐藤春夫『春夫詩抄』(岩波文庫、1936,1963)p.38
★7 ガブリエル・ガルシア=マルケス『愛その他の悪霊について』(旦敬介訳、新潮社、1996)p.3
★8 ロラン・バルト『偶景』(みすず書房、1989)p.83
★9 ロラン・バルト「省察」『テクストの出口』(みすず書房、1987)pp.220-242 「省察」は日記論であるが、「書くこと」「文学」についての論考にもなっている。ちなみにここに掲載されているバルトの日記を、私はとても面白く読んだ。
★10 花輪光「小説家バルト? ──解題に代えて」 『偶景』pp.172-173 花輪光(1932-1999)はロラン・バルトの研究者で『物語の構造分析』『明るい部屋』などの翻訳者。
「省察」からの引用箇所にある「どうしようもない」(ne pas s’en sortir)の「ne pas」は否定辞、「sortir」は「外へ出る・外へ出す」意で、「s’en sortir」で自分で自分をそこから救い出す=「困難な状況から抜け出る」意味を表す。その否定形で、「自分で自分を救い出せない=どうしようもない」という訳語になる。一方、「パリの夜」のエピグラフの「tirer」は「引く・引き出す」意で、「s’en tirer」(エピグラフでは一人称複数形に活用して「nous nous en sommes tiré」の形となっている)は自分で自分をそこから引っぱり出す=「事態をうまく切り抜ける」意味となる。(ショーペンハウアーが死の間際にこの言葉を手元に書きつけた、しかも主語が「われわれ」だったというのはどういうことなのだろう……?と、好奇心はさらに広がる)
なお、「小説家バルト?」の中の「省察」からの引用箇所は、『テクストの出口』(前掲書)所収の「省察」のテキストとは字句や記号が一部異なっている。
★11 『偶景』pp.147-148
★12 『偶景』p.150
◎プロフィール
藤本なほ子(ふじもと なほこ)
美術作家、編集者。
美術の領域でことばに関する作品をつくっている。また、辞書や一般書籍の編集・執筆・校正に携わる。
ウェブサイト https://nafokof.net/
Facebook nahoko.fujimoto.9
Twitter @nafokof
★「エピグラフの本(仮)」マガジンページはこちら
「異界をつなぐエピグラフ」山本貴光
第1回 夢で手にした花のように
第2回 モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道
第3回 ホラーの帝王にしてエピグラフの王
第4回 私は引用が嫌いだ
「エピグラフ旅日記」藤本なほ子
第1回
第2回
第3回
